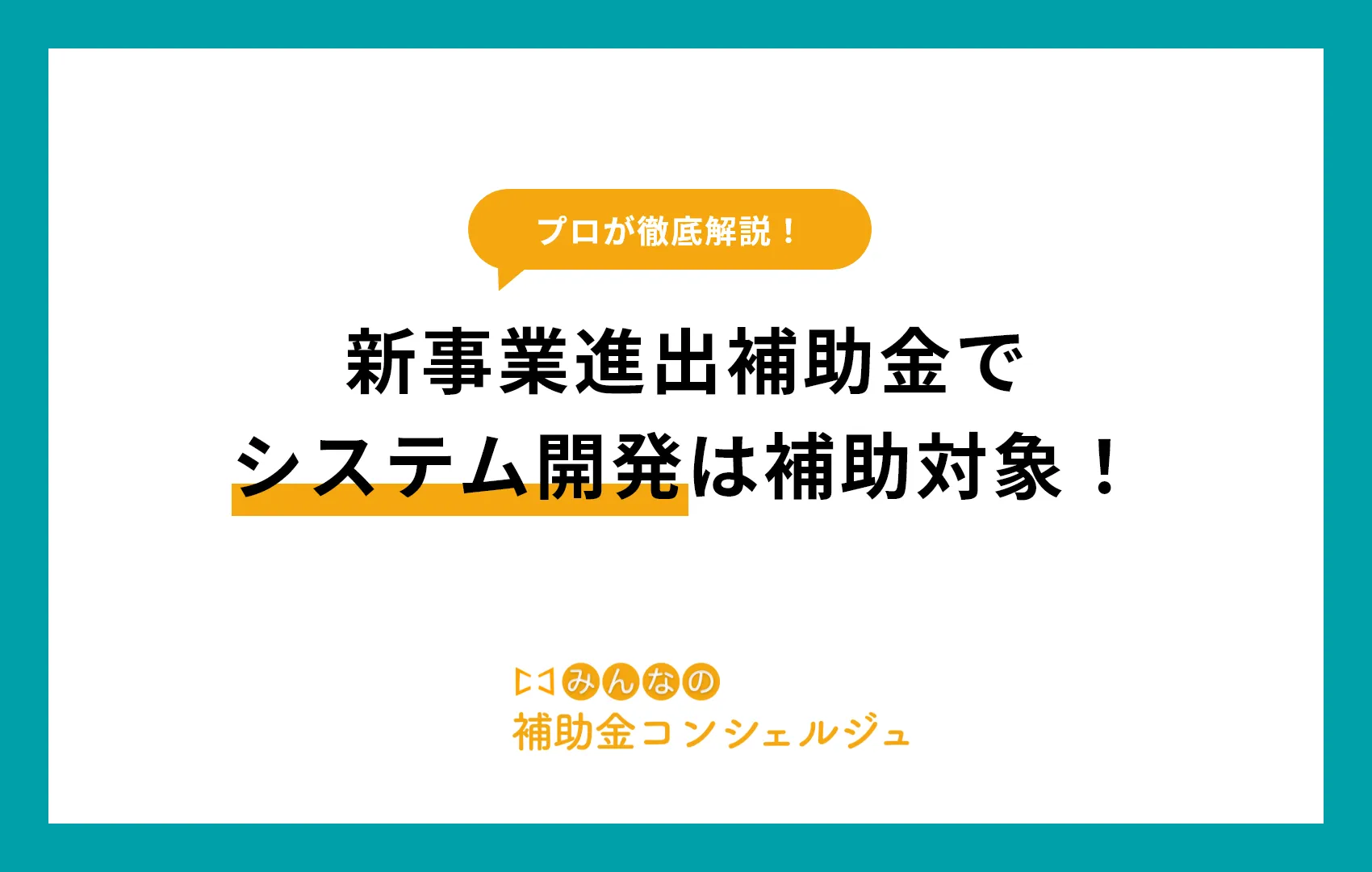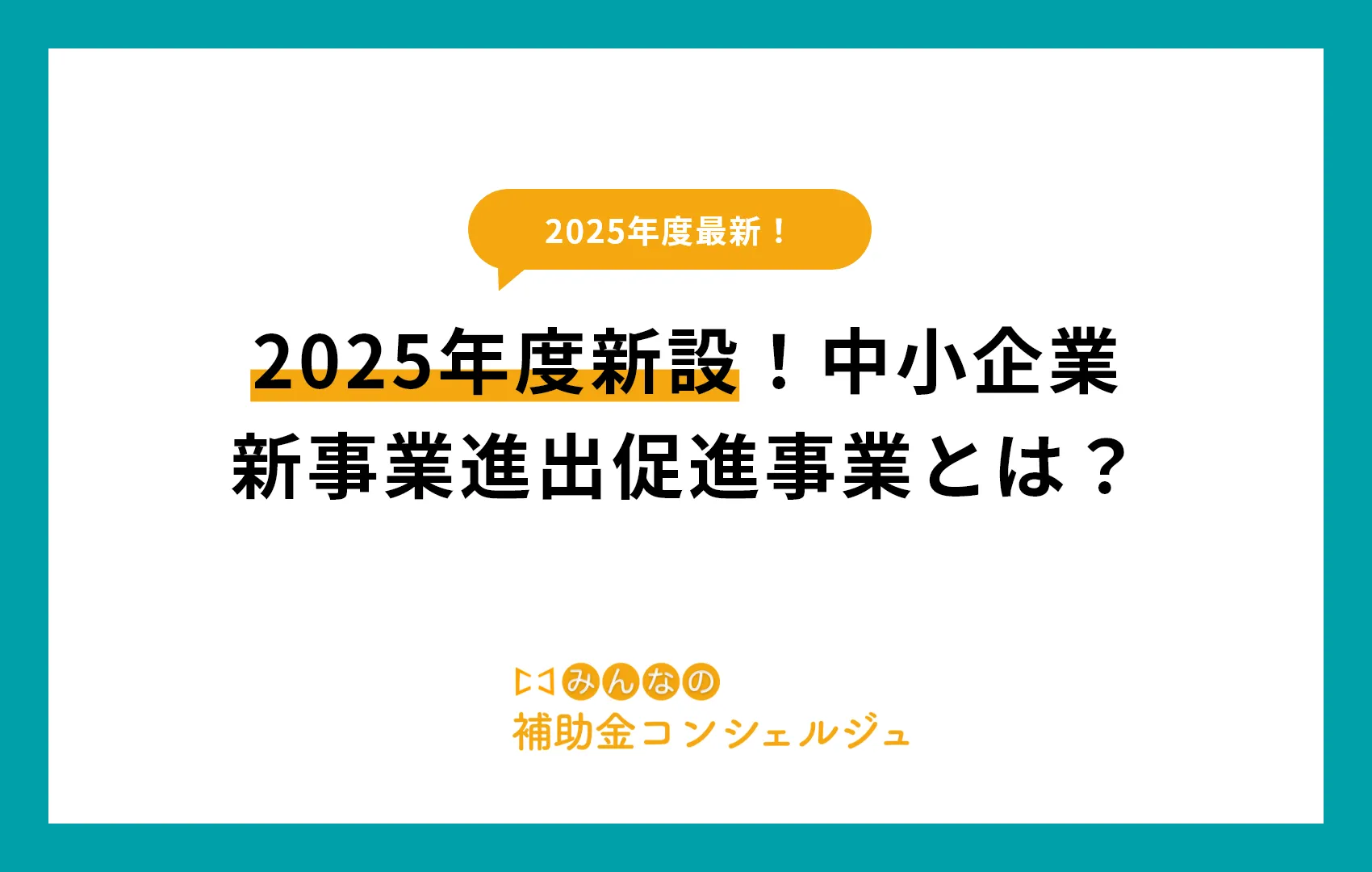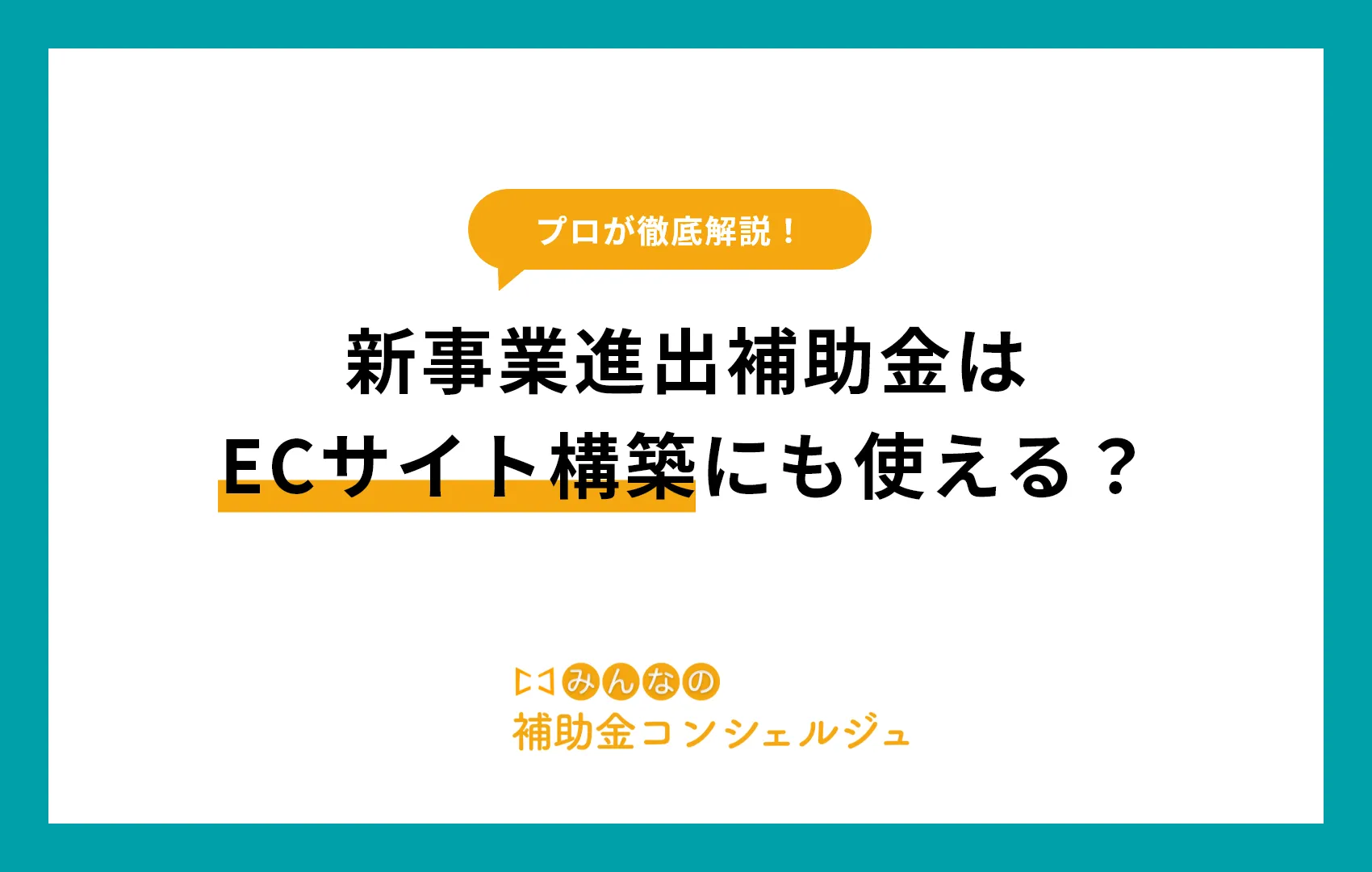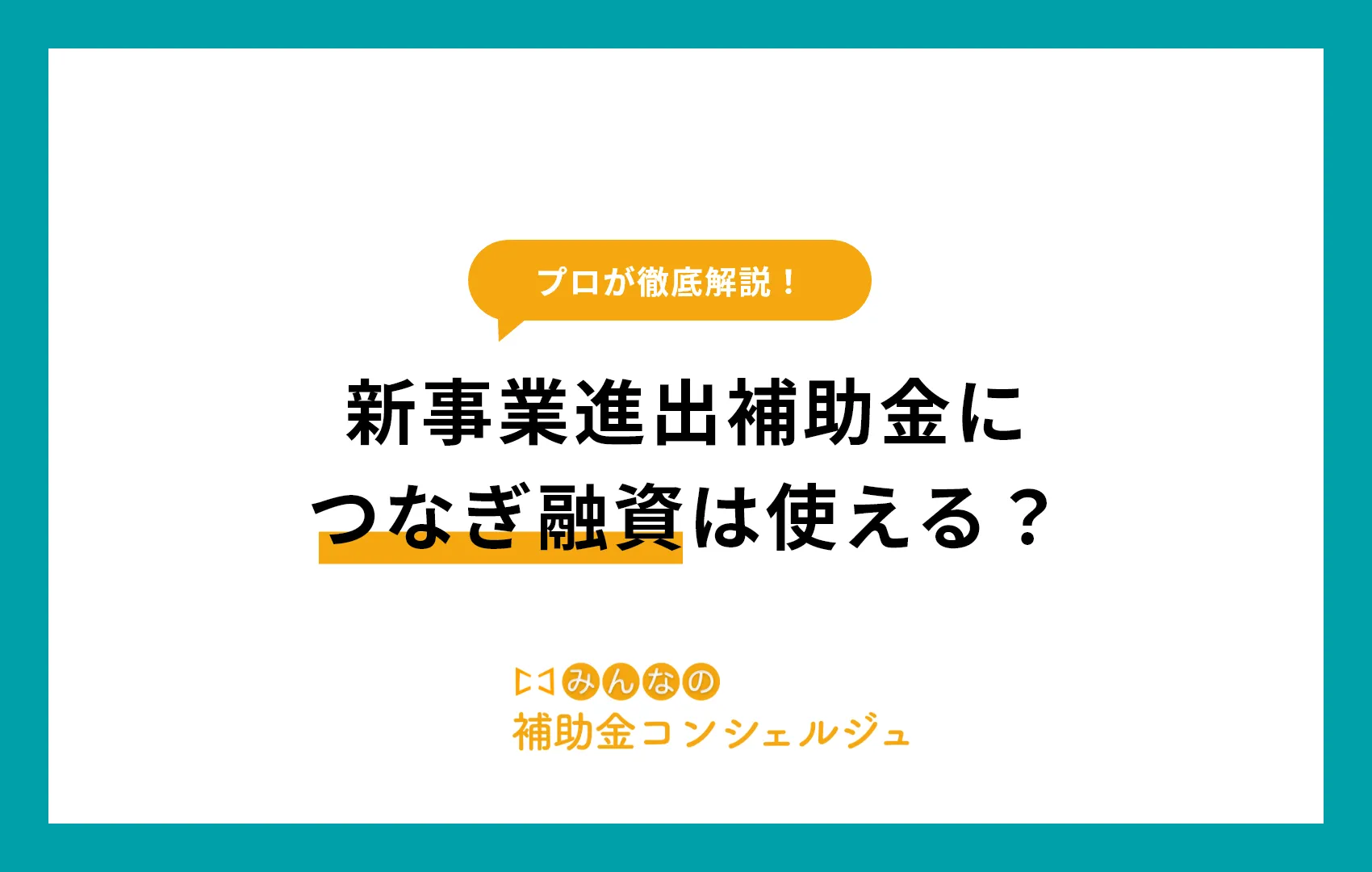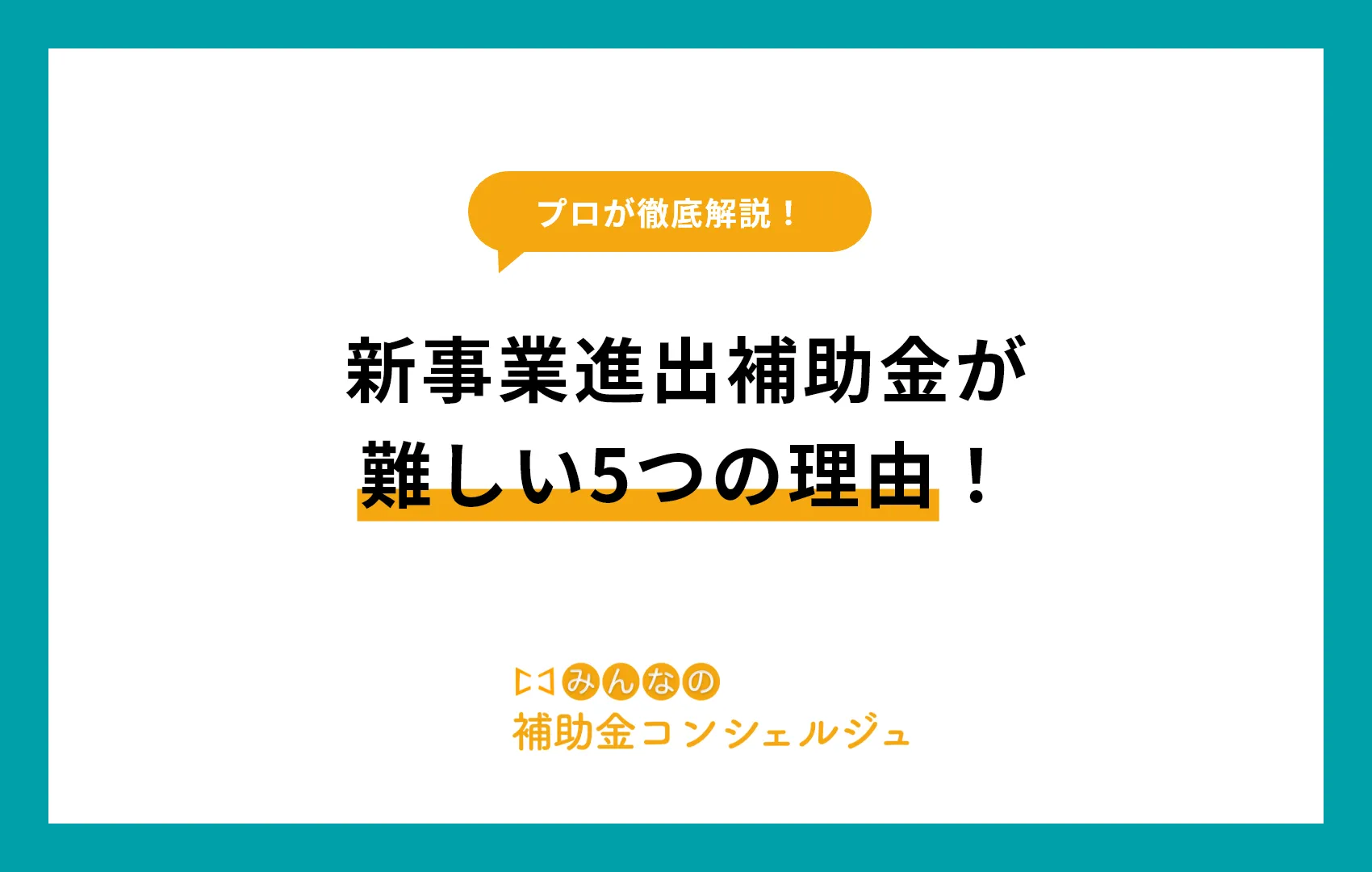新事業進出補助金でシステム開発は補助対象!申請要件や事例は? 事業再構築補助金の後継である中小企業新事業進出促進補助金(以下、新事業進出補助金)。新事業進出補助金はシステム開発に活用できます。本コラムでは、新事業進出補助金の概要と、システム開発に活用する際の事例などを分かりやすく解説します。 この記事を監修した専門家 補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
新事業進出補助金とは? 新事業進出補助金(正式名称:中小企業新事業進出促進補助金)のポイントは以下4点です。
従来の「事業再構築補助金」の後継にあたる 2025年度から新設された経済産業省系の補助金 中小企業の「新たな事業分野」への挑戦を支援 高付加価値化・地域経済活性化・賃上げを目的とする 本補助金は、既存事業の延長ではなく、新市場や新製品・新サービスに挑戦する事業を対象 としています。
支援対象となる取り組み例 地域課題を解決するための新事業 既存サービスとは異なる新規事業部門の立ち上げ 異業種への進出を目指す製品開発や販路開拓 DX・デジタル技術を活用した新サービス提供 補助金の目的は、こうした挑戦を通じて、企業の付加価値向上や雇用創出、そして継続的な賃上げにつなげること にあります。
新事業進出補助金の概要を確認する! DXやシステム開発にも使える可能性がある! 補助対象となり得るデジタル施策 自社ECサイトやスマートフォンアプリの開発 顧客管理・予約管理などの業務効率化システムの構築 オリジナルのSaaS型サービス開発 IoTやAIを活用した製品・サービスの新規提供 これらはすべて、「新市場向けに新たな製品・サービスを提供する取り組み」として正当性があれば対象になります。 オリジナル開発や自社向けのカスタマイズ型DX も支援対象となるのが、この補助金の特徴です。
なぜシステム開発が補助対象になるのか? 「新事業進出」の手段として、システム開発が重要な役割を果たすため 単なる業務改善ではなく、“新たな売上・価値を生み出す仕組み”であることが条件 製品の新規性・市場の新規性が認められれば、IT・DX領域も対象 DX、SaaS、WEBサービス開発なども新規事業として補助対象になる可能性あり 本補助金の最大のポイントは、「既存事業の延長ではない、新たな事業への進出」であること です。新たな顧客提供価値を生むビジネスモデルの核 になる場合は補助対象になり得ます。
補助対象となる可能性があるシステム開発の例 例 目的・背景 受発注自動化システム 製造業がBtoB向けに自社製品をEC化・全国展開する新事業として 顧客マッチングプラットフォーム 既存顧客基盤を活かし、新たにマッチングサービスを立ち上げる場合 モバイルオーダーアプリ 飲食業が新規にテイクアウト・宅配市場へ参入するためのインフラ 自社開発SaaSの提供 社内利用していた工程管理システムを製品化し、外販を開始する事業 オンライン予約+決済システム 予約管理業務を自動化しつつ、無人化店舗展開による業態転換を図る
こうしたシステムは、単に効率化するだけではなく、「新しい顧客」「新しい市場」「新しい収益構造」を創出する仕組み として位置づけられる場合に、補助対象となる可能性が高くなります。
新事業進出補助金の概要 対象者 日本国内に本社および補助事業の実施場所がある中小企業・個人事業主 「中小企業基本法」に定められた資本金・従業員数の要件を満たすこと 決算書が1期以上あり、従業員が1名以上いること (創業直後や0人の事業者は対象外) 「みなし大企業」や、過去に重大な補助金違反歴がある事業者は対象外 新事業進出補助金は個人事業主でも申請できる? 基本要件 補助金を受けるためには、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
要件 内容(簡略説明) 新事業進出 今やっている事業とはまったく異なる事業であること(市場・製品・サービスが新しい) 付加価値の向上 3〜5年で会社全体の売上や利益、人件費を合計した「付加価値額」が年4%以上伸びる計画があること 賃上げの実施 3〜5年で社員の給料(給与総額 or 一人あたりの平均)を継続的に引き上げること(国の定める基準以上)
さらに、最低賃金より30円以上高い給与水準を維持し、「子育てしながら働ける環境づくり」への取り組み(行動計画の策定・公表)も必要です。
ポイント整理 補助金の対象となるためには、「新しい製品を作って売る」だけでは不十分であり、それを新たな市場に向けて提供する という視点も必要です。社外に向けた新たな価値の提供 が求められます。
新事業進出補助金の要件を分かりやすく解説! 補助金額・補助率(2025年度第1回公募) 従業員数 補助上限額 賃上げ特例適用時の上限額 補助率 20人以下 2,500万円 3,000万円 1/2(50%) 21~50人 4,000万円 5,000万円 1/2(50%) 51~100人 5,500万円 7,000万円 1/2(50%) 101人以上 7,000万円 9,000万円 1/2(50%)
補助対象経費の代表例 主な費目 内容の例 システム開発費 新サービス用アプリやWEBシステムの構築費 クラウド利用料 SaaS導入やサーバー利用料など 機械装置費 自動化機器や業務用IT機器の導入 広告宣伝費 LP制作費、ネット広告費、販促物制作 外注費 デザイン、プログラム開発、業務委託など 専門家経費 認定支援機関、ITコンサルの支援費用
補助対象外となる主な例 既存業務の延長(例:今あるシステムの改修) 保守契約や更新料などの日常的なコスト 補助金の交付決定前に発注・契約した費用 自社社員の人件費(内製の場合は原則対象外) この補助金は、「今とは違う新たなチャレンジ」を応援する制度です。その開発が“新しい市場や顧客向け”かどうか が最大のチェックポイントとなります。
補助対象になるシステム開発の具体例:ECサイト導入 ECサイトの開発も、補助対象として評価される場合があります。特に、従来とは異なる顧客層や販路への進出が明確であれば、「新事業」として認められる可能性が高まります。
採択実績を参考にした活用例(事業再構築補助金を参考) 事例名 業種・事業形態 導入したシステム 新事業として評価されたポイント 日本の伝統工芸品EC 観光業 → 小売・海外販売 多言語対応ECサイト 観光ノウハウを活かし、文化的価値を商品として世界に発信 輸入電子機器EC 輸出入業 → BtoC物販 ECサイト+倉庫管理システム 既存の海外仕入ルートを活用し、日本向けに新市場を開拓
新事業進出補助金でも活用が期待されるEC開発例 地域特産品を全国・海外に展開するECサイト構築 業務用製品の直販モデル(BtoB→BtoC)への業態転換 既存店舗とは異なるブランドでのD2C展開とECシステム新設 SNS連携・動画販売機能付きECアプリの新規開発 体験型・サブスク型商品提供に対応した予約ECサイト 補助対象となるポイントの整理 補助対象となるポイントとして重要なのは、これまで取り扱っていなかった商品を、まったく新しいターゲット層に向けて販売することや、既存のリアル販売からオンライン販売へと事業形態を転換すること、さらに新ブランドや海外市場向けに独立した販路を新たに構築することです。こうした「新しい価値を顧客に届ける仕組み」としてのECサイトは、新事業進出補助金の目的に非常に合致しており、補助対象として十分な可能性があります。
補助対象になるシステム開発の具体例:アプリ開発の事例 アプリ開発も補助対象となる可能性があります。たとえば、新たなサービス提供手段としてアプリを開発する場合は、補助金の対象と認められるケースがあります。
活用が期待されるアプリ開発の事例(事業再構築補助金を参考) 事例名 業種・背景 アプリ内容 新事業として評価されたポイント 出張リラクゼーションマッチングアプリ 整体業 × アプリ販売 顧客とセラピストをつなぐアプリを自社開発 既存の技術・顧客資産を活かし、従来にない広域・効率的なサービス展開を実現 フードロスマッチングアプリ 老舗食品卸業者 余剰食品と必要とする企業・団体を結ぶアプリを開発 社会課題の解決+既存取引先ネットワークの活用による新ビジネス創出
その他、補助対象として想定されるアプリ開発例 地域観光と宿泊施設をつなぐ予約・ガイドアプリ: 観光業が新たに旅行支援プラットフォームを展開 スポーツ指導のオンライン配信・予約アプリ:プロ選手や講師が地域を超えて指導できる収益モデル 自社独自のスキル学習アプリ(eラーニング):教育事業・人材育成事業として事業化する例 補助対象のポイント整理 補助対象となるかどうかのポイントは、まず、従来の提供方法(対面・紙・電話など)とは異なる、新しい体験を顧客に提供できているかどうかです。
新事業進出補助金の申請要件 補助対象者の基本要件(中小企業基本法に基づく) 業種 資本金 常時雇用の従業員数 製造業・建設業等 3億円以下 300人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 小売業 5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
上記のいずれかに該当し、日本国内に本社および補助事業の実施場所を持つ中小企業者や個人事業主等 が対象です。
その他の主な要件 決算実績が1期以上あること 常時雇用する従業員が1人以上 いること 申請時点で「みなし大企業」に該当しないこと 不正受給歴や重大な法令違反がないこと 申請者が法人・個人事業主どちらであっても、上記の条件をすべて満たしていなければ申請はできません。特に、創業直後の事業者(決算が未到来)や従業員ゼロの個人事業主は対象外になる点には注意が必要です。
システム開発で新事業進出補助金を使う際の注意点 システム開発に関するよくある不採択例 不採択例 主な理由 自社予約システムの機能追加 既存業務の延長であり、新規性がない ECサイトのリニューアル 顧客・市場・提供価値が変わっていない アプリ開発の目的が曖昧 誰のどんな課題を解決するのか不明確
補助対象となるには、そのシステムが明確に新しい市場や顧客層を対象としていること、従来とは異なるビジネスモデルの構築に繋がっていること が不可欠です。“何が新しいのか”を明確に説明できる事業計画 が求められます。
地域・自治体による違いにも注意 補助金名や制度内容が自治体ごとに異なることがある(例:「新分野展開補助金」など) 補助率・上限額・対象経費・スケジュールが独自に設定されている場合がある 自治体補助金との併用可否は制度ごとに異なる(原則、同一経費への重複補助は不可) 本補助金は国の制度 であるため、公式サイトから最新の情報を確認するのが基本です。独自の補助制度が同時展開されている場合 もあるため、必要に応じて都道府県や市区町村の産業振興課にも問い合わせることをおすすめ します。新事業進出補助金の公式サイトはこちら!
システム開発に新事業進出補助金を使う時の申請の流れ 新事業進出補助金の申請の流れは以下のとおりです。
事前相談 gBizIDプライムの取得 事業計画書の作成 電子申請(jGrants) 採択通知の受領 交付申請・交付決定 補助事業の開始・実施 実績報告・精算 1.事前相談 「この補助金、自分の会社でも使えるの?」という不安がある場合は、まず公的な相談窓口を活用しましょう。
よろず支援拠点(中小企業庁が全国に設置している無料の経営相談窓口) 商工会議所・商工会(地域の中小企業を支援する団体) これらの機関では、補助金の制度内容や申請方法などについて無料で相談ができます。参考:よろず支援拠点の一覧 参考:商工会議所の検索
2.gBizIDプライムの取得 補助金の電子申請には、法人・個人事業主どちらも「gBizIDプライムアカウント」が必須です。参考:gBizIDプライムの公式サイト
3.事業計画書の作成 補助金の申請では、以下のような内容を盛り込んだ「事業計画書」の作成が必要です。
新しく始める事業の内容(対象市場・提供サービスなど) 開発にかかる費用の内訳(システム構築費など) 今後の収益見込みや事業の成長計画 賃上げ計画(制度上の必須要件) ※事業計画書は採択率を左右する重要書類なので、認定支援機関(商工会・税理士・中小企業診断士など)と連携して作成するのがおすすめです。
4.電子申請(jGrants) 必要な書類を整えたら、補助金専用の電子申請システム「jGrants(ジェイグランツ)」から申請します。参考:jGrants公式サイト
5.採択通知の受領 申請内容が審査された結果、「交付候補者」として採択された場合は通知が届きます。この時点ではまだ補助事業は始められません。ここからさらに「交付申請」という手続きが必要です。
6.交付申請・交付決定 採択されたら、具体的な支出計画やスケジュールを記載した「交付申請書」を提出し、最終的な審査を受けます。
7.補助事業の開始・実施 交付決定日以降に行った契約・発注・支払いが、補助対象になります。
8.実績報告・精算 事業が完了したら、支出内容や実際の成果をまとめて「実績報告書」を提出します。
gBizIDやjGrantsの事前準備がカギ gBizIDプライムは、法人・個人事業主問わず必須の申請アカウントです。ID発行には時間がかかるため、公募開始前からの取得が強く推奨されます。
専門家(認定支援機関)との連携の重要性 事業計画の内容が精緻になり、採択率向上につながる 補助要件や賃上げ条件への適合性を確認できる 書類作成や申請手続きの負担を軽減できる 実績報告までの伴走支援も受けられる 新事業進出補助金では、認定経営革新等支援機関との連携が強く推奨されています。 支援を受けた内容や関与機関の情報は、電子申請時に申告項目として明記されます。
システム開発で新事業進出補助金の採択を目指すためのポイント 採択されるために重視される主なポイントは以下4点です。
システムが「誰の・どんな課題をどう解決するか」が明確であること 売上見込みや事業の成長性に現実味があること 収支計画や事業スケジュールに無理がないこと 「新規性」「地域への貢献」「社会課題の解決」といった加点要素が含まれていること 補助金の審査では、「ただ作りたいシステムがある」だけでは通過は難しく、そのシステムを通じて、どのように新たな市場を開拓し、どのような価値を生むのかが明確であることが求められます。
新規性:今までになかったサービス、あるいは自社として全く新しい取り組みかどうか 地域性:地元企業・特産品・地域雇用など、地域社会への波及効果があるかどうか 社会性:フードロス削減、働き方改革、子育て支援など、社会課題の解決に貢献するかどうか これらの視点をふまえて、「誰のために、なぜ、何を、どう提供するのか」を一貫したストーリーとして事業計画に落とし込むことが、採択を目指すうえでのカギになります。
新事業進出補助金と他の補助金は併用できる? 結論から言うと、他の補助金との併用(併給)は可能な場合もありますが、同一の経費・事業内容について重複して補助を受けることは一切できません。
募集要項で明記されている禁止例 診療報酬、介護報酬、固定価格買取制度等との併用 国・自治体・独立行政法人等が交付する補助金や助成金と同じ経費を対象とする申請 他の法人・事業者と酷似・同一内容の申請(共同開発の偽装など) 既に採択・実施中の事業再構築補助金・IT導入補助金等と経費が重複する申請 補助金等の交付実績や申請中の情報は、申請時に電子申請システム(jGrants)で必ず記載する必要があるため、記載漏れや虚偽申告は不採択・返還対象になります。
ポイント整理 他の補助金と併用する場合でも、目的や経費が明確に分かれていれば原則として申請可能です。ただし、同一の支出に対して複数の補助を受けること(二重補助)は厳格に禁止されています。
まとめ 新事業進出補助金は、「これまでにない新たな事業」への挑戦を支援する制度です。システム開発も、新たな市場や顧客に向けた事業の中核 であれば補助対象になります。
新事業進出補助金を活用したい方はこちら! 実は、「補助金は申請すれば受給できる」わけではありません。 4社に1社しか通過できない難関補助金も多い のです。
弊社がサポートさせていただいた方のお喜びの声 弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります。 急な変更にもすぐ対応してくれて 、とても満足です!」本業に集中することができました! 」補助金に関するお悩みやご相談がある方は、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。担当者があなたのお悩みに丁寧に回答いたします。
監修者からの ワンポイント アドバイス 新事業進出補助金は新規性要件が鍵となってきます。DX、SaaS、WEBサービス開発なども新規事業の対象であり、明確に新しい市場や顧客層を対象としていることが求められます。カスタマイズしたりオリジナルのものを導入するといった工夫が必要になります。