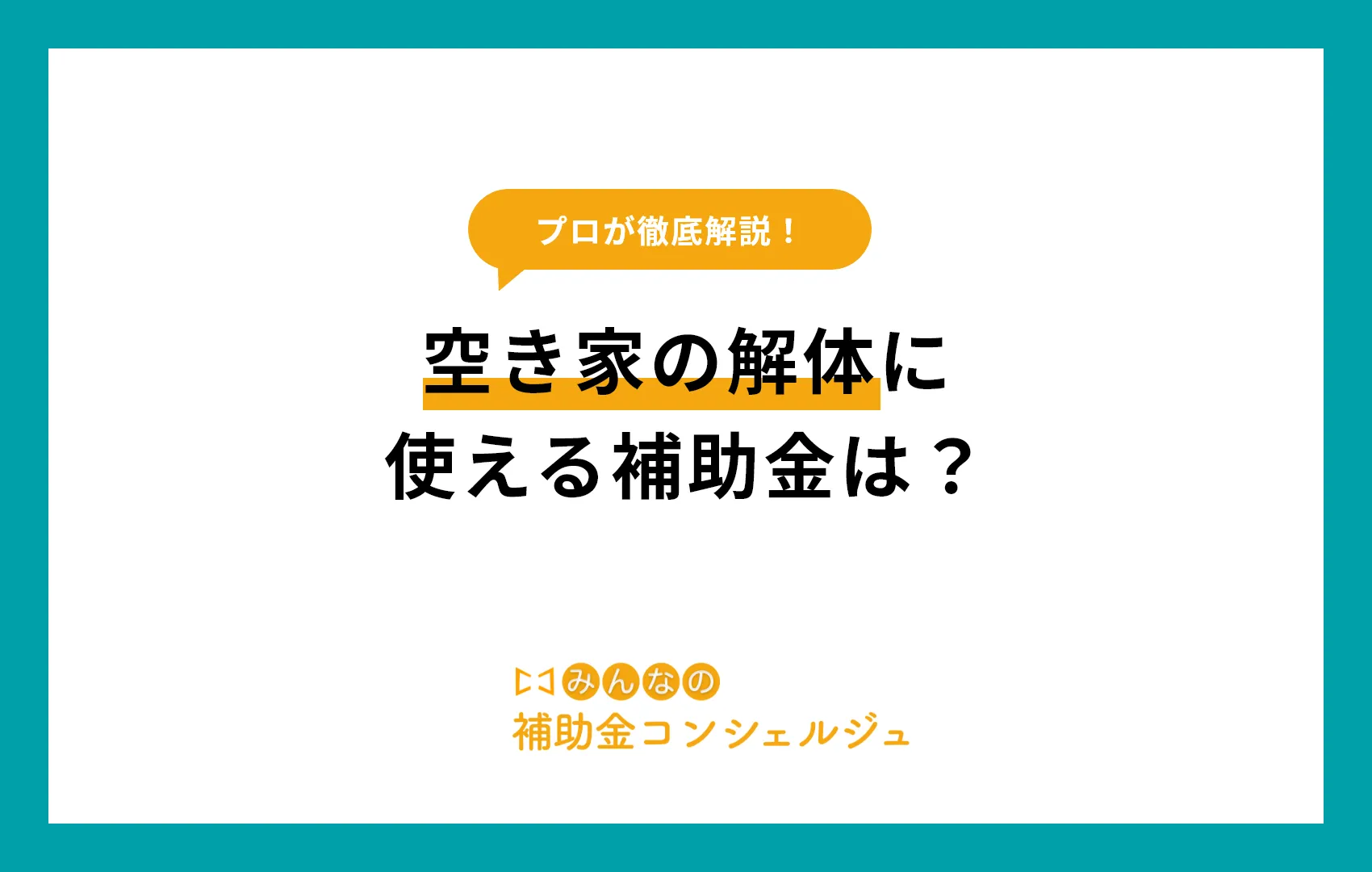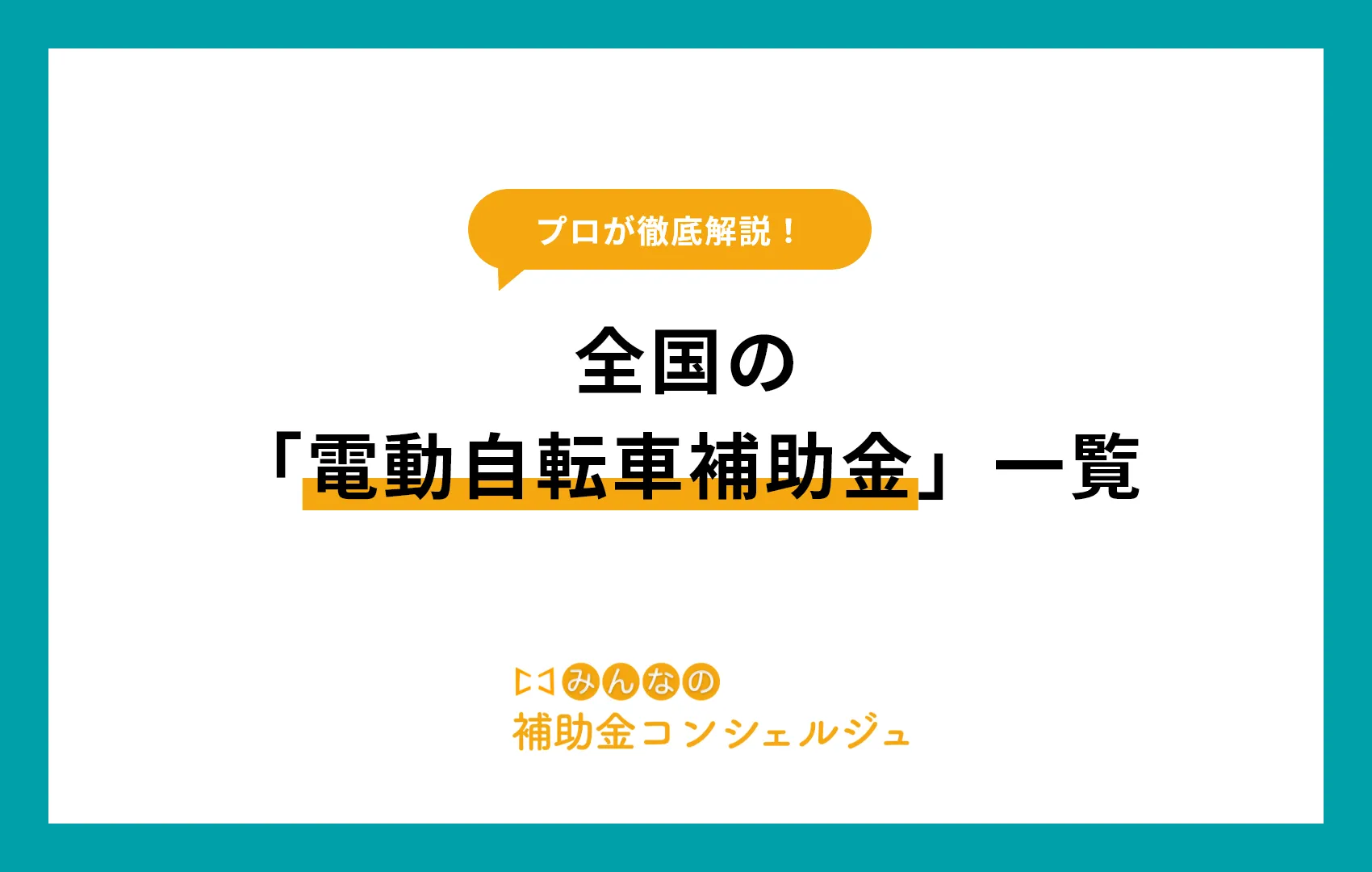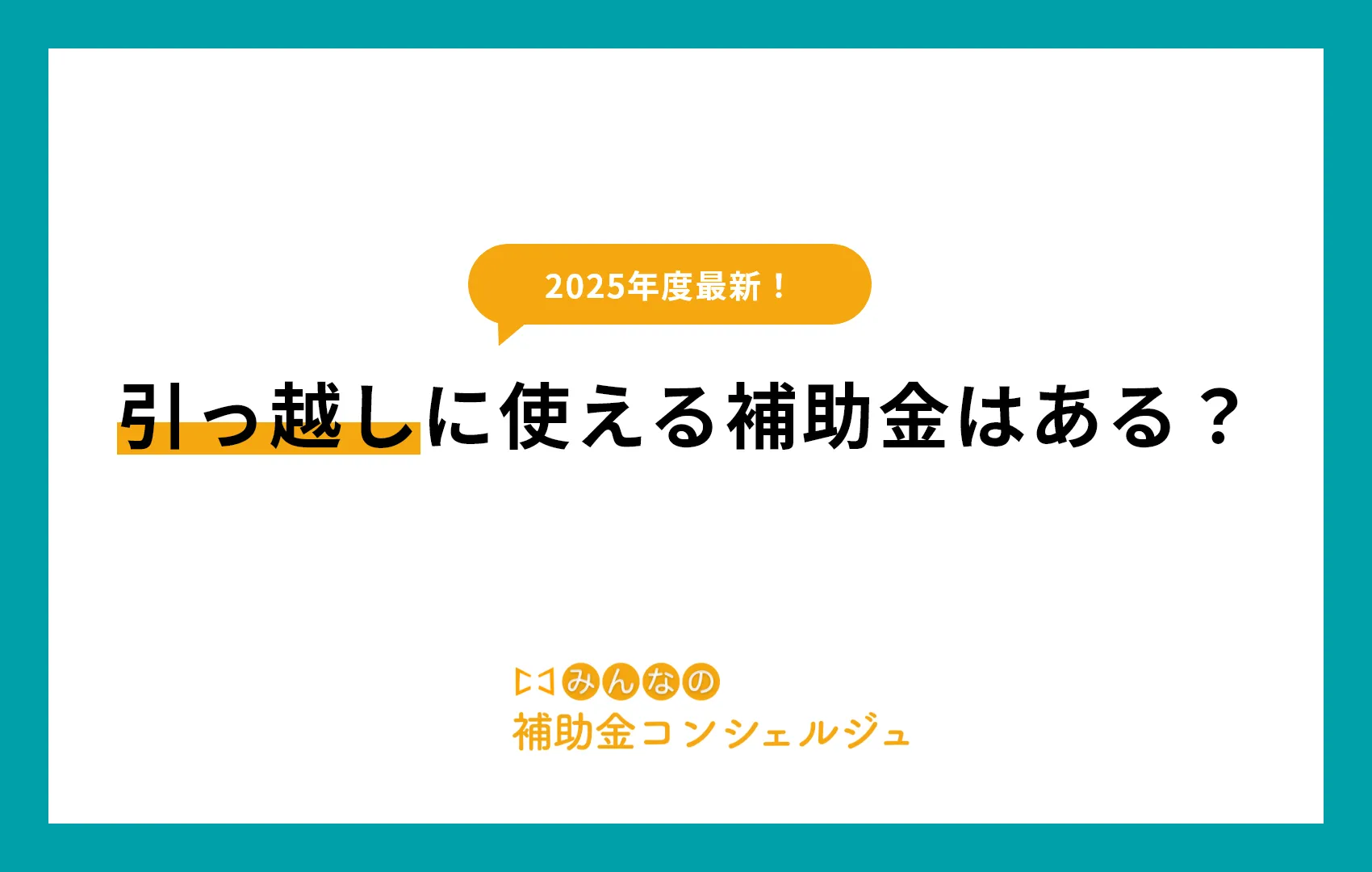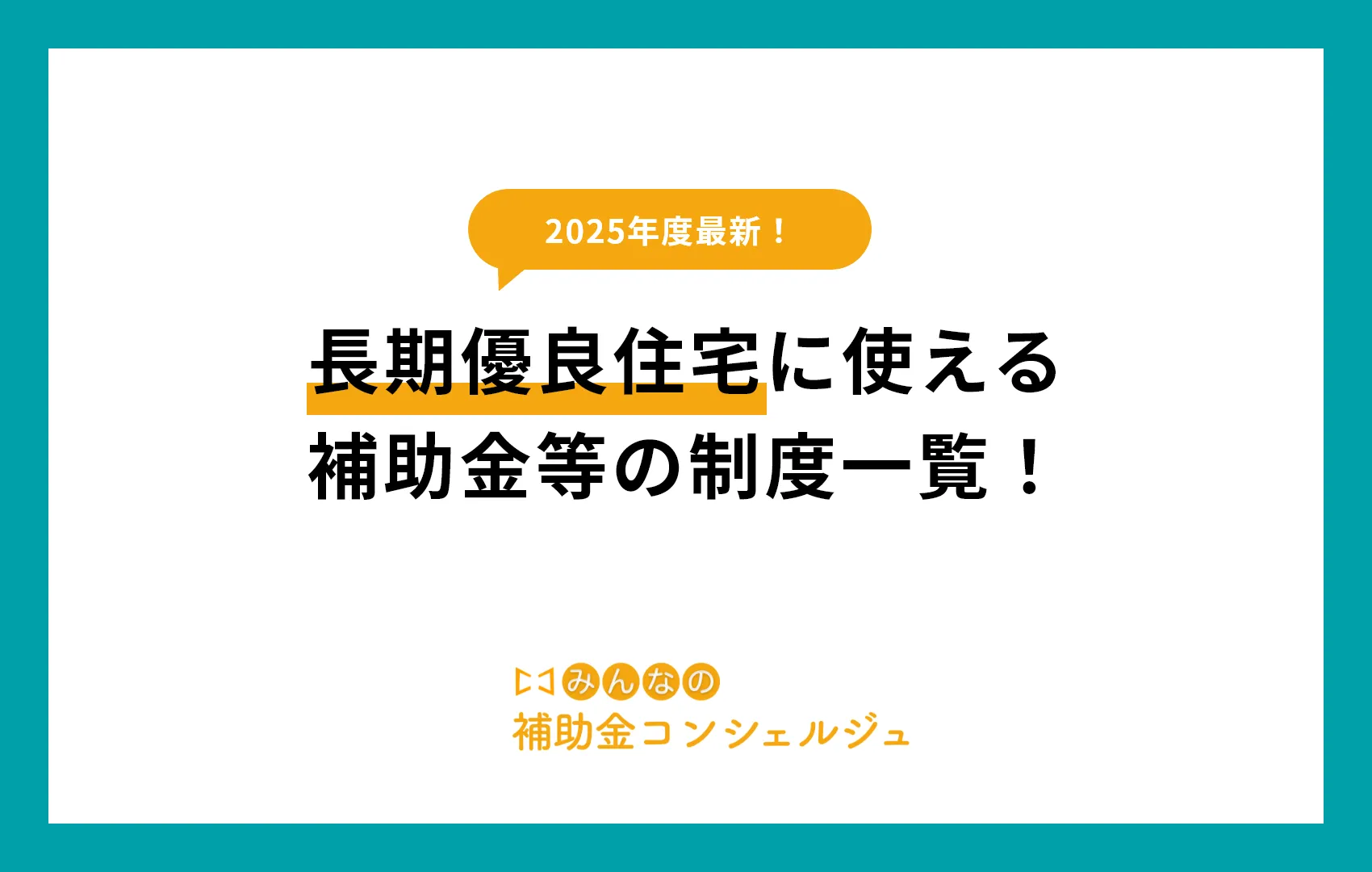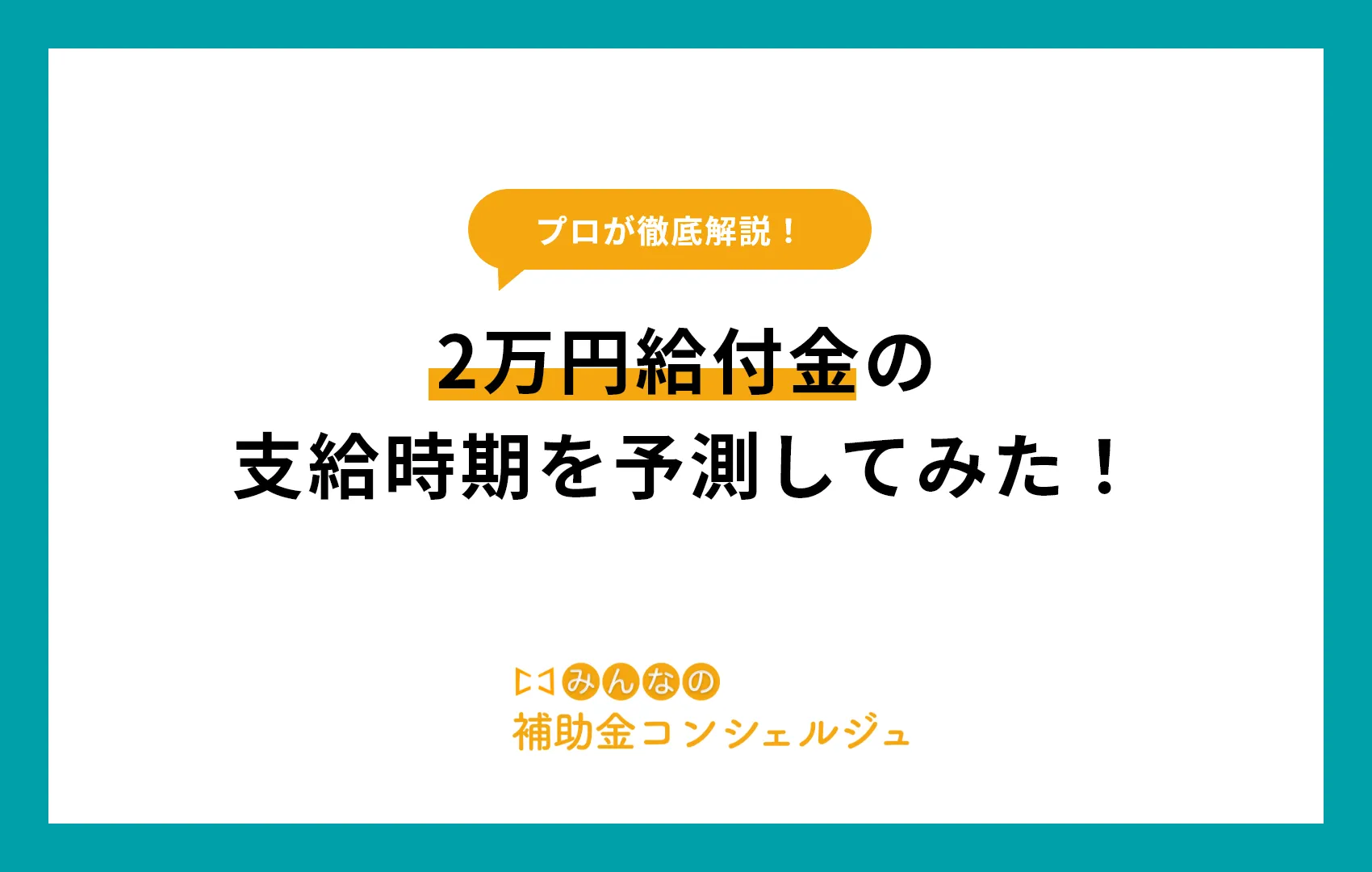空き家の解体に使える補助金は?
空き家を解体せずに放置していると、税金面でも負担がかかる場合があります。とはいえ、費用を考えるとどうしても解体に踏み切れない方も多いでしょう。実は自治体によっては、空き家の解体に個人が使える補助金があります。本コラムでは空き家の解体に使える補助金の概要や申請の流れ、おすすめの土地活用方法について分かりやすく解説します!
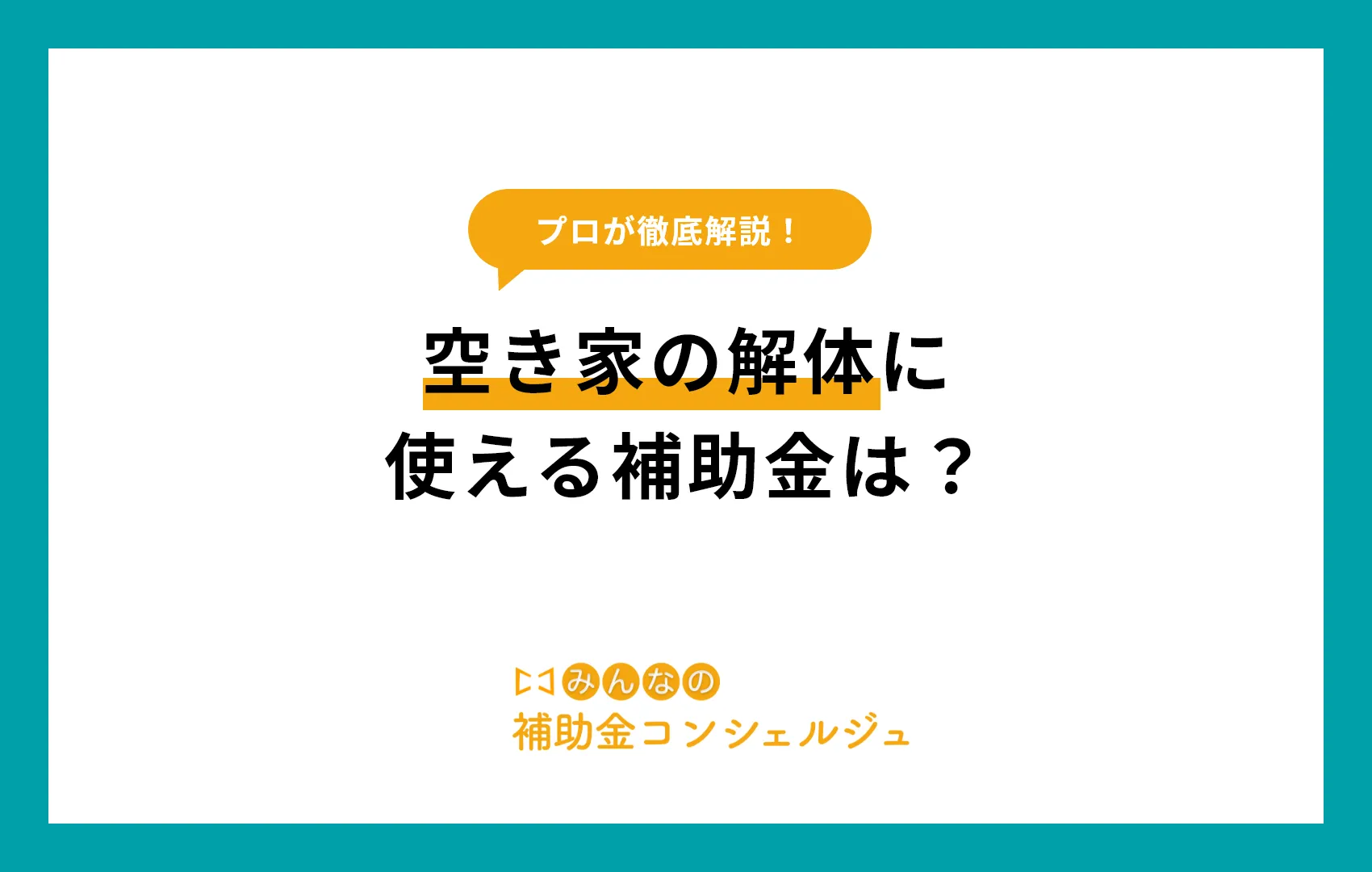
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
空き家解体に補助金は使える?
空き家の解体には、国の制度と自治体の制度を通じて補助金が活用できます。結論として、全国一律の補助金は存在せず、多くは各自治体が独自に設けている制度です。そのため、まずはお住まいの地域で制度があるかを確認することが重要です。
国の制度と自治体の制度の違い
国が直接「空き家解体」を対象とした補助金を用意しているわけではありません。国土交通省や総務省は、自治体の空き家対策を後押しするための交付金を市区町村に配分しています。自治体はこの交付金などを活用し、独自の「空き家解体補助金」や「除却費補助金」を設けています。
つまり、実際に補助を受けられるのは、自治体が運営する制度に申請した場合です。制度内容や補助金額、対象条件は自治体ごとに異なります。
| 制度の種類 | 対象 | 特徴 |
| 国の制度 | 自治体 | 直接個人には支給されず、自治体の事業を支援 |
| 自治体の制度 | 個人・法人 | 空き家解体費用の一部を補助。上限額や条件は地域ごとに異なる |
どんなケースで補助が受けられるのか
空き家解体補助金は、以下のようなケースで対象となることが一般的です。
長期間利用されていない空き家:おおむね1年以上居住実態がない建物が対象とされるケースが多い。
老朽化して危険な状態にある空き家:倒壊の恐れがある、周辺住民に危険を及ぼす可能性があると判断された建物。
自治体の指定区域にある空き家:景観や防災の観点から重点的に解体が進められるエリアに指定されている場合。
ただし、条件は自治体によって細かく異なり、「相続した空き家」「居住実態がない住宅」「税金を滞納していないこと」など、追加条件が設けられていることもあります。
空き家解体 補助金の金額と条件
空き家解体の補助金は、自治体によって上限額や条件が異なります。結論として、補助金の上限はおおむね50万円〜100万円程度が中心で、対象となる建物は「長期間使われていない」「老朽化して危険」といったケースです。
上限額の目安(例:50万円〜100万円)
多くの自治体では、解体費用の一部を補助金として支給しています。補助率は工事費の2分の1程度とされることが多く、上限額は以下の範囲に収まるのが一般的です。
| 項目 | 内容 | 補足 |
| 補助率 | 工事費の1/2程度 | 自己負担が必ず発生する |
| 上限額 | 50万〜100万円前後 | 一部の自治体では200万円規模もあり |
| 支給方法 | 工事完了後に精算払い | 交付決定前の工事は対象外 |
解体費用の総額は100万〜300万円以上になるケースが多いため、補助金を活用しても自己負担は残ります。そのため、費用全体の見積もりと補助金の上限を事前に比較することが重要です。
築年数や所有状況などの主な条件
空き家解体補助金には、自治体ごとにさまざまな条件があります。代表的な条件は以下の通りです。
築年数・使用状況:おおむね築20年以上、または1年以上使用実績がない建物が対象。
所有者の条件:所有者本人や相続人であること。税金の滞納がないことが求められるケースが多い。
建物の状態:倒壊の危険性がある、または防災・景観上問題があると判断された空き家。
条件は地域ごとに異なるため、必ず自治体の募集要項を確認してください。
「古い家の解体」も対象になる?
古い住宅の解体も補助対象になることがあります。結論として、築年数が古くても「使用実態がある住宅」は対象外である点に注意が必要です。
例:
居住中の古い家を建て替えるための解体 → 原則補助対象外
長年空き家になっている古い家を解体 → 補助対象になり得る
つまり、「古い家だから必ず対象」というわけではなく、空き家として放置されているかどうかが補助対象かどうかを分ける重要なポイントです。
空き家解体の補助金は上限50〜100万円前後が多く、対象は長期間利用されていない老朽化空き家です。築年数が古くても使用中の住宅は対象外となるため、制度の条件を必ず確認する必要があります。
空き家解体費用と補助金の関係
空き家の解体には高額な費用がかかります。結論として、補助金を活用しても自己負担は残るため、費用全体の相場と補助金の上限額を事前に把握することが重要です。
解体費用の相場はいくら?
解体費用は建物の構造や広さ、立地条件によって異なります。一般的な目安は以下のとおりです。
| 建物の種類 | 坪単価の目安 | 総額の目安 |
| 木造住宅 | 3万〜5万円/坪 | 100万〜250万円程度 |
| 鉄骨造住宅 | 4万〜6万円/坪 | 150万〜300万円程度 |
| RC造住宅 | 5万〜8万円/坪 | 200万〜400万円以上 |
例えば、延床面積30坪の木造住宅なら解体費用は約90万〜150万円、RC造40坪なら200万〜300万円を超えるケースもあります。
補助金で実際にどこまでカバーできるか
補助金の上限額は多くの自治体で50万〜100万円程度です。そのため、解体費用の全額をまかなうことはできず、自己負担は必ず発生します。
木造30坪の解体(費用120万円):補助金上限80万円の場合でも、自己負担は40万円程度。
鉄骨造40坪の解体(費用200万円):補助金上限100万円でも、自己負担は100万円程度。
また、補助対象となるのは解体工事費そのものに限られる場合が多く、「整地費用」「外構撤去費用」などは補助対象外となるケースもあります。
空き家の解体には100万〜300万円以上の費用が必要であり、補助金はその一部(50万〜100万円程度)を軽減する役割にとどまります。補助金を過信せず、自己負担を見込んだ資金計画を立てることが不可欠です。
主要自治体の空き家解体 補助金制度
空き家解体の補助金制度は自治体ごとに内容が異なります。結論として、東京都では「東京都空き家家財整理・解体促進事業」によって解体または家財整理費用の一部を補助しており、令和5年度では補助上限額や申請条件が明確に定められています。
東京都「東京都空き家家財整理・解体促進事業」
この制度は、都内の空き家の家財整理や解体にかかる費用の一部を補助する仕組みです。補助率は1/2、家財整理は上限5万円、解体は上限10万円が支給されます。
家財整理:上限50,000円
解体:上限100,000円
補助率:対象経費の1/2
| 区分 | 内容 | 補足 |
| 補助対象 | 家財整理または解体のいずれか | 両方同時の申請は不可 |
| 申請方法 | 東京都空き家ワンストップ相談窓口を通じて申請 | 相談・契約が必須 |
| 注意点 | 他の補助金との併用不可、予算枠に達すると終了 | 交付決定前に着手した工事は対象外 |
このように東京都の制度は、金額は比較的小規模ながら、解体や家財整理の自己負担を軽減できる制度です。特に、相談窓口を通じた申請が必須である点には注意しましょう。
大阪市「狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度」
大阪市では、狭小道路に面する古い住宅の解体費用を支援しており、対策地区と重点対策地区ごとに補助率や上限額が異なります。補助対象となるのは、解体および整地に要する費用の一部で、下表の条件に基づいて支給されます。
| 区分 | 内容 | 補足・対象エリア別詳細 |
| 補助率 | 対策地区:1/2以内重点対策地区:2/3以内 | 面積あたりの上限単価との比較による |
| 上限額 | 戸建て:対策地区75万円/重点地区100万円集合住宅:対策地区150万円/重点地区200万円 | 長屋等一部解体は戸建て同等限度 |
| 申請条件 | 解体工事前に事前申請および交付決定が必要 | 工事契約前に申請、承認後スタートが原則 |
対象建物
対策地区:幅員4m未満、昭和25年以前に建築の木造住宅
重点地区:幅員6m未満、昭和56年5月31日以前に建築の木造住宅
補助対象経費
解体および整地にかかる費用が対象で、建物内の残存物撤去費用などは含まれません。
申請期間・手続き
例として令和7年度は「4月1日〜12月26日」とされていましたが、年度や予算によって変わるため最新情報の確認が必要です。
このように、補助額は対策地区で最大75万円、重点地区で最大100万円(戸建ての場合)であり、補助率も地区によって異なる点が特徴です。制度は工事前の申請が必須で、対象経費や地区要件などにも細かい条件があるため、必ず大阪市の公式サイトでご確認ください。
参考:大阪市
名古屋市「老朽危険空家等除却費補助金」および「老朽木造住宅除却助成」
名古屋市では、周辺に著しい危険を及ぼす空き家の除却に対し、 最大80万円まで解体費用の一部を補助する「老朽危険空家等除却費補助金」と、 木造密集地域の老朽住宅に最大40万円の助成を行う「老朽木造住宅除却助成」の2制度を設けています。内容や対象条件が異なるため、どちらが適用されるか事前に確認が必要です。
| 制度名 | 補助内容 | 上限額 |
| 老朽危険空家等除却費補助金 | 評価点数75点以上:工事費の1/3評価点数125点以上:工事費の2/3 | 40万円(75点以上)80万円(125点以上) |
| 老朽木造住宅除却助成 | 木造住宅密集地域で老朽化が進んだ住宅を対象。解体費用または延床面積×9,600円のうち低い額の1/3 | 40万円 |
| 制度名 | 内容 | 補足 |
| 対象者 | 所有者本人または所有者全員の同意がある者、法人不可、市税滞納なし | 対象建物が「特定空家等」と判断されたもの |
| 対象物件 | 評価表による評価で75点以上(125点以上でより高額補助) | 現地調査に基づく評価 |
| 申請時期・手続き | 交付決定前の工事着手は禁止。年度内(2月末)までに完了報告が必要。 | 予算に達し次第受付終了 |
名古屋市の空き家解体支援制度には、空き家の危険度や構造、地域性に応じて2つの制度があります。どちらが適用されるかは建物の評価と条件次第です。申請前には必ず事前相談を行い、交付決定後に工事着手することを忘れないでください。
横浜市「住宅除却補助制度」および「建築物不燃化推進事業補助」
横浜市では、耐震性が低い木造住宅等や災害リスクの高い老朽建築物の解体費用に対し、補助を行っています。主な制度は以下の2つです。
住宅除却補助制度:耐震基準を満たさない木造住宅の解体に対し、課税世帯で上限20万円、非課税世帯で上限40万円の補助があります。
建築物不燃化推進事業補助:重点対策地域(不燃化推進地域)にある老朽建築物を対象に、最大150万円の補助が受けられる制度です。
| 制度名 | 補助率・上限額 | 内容のポイント |
| 住宅除却補助制度 | 上限:課税世帯20万円/非課税世帯40万円補助率:約1/3(解体費 or 延床面積×13,500円/㎡) | 昭和56年5月以前の木造住宅で耐震性が低いと認定された住宅が対象。法人除く所有者が申請可能。 |
| 建築物不燃化推進事業補助 | 補助率:重点対策地域 3/4、その他地域 2/3上限:150万円 | 不燃化推進地域内の老朽建築物(昭和56年以前築等)が対象。解体工事費用の一部が補助される。 |
補助対象者は、個人(法人不可)で、対象建物の所有者か、その同意を得た者。市税の滞納がないことが前提です。申請手続きの注意点として、事前相談および交付決定後の工事実施が必須です。すでに解体工事の契約を締結している場合は補助対象外となります。過去10年以内に同様の補助を受けた建物は対象外となる場合があります。
横浜市では、耐震性不足や火災リスクの高い老朽建築物の解体に対して、補助制度が整備されています。対象によって上限額や補助率が異なるため、制度の内容を正しく把握し、事前相談・交付決定・工事開始の順序を守ることが重要です。
参考:横浜市
「みんなの補助金コンシェルジュ」で空き家解体に使える補助金を検索する!
参考:国土交通省「空き家対策ポータルサイト」はこちら!
空き家を解体した後の注意点
空き家を解体すると補助金を活用できる一方で、税金や申請手続きに関して注意すべき点があります。結論として、固定資産税の負担増と補助金申請時のルール確認が大きなポイントです。
固定資産税は上がる?下がる?
固定資産税は、住宅が建っている土地に「住宅用地特例」が適用されることで軽減されています。
しかし、空き家を解体して更地にするとこの特例が外れるため、固定資産税が最大で約6倍に増える可能性があります。
住宅がある場合(住宅用地特例あり):200㎡以下の部分は課税標準が1/6に軽減
解体後の更地(特例なし): 本来の課税額で算定される
そのため、補助金を使って解体しても、税負担が増える可能性がある点に注意してください。自治体によっては「解体後の土地活用を条件にした補助金」もあるため、制度内容を必ず確認しましょう。
補助金を申請するときの注意事項
補助金の申請には厳格なルールがあります。特に重要なのは、交付決定前に解体工事を始めると補助対象外になることです。
申請時の注意点は以下の通りです。
- 解体後の報告書や領収書が必要
- 交付決定を受ける前に契約・工事を開始しないこと
- 整地や外構撤去など、補助対象外の工事が含まれないか確認すること
申請から交付決定までは数週間以上かかるケースも多いため、スケジュールに余裕を持って手続きを進めることが大切です。
空き家を解体した後は固定資産税が増加する可能性があり、さらに補助金は交付決定前の着工が不可という点に注意する必要があります。解体前に自治体へ相談し、税制や補助制度を踏まえた上で計画を立てることが安心につながります。
空き家解体補助金のよくある質問
Q1. 空き家の解体に国は補助金を出しているのですか?
A.国が直接お金を出す制度はありませんが、市区町村が国の交付金を活用して補助金制度を設けているケースが多いです。つまり、実際に補助金を申請するのは、お住まいの市区町村の窓口(例:空き家対策室や都市整備課)です。必ず自治体の公式サイトや窓口で制度の有無を確認しましょう。
Q2. 空き家を取り壊すとき、補助金はいくらもらえますか?
A.自治体によって金額は異なりますが、一般的には30万〜100万円程度が上限です。補助率(解体費用のうち何%が対象か)や上限額は自治体ごとに設定されているため、見積もりを取る前に条件を確認することが大切です。
Q3. 解体したいけど、お金がなくて困っています。どうしたらいいですか?
A.補助金の活用に加えて、分割払いやローンに対応した解体業者もあります。また、相続放棄・空き家バンクへの登録・土地ごとの売却など、費用負担を軽くする方法も検討しましょう。生活保護や災害による損壊があった場合は、別の支援制度が使えることもあります。
Q4. 空き家を解体すると固定資産税が上がると聞いたのですが?
A.はい。住宅がなくなると「住宅用地の特例」がなくなり、固定資産税が最大で6倍程度に上がることがあります。そのため、解体後は更地としての活用方法(駐車場、アパート建設、売却など)もあわせて考えることが大切です。
まとめ
空き家を放置すると、倒壊や近隣トラブル、税金の負担増といったリスクが高まります。とはいえ、解体には高額な費用がかかるため、簡単に決断できないのが現実です。
そこで活用したいのが、自治体の「空き家解体補助金」制度です。補助金を使えば、費用の一部を軽減でき、さらに地域の防災・美観にも貢献できます。
ただし、補助金には「事前申請が必要」「条件を満たす必要がある」などの注意点もあるため、まずはお住まいの自治体に相談することから始めましょう。空き家を資産として活かすためにも、補助制度を上手に使って、計画的な解体と活用を検討してみてください。