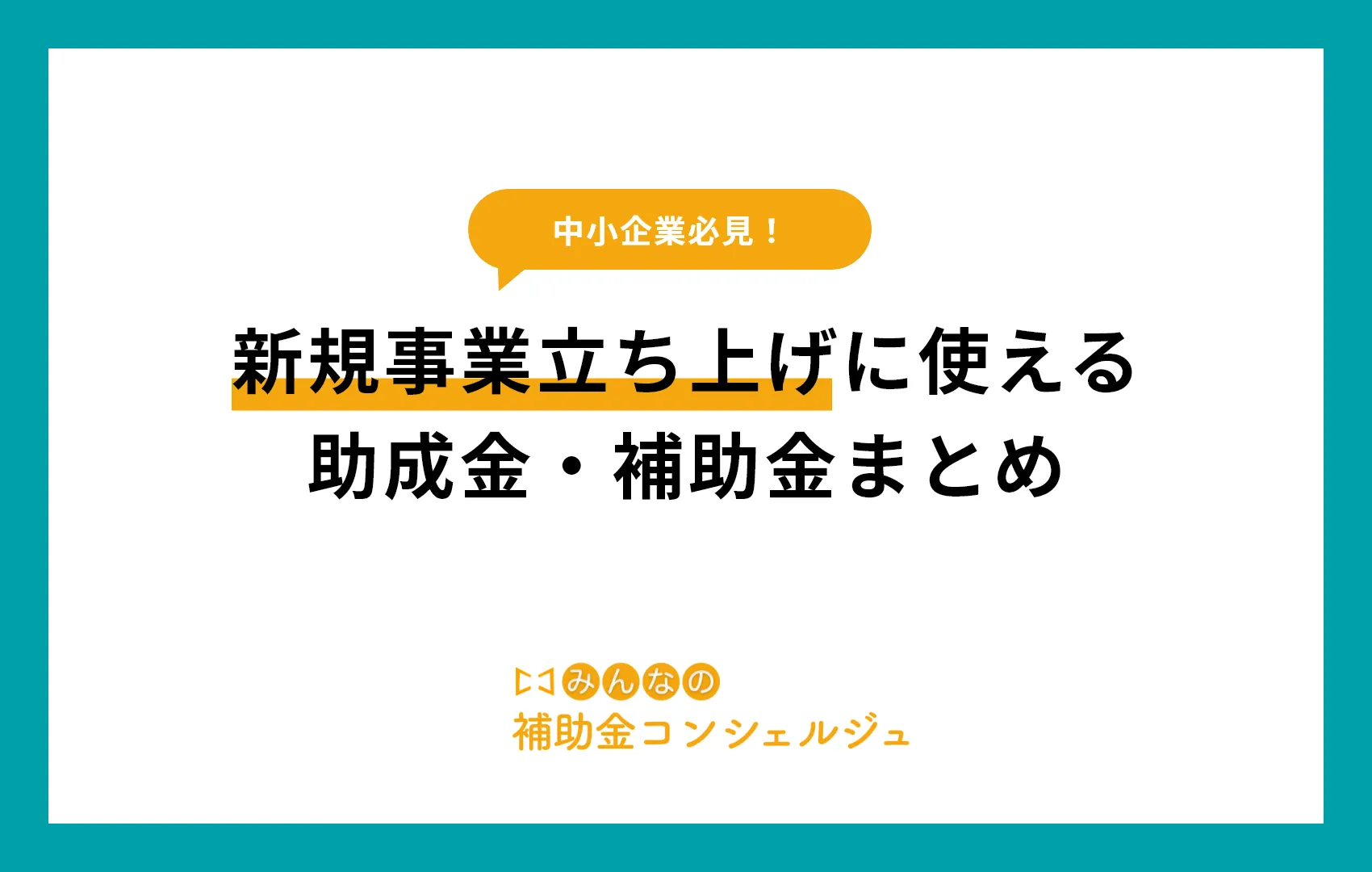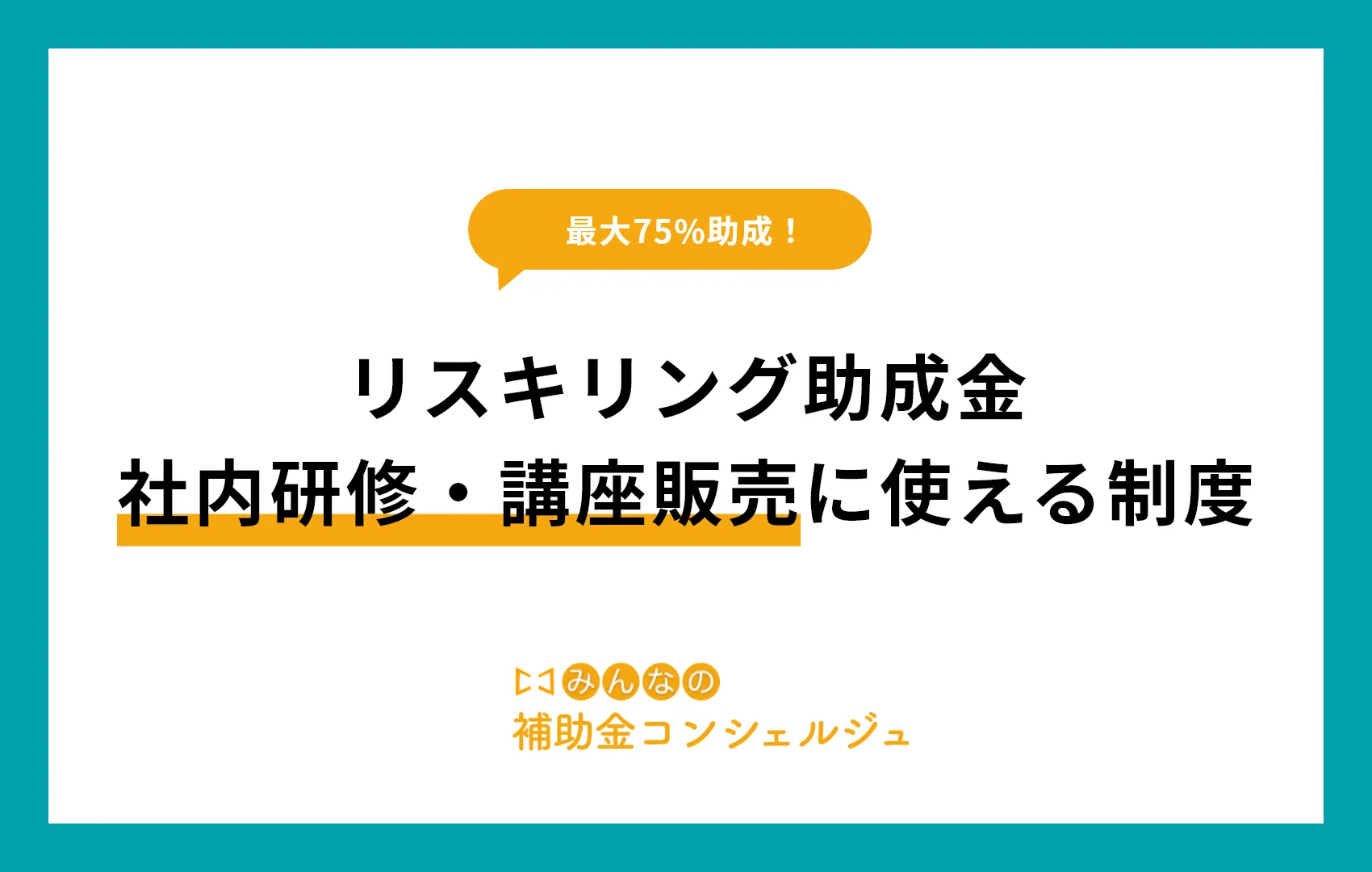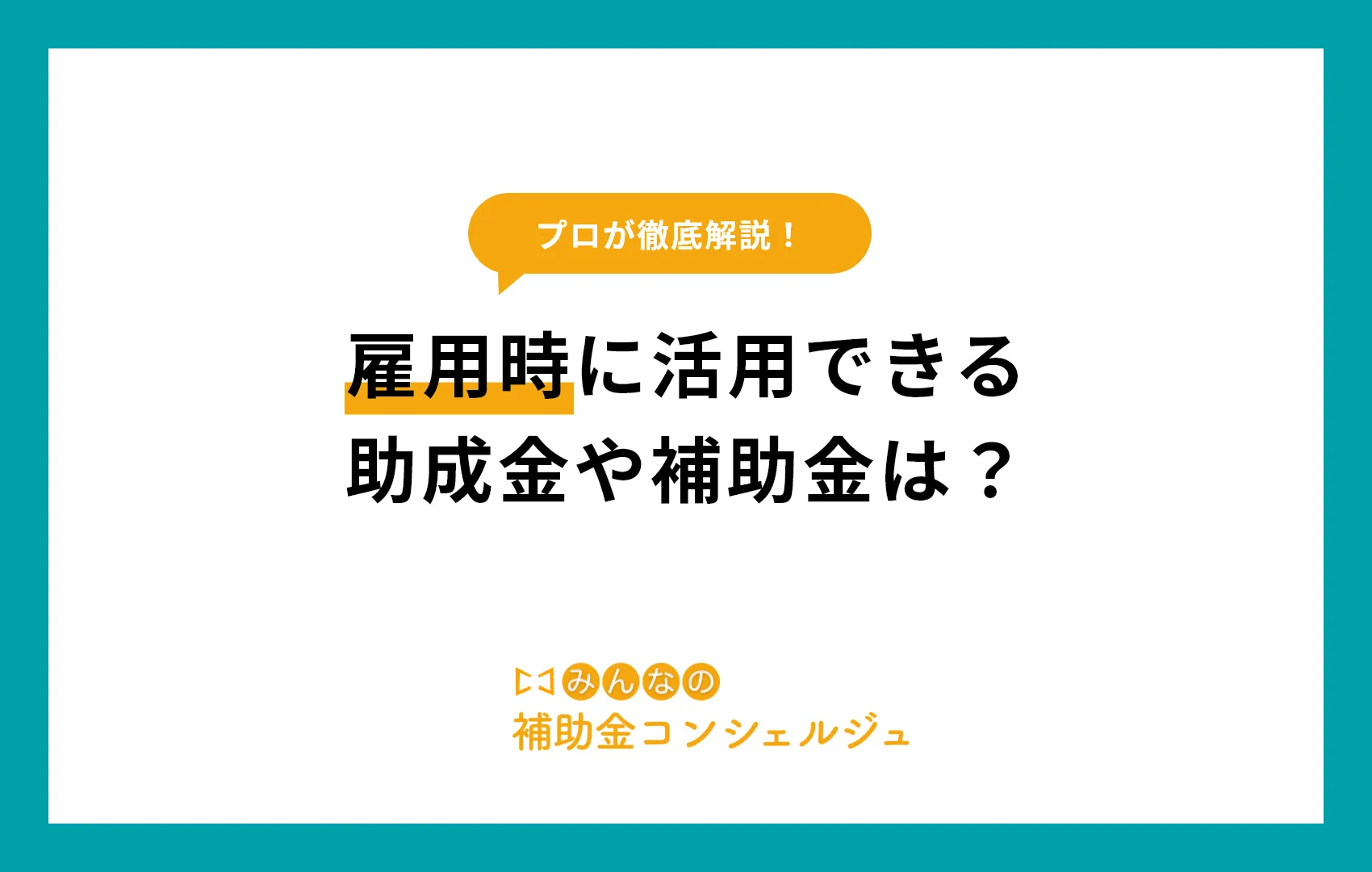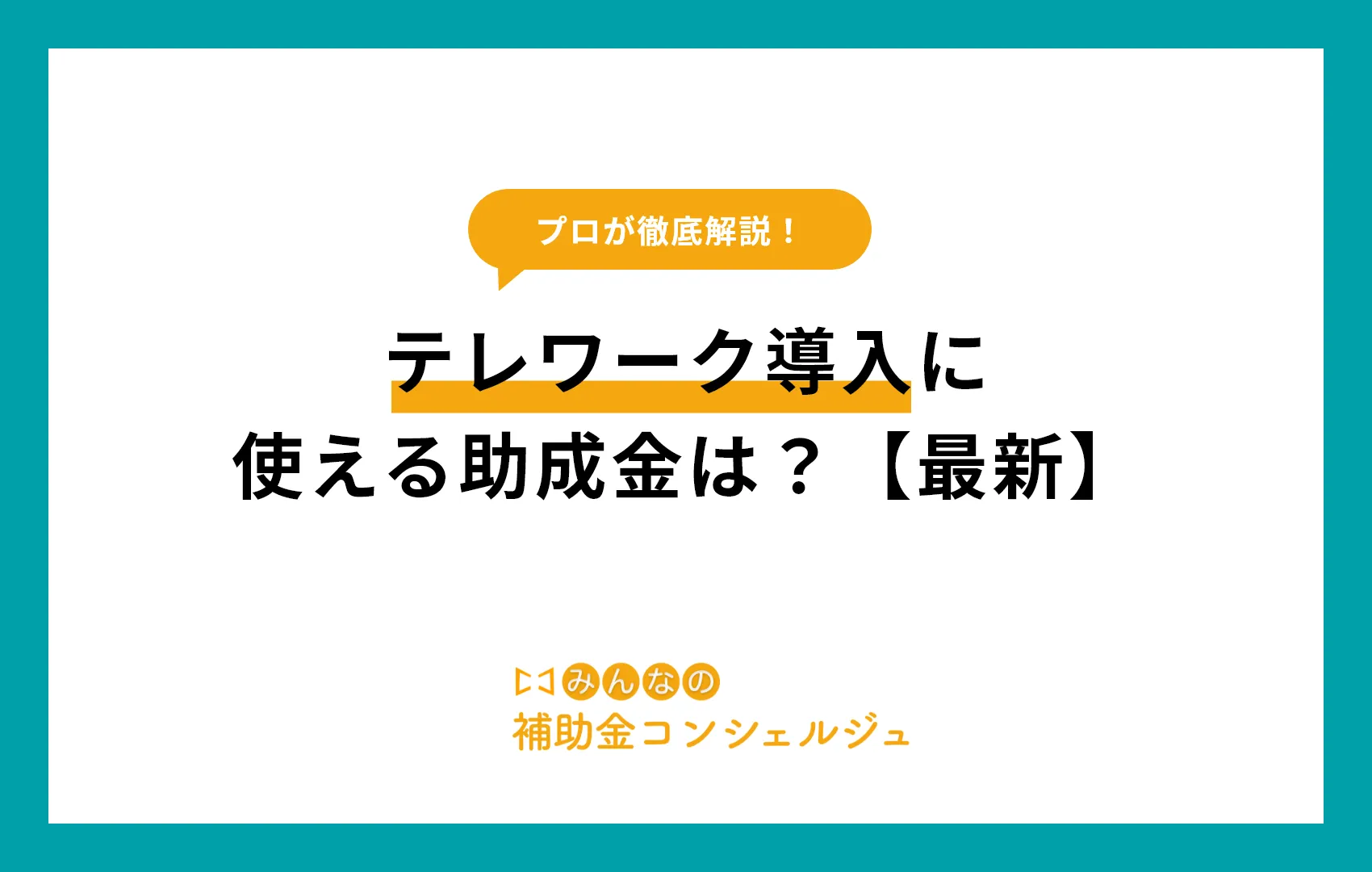新規事業立ち上げに使える助成金・補助金一覧
新規事業の立ち上げには、初期投資や運転資金など多くの費用がかかります。こうした課題に対応するため、国や自治体では各種の助成金・補助金制度を設けています。このコラムでは、2025年時点で活用できる主な制度を、国の制度・自治体の制度・個人事業主向けに分けて紹介します。
| 制度名 | 補助額・補助率 | 主な対象 | 用途・特徴 |
| 中小企業新事業進出促進事業 | 最大5,000万円/2/3以内 | 中小企業・個人事業主 | 新市場・新分野への進出支援 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 最大200万円/2/3〜3/4 | 小規模事業者(法人・個人) | 販路開拓・広告・設備導入など |
| IT導入補助金 | 最大450万円/2/3以内 | 中小企業・個人事業主 | 会計ソフト・ECなどITツール導入 |
| ものづくり補助金 | 最大3,000万円/ 1/2~2/3 | 中小企業・個人事業主 | 新製品や新サービスを開発するための投資 |
| 創業助成金(例:東京都) | 最大300万円/2/3以内 | 創業5年以内・都内の起業者など | 人件費・賃料・広報費 |
新規事業の立ち上げに助成金・補助金を活用したい方は、弊社にお任せください!御社に最適な制度をご提案します。弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績がございます。
【無料】新規事業の立ち上げ助成金・補助金の相談をする!
中小企業新事業進出促進事業
「中小企業新事業進出促進補助金」は、既存事業とは異なる新市場や新分野に挑戦する中小企業を支援する制度です。高額な設備投資や新サービス立ち上げに使えるため、本格的に新規事業を始めたい企業に適しています。
活用できる場面
- 製造業が新分野に進出するケース:金属加工技術を活かして半導体部品を製造
- 医療メーカーの新製品立ち上げ:医療機器のノウハウを応用して新市場へ参入
- サービス業のデジタル化:従来の対面サービスをクラウドやオンラインへ展開
補助額・補助率
| 補助額(上限) | 補助率 |
| 9,000万円 | 1/2 |
基本要件
- 新しいことに挑戦すること:これまでと違う商品やサービスをつくり、新しいお客さんに提供すること。
- 売上や利益をしっかり伸ばすこと:会社全体の付加価値(=売上から仕入や外注費を引いた利益に近いもの)や、従業員1人あたりの成果を、年平均で4%以上アップさせること。
- 給料を増やすこと:給与の総額を年平均で2.5%以上アップするか、最低でも国が定める賃金の上昇に合わせて上げること。
- 最低賃金を少し上乗せすること:社員に支払う最低時給を、地域ごとの最低賃金より30円以上高く設定すること。
- 子育て支援の取り組みを公表すること:次世代育成支援のための計画(例:子育てしやすい職場づくり)を策定して、公表すること。
対象経費
- 機械装置・システム構築費
- 建物費・運搬費
- 技術導入費・知的財産関連経費
- 外注費・専門家経費
- クラウドサービス利用費
- 広告宣伝・販売促進費
活用事例(製造会社の事例)
課題:既存の建材部品の需要が伸び悩み、新市場開拓が急務。しかし新ライン立ち上げの投資資金が不足。
施策:補助金を活用し、半導体製造装置部品の新ラインを構築。設備導入費用の半分が補助され、実質2,250万円の企業負担で4,500万円規模の投資を実現。
効果:新規取引に成功し初年度3億円の売上。付加価値額+5.2%、給与+3.0%増加を達成。社員のモチベーションも向上。
このように、新事業進出補助金は「本格的に新市場へ挑戦する企業」向けの大型支援制度と言えます。
中小企業新事業進出促進事業の概要をチェックする!
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)」は、小規模事業者の販路開拓や業務効率化を支援する制度です。ホームページ制作や広告費、店舗改装など幅広い経費に使えるため、比較的使いやすい補助金として人気があります。
活用できる場面
- 新規顧客を開拓したい:チラシやWeb広告を使って集客を強化
- ネット販売を始めたい:ECサイト制作やオンライン予約システム導入
- 店舗を改善したい:外装や内装のリニューアルで来客増を狙う
補助額・補助率
| 補助額(最大) | 補助率 |
| 200万円 ※ | 2/3 |
※インボイス対応類型や賃上げ・事業再建などの加点要件を満たす場合に最大200万円(通常は上限50万円〜100万円)。
基本要件
- 小規模事業者であること:従業員が商業・サービス業で5人以下、製造業などで20人以下
- 販路開拓や業務効率化につながる取組であること:単なる運転資金や人件費ではなく、売上アップや効率化に直結する投資であること
- 賃上げなどの取り組みを行うこと:類型によっては、賃上げや事業再建といった条件を満たす必要あり
- GビズIDプライムの取得:電子申請のため必須
対象経費
- 外注費
- 専門家謝金・旅費
- 機械装置・システム導入費
- 広告宣伝費(チラシ・Web広告・動画制作など)
- 販売促進費(展示会出展、ECサイト制作など)
- 店舗改装費(バリアフリー化やレイアウト改善)
活用事例(小売業の場合)
課題:常連客中心で売上が伸び悩み。新規顧客を獲得したいが、販促にかける予算が不足していた。
施策:補助金を活用し、ECサイトの立ち上げとSNS広告キャンペーンを実施。補助率2/3のため、150万円の施策に対し100万円を補助金でカバー。
効果:オンライン販売開始後、県外からの注文が増加。1年で売上が20%アップ。新規顧客比率も上昇し、安定的に販路拡大できた。
小規模事業者持続化補助金の概要をチェックする!
IT導入補助金
「IT導入補助金」は、中小企業が業務効率化や売上拡大につながるITツールを導入する際に活用できる制度です。クラウドサービス、POSレジ、予約システム、AIツールなど幅広く使えるため、新規事業の立ち上げにも役立ちます。
活用できる場面
- ネット販売を始めたい:ECサイトや決済システムを導入
- 業務を効率化したい:会計・受発注・在庫管理のクラウド化
- 新サービスを展開したい:顧客管理システム(CRM)やAIチャットボットを導入
補助額・補助率
| 補助額(最大) | 補助率 |
| 450万円 | 1/2〜3/4 |
※「デジタル化基盤導入類型」で、PC・タブレット・クラウド利用料などに対応。セキュリティ対策や電子取引対応も対象。
基本要件
- 登録ITツールを導入すること:経産省に認定されたITベンダー・サービスのみ対象
- 業務効率化や売上拡大につながること:単なる備品購入や趣旨外の経費は不可
- 賃上げ目標を掲げること:補助額が一定以上の場合、賃上げの取り組みが必須
- 電子申請ができること:GビズIDプライムの取得が必要
対象経費
- ITツール導入費(会計・受発注・在庫管理・顧客管理など)
- クラウドサービス利用料(最大2年分)
- PC・タブレット・レジ・券売機(類型による)
- セキュリティソフト・電子取引対応システム
活用事例(飲食業)
課題:新規出店に伴い、予約管理や会計処理の効率化が必要だったが、システム導入費用が大きな負担だった。
施策:補助金を活用し、オンライン予約システム+クラウド会計ソフト+POSレジを導入。総額300万円の導入費用に対し、200万円を補助金でカバー。
効果:予約の無断キャンセルが減少、店舗回転率が改善。会計処理の時間が大幅に削減され、スタッフの負担軽減と新サービス開発へのリソース確保につながった。
IT導入補助金の概要をチェックする!
ものづくり補助金
「ものづくり補助金」は、中小企業が新製品や新サービスを開発するための投資を支援する制度です。新しい市場に挑戦する事業立ち上げにも活用できます。単なる工程改善(効率化や省力化だけ)では対象になりません。必ず「新しい製品・サービスをつくること」が前提です。
活用できる場面
- 製造業が新分野に挑戦:医療機器部品など、新しい製品カテゴリーを立ち上げる
- サービス業がITを活用:AIやIoTを組み込んだ新サービスを開発
- 食品業が新商品を展開:新しい加工設備を導入して付加価値の高い商品を作る
補助額・補助率(最大)
| 補助額(最大) | 補助率 |
| 3,000万円 | 中小企業 1/2、小規模事業者 2/3 |
※通常枠は規模により750万〜2,500万円。グローバル展開など特定枠で最大3,000万円。
基本要件
- 事業所内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上
- GビズIDプライムの取得(電子申請必須)
- 賃上げに取り組むこと(一定以上で補助上限が加算)
- 新製品・新サービスを開発すること(工程改善だけは不可)
- 事業終了後3〜5年で付加価値額を年平均+3% or+5%向上させること
対象経費
- 機械装置・システム構築費(必須)
- 技術導入費・知的財産関連費
- 外注費・専門家経費
- 運搬費・クラウド利用料・原材料費
活用事例(機械部品メーカー)
課題:既存の自動車部品市場が縮小し、新たな収益源を模索していた。
施策:補助金を活用して、半導体製造装置向けの精密部品を開発。新しい工作機械を導入し、試作品の製造から量産体制を整備。
効果:新分野で大手半導体メーカーとの取引を獲得。売上は初年度で2億円増加。従業員の賃上げも実施でき、成長基盤を強化。
ものづくり補助金は、「新しいものを生み出す企業」専用の支援策と言えます。新規事業立ち上げでも「開発」の要素があれば強力な後押しになります。
東京都の創業助成金
「東京都創業助成金(創業助成事業)」は、新規事業立ち上げにそのまま使える制度です。事務所の賃料、広告宣伝費、備品購入、人件費など創業初期に必要な幅広い経費をサポートしてくれるため、事業準備段階から活用できます。
ただし、
- 東京都内で創業すること
- 公社が実施する創業支援プログラムを修了していること
申請にはこうした条件を満たす必要があります。
補助額・補助率(最大)
| 補助額(最大) | 補助率 |
| 400万円 | 2/3 |
活用できる場面
- 事務所を構えたい:賃料や内装費を助成対象に
- 集客を強化したい:チラシ・Web広告・SNSプロモーションに活用
- 新サービスを始めたい:PCや機材を揃え、販路開拓につなげる
活用事例(デザイン事務所の事例)
課題:デザイン事務所を立ち上げたいが、賃料・PC購入・広告費が不足
施策:創業助成金で総額300万円の経費を申請し、200万円の助成を受ける
効果:開業初月からクライアント獲得に成功、初年度黒字化の見込み
東京都の創業助成金は、創業初期の資金不足を補い、新規事業立ち上げを加速できる心強い制度です。
参考:東京都中小企業振興公社|創業助成事業
大阪府、札幌市、福岡市など他の自治体にも同様の創業支援制度があります。地域によって内容や条件が異なるため、必ず各自治体の公式サイトで最新情報をご確認ください。
創業者向け補助金・給付金(都道府県別)をチェックする!
新規事業の立ち上げに助成金・補助金を活用したい方は、弊社にお任せください!御社に最適な制度をご提案します。弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績がございます。
【無料】新規事業の立ち上げ助成金・補助金の相談をする!