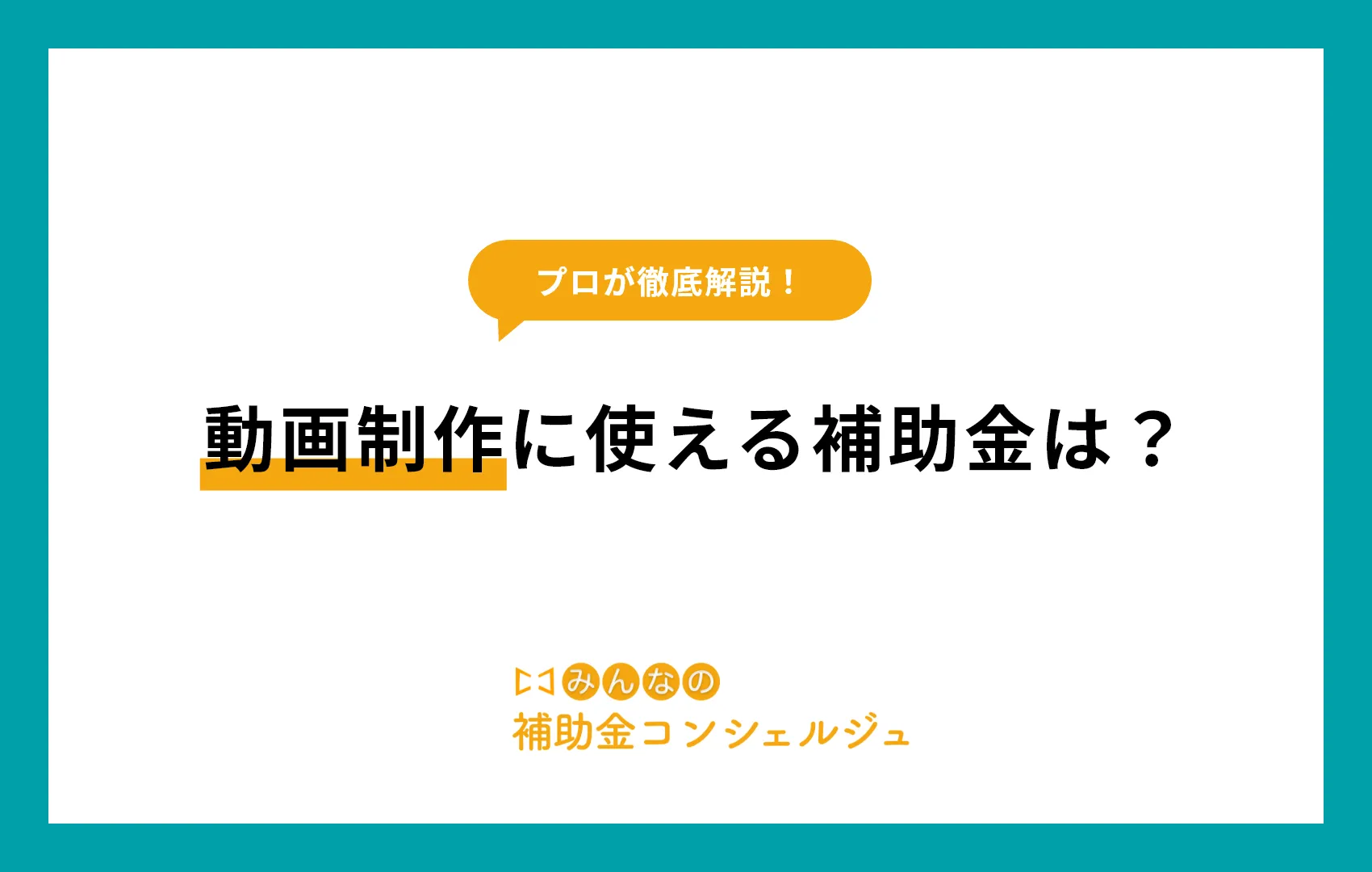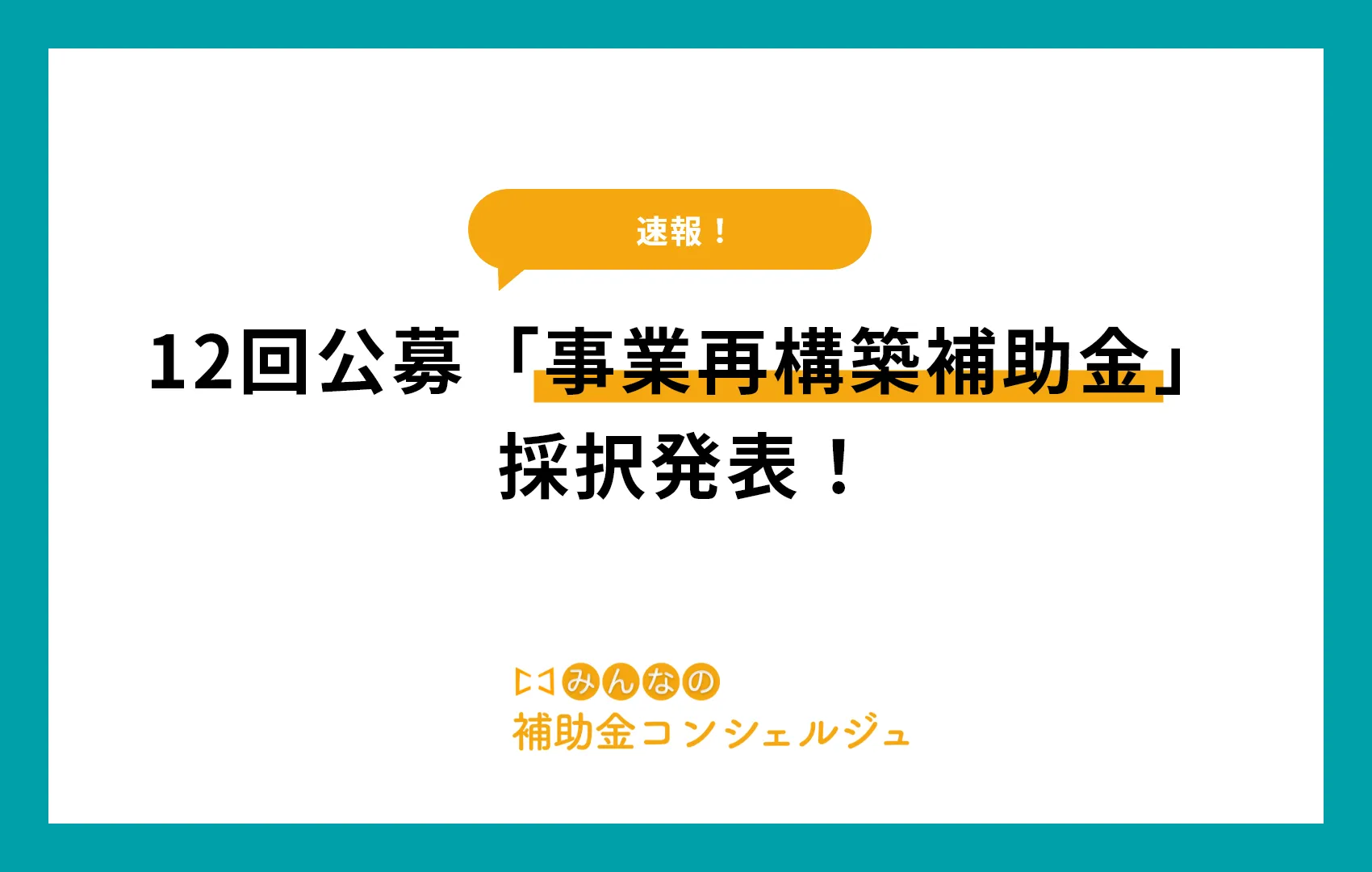動画制作に使える補助金は?【最新版】
事業に使う動画制作費用に国や自治体の補助金が活用できます。本コラムでは、動画制作に使える代表的な補助金を紹介します。
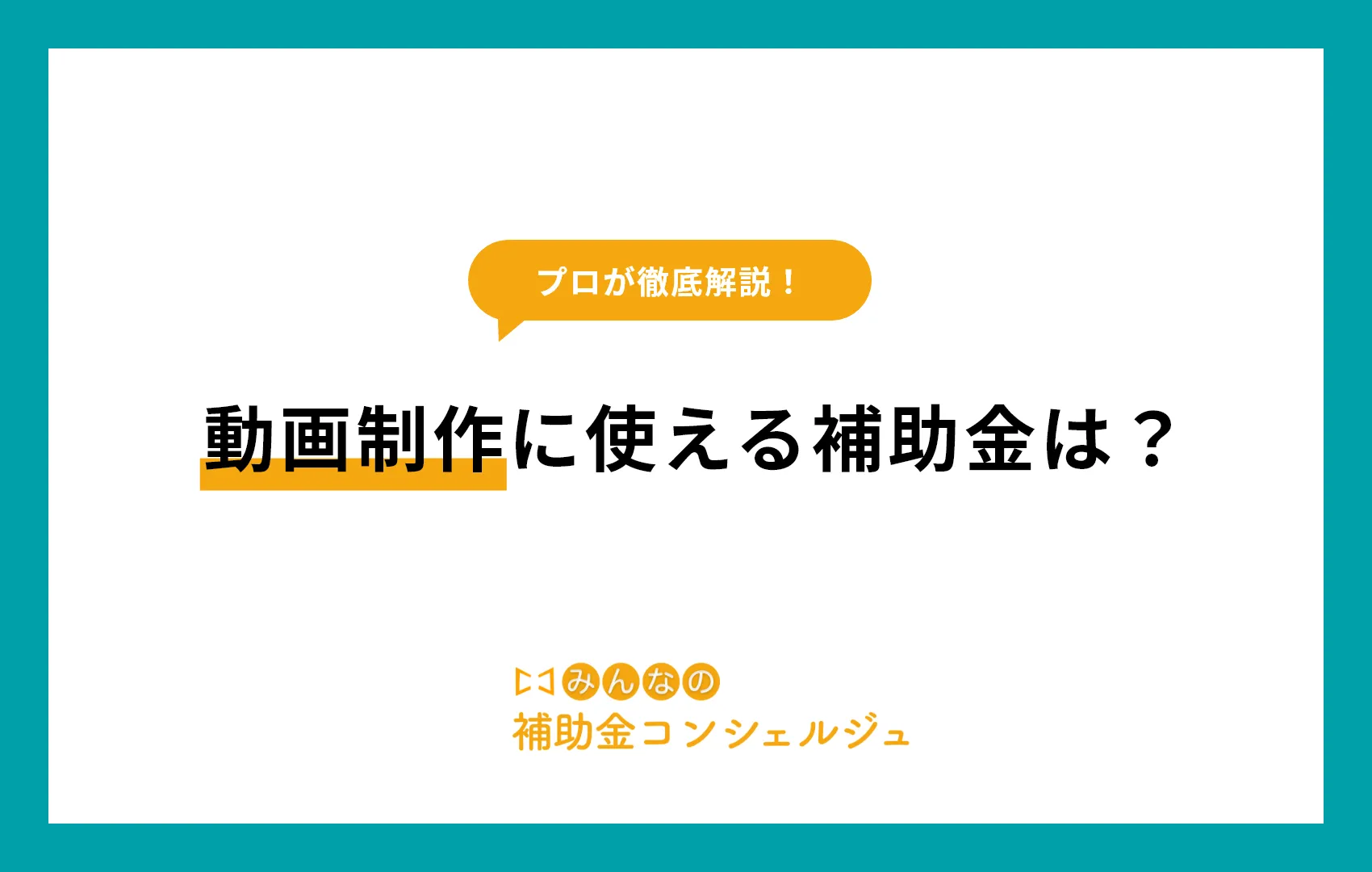
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
動画制作に補助金が使える!
動画制作に活用できる補助金は、国の制度と自治体の制度があります。目的や規模によって最適な制度が異なるため、以下の見出しを参考に、自社に合う補助金を選びましょう。
小規模事業者で販路開拓を始めるなら「小規模事業者持続化補助金」
動画を使って販路開拓をしたい方には、この補助金が最も使いやすい制度です。小規模事業者持続化補助金は、販路開拓・集客支援を目的とした国の代表的な制度です。
動画制作費は「ウェブサイト関連費」で申請できますが、単独では申請できず、補助金額の1/4(最大50万円)までという上限があります。チラシやホームページとあわせて動画を作りたい小規模事業者に最適です。比較的少額から取り組め、採択実績も豊富です。
具体事例
事業者概要:大阪府でカフェを経営する個人事業主(従業員3名)
課題:
地元客の来店は安定していたものの、観光客や新規顧客への認知が広がらず、SNS発信も十分にできていませんでした。広告に大きな予算をかけることが難しく、効果的な販促手段を模索していました。
補助金を使った取り組み:
小規模事業者持続化補助金を活用し、
- 店舗紹介動画とドリンク作りの様子を撮影(ウェブサイト関連費)
- 新メニューを紹介するチラシを制作(広報費)
- 店頭看板を刷新(機械装置等費)
- といった複数の経費を組み合わせて申請しました。
成果:
制作した動画をInstagramとホームページに掲載した結果、観光客の来店が増加し、動画公開から3か月で新規客数が約25%増加。「おしゃれな雰囲気が伝わる」と口コミサイトの評価も向上し、リピーター獲得にもつながりました。
小規模事業者持続化補助金の概要をチェックする!
参考:小規模事業者持続化補助金
海外向けPR動画を作るなら「ものづくり補助金(グローバル枠)」
海外展開を視野に入れたPR動画を制作するなら、ものづくり補助金のグローバル枠が有効です。
ものづくり補助金は、生産性向上や海外市場開拓を支援する国の代表的な制度です。「グローバル市場開拓枠」では、海外販路開拓のためのPR動画やパンフレット制作費が「広告宣伝・販売促進費」として認められています。
ただし、国内向け動画は対象外です。設備投資や新製品の海外PRとセットで申請することで、効果的に活用できます。
具体事例
事業者概要:愛知県の金属加工メーカー(従業員35名・創業25年)
課題:
国内では取引先が安定していたものの、将来の成長を見据えて海外自動車部品メーカーとの取引拡大を検討していました。しかし、英語での技術紹介資料や動画がなく、自社の強みを海外バイヤーに効果的に伝えられないという課題がありました。
補助金を使った取り組み:
ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠)を活用し、
- 最新CNC旋盤の導入(機械装置費)で高精度部品の量産体制を構築
- 英語ナレーション付きの技術紹介動画を制作(広告宣伝・販売促進費)
- 海外展示会出展に向けたパンフレット作成と通訳費(外注費)
- といった取組を一体的に実施しました。
成果:
制作したPR動画を海外展示会で放映した結果、ドイツの部品メーカー2社から新規発注を獲得。初年度で海外売上比率が5%から15%に上昇し、海外取引の基盤づくりに成功しました。
また、動画は自社サイトでも公開し、海外からの問い合わせが月10件以上に増加しました。
ものづくり補助金の概要をチェックする!
参考:ものづくり補助金
新事業の立ち上げに広告を活用するなら「新事業進出補助金」
新しい事業を本格的に立ち上げ、動画を戦略的に活用したい方には、新事業進出補助金がおすすめです。
この補助金は、既存事業とは異なる新分野・新業種への挑戦を支援する制度です。動画制作費は「広告宣伝・販売促進費」に含まれますが、補助下限は750万円(事業費はおおむね1,500万円規模)と比較的大きな事業を対象としています。広告だけでなく、新事業の内容・売上・付加価値の計画性が重視されるため、新サービスや新ブランドの立ち上げと併せて申請するケースに適しています。
具体事例
事業者概要:福岡県の印刷会社(従業員25名・創業40年)
課題:
長年にわたり紙媒体の印刷を主力としてきたが、コロナ禍を機に需要が減少。デジタル領域に進出したいと考えたものの、ノウハウや認知が不足しており、新しい顧客層に訴求できていなかった。
補助金を使った取り組み:
新事業進出補助金を活用し、
- 自社スタジオを新設して「動画編集サービス」事業を新規立ち上げ(機械装置・システム構築費)
- 新サービス紹介用のPR動画を制作(広告宣伝・販売促進費)
- 動画編集セミナーを実施して新規顧客との接点を創出(外注費・専門家経費)
- という3本柱で申請・実施。
動画では、紙の印刷からデジタル映像制作までを一貫して担えることをわかりやすく紹介しました。
成果:
補助事業終了後、PR動画をきっかけに地元企業からの制作依頼が10件以上寄せられ、初年度で新サービスの売上が全体の20%を占めるまでに成長。従来の印刷業から「デジタルクリエイティブ事業」への転換に成功し、社員のスキルアップと新規顧客の獲得につながりました。
新事業進出補助金の概要をチェックする!
参考:新事業進出補助金
国と自治体の補助金、どちらを使うべき?
国と自治体、どちらの補助金を活用すべきか迷う場合は、事業の規模と目的に応じて最適な制度を選び分けましょう。
| 目的・規模 | 向いている補助金 |
| 全国・海外向けに大規模なPRや新事業を展開したい | 国の補助金(小規模事業者持続化・ものづくり・新事業進出) |
| 地域密着のPRや初めての動画制作、低予算の販促をしたい | 自治体の補助金(都道府県・市区町村) |
国の補助金が向いているケース
国の補助金は、広報や販促の規模が大きく、成長投資の一環として動画を活用したい企業に適しています。
採択までに時間や手間はかかりますが、補助上限が高く、全国・海外への展開を目指す場合に効果的です。
たとえば、
- 新商品・新ブランドの立ち上げ(新事業進出補助金)
- 海外市場に向けた製品PR(ものづくり補助金・グローバル枠)
- 全国規模で販路を広げるWeb動画制作(小規模事業者持続化補助金)
- といった活用が可能です。
自治体の補助金が向いているケース
一方で、地域密着でのPRや小規模な動画制作を検討している場合は、自治体の補助金が現実的です。自治体補助金は、地域経済の活性化やデジタル化支援を目的としており、動画制作を対象にした制度も多くあります。採択率が比較的高く、「まずは試しに動画を作ってみたい」「地元顧客に向けた発信を強化したい」といった企業に最適です。
例:
- 東京都「展示会出展助成プラス」(上限150万円)
- 岐阜県西美濃3市9町「ホームページ・動画制作支援補助金」(上限24万円)
併用する際の注意点
国と自治体の補助金は、原則として併用が可能です。ただし、同じ経費(例:同じ動画制作費)を二重で申請することは禁止されています。
たとえば、
- 国の補助金で動画制作費を申請した場合、同じ費用を自治体補助金に重複申請することは不可。
- しかし、「国の補助金で広告制作」「自治体補助金で展示会出展費用」といった目的を分けた申請であれば認められるケースもあります。
必ず各制度の公募要領を確認し、経費区分を明確に分けて申請しましょう。
動画制作に使える自治体の補助金
自治体の制度は、小規模・地域密着の事業者に有利な内容が多く、国の補助金と併用できる場合もあります。ここでは動画制作に使える自治体の制度を3つ紹介します。
東京都:「展示会出展助成プラス」≪第10回≫
都内中小企業の販路拡大・PR活動を支援する助成制度です。動画制作費そのものではなく、展示会出展や販促活動にかかる経費として動画を含めることができます。
| 項目 | 内容 |
| 助成限度額 | 150万円 |
| 助成率 | 2/3以内 |
| 申請期間 | 2026年1月1日〜2026年1月20日 |
東京都では、展示会出展や販促動画の制作を伴うPR活動も対象に含まれます。広報動画を制作して出展ブースやSNSで活用するケースに最適です。「展示会出展助成プラス」は、9回、10回とコンスタントに実施されているので、申請期間以降も11回が実施される可能性が高いです。
参考:東京都中小企業興進公社
長野県:「令和7年度中小企業海外販路開拓助成金」
海外マーケットへの販路拡大を目的とした制度で、展示商談会・海外PR活動に動画を活用する場合に利用可能です。
| 項目 | 内容 |
| 助成限度額 | 100万円 |
| 助成率 | 2/3以内 |
| 申請期間 | 2025年10月14日〜2025年11月28日 |
海外商談会での商品紹介動画や、越境EC向けのプロモーション映像も対象になります。国の「ものづくり補助金(グローバル枠)」と目的を分けて活用するのも有効です。
参考:長野県産業興進機構
岐阜県西美濃3市9町:「ホームページ・動画制作支援事業補助金」
地域企業のデジタル活用を支援する補助金で、販路拡大目的の動画制作費が対象となります。
| 項目 | 内容 |
| 助成限度額 | 24万円 |
| 助成率 | 1/2以内 |
| 申請期間 | 2025年5月21日〜 |
ソフトピアジャパンエリア内の制作会社に依頼することが条件。初めて動画制作に挑戦する小規模事業者に適しています。
参考:大垣市
お住まいの自治体の動画制作に使える制度を探す!
申請プロセスの流れと必要書類
補助金の申請は、「計画を立てて申請し、採択後に実施・報告する」という明確な流れがあります。ここでは、多くの補助金に共通する手順と、準備すべき書類をわかりやすく解説します。
申請の基本ステップ
補助金は、申請前の準備から入金までに複数の手続きがあります。手順を間違えると補助対象外になる場合があるため、各ステップの順番を正確に把握しましょう。
| ステップ | 内容 | ポイント |
| 1. 申請準備 | GビズIDを取得し、事業計画書を作成する | 補助金申請にはGビズIDが必須。取得に数日かかる場合があります。 |
| 2. 電子申請・審査 | 申請システムから電子申請を行い、審査・採択を待つ | 申請後は修正ができないため、提出前に内容を必ず確認。 |
| 3. 実施・報告 | 採択後に計画を実行し、実績報告書を提出 | 発注・支払い・納品の順番を守る。期間外の支出は補助対象外です。 |
例えば、新事業進出補助金では、「交付決定日から原則14か月以内」が実施期間として定められています。この期間内にすべての発注・支払い・完了報告を終える必要があります。
書類の準備も早めに進めましょう。申請では、事業の信頼性と経費の妥当性を証明する書類が求められます。以下の書類を早めに揃えておくとスムーズです。
| 種類 | 内容 | 目的 |
| 事業計画書 | 取り組み内容・目的・成果指標をまとめた書類 | 審査の中心資料。補助金の趣旨との整合性が重要です。 |
| 見積書・決算書類 | 費用根拠や事業の経営実態を示す書類 | 経費の妥当性を判断するために必要です。 |
| 登記事項証明書・賃上げ計画書など | 企業情報や要件を証明する書類 | 要件適合(例:中小企業要件、賃上げ実施)を確認するために提出します。 |
書類の名称や枚数は補助金ごとに異なります。必ず最新の公募要領を参照し、不備のないように準備しましょう。補助金は、「正しい順番での手続き」と「証拠書類の整備」が成功の鍵です。特に、実施期間中の支出や発注順序は厳密にチェックされます。まずはスケジュールを立て、必要書類を早めに準備しておきましょう。
動画制作に国の補助金を使う際の注意点
動画制作を補助金で行う際は、制度の目的・経費の範囲・事業計画との整合性をしっかり理解しておくことが大切です。動画の内容や活用方法が補助金の趣旨から外れていると、不採択や経費の返還を求められる可能性もあります。
申請前に、特に次の3点を確認しましょう。
- 対象外となる動画の条件を確認する
- 制度の目的に沿った活用計画を立てる
- 動画を「事業の一部」として位置づける
1. 対象外となる動画の条件を確認する
まず確認すべきは、どんな動画が補助対象外となるかです。有料配信や広告収益を目的とした動画、または補助事業期間内に公開されなかった動画は対象外とされます。
たとえば「小規模事業者持続化補助金」では、動画制作費を「ウェブサイト関連費」として申請できますが、この費目だけでの申請は認められておらず、補助金申請額の1/4(最大50万円)までという上限があります。チラシ制作や設備導入など、他の経費と組み合わせて計画的に申請する必要があります。
2. 制度の目的に沿った活用計画を立てる
補助金で認められる動画は、制度ごとの目的に合致していることが前提です。目的が販路開拓であれば商品紹介や企業PR動画、海外展開支援であれば英語字幕付きの製品紹介動画など、動画が「どの市場の拡大に寄与するのか」を明確にしておく必要があります。
たとえば「ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠)」では、海外販路開拓のためのPR動画やパンフレット制作が対象経費として認められています。一方で、国内向けの一般的な広告動画は補助対象外です。このように、制度の目的と動画の役割を一致させることが採択の第一条件です。
3. 動画を「事業の一部」として位置づける
補助金の審査では、広告や動画はあくまで事業全体を構成する要素のひとつとして見られます。動画単体の出来栄えよりも、事業計画の中でどのような成果を生み出すかが評価のポイントです。
たとえば「中小企業新事業進出補助金」では、新事業の定義に適合しているか、売上・付加価値の目標が妥当か、そして動画が新サービスの市場浸透にどう寄与するかといった全体の整合性が審査対象となります。つまり、動画は“主役”ではなく、新事業の成果を伝えるための手段として位置づけることが重要です。
まとめ
動画制作は、今や企業の販路開拓やブランド強化に欠かせない手段です。動画制作には国や自治体の補助金を活用することで、費用を抑えながら効果的に実施できます。
いずれの制度も共通して重要なのは、
- 動画が補助対象となる条件を理解すること
- 制度の目的(販路開拓・海外展開・新事業化など)に沿った活用を計画すること
- 動画を事業全体の中でどう位置づけるかを明確にすること
この3点を押さえると、採択の可能性は高まります。
単なる広告ではなく、「事業の成果を生むための動画」として企画・申請することが成功の鍵です。補助金の申請は制度ごとに要件や流れが異なります。最新の公募要領を必ず確認し、必要に応じて専門家や支援機関に相談しながら準備を進めましょう。
監修者からのワンポイントアドバイス
動画制作には本記事のような様々な補助金が活用出来ます。ただし補助金によっては動画制作単独では申請できなかったり、補助金額の制限がある場合がありますので必ず公募要領で申請要件を確認するようにしましょう。