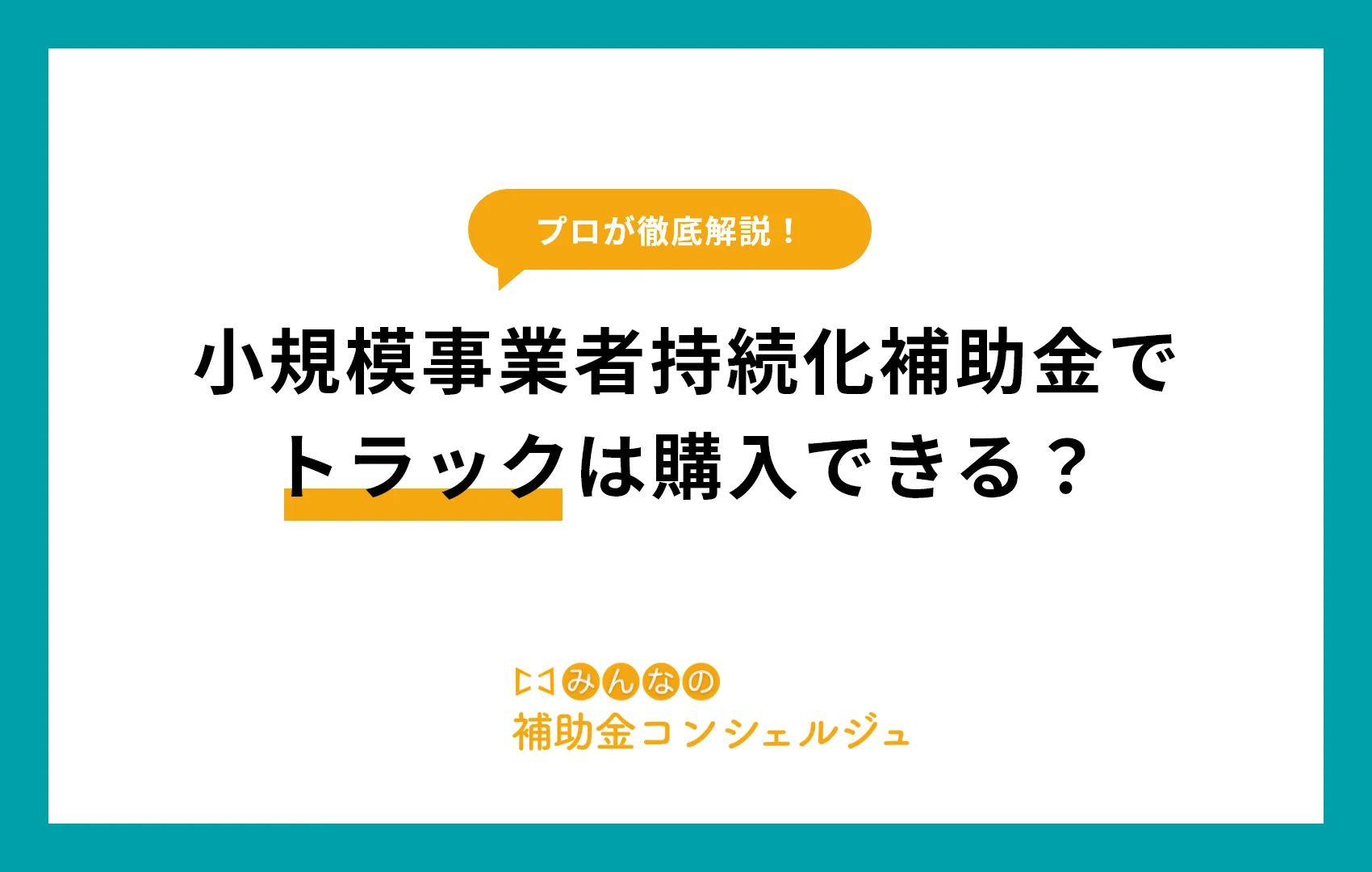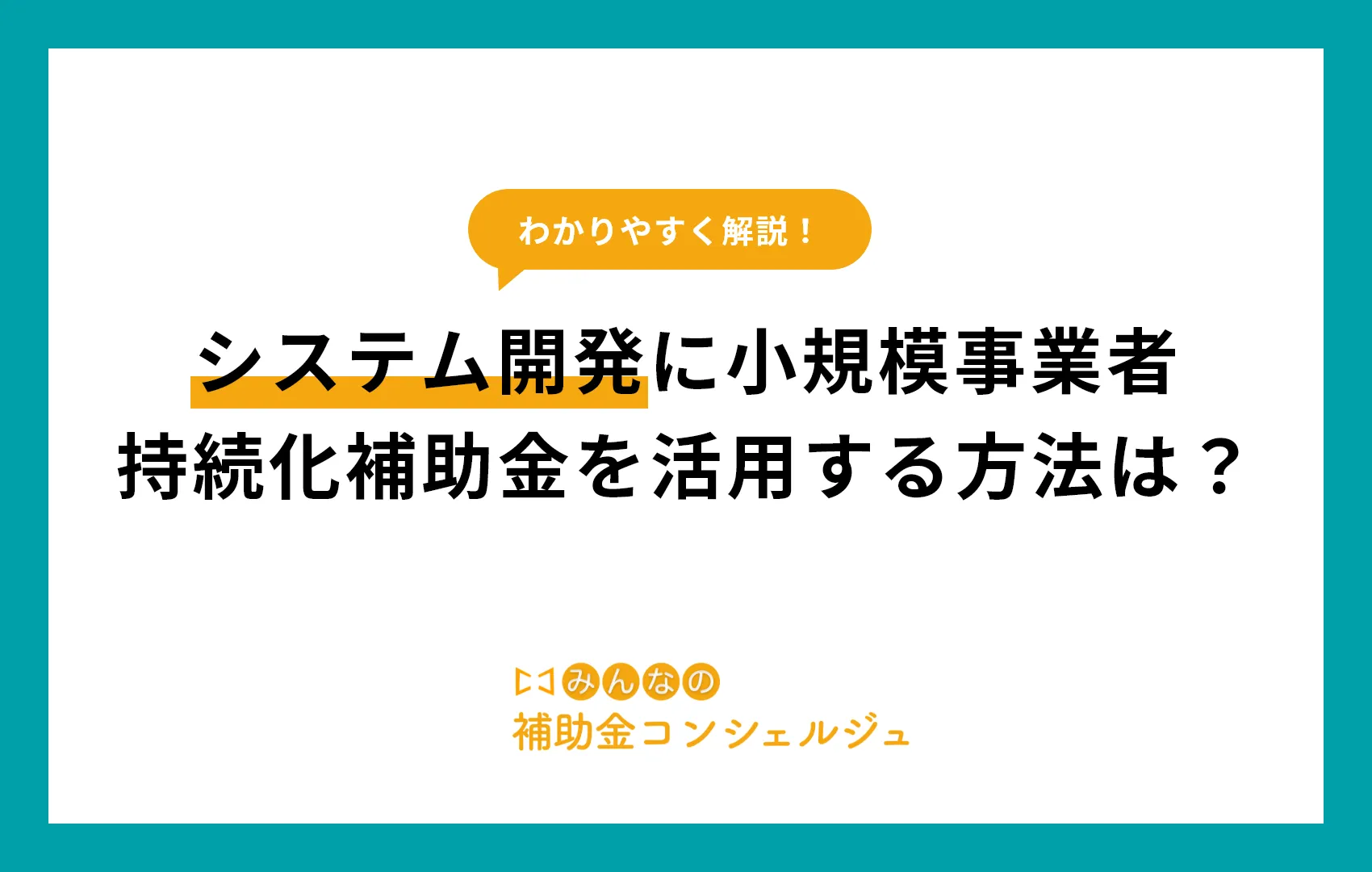小規模事業者持続化補助金でトラックは購入できる?
小規模事業者持続化補助金を活用してトラックを購入したい方必見!本コラムでは、持続化補助金でトラックを購入できる条件や申請手順を解説します。また、活用事例もご紹介するのでぜひお役に立てください。
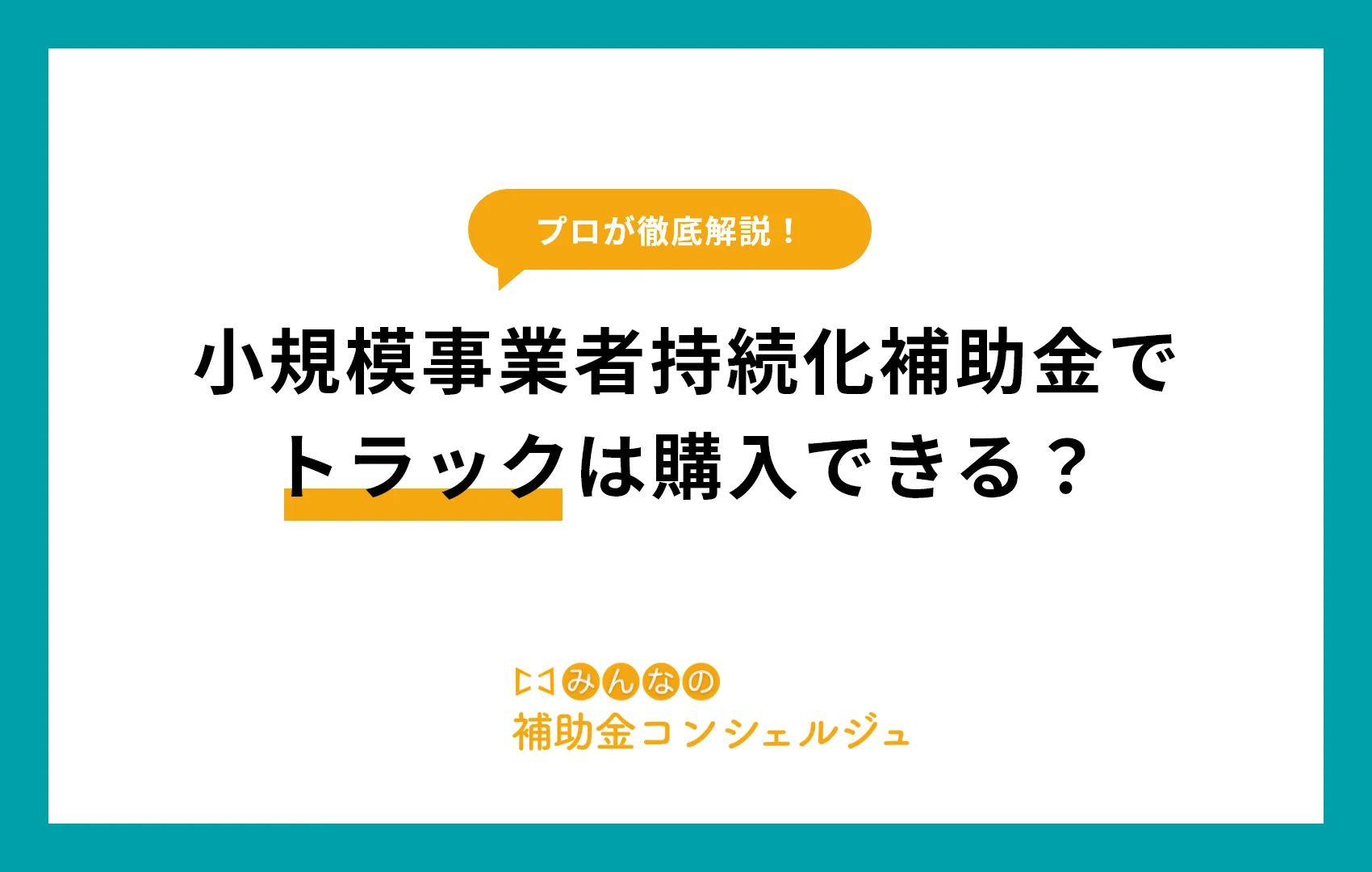
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、中小企業庁が実施する補助制度で、全国の小規模事業者が行う「販路開拓」や「業務効率化」の取り組みに対して、その経費の一部を支援する制度です。商工会・商工会議所のサポートを受けながら申請・実施する点が特徴で、地域経済の担い手である小規模事業者の生産性向上と持続的発展を目的としています。
対象者「小規模事業者」とは?
本補助金の対象となるのは、次のいずれかに該当する日本国内の小規模事業者です。
| 業種区分 | 常時使用する従業員数の上限 |
| 商業・サービス業(※) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業を含むサービス業 | 20人以下 |
| 製造業・その他の業種 | 20人以下 |
※商業とは卸売業・小売業などを含みます。
個人事業主や中小法人(株式会社・合同会社など)だけでなく、要件を満たせば一部のNPO法人も対象となります。
補助金額・補助率
通常枠の補助上限は50万円で、補助率は対象経費の2/3です(自己負担1/3)。
ただし、以下のような特例措置があり、条件を満たすと補助上限額が加算されます。
| 特例区分 | 上限加算額 | 補助率 |
| インボイス特例 | +50万円 | 2/3(据え置き) |
| 賃金引上げ特例 | +150万円 | 2/3(赤字事業者は3/4) |
| 両特例を満たす場合 | +200万円 | 2/3または3/4 |
例:インボイス特例と賃金引上げ特例を同時に活用した場合、補助上限額は最大で250万円になります。
この補助金は、「事前の計画策定」+「商工会議所の支援」+「販路拡大などの具体的な取り組み」がそろって初めて申請可能になります。特に高額な設備投資を行いたい方や、移動販売・広告車両などの導入を考えている方にとっても、有力な選択肢となり得ます。
小規模事業者持続化補助金の概要を確認する!
トラックの購入は小規模事業者持続化補助金の補助対象になる?
基本的にトラック本体の購入は補助対象外ですが、例外もあります。
小規模事業者持続化補助金では、原則としてトラックなどの車両本体の購入は補助対象外とされています。
しかし、条件を満たす場合や特定の用途であれば、車両に関する費用の一部が補助対象になることもあります。
通常のトラック購入は補助対象外
トラックは「汎用性が高く、事業以外の目的にも利用できる」と判断されるため、通常は「機械及び装置」ではなく**「車両・運搬具」**として減価償却される扱いになります。
このため、持続化補助金においては対象経費とみなされません。
【対象外となる例】
- 通常の営業車、配達車、キッチンカー
- カーナビ、ドラレコなどの車載機器類
例外1:ブルドーザーやトラクターなどの特殊車両は補助対象
一方で、ブルドーザーやトラクターなどの特殊車両は、事業のみに用いることが明確なため、「機械及び装置」として扱われ、補助対象となります。
公募要領(第17回)では、「自動車等車両のうち“機械及び装置”に該当するもの(ブルドーザー、パワーショベル等)」は補助対象と明記されています。
つまり、「機械及び装置」として減価償却される車両であれば、補助対象になり得るということです。
例外2:災害支援枠でのトラック購入は可能な場合あり
2024年の能登半島地震を受けた災害支援枠では、条件を満たす場合に限り、トラックなどの通常車両の購入も補助対象になる特例があります。
【主な条件】
- 罹災証明書などの提出が必要
- 石川・富山・福井・新潟の被災地域で営業していること
- 令和6年能登半島地震で、事業用の車両が損壊したこと(直接的な被害)
参考:災害支援枠公募要領(第5回)p.21
※「補助事業で特定業務のみに用いることが明らかな車両の購入」は補助対象と記載
小規模事業者持続化補助金の災害支援枠とは?
関連費用での申請は可能!補助対象となる費目例
たとえトラック本体が補助対象外であっても、以下のような関連費用であれば、補助対象になる可能性があります。
| 費目区分 | 内容 | 申請の工夫例 |
| 広報費 | 車体ラッピング(ロゴ・サービス名) | 営業車を「走る広告塔」として活用 |
| 委託・外注費 | 荷台の内装改造や設備設置 | 移動販売用トラックの天幕設置など |
| 通信費 | 位置情報や予約機能の導入 | 移動先での販売管理・顧客通知に活用 |
このように、車両を販路拡大の“媒体”として活用することで、周辺費用を補助対象に含めることが可能です。
トラック本体の購入は、原則として補助対象外と理解しておきましょう。どうしても必要な場合は、特殊車両の扱いや災害支援枠の条件を確認します。ラッピングや改造など周辺費用を活用する発想に切り替えるのが現実的です。
【2025年度版】小規模事業者持続化補助金で車両購入はできる?
小規模事業者持続化補助金でトラック購入が認められた事例3選
小規模事業者持続化補助金を活用してトラック購入が認められた事例を3つ紹介します。
事例1:移動販売車で新エリアへの販売開始
この事例は、地方の食品製造業者が新たな販売チャネルとして移動販売を導入し、地域外への販路を開拓した成功例です。
取り組んだ施策
- 移動販売用の軽トラックを導入(本体費用は自己負担)
- 車内に販売用設備を設置(補助対象の内装費として申請)
- 地元新聞への出店情報の掲載など広報活動
成果とポイント
- 新エリアの顧客を開拓し、月商は従来の1.3倍に
- 顧客との直接対話によるニーズ把握が商品改良に貢献
- 「単なる配送」ではなく「販売そのもの」としての明確な目的が評価され、補助対象に
事例2:装飾を施した営業車(広報効果のある看板付き)
この事例は、訪問型の住宅リフォーム会社が自社サービスの認知向上を目的に、装飾付き営業車を導入したケースです。
取り組んだ施策
- トラックの車体に社名・ロゴ・サービス内容をラッピング
- 地元イベントや展示会への積極的な参加
- 名刺代わりに営業車を活用し、地域内での露出強化
成果とポイント
- SNSに車両写真が投稿されるなど話題性が向上
- ラッピング費用を「広報費」として補助対象に計上
- 見積やデザイン案を丁寧に準備し、審査時の評価がアップ
事例3:イベント出店用トラックで販促機会を拡大
この事例は、地方の雑貨メーカーが、地域イベントやフェスに自社製品を出品するためのトラックを導入し、販促の場を広げた成功例です。
取り組んだ施策
- イベント出店用に装飾できる軽トラックを導入
- 出店先ごとにSNSで告知・ライブ配信も実施
- 車体の側面を開閉式に改造し、即席販売ブースを設置
成果とポイント
- 地元イベントでの販売実績が前年の2倍以上に
- 移動式ブースという新たな販売形態が、地域活性化にも貢献
- 改造費・ディスプレイ装飾費は「委託・外注費」や「広報費」として補助対象に
これら3つの事例に共通しているのは、「単なるトラック購入」ではなく、明確な販路拡大の目的と手段が結びついていた点です。経営計画に基づいたストーリーと、補助対象経費の正しい申請が採択のカギとなっています。
小規模事業者持続化補助金のトラックに関する補助対象経費
トラック本体の購入費用は補助対象外ですが、車両を活用した販路開拓の取組に関連する費用は、工夫次第で補助対象になる可能性があります。
特に、広報や販売促進、情報発信に関する費用として申請すれば、採択されるケースがあります。
広報費:車体にロゴ・ラッピングを施す費用
「走る広告塔」としてトラックを活用する場合、車体に会社名や商品ロゴを入れるラッピング費用は広報費として申請可能です。
たとえば、キッチンカーや移動販売車にロゴやサービス内容を記載すれば、通行人への視認性向上につながり、販路開拓の一環と認められます。
販促用備品費:展示台やのぼりなどの備品
イベントや地域フェスでトラックを使って出店する場合、販売用の展示台・のぼり・テーブル・看板などの備品は、「販促用備品費」や「機械装置等費」に該当することがあります。
販路拡大のための「移動式店舗」としてトラックを使用するケースでは、これらの付随設備の購入も補助対象になり得ます。
通信費:オンライン予約や発信機能の導入
例えば、移動販売スケジュールをオンライン上で予約・確認できる仕組みを導入する場合、その構築費用は通信費やウェブサイト関連費として申請できます。
販売活動と連携した情報発信の仕組み(位置情報、SNS連動、予約フォームなど)は、販路拡大に直結するため、積極的に活用すべきポイントです。
補助対象になりやすくするためのコツ
| 対象外になりやすい例 | 補助対象になりやすい工夫 |
| 単なる配達用車両の購入 | 移動販売・営業活動など「販路開拓」を目的とした活用 |
| 無装飾のトラック | ロゴや商品画像を施した「広告効果のある装飾」付き |
| 通常の車内設備 | 商品展示や販売に特化した改造・備品導入 |
小規模事業者持続化補助金では、トラック本体は原則補助対象外ですが、車両を“販路開拓のツール”として位置づけた関連費用は補助対象になる可能性があります。申請時は、「販路拡大につながるかどうか」を基準に、経費区分と活用目的を明確に整理することが重要です。
トラックを小規模事業者持続化補助金の補助対象にするポイント
トラック本体の購入は原則補助対象外ですが、関連する取組をうまく計画に組み込めば、一部の経費を補助対象とすることは可能です。
そのためには、申請時のポイントを押さえることが重要です。
1. 事業計画書で「販路開拓目的での使用」であることを明確に説明する
小規模事業者持続化補助金は、販路拡大や業務効率化につながる取り組みを支援する制度です。
そのため、トラックに関する費用を補助対象に含めたい場合は、「販路開拓にどのように寄与するのか」を明確に示すことが不可欠です。
たとえば、
- 移動販売車として新規エリアに出店する
- ラッピングトラックで地域イベントに参加し、商品PRを行う
といったように、“売上拡大や認知向上の手段”として活用する計画を具体的に記載しましょう。
2. 補助対象経費として認められやすい「付随的な費用」に焦点を当てる
トラック本体ではなく、以下のような関連する装飾・改造・情報発信費用で申請するのが現実的です。
| 費目 | 内容の例 |
| 広報費 | 車体ラッピング、看板設置など |
| 委託・外注費 | 荷台の改造、展示用棚の設置など |
| ウェブサイト関連費・通信費 | トラック位置情報の発信や予約機能の連携 |
これらの費用は、補助対象経費として採択された事例も多く、事業目的との一貫性があれば通りやすい傾向にあります。
3. 単なる移動手段としての購入は不採択の可能性が高い
「荷物の運搬」「スタッフの送迎」など、単に業務を支えるためのトラック導入は、販路開拓や業務効率化の範囲外と判断されやすく、審査でマイナス評価となる可能性があります。
補助金で認められるかどうかのカギは、「その取組が、補助金の目的である“販路開拓”に直結しているか?」にあります。汎用性が高く、事業専用と見なされにくいものは、極力申請から除くか、明確な用途を書き込むことが重要です。
事業目的とトラック活用の関係性をストーリーとして描くことが重要です。補助対象経費になりやすい装飾・改造・広報等の費用に注目しましょう。
「トラック=単なる車両」ではなく、販促の一環として位置づける点がポイントです。
持続化補助金を活用してトラックを購入する場合の注意点
小規模事業者持続化補助金では、トラック本体の購入は原則として補助対象外です。
それでも関連経費での申請を検討する場合には、申請内容や書類の不備によって不採択になるケースが多くあります。
以下のような点に注意して申請を進めましょう。
NG1:トラックの購入目的が「配達効率の向上」のみになっている
たとえば、「商品の配達を効率化するためにトラックを導入したい」という理由だけでは、販路拡大という補助金の目的と一致しないため、不採択となる可能性が高くなります。
補助金は「売上を増やすための取り組み」に対して交付されるもの。
そのため、販売チャネルの拡大や新規顧客の獲得などと結びつけて説明することが必須です。
NG2:車両の用途や活用内容があいまい
「営業用に使用予定」「地域イベントにも使うかも」といった、目的や使い方が曖昧な表現は避けましょう。
審査側が「これは事業に本当に必要なのか?」と判断できなければ、採択は難しくなります。
「毎週末、○○市のマルシェに出店し、商品を対面販売するために改造トラックを使用。これにより月○件の新規顧客獲得を見込む」など、具体的かつ数字を交えた計画を示すのがベストです。
NG3:申請書類に根拠資料や見積書が不十分
補助対象経費として申請する場合には、見積書や用途を証明する根拠資料が必須です。
例えば、
- トラック改造の内容がわかる設計図や写真
- 装飾内容のラフデザイン
- 比較見積(相見積)を取って価格の妥当性を示す
これらが不足していると、「費用の適正性が不明」と判断され、補助対象から外される可能性があります。
トラックは販路拡大の手段として活用する計画になっているかを確認します。また、具体的な用途と、それに伴う成果目標(売上・集客等)があるか、経費の妥当性を示す見積書・資料を揃えているか、も必ず確認しましょう。
持続化補助金でトラックを購入する場合の申請の流れ
小規模事業者持続化補助金でトラックに関連する経費を申請する場合、計画の練り方や準備書類の精度が重要です。
以下の流れに沿って準備を進めましょう。
1.商工会・商工会議所に相談する(経営計画書の確認)
申請にあたっては、地域の商工会または商工会議所との連携が必須です。
申請者自身が作成した経営計画書や補助事業計画の内容について、支援を受けながらブラッシュアップします。
- 計画に販路開拓としてのトラック活用目的が記載されているか
- 対象となる経費の内訳や内容が妥当かどうか などを確認してもらいます。
2.必要書類を準備する(見積書・事業計画書など)
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 内容 |
| 事業計画書 | トラック活用が「販路拡大」につながることを明記 |
| 経営計画書 | 補助事業の目的や5年間の成長見通しなどを記載 |
| 見積書・比較見積 | 車体装飾費・改造費・関連備品費用などの見積り(2社以上から取得が原則) |
| 補助対象経費の根拠資料 | 写真・図面・広告デザイン案などがあると説得力が高まります |
特にトラック関連の改造・装飾費などを申請する場合、具体的な仕様や使い方が分かる資料が重要になります。
3.採択後に購入・事業実施 → 補助金の申請 → 実績報告
補助金は事前購入NG・後払い制です。必ず「交付決定通知」が届いてからトラック関連の支出を行いましょう。
流れは以下の通りです:
- 採択結果の通知を受ける
- 「交付決定通知」が届いた後に、補助対象となるトラック関連経費を支出
- 補助事業終了後に「実績報告書」を提出
- 内容が承認されれば、補助金が振り込まれます
事前の購入や発注は補助対象外になるので注意しましょう。小規模事業者持続化補助金の申請の順番は、必ず採択→交付決定→購入→報告の順です。
トラック関連費用は用途・目的の明確化と見積の整備がカギになります。
ガソリン代高騰と小規模事業者持続化補助金の関連
近年のガソリン代の高騰は、日常的に車両を使用する小規模事業者、特に運送業・移動販売・訪問型サービスなどの業態に大きな影響を与えています。
小規模事業者持続化補助金はその名の通り、小さな事業者の継続と成長を支援することを目的とした制度です。
とくに災害支援枠のように、「今まさに困っている事業者」を優先的に支援する側面もあるため、燃料費高騰の影響をどう乗り越えるかという視点を申請書に盛り込むことは有効です。
ガソリン代高騰を申請にどう活かす?
トラックを使う業態では、以下のような構成で申請内容をまとめると、補助対象としての妥当性が高まります。
影響の明示:ガソリン価格の上昇により、これまで通りの営業エリア維持が困難になっている。
打開策の提案:移動販売車に販促機能を追加し、訪問先での成約率を高める。1台で複数業務を担える改造で、無駄な移動を減らす。
補助金活用の位置づけ:販路拡大と業務効率化を両立させるトラック改装費やPR費として補助を活用。
なぜ“トラック”なのかを説明できると強い
トラックをただの移動手段としてではなく、「事業戦略の中核」として位置づけることで、説得力のある申請が可能になります。
ガソリン代の高騰という外部要因を踏まえたうえで、
- なぜ今トラックの工夫が必要なのか
- トラックをどう活用して事業を回復・拡大していくのか
といった「背景+戦略」をしっかり描くことが、審査での評価につながるポイントです。
まとめ
小規模事業者持続化補助金でトラックに関する費用を補助対象にしたい場合、最も重要なのは「販路拡大にどうつながるか」を明確に示すことです。
トラック=広告媒体や販売チャネルの一部として使うことが前提です。例えば、ラッピングによるPR、移動販売による新規開拓、イベント出店用の展示車両などが該当します。
また、通常の業務車両(配達・営業など)としての導入は原則対象外です。汎用性が高く、事業専用と見なされにくい用途は避けましょう。そのためには、申請書の中に「戦略的に必要な取組」であることを丁寧に説明し、根拠となる資料や見積書も整えることが不可欠です。
正しい経費区分の理解と、具体的な活用計画を持って申請することで、トラック関連の補助も現実的な選択肢となり得ます。
まずは商工会・商工会議所に相談し、あなたのアイデアが補助対象になり得るかを確かめてみましょう。
持続化補助金でトラックを購入したい方はこちら!
実は、「補助金は申請すれば受給できる」わけではありません。
厳しい審査をクリアする必要があり、4社に1社しか通過できない難関補助金も多いのです。
審査通過率を飛躍的に上げるには、申請サポート会社の力を借りるのが鉄則!
提出書類の抜け・漏れがないように、弊社が万全のサポートで審査通過を目指します。
弊社がサポートさせていただいた方のお喜びの声
弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに70億円以上の申請総額、2,000件以上の申請実績があります。
専門家による的確なアドバイスとサポートで、御社を採択へ導きます!
サポートさせていただき見事採択された方々のお喜びの声をご紹介します。
「簡単な内容を伝えただけで、立派な書類に仕上げていただきました。急な変更にもすぐ対応してくれて、とても満足です!」
「電話やメールで手続きが完了するので非常に楽でした!LINEでも相談できる気軽さもよかったです。」
「必要な情報を渡すだけで専門家がすべて対応してくれます!リアリゼイションのマニュアルを活用すれば、必要なところを穴埋めするだけで書類ができますし、とにかく時間が浮いて、本業に集中することができました!」
補助金に関するお悩みやご相談がある方は、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。担当者があなたのお悩みに丁寧に回答いたします。
監修者からのワンポイントアドバイス
補助金での車両の取り扱いは原則的には不可となります。しかし専ら補助事業の為に使用する車両である場合には例外的に検討できるケースもあります。事前に商工会や商工会議所などにご相談の上、専門家と連携して申請できるか否かを判断されることをお薦めさせて頂きます。