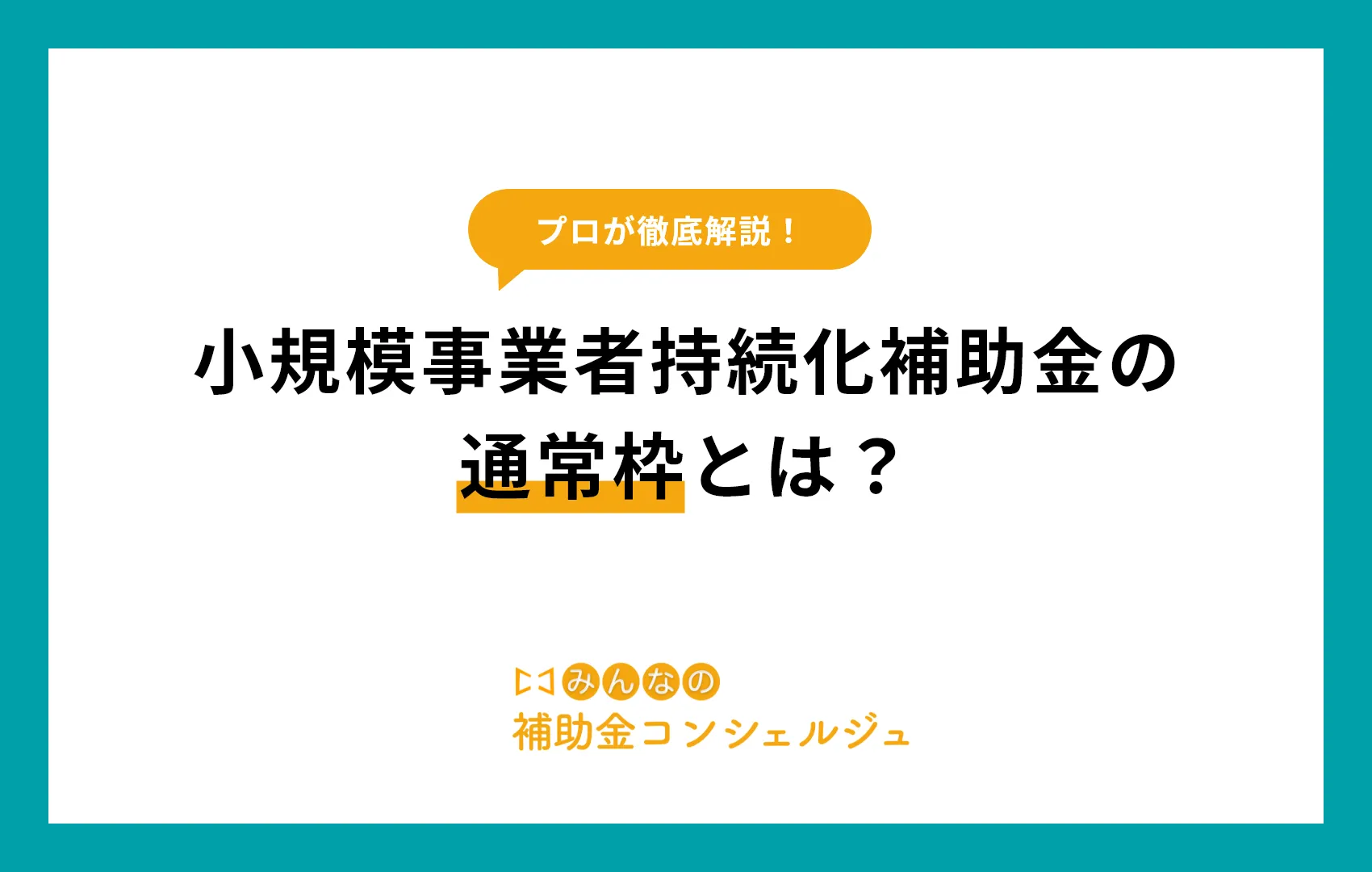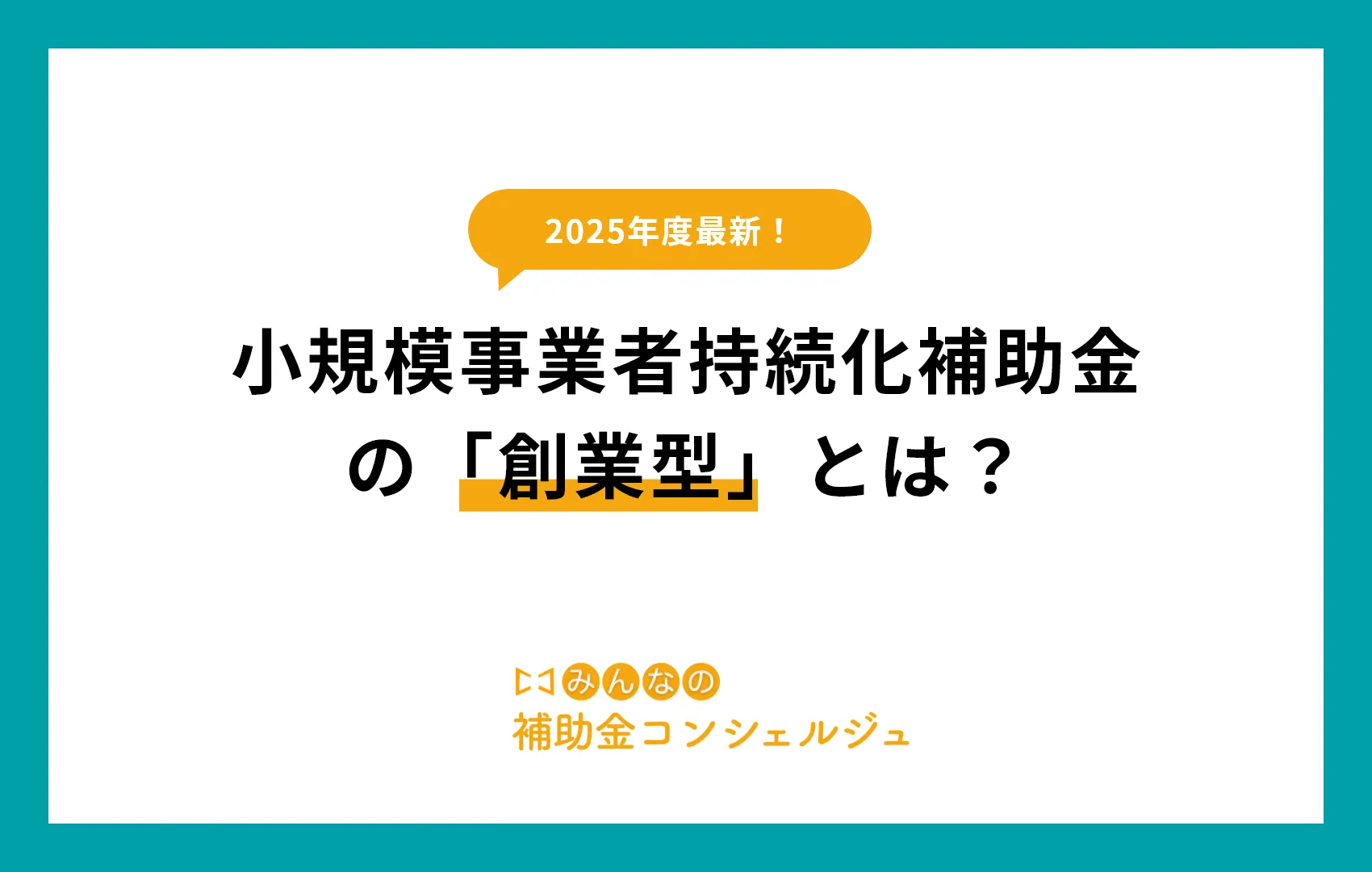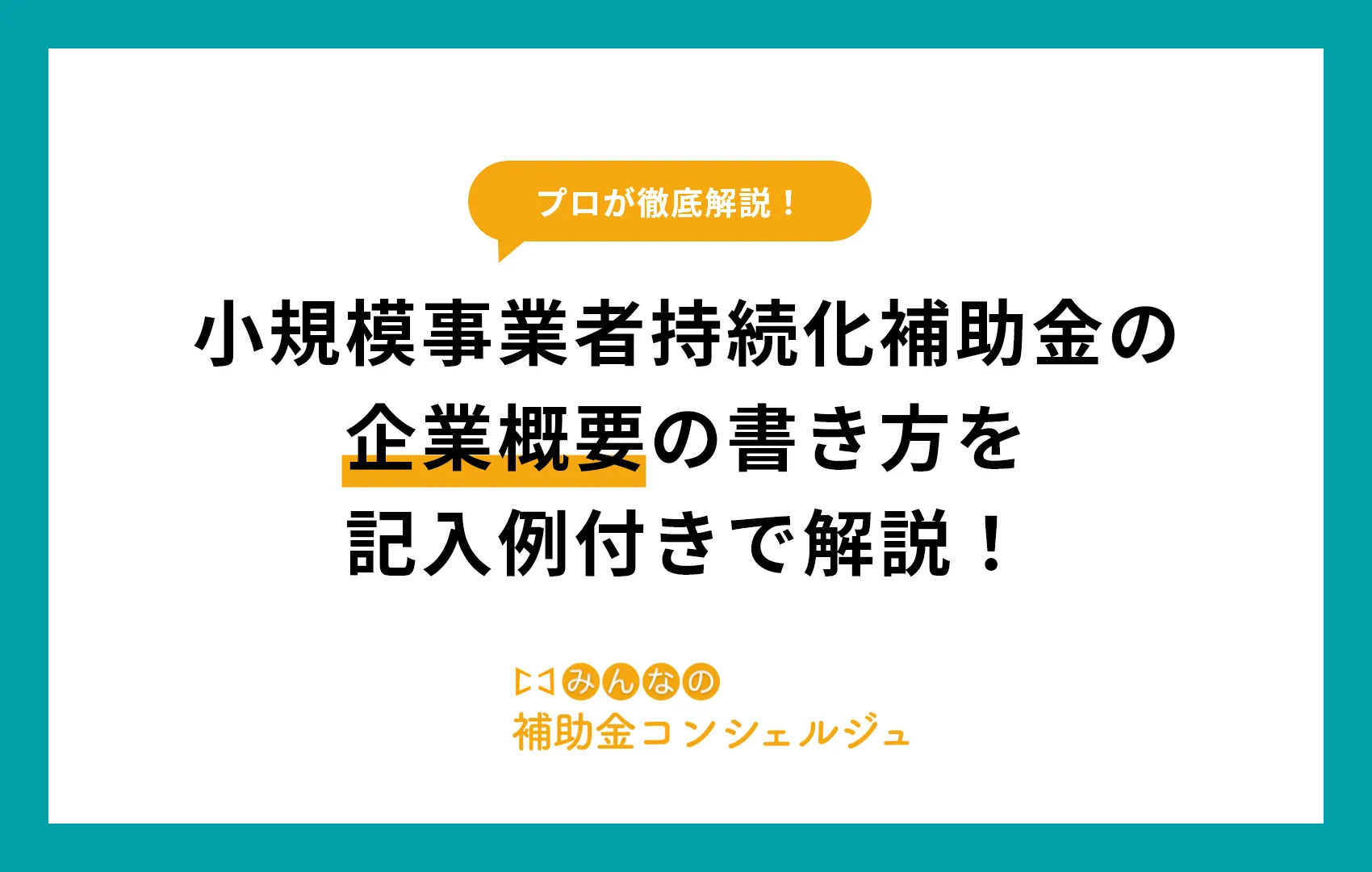小規模事業者持続化補助金の通常枠とは?活用事例も紹介!
小規模事業者持続化補助金にはさまざまな申請枠がありますが、最も活用しやすい通常枠。本コラムでは、幅広い事業者が活用できる通常枠について解説します!通常枠の概要や実際の活用方法を分かりやすご紹介。2025年度、通常枠への申請を検討している方はぜひお役立てください。
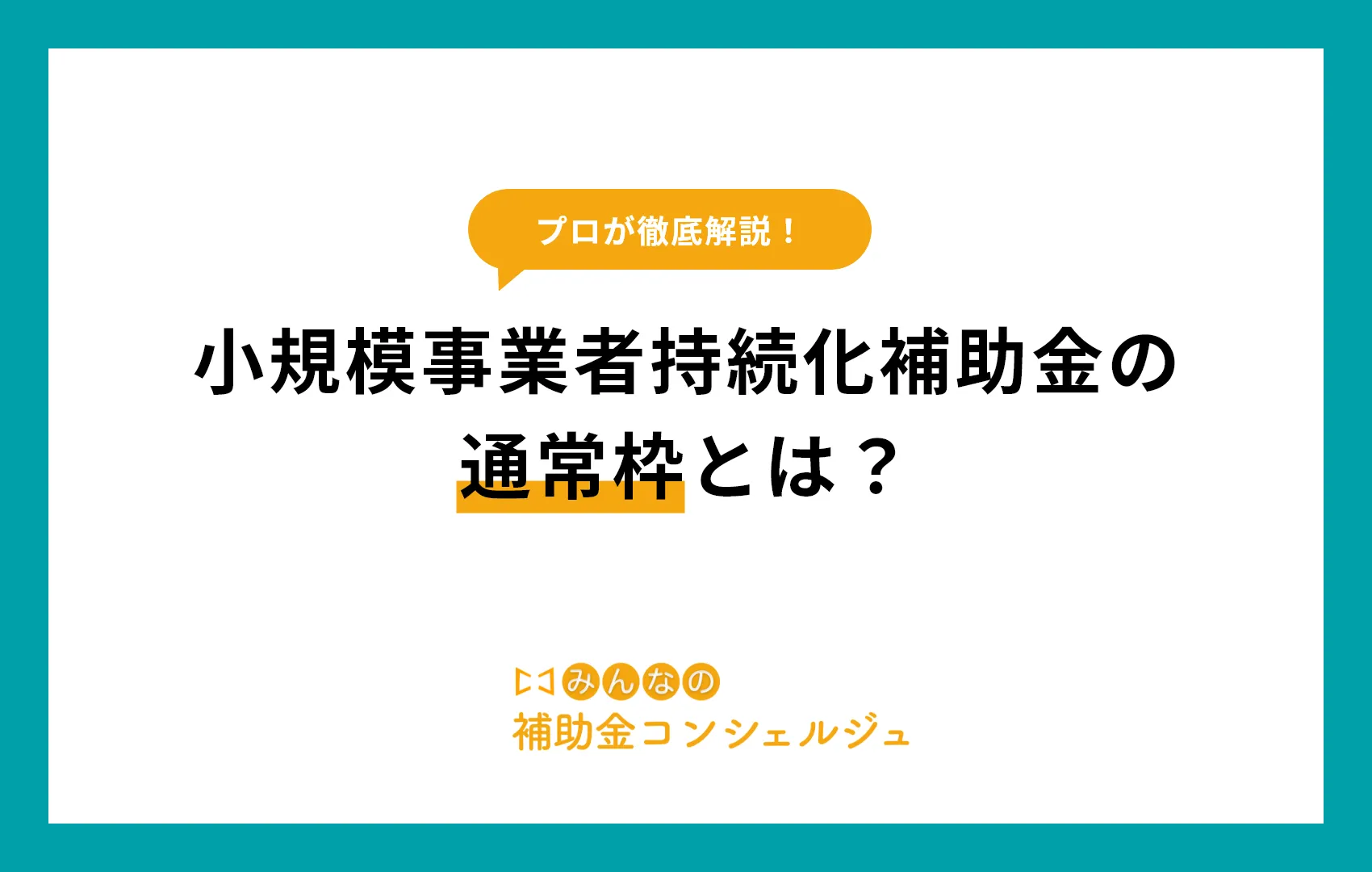
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
小規模事業者持続化補助金の通常枠って何?
「小規模事業者持続化補助金」は、地域の小さな企業や個人事業主が、新しいお客様を増やすための取り組み(販路開拓)や、仕事の効率を上げる工夫(業務効率化)に使える費用をサポートしてくれる制度です。
その中でも「通常枠」は、特別な事情がなくても使える基本的な枠です。創業したばかりでなくても、事業再構築などの計画がなくても申請できるため、もっとも多くの事業者に利用されています。
通常枠は、「一般型」と呼ばれる補助金の中の1つで、以下のように分類されています。
- 通常枠:最もスタンダードな枠。販路開拓や業務効率化が対象。
- 災害支援枠:地震などの自然災害で被害を受けた事業者向け。
こんな方におすすめ
- 新たな機械を導入して作業の効率を上げたい
- 今ある商材・サービスをもっと多くの人に届けたい
- 地元で長く事業を続けてきたが、そろそろ販路開拓に力を入れたい
こうした「日々の事業を一歩進める」ための投資を、しっかり後押ししてくれるのが通常枠です。
| 項目 | 内容 |
| 補助対象経費 | 広告宣伝費、機械装置費、ITツール費、建物改修費、開発費、資料購入費、専門家謝金など |
| 取組内容例 | チラシ・ホームページ制作、新規設備の導入、作業効率化の仕組みづくり など |
| 加算措置 | 賃上げ、被災地での事業、事業再構築 などに該当すると上限額が引き上げられる |
| 補助上限額 | 原則50万円(加算により最大200万円まで拡大) |
| 補助率 | 原則2/3(賃上げ要件などを満たすと3/4) |
創業間もない事業者や大規模な変革を伴う事業ではなくても、日常の販促や業務改善など、堅実な取組を支援対象とするのが特徴です。
小規模事業者持続化補助金の概要をチェックする!
通常枠と他の枠(創業枠、成長枠)の違い
小規模事業者持続化補助金「一般型」には、事業者の状況や目的に応じて複数の申請枠が用意されています。「一般型」には「通常枠」のほか、「創業枠」「成長枠」があり、それぞれ補助額や要件が異なります。以下に3枠の主要な違いをまとめました。
| 比較項目 | 通常枠 | 創業枠 | 成長枠 |
| 補助上限額 | 50万円(最大200万円まで加算可能) | 200万円 | 200万円 |
| 補助率 | 原則2/3(条件により3/4) | 2/3 | 2/3 |
| 申請対象者 | 小規模事業者等(広く対象) | 開業5年以内の者で創業関連事業を実施 | 成長戦略を策定・実行する者 |
| 特記事項 | インボイス・賃上げ特例で加算あり | 創業に関連した新事業や地域課題解決が主旨 | 収益性・付加価値向上が見込まれる成長分野での取組が必要 |
| 審査基準 | 基本要件+加点項目 | 通常枠に加え、創業性・社会的意義 | 通常枠に加え、収益見通し・市場拡大性など |
創業枠:「地域の社会課題を解決する新ビジネス」や「創業直後の認知拡大」など、スタートアップ段階での活動支援に適しています。
成長枠:例えば「新製品を開発して新市場に参入したい」「事業の拡張によって売上を倍増させたい」といった中長期的な成長戦略に沿った投資が前提です。
「創業枠」「成長枠」はいずれも要件や審査基準がやや厳しくなる傾向があります。一方で「通常枠」は初めての申請にも適しており、採択実績も豊富です。迷った場合は、まず「通常枠」での申請を検討し、将来的に成長枠へのチャレンジを視野に入れるとよいでしょう。
特例措置との併用で、上限額は最大200万円に!
通常枠では、条件を満たすことで上限額を段階的に引き上げる「特例措置」を活用できます。
以下の2つの特例のうち、どちらか一方、あるいは両方を満たすと、最大で+200万円の補助が受けられる可能性があります。
| 特例 | 上限引上げ | 主な要件 |
| インボイス特例 | +50万円 | 一度でも免税事業者だった者が、現在「適格請求書発行事業者」であること |
| 賃金引上げ特例 | +150万円 | 事業場内最低賃金を+50円以上引き上げていること(赤字企業の場合、補助率も3/4に引上げ) |
| 両特例併用 | +200万円 | 上記2要件をいずれも満たす場合 |
特例を活用することで、通常は最大50万円の補助上限が、最大200万円まで拡大されます。たとえば、ホームページ制作や設備導入だけでなく、複数の施策を組み合わせた大規模な販路開拓や業務改善も実現しやすくなります。
特例を申請する場合、要件を満たしていることを証明する書類の提出が必須です。
たとえば、
- インボイス発行事業者であることを示す登録番号
- 最低賃金引き上げを証明する賃金台帳や給与明細
さらに、特例の申請を行って1つでも条件を満たしていないと、補助金全体が交付対象外になるため、十分な確認が必要です。
これらの特例措置は、通常枠と併用可能であり、「通常枠の中での加算要素」という位置づけです。創業枠や成長枠では利用できない特例もあるため、通常枠を選ぶメリットの一つと言えるでしょう。
第18回公募「通常枠」の概要
小規模事業者持続化補助金は、年に数回申請できる補助金です。申請できるタイミング(公募期間)はあらかじめ決まっており、毎回その都度スケジュールが発表されます。現在は、2025年6月30日に公募要領が公開された「第18回公募」が受付中です。この回のスケジュールに沿って申請準備を進めましょう。
| 項目 | 内容 |
| 補助率 | 原則 2/3(※赤字事業者で賃上げ要件を満たす場合は 3/4) |
| 補助上限額 | 通常枠:50万円インボイス特例:+50万円賃金引上げ特例:+150万円両方適用:最大200万円まで上限引上げ可能 |
| 対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費など |
| 申請方法 | 電子申請のみ(郵送不可) |
| 必須アカウント | GビズIDプライムアカウントが必要(事前取得を推奨) |
公募スケジュール
| 項目 | 内容 |
| 公募要領公開 | 2025年6月30日(月) |
| 申請受付開始 | 2025年10月3日(金) |
| 申請受付締切日 | 2025年11月28日(金)17:00 |
| 事業支援計画書交付の受付締切 | 2025年11月14日(金)(※予想) |
| 交付決定日 | 2026年1月17日(金)頃(※予想) |
| 事業実施期間 | 2026年1月下旬 ~ 2026年11月末頃(※予想) |
| 実績報告書提出期限 | 2026年11月30日(月)(※予想) |
※事業支援計画書(様式4)は、商工会・商工会議所から発行を受ける必要があります。締切を過ぎると発行できません。
補助対象となるには、「商工会または商工会議所」の支援(事業支援計画書)が必須です。申請を検討している場合は、早めに地域の商工会・商工会議所に相談することをおすすめします。
申請対象者
小規模事業者持続化補助金の通常枠は、常時使用する従業員が一定数以下の「小規模事業者」が対象です。個人事業主も法人も申請可能ですが、業種ごとに人数の上限が異なります。小規模事業者の定義は以下の通りです。
| 業種区分 | 常時使用する従業員数の上限 |
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業・製造業・その他 | 20人以下 |
※ここでいう「常時使用する従業員」には、パート・アルバイト等も一定の条件で含まれます。役員や外注先は含まれません。
対象となる主な事業者の例
- 個人事業主(建設業、美容業、飲食業、製造業など)
- 商工会または商工会議所の管轄地域で事業を営む者
- 株式会社・合同会社・NPO法人など(小規模企業であれば可)
以下のような場合は申請対象外となるのでご注意ください。
- 常時使用する従業員が上限を超えている
- 申請時点で事業実態がない(開業届未提出等)
- 風俗営業等の規制対象業種(公募要領P.5参照)
- 医療法人、農業法人、学校法人、宗教法人、任意団体など(一般型・通常枠では対象外)
小規模事業者持続化補助金は、創業したばかりの事業者でも申請が可能です。ただし、申請時点で実際に事業を行っていること(店舗がある、売上が出ている など)が条件となります。
また、「小規模事業者」に該当するかどうかは、従業員数で判断されます。この人数は、雇用契約があるかどうか、実際に働いているかどうかなどで決まるため、判断が難しい場合は、最寄りの商工会や商工会議所に事前に確認しておくと安心です。まずは、自社が補助金の対象となる「小規模事業者」にあたるかを、しっかりチェックしましょう。
弊社では、小規模事業者持続化補助金に関するご質問を受け付けております。些細な疑問でもOK!以下のフォームよりお気軽にご相談ください。
【無料】補助金のプロに持続化補助金の相談をする!
通常枠の活用事例|外壁塗装業(建設業)の場合
小規模事業者持続化補助金は、飲食店や小売業だけでなく、地域密着型の建設業でも活用できる補助金です。ここでは、千葉県で外壁塗装や屋根修繕を行っている個人事業主の活用事例をご紹介します。
抱えていた課題
地域の紹介や口コミに頼った営業スタイルで事業を続けていましたが、コロナ禍の影響もあり紹介案件が減少し、売上に不安を感じるようになっていました。技術には自信がある一方で、新規顧客の獲得や自社の魅力を伝える手段が不足していることに課題を感じていました。
補助金を使って行った施策
| 活用内容 | 詳細 |
| チラシの制作・配布 | 地元の戸建住宅をターゲットに、施工事例やお客様の声を掲載したチラシを2,000部配布 |
| ホームページ制作 | スマートフォン対応のWebサイトを新たに開設。施工実績や料金の目安を写真付きで掲載 |
| 施工写真の撮影 | プロのカメラマンに依頼して施工写真を撮影。見た目の品質や信頼感を訴求できるように整備 |
これらの費用は、補助金の「広告宣伝費」「ウェブサイト関連費」「委託費」として申請し、補助対象として認められました。
施策の結果
こうした施策の結果、地域の見込み客からの問い合わせが目に見えて増加しました。なかでもホームページ経由での新規相談が大きく伸び、以前の約2倍にまで増加。これまで「紹介がないと不安」と感じていた集客面での不安が軽減され、Webや紙媒体を通じて“信頼できそうな会社”として認知されるようになったのです。
建設業が小規模事業者持続化補助金を活用する方法は?
建設業に限らず、技術やサービスに自信がある事業者こそ、それをお客様に伝える手段が必要です。ホームページやチラシ、施工事例などを通じて、初めての方にも安心感や信頼感を伝えることができれば、集客や売上の改善に直結します。
補助金の申請は「難しそう」と感じるかもしれませんが、まずは「何に使いたいか」「どんな課題を解決したいか」を整理することが第一歩です。しっかりと準備をすれば、補助金を使った取り組みが事業の成長に大きく貢献してくれます。
「こんな課題を解決したいけど持続化補助金が使えるかな?」等、活用を迷われている方はぜひ弊社にご相談ください!弊社は補助金申請のお手伝いをしており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります。些細な疑問もOK!お気軽にご相談くださいませ。
【無料】補助金のプロに持続化補助金の相談をする!
持続化補助金の申請の流れ
小規模事業者持続化補助金の通常枠の申請は、「準備→申請→採択→実施→報告」という流れで進みます。特に初めての申請では、事前準備の段階で時間を要するため、早めの行動が成功のカギです。
| ステップ | 内容 |
| ① 事業内容の検討 | 補助対象となる経費や取り組み内容を整理し、「どの申請枠に該当するか」を確認 |
| ② gBizIDの取得 | 電子申請に必要。取得には1〜2週間かかるため、早めの申請が必要(gBizIDプライム) |
| ③ 商工会・商工会議所との相談 | 管轄地域の商工会等に事業計画を相談し、様式4「事業支援計画書」を発行してもらう |
| ④ 申請書類の作成 | 指定の様式(様式1、様式2、様式3、様式4など)に記入。事業の目的や経費、実施体制などを具体的に記載 |
| ⑤ 電子申請(Jグランツ) | 申請期間内にJグランツから提出。郵送は不可。添付書類の不備に注意 |
| ⑥ 採択結果の発表 | 審査後、交付決定通知が届いたら事業スタートが可能に |
| ⑦ 事業の実施と報告 | 実績報告書や経費証憑の提出、成果報告書の作成を期限内に行う |
gBizIDの取得は申請の大前提。忘れていたり遅れると、そもそも申請ができません。様式4(商工会の支援計画書)の取得には打ち合わせや修正が必要な場合もあるため、公募締切の2〜3週間前までに相談するのが理想です。
計画書の内容は、数値目標(売上・付加価値・給与支給額)や経費の妥当性、地域経済への貢献といった観点で審査されます。漠然とした記述は避け、できるだけ具体的に書くことが大切です。
「計画書の書き方が分からない」「申請準備が不安」という方は、ぜひ弊社にサポートさせてください!弊社は補助金申請のお手伝いをしており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります。些細な疑問もOK!お気軽にご相談くださいませ。
【無料】補助金のプロに持続化補助金の相談をする!
持続化補助金の申請書類
| 書類名 | 概要 |
| 様式1 | 申請者情報・補助事業の概要 |
| 様式2 | 経費明細書(補助対象となる経費の内訳) |
| 様式3 | 事業計画書(取組内容、効果、収支など) |
| 様式4 | 商工会等による事業支援計画書(原則紙面提出が必要) |
| 添付資料 | 決算書、開業届、法人登記簿、本人確認書類など、事業者の形態により異なる |
よくある質問
Q1. 補助率はどれくらいですか?
通常枠の補助率は原則「2/3」です。ただし、一定の条件(インボイス発行事業者+賃上げなど)を満たす場合、補助率が「3/4」に引き上がります。
Q2. 補助上限額はいくらですか?
通常枠の基本上限額は50万円です。ただし以下の加算措置により、最大200万円まで引き上げが可能です。
| 加算要件 | 加算額 |
| 賃上げに取り組む | +50万円 |
| 被災地での事業実施 | +50万円 |
| 事業再構築に取り組む | +50万円 |
※要件をすべて満たした場合、最大200万円まで申請可能です。
Q3. 個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主も対象です。ただし、業種や従業員数の条件(小規模事業者の定義)を満たす必要があります。
Q4. ホームページ制作やチラシも対象になりますか?
はい、販路開拓のための広告宣伝費やウェブサイト関連費は補助対象です。ただし、以下のようなケースは対象外となるため注意が必要です。
- 自社の業務委託先や親族への発注
- 補助事業と無関係な内容のホームページ制作
Q5. 採択されるためにはどんな工夫が必要?
審査で重視されるのは、計画の具体性・数値目標の明確さ・地域経済への波及効果です。以下の点に気をつけるとよいでしょう。
- 抽象的な表現を避け、「誰に何をどう売るか」を具体的に書く
- 売上・付加価値額・給与支給額の3〜5年後の目標を明示する
- 地域性や社会性をアピールできる要素を加える(例:高齢者支援、環境配慮など)
Q6. 不採択だった場合、次回公募に再チャレンジできますか?
はい、可能です。事業内容を見直し、計画の練り直しや相談支援を受けることで、再申請で採択される例も多くあります。
Q7. 他の補助金と併用できますか?
原則として、同一内容・同一経費での重複補助は不可です。ただし、補助対象経費が明確に分かれていれば、他制度との併用が認められるケースもあります(事前に要確認)。
まとめ
小規模事業者持続化補助金の通常枠は、販路開拓や業務効率化に取り組む個人事業主や小規模法人を支援する制度です。補助率や補助上限額に加算措置がある点も魅力で、建設業など現場中心の業種でもしっかり活用可能です。申請にはgBizIDの取得や商工会との連携、具体的な事業計画の策定など、準備に時間がかかる項目もあります。しかし、事前にスケジュールを把握し、支援機関の力を借りながら進めれば、初めてでも十分に採択を狙える制度といえるでしょう。
【無料】補助金のプロに持続化補助金の相談をする!
2025年度、小規模事業者持続化補助金を活用したい方はこちら!
実は、「補助金は申請すれば受給できる」わけではありません。
厳しい審査をクリアする必要があり、4社に1社しか通過できない難関補助金も多いのです。
小規模事業者持続化補助金の直近の採択率は30%台です。
審査通過率を飛躍的に上げるには、申請サポート会社の力を借りるのが鉄則!
提出書類の抜け・漏れがないように、弊社が万全のサポートで審査通過を目指します。
弊社がサポートさせていただいた方のお喜びの声
弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります。
専門家による的確なアドバイスとサポートで、御社を採択へ導きます!
サポートさせていただき見事採択された方々のお喜びの声をご紹介します。
「簡単な内容を伝えただけで、立派な書類に仕上げていただきました。急な変更にもすぐ対応してくれて、とても満足です!」
「電話やメールで手続きが完了するので非常に楽でした!LINEでも相談できる気軽さもよかったです。」
「必要な情報を渡すだけで専門家がすべて対応してくれます!リアリゼイションのマニュアルを活用すれば、必要なところを穴埋めするだけで書類ができますし、とにかく時間が浮いて、本業に集中することができました!」
補助金に関するお悩みやご相談がある方は、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。担当者があなたのお悩みに丁寧に回答いたします!
監修者からのワンポイントアドバイス
小規模事業者持続化補助金は補助対象経費の範囲の広さから非常に人気のある補助金となっています。特に個人事業主などの小規模事業者の方が活用出来る補助金として年に数回の公募があります。商工会議所の会員でなくても申請出来ますのでご安心下さい。