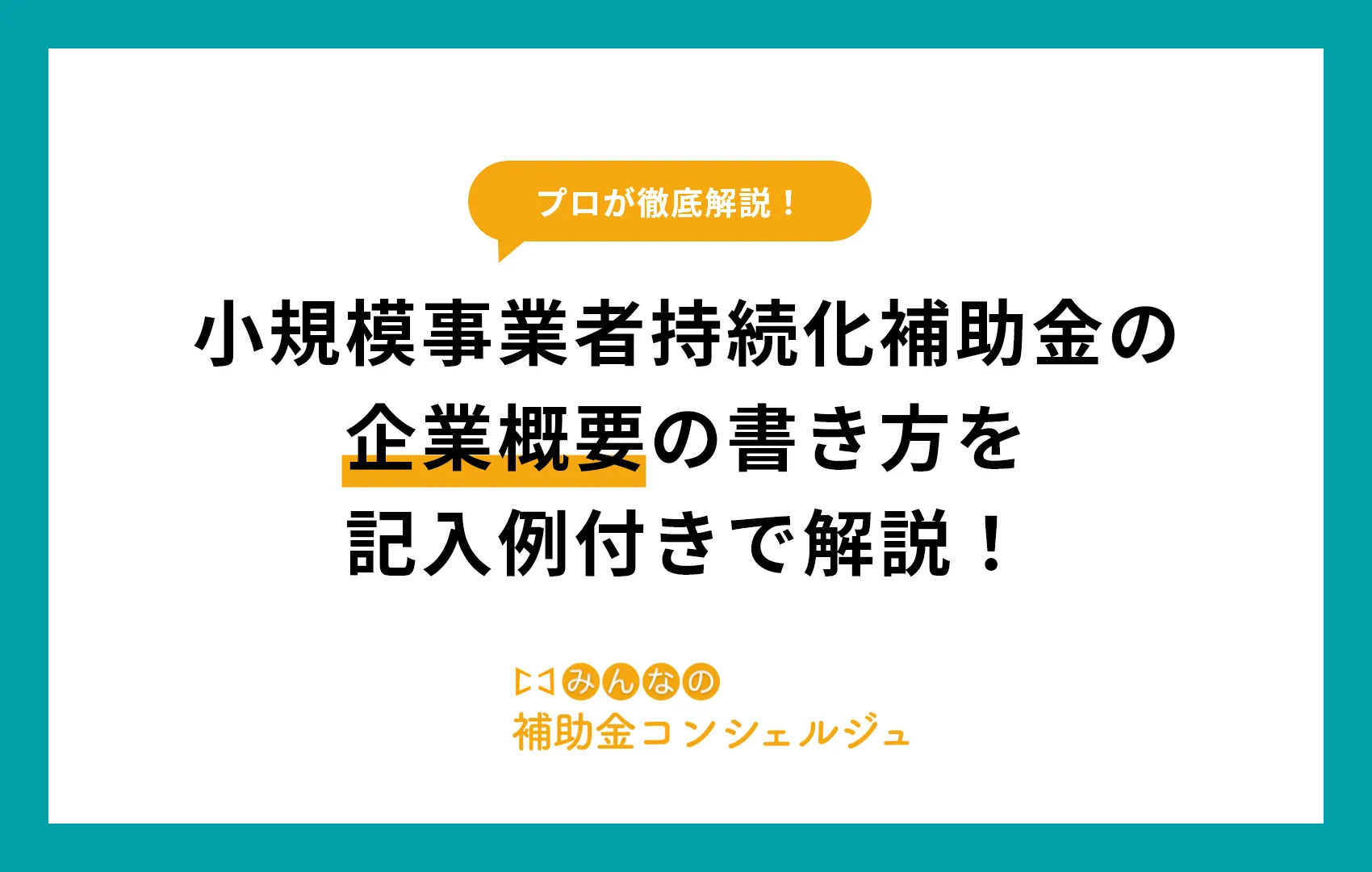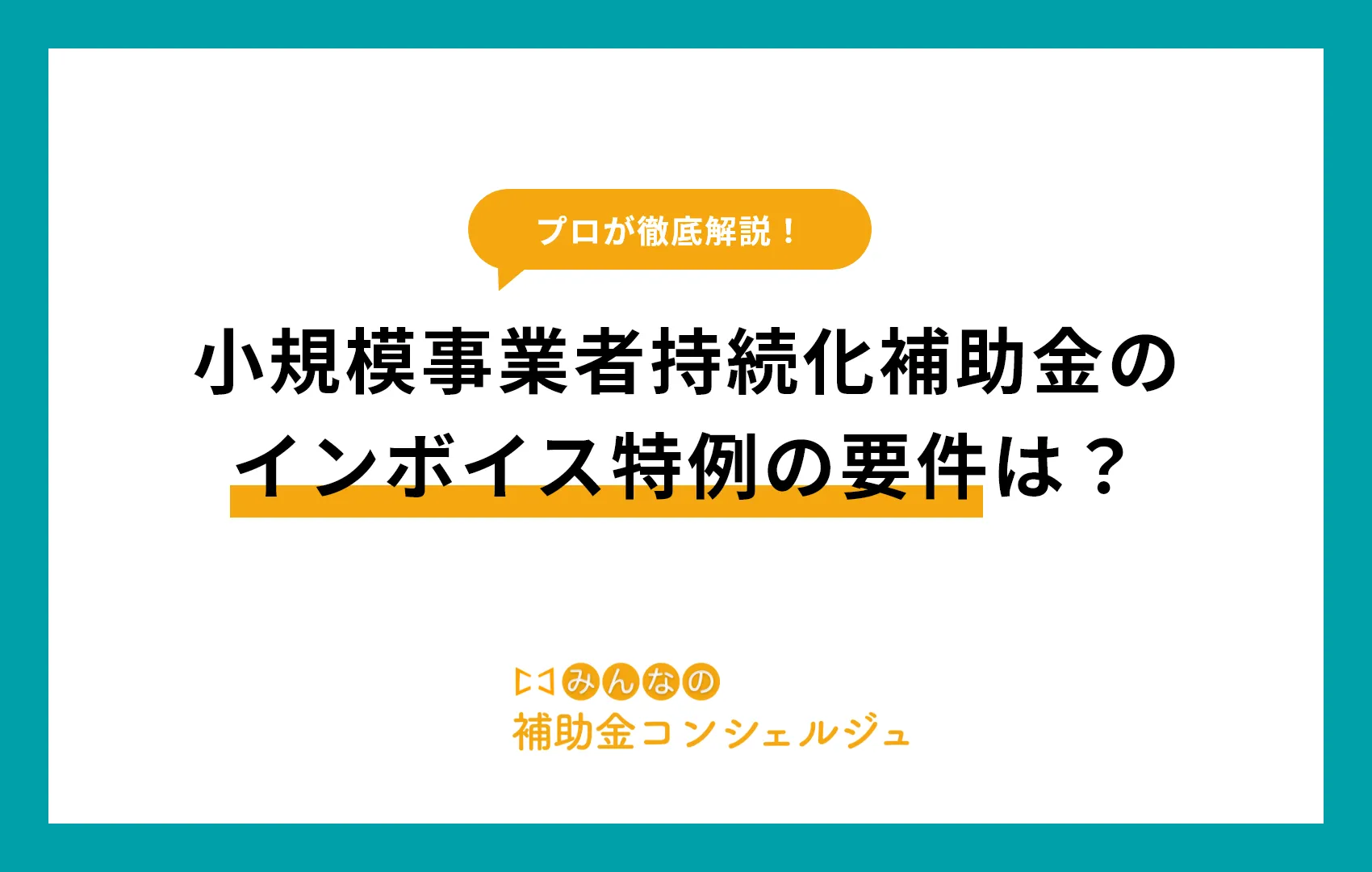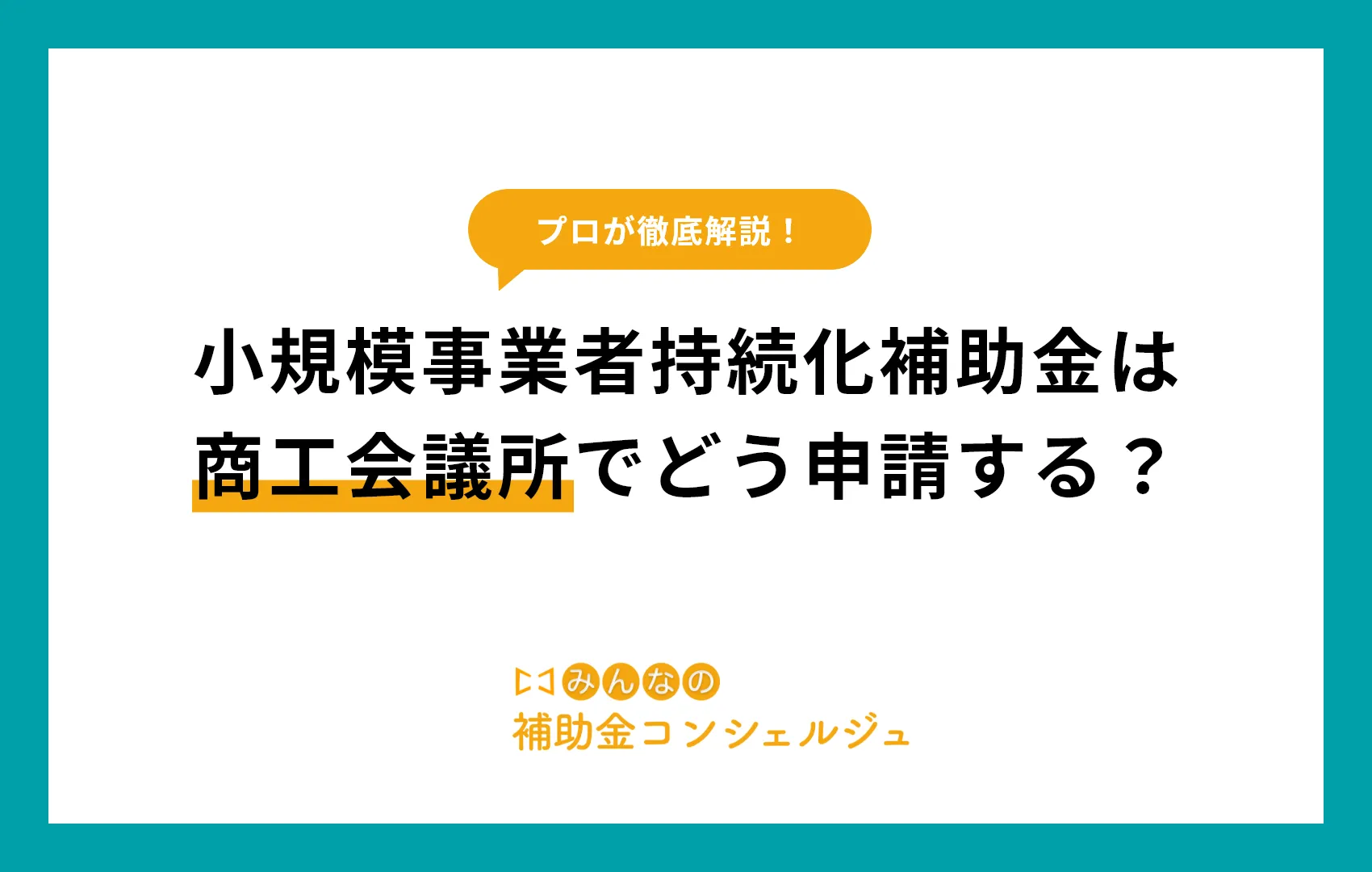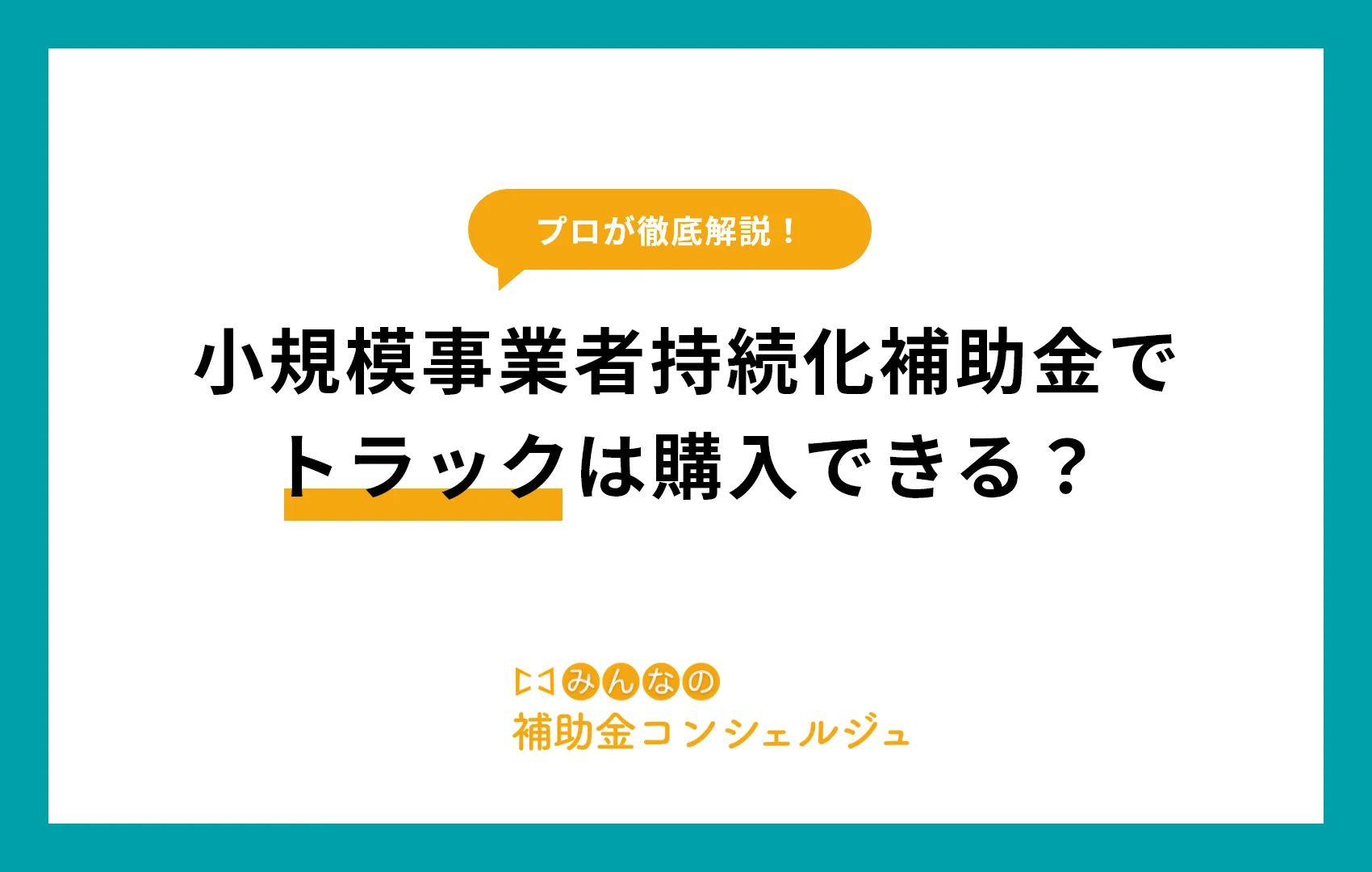小規模事業者持続化補助金の企業概要の書き方を記入例付きで解説!
小規模事業者持続化補助金の様式3「企業概要」の書き方を、記入例や具体的な事例を交えてわかりやすく解説。盛り込むべき項目や採択されるためのコツも丁寧に紹介します。
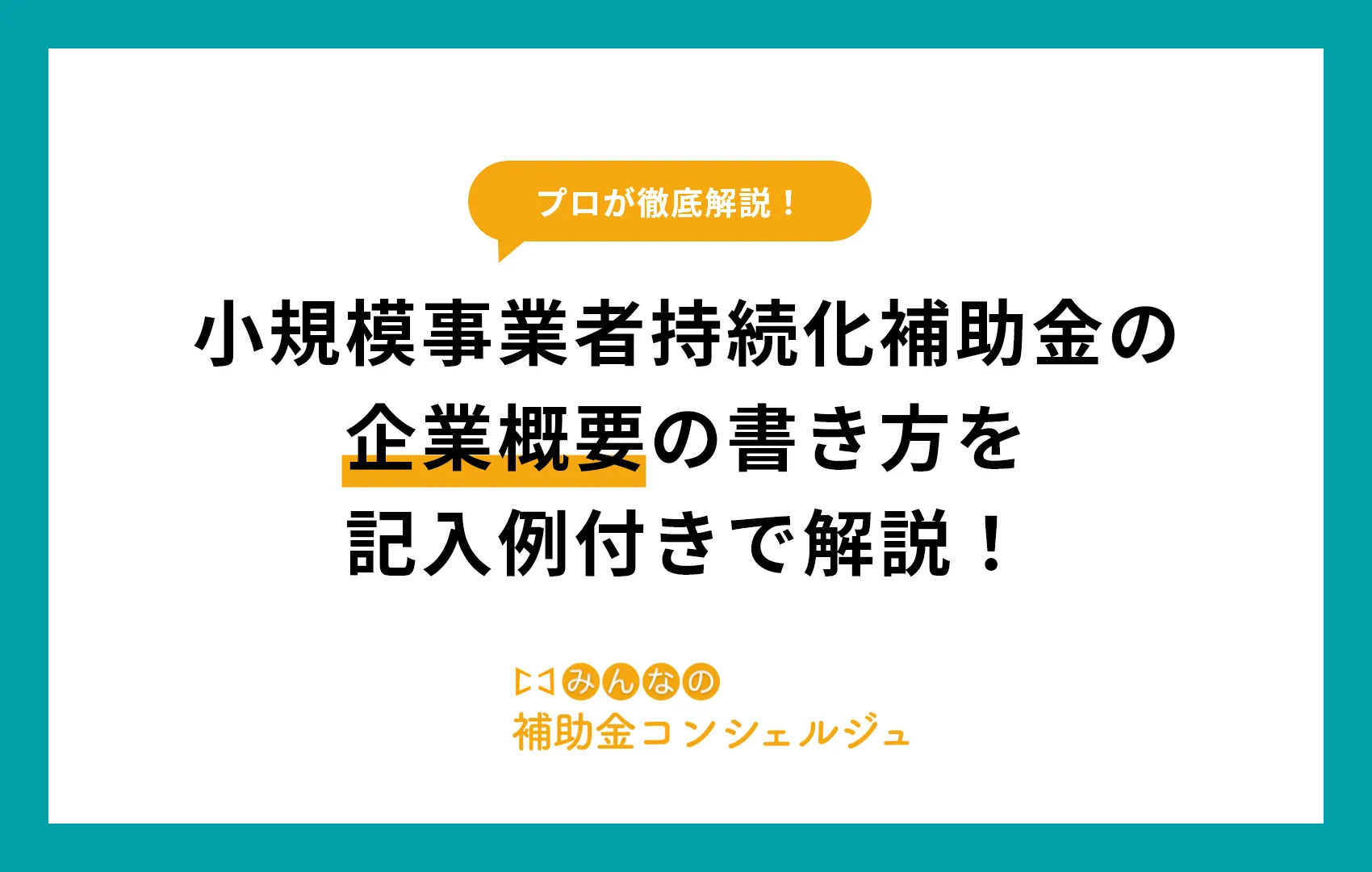
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
小規模事業者持続化補助金の様式3の「企業概要」とは?
小規模事業者持続化補助金の様式3の「企業概要」とは、自社の基本情報や沿革、事業内容、強みなどを簡潔にまとめ、補助事業を実施するうえでの信頼性や実現可能性を審査員に伝えるための項目です。補助事業そのものが魅力的であっても、それを担う事業者に説得力がなければ採択されにくくなるため、企業概要は申請全体の土台となる重要なパートです。
以下に、企業概要欄の基本的な位置づけや提出形式を表にまとめました。
| 項目 | 内容 |
| 提出書類名 | 様式3(企業概要) |
| 目的 | 事業者の概要・沿革・強みなどを記載し、補助事業の背景を明らかにする |
| 位置づけ | 審査員が企業の信頼性や事業の実現性を判断するための「土台」となる情報 |
| 提出形式 | 所定の様式に記入して、申請書類として提出(PDFやWordなど) |
補助事業の魅力だけでは採択は勝ち取れません。企業概要では、事業者としての信頼性や実行力をいかに具体的に伝えるかが鍵となります。たとえば、「なぜこの事業を自社が行う意義があるのか」「どんな実績や強みがあるのか」といった視点を盛り込むことで、審査員に納得感を与えることができます。単なる事実の羅列ではなく、補助事業との関連性を意識して記述することが重要です。記入のコツや構成例については、次の章で詳しく解説します。
「企業概要」の項目は自分で一から考えて書く
申請に使う様式3の書式には、あらかじめ詳細な入力欄や定型フォーマットが用意されているわけではありません。「まっさら」な状態に「企業概要」という項目名だけがあるだけで、内容は自分で一から考えて埋めていく必要があります。どのように書くべきか迷う場合は、以下のような支援先を活用するのが一般的です。
- 商工会議所・商工会の担当者による助言
- 中小企業診断士や補助金コンサルタントなど専門家のサポート
これらの支援を受けることで、客観的な視点から事業の特徴や強みを整理でき、審査員に伝わる内容へとブラッシュアップできます。
企業概要は、補助金申請における「第一印象」となるパートです。事業者の信頼性や、なぜその企業が補助事業に取り組むのかを理解してもらうために、定量的な情報や他社との違い、自社の強みを明確に伝える必要があります。テンプレートに頼るのではなく、自社の言葉で具体的に書くことが、採択率アップの鍵になります。
小規模事業者持続化補助金の企業概要に書く内容は?
様式3「企業概要」には、補助事業の背景となる企業情報を具体的かつ簡潔に記載することが求められます。ここでは、公募要領に沿って、書くべき主な項目とその内容を整理します。
企業概要に盛り込むべき情報
以下の6項目をバランスよく記載することで、事業者としての信頼性や補助事業の妥当性を審査員に伝えることができます。
| 項目名 | 内容のポイント |
| 1.基本情報 | 屋号または法人名、所在地、設立年、法人/個人の別など。誰が・どこで・いつから事業をしているかを明確に記載。 |
| 2.事業内容 | 主力商品・サービス、取引先、顧客層、地域的な特徴などを具体的に。専門用語は避け、第三者が読んでわかる表現で。 |
| 3.自社の強み | 技術力、サービス品質、接客力、スピード対応、地域密着など、他社との差別化ポイントを端的に示す。数字や実績があれば加える。 |
| 4.沿革 | 創業の経緯や、これまでの主要な事業展開、業態転換など。長く続けてきた信頼性や、変化への対応力を伝える場。 |
| 5.従業員構成 | 常時使用する従業員数(※)や、職種・雇用形態の内訳。将来の雇用創出につながる記述があると好印象。 |
| 6.補助事業との関連性 | なぜこの企業がこの補助事業に取り組むのか、その背景や課題意識。事業内容とのつながりを簡潔に触れる。 |
※「常時使用する従業員数」の考え方は、業種ごとに上限が定められており、アルバイト・パートも一定の条件で含まれます(例:製造業なら20人以下)
参考:小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第18回公募要領
書き方のポイント
企業概要を書く際は、単なる情報の羅列ではなく、「読みやすく、納得感のある文章」に仕上げることが大切です。以下の3つの観点から、具体的な書き方のコツを押さえておきましょう。
1. 構成:400〜600文字を目安に、段落で整理する
全体の文字数は400〜600文字が適量です。項目ごとに段落を分け、次のような流れで整理すると読みやすくなります。
- 1段落目:基本情報と事業内容(例:設立年、所在地、主力商品)
- 2段落目:強み・沿革(例:創業背景、技術力、地域密着の取り組み)
- 3段落目:従業員構成・補助事業との関係(例:従業員の特性と補助事業への活用理由)
2. 文体:自然な語り口で、主語+述語を明確に
「当社は〇〇業を営んでおり、△△地域を中心に□□を提供しています。」のように、主語と述語がはっきりした文体を意識しましょう。読み手(審査員)にとって、誰が何をしているのかがすぐに分かる文章が好まれます。
3. 表現:曖昧な言葉は具体例で補強する
「地域密着」「高いサービス力」「信頼されている」といった抽象的な表現だけでは伝わりません。たとえば、
- ✕ 地域に密着したサービスを展開
- ○ 半径5km圏内の高齢者宅を週2回訪問し、訪問販売を継続
のように、具体的な数字やエピソードで裏づけると説得力が高まります。
企業概要は、事業計画全体の「背景説明」としての機能を持ち、補助事業の必要性を補強する役割を果たします。単なる会社紹介にとどめず、「なぜこの事業を行うのか」を自然に連動させる構成が、採択の鍵となります。
小規模事業者持続化補助金の企業概要の書き方のコツ3選
企業概要は、申請書の中でも「誰がこの補助事業を行うのか」を審査員に伝える重要なパートです。ただ情報を羅列するのではなく、次の3つの視点を意識することで、説得力のある内容に仕上がります。
- 具体的な表現・数値で信頼性を高める
- 他社と差別化されたポイントを書く
- 補助事業とのつながりを自然に含める
それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。
コツ1:具体的な表現・数値で信頼性を高める
抽象的な言い回しは避け、実績や規模を示す具体的な数値を盛り込むことで、企業としての信頼性が高まります。
| 抽象的な表現 | より具体的な言い換え例 |
| 長年の実績がある | 創業20年、地域での施工実績1,200件 |
| 顧客対応に力を入れている | クレーム発生率0.1%、リピート率80% |
| 小規模ながら堅実に運営 | 年間売上3,000万円、従業員4名体制 |
コツ2:他社と差別化されたポイントを書く
審査員は、多数の申請書に目を通しています。「この会社ならではの特長」を記載することで、記憶に残る企業概要になります。差別化ポイントの一例として、以下のようなものが挙げられます。
- 地域特化(○○市内限定で展開)
- スピード対応(当日見積・翌日納品)
- 顧客層に特化(介護施設専門、訪問美容など)
- 特殊資格の保有(管理栄養士、施工管理技士など)
コツ3:補助事業とのつながりを自然に含める
企業概要の中で、補助事業の計画につながる自然な流れを意識することで、申請全体に一貫性が生まれます。補助事業だけが浮いた印象になるのを防ぎ、計画の必要性や妥当性にも説得力をもたせることができます。企業概要と補助事業が無理なくつながるよう、以下のように背景や課題を交えて記述すると効果的です。
| 補助事業の内容 | 背景・課題 | 取り組みの目的・方向性 |
| EC販売の強化 | 地方顧客からの購入希望があるが、対面販売に限定されている | オンライン販売を整備し、全国展開を目指す |
| 新商品の開発 | 創業以来の技術を活かせるが、既存商品では競争力が弱まっている | 高付加価値商品を開発し、新規顧客層へアプローチする |
| 店舗のバリアフリー改修 | 高齢顧客の来店が増える中、設備面の不安がある | スロープや手すりを設置し、誰でも来店しやすい店舗づくりを実現する |
小規模事業者持続化補助金の企業概要【記入例】
「企業概要」は、計画書の冒頭に記載する重要なパートであり、申請者である事業者の背景や特徴を審査員に伝える役割を果たします。自社の状況に合わせて、必要な情報をわかりやすく整理・構成することが求められます。ここでは、よく使われる6つの構成パートと、それに沿った記入例をご紹介します。
| パート | 内容 |
| 1.事業内容 | 創業の経緯や所在地、事業の基本情報を簡潔に説明 |
| 2.自社の強み | 他社と差別化できる要素(技術・対応力・地域密着など) |
| 3.沿革 | これまでの実績や事業転換の経緯、展望 |
| 4.商品・サービス実績 | 主力商品やサービス、利益率、売上構成など |
| 5.従業員構成 | 現在の従業員数や雇用形態、今後の体制について |
| 6.補助事業との関連性 | 補助事業がどのように企業の成長や課題解決につながるか |
企業概要の記入例
1.事業内容
当社は、2020年4月に創業し、2022年に法人化した薬膳料理教室を運営しています。東京都新宿区に事務所を構え、平日10:00〜19:00の時間帯で営業しています。「健康的な薬膳料理を誰もが楽しめるように」をコンセプトに、初心者向け講座から専門家向けのライセンス発行までを一貫して提供しています。
2.自社の強み
講座で使用する教材はすべて自社で開発しており、薬膳の理論と実践をバランスよく学べる点が好評です。生徒の8割以上が継続受講をしており、SNSや口コミでの集客にも成功しています。高い粗利率(80~90%)を維持しながら、地域や年齢層を問わず受講生を増やしています。
3.沿革
創業当初は家庭向けの出張型教室を展開していましたが、コロナ禍を契機にオンライン講座へ移行。2022年の法人化を経て、現在では対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型の運営体制を確立しています。2023年からはプロ向けのライセンス発行事業も開始しました。
4.商品・サービス実績
主力サービスは月額2万円の薬膳料理教室および10万円のライセンス発行講座です。以下に昨年度の実績を示します。
| サービス名 | 利用者割合 | 利益率 | 年間売上(千円) |
| 月額スクール | 約90% | 約70% | 約6,800 |
| ライセンス発行講座 | 約10% | 約90% | 約300 |
5.従業員構成
現在は代表1名体制で事業を運営しています(従業員数:3名)。今後は事業拡大に合わせて、事務作業や運営補助のための人員確保(外注または雇用)を計画しています。
6.補助事業との関連性
今回の補助事業では、ホームページに新たにEC機能と講座予約システムを導入し、教材のオンライン販売と受講申し込みの利便性を高める予定です。これにより、地方や遠方の顧客にもサービスを提供でき、販路拡大と業務効率化を両立させることが可能となります。
企業概要を書く際は、「誰が・何を・なぜ・どうやって」事業を行っているのかが明確に伝わるように意識しましょう。売上や顧客数などの数字を取り入れることで信頼性が高まり、他社との違い(強み)をひとつでも示すと印象に残りやすくなります。また、補助事業と企業の課題や将来の展望をつなげることで、「なぜこの事業に補助金が必要なのか」という説得力を持たせることができます。
小規模事業者持続化補助金の企業概要でよくあるNG例と修正ポイント
企業概要は自由記述である分、内容に差が出やすいパートです。よくあるNG表現を避け、読み手(審査員)にしっかりと伝わる内容にすることが、採択率を上げるうえで欠かせません。
以下によくあるNG例と、その改善ポイントを紹介します。
| NG内容 | よくあるNG表現 | 修正ポイント・改善例 |
| 1.抽象的すぎて中身が伝わらない | 地域密着のサービスを提供 | 地域半径5km圏内の高齢者宅を週2回訪問し、買い物代行・生活相談を実施 |
| 2.強みが曖昧・差別化できていない | 丁寧な対応でお客様に好評 | 年間100件以上の施工実績と、顧客アンケートで満足度90%超の対応力 |
| 3.補助事業とのつながりが見えない | 新しい設備を導入したい | 現在の設備では生産効率が頭打ちのため、自社の成長と雇用維持のために設備投資が不可欠 |
ポイントは、数字や実績を交えながら、「だからこそこの補助事業が必要だ」と読み手に納得させる構成にすることです。抽象的な言い回しは一見きれいに見えますが、審査の現場では情報量の少なさとしてマイナスに働きがちです。企業の現状や課題、補助事業の必然性を、できる限り具体的に言葉で補っていきましょう。
まとめ
様式3「企業概要」は、審査員に企業の信頼性や補助事業の妥当性を伝えるための重要なパートです。単なる会社紹介ではなく、数字や具体例を交えて他社との違いや強みを明確にすることが、採択率を高めるポイントになります。形式的な情報だけで終わらせず、「自社ならではの特徴」や「補助事業とのつながり」を丁寧に盛り込むことで、読み手の納得感を高められます。自社の魅力を的確に伝えることを意識して、企業概要をしっかりと仕上げましょう。
監修者からのワンポイントアドバイス
企業概要は補助金の必要性や補助事業の適格性を伝えるための重要なパートとなります。具体的な数値を盛り込むことにより補助事業によりどのような変化を見込むことが出来るかが説明出来るようになります。補助事業による成果を示していくためにも重要です。