事業承継・M&A補助金とは?
事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金)とは、中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資や、M&AやPMIの専門家活用費用等を支援する補助金です。以下4つの申請枠で実施されます。
- 事業承継促進枠
- 専門家活用枠
- PMI推進枠
- 廃業・再チャレンジ枠
2025年最新版事業承継・M&A補助金の概要は?
事業承継・M&A補助金は個人事業主でも申請でき、売買の相手が個人事業主であっても対象となります。ただし、すべての個人事業主が申請できるわけではなく、一定の要件があります。本コラムでは、個人事業主が申請できる補助金額や補助率、申請時の注意点について解説します。2025年度、事業承継・M&A補助金の活用を検討されている個人事業主さまはぜひ本コラムをお役立てください。
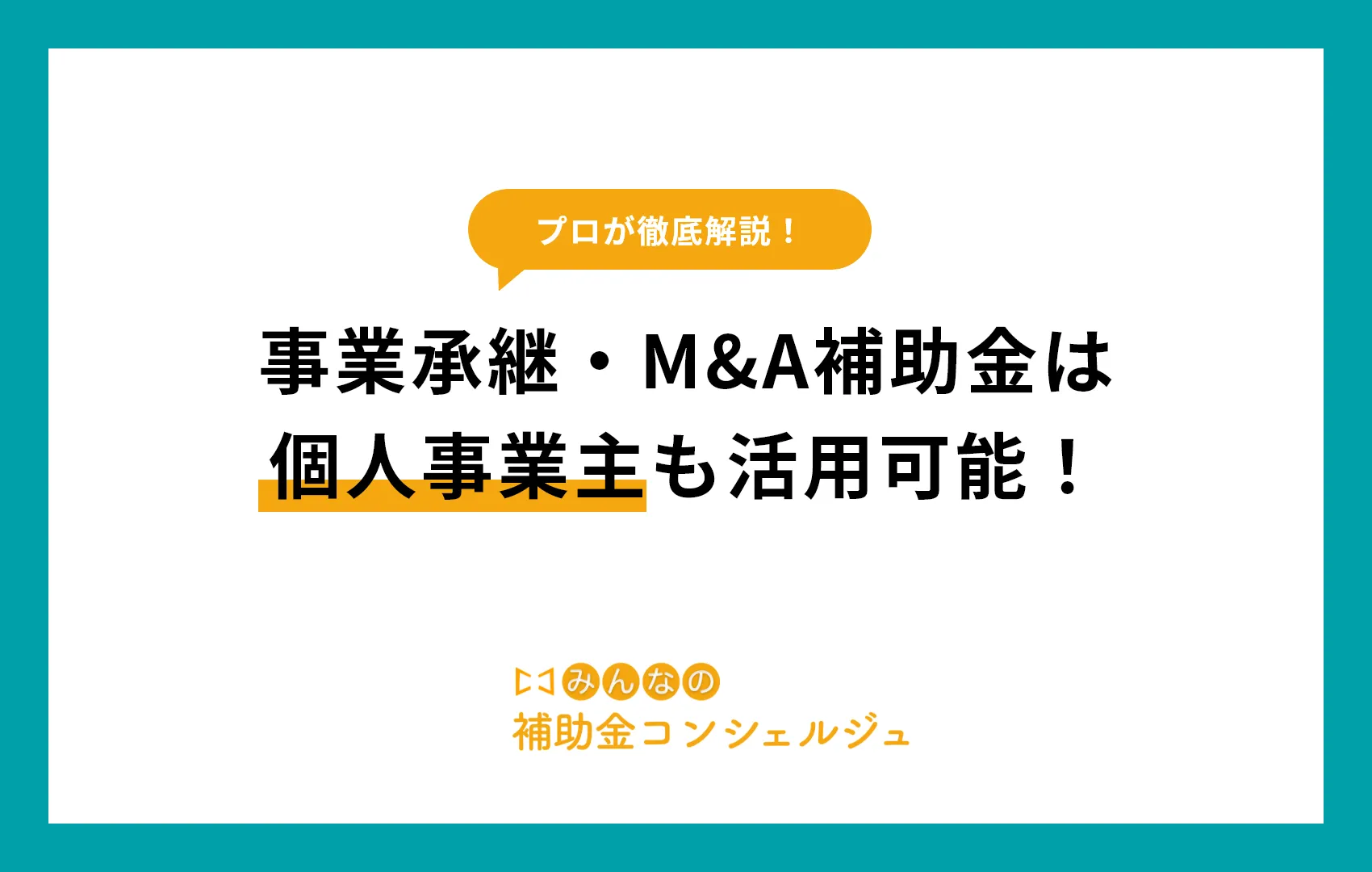

カミーユ行政書士事務所代表・行政書士
補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金)とは、中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資や、M&AやPMIの専門家活用費用等を支援する補助金です。以下4つの申請枠で実施されます。
2025年最新版事業承継・M&A補助金の概要は?
事業承継・M&A補助金を申請できる個人事業主の条件は以下のとおりです。まずは申請に必要な主な要件を一覧でチェックしましょう。
| 要件 | 内容 |
| 青色申告をしていること | 白色申告では申請不可 |
| 個人事業主であること | 法人でない「個人」は対象外 |
| 専門家活用枠の場合 | 青色申告を開始して5年以上経過している必要あり |
| 提出書類がそろっていること | 「確定申告書B」と「青色申告決算書」の写し(税務署の受領印または受付メールが必要) |
補助金の申請には、青色申告をしている個人事業主であることが条件です。白色申告では申請できません。青色申告とは、帳簿付けや貸借対照表の作成などが求められる分、税制上のメリットがある申告方法です。
たとえば「青色申告特別控除」による節税効果が期待できます。まだ白色申告をしている場合は、この機会に青色申告への変更を検討しても良いでしょう。
変更には、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告について調べる!
申請には、以下の書類のコピーが必要です。
これらの書類を提出書類として使うには、実際に税務署に提出した証拠(=受付印またはe-Taxの受付完了メール)が必要です。
青色申告の申請書をダウンロードする!
個人事業主でも、これらの書類が揃っていれば補助金をしっかり活用できます。まずは、ご自身の申告状況と書類の保管状況を確認してみましょう。
事業承継・引継ぎ補助金(令和5年度補正予算)の採択率は以下の通りです。
| 事業区分 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |
| 経営革新事業 | 313件 | 190件 | 60.7% |
| 専門家活用事業 | 498件 | 299件 | 60.0% |
| 廃業・再チャレンジ事業 | 28件(単独2件、併用26件) | 10件 | 35.7% |
※「経営革新事業」については、採択者一覧が公開されています。
採択率は事業区分ごとに異なり、経営革新事業・専門家活用事業は60%前後と比較的高い水準ですが、廃業・再チャレンジ事業は35.7%とやや低めです。
令和7年度の事業承継・引継ぎ補助金は、「事業承継促進枠」「専門家活用枠」「PMI推進枠」「廃業・再チャレンジ枠」に分かれると予想されます。それぞれの採択率について、過去の実績を踏まえた予測を行います。
昨年度の経営革新事業に相当する枠と考えられます。令和5年度の採択率は60.7%だったことから、令和7年度も55%〜65%の範囲に収まる可能性が高いでしょう。
特に、事業承継支援が強化される場合は、採択率がやや上昇する可能性もあります。
昨年度の専門家活用事業の採択率が60.0%だったため、同程度の水準となることが予測されます。55%〜65%の範囲で推移すると考えられ、事業者のニーズに応じて若干の変動があるかもしれません。
M&Aの後継支援を目的とした枠として新設されると予想されます。過去に類似の枠がないため正確な比較はできませんが、経営革新事業の採択率を参考にすると、50%〜60%の範囲になる可能性が高いでしょう。PMIはM&Aの成功を左右する重要なプロセスであり、支援の必要性も高いため、比較的高めの採択率が期待できます。
令和5年度の廃業・再チャレンジ事業の採択率が35.7%だったため、30%〜40%の範囲に収まると考えられます。この枠は事業承継促進よりも優先順位が低くなりやすいため、他の枠と比べて採択率が低めに設定される傾向が続くと考えられます。
これらの予測を踏まえると、令和7年度の補助金申請に向けて、採択率が高い枠を選ぶ戦略も重要になってくるでしょう。正式な公募情報が発表され次第、最新の採択率を確認することをおすすめします。
個人事業主が事業承継・M&A補助金を申請するには、補助対象事業の確認、認定経営革新等支援機関への相談、電子申請システムの利用など、いくつかの手順を踏む必要があります。
申請の流れは以下のとおりです。
補助対象事業が決まったら、次は認定経営革新等支援機関に相談しましょう。これは、中小企業庁が認定する、事業承継や経営改善の支援ができる専門機関です。
主な機関の例
とくに「経営革新枠」や「廃業・再チャレンジ枠」を申請する場合は、この機関からの確認書の発行が必須となります。申請前に必ず相談・連携しておきましょう。
事業承継・引継ぎ補助金を申請するには、gBizIDプライムアカウントの作成が必要です。このアカウントは、政府が運営する「jGrants(Jグランツ)」という電子申請システムを利用するためのものです。申請は以下の流れで進めます。
手続きには時間がかかるため、できるだけ早めにアカウントを取得しておくことがポイントです。
補助金の申請後、審査結果はjGrants上で通知されます。通知を受け取ったら、必ず内容を確認し、交付条件などをしっかり把握しておきましょう。
もし申請に不備があった場合は、jGrantsから連絡が来ますので、速やかに修正・再提出してください。なお、交付申請を取り下げたい場合は、通知を受けた日から10日以内に事務局へ申し出る必要があります。
実績報告の後には、事務局による「確定検査」が実施されます。この検査では、提出した報告書や証拠書類をもとに、補助金の使い方や事業の実施状況がチェックされます。問題がなければ補助金の額が確定し、指定口座に入金されます。
つまり、交付には申請だけでなく、報告・検査まで含めた一連の手続きが完了している必要があります。
個人事業主が事業承継・M&A補助金を申請する際には、募集期間と審査の加点ポイントに注意が必要です。
事業承継・M&A補助金は、常時募集ではなく、公募期間が設定されています。申請を検討している場合は、中小企業庁の公式サイトで最新のスケジュールを確認しましょう。
公募期間には、
が明確に定められています。準備を始める前に必ずチェックし、締め切りに間に合うよう計画を立てましょう。
補助金の審査では、事業計画の内容や各種認定・取組実績に応じて「加点評価」される制度があります。公募要領を確認のうえ、該当する加点条件を満たし、証明書類を添付することで採択率の向上が期待できます。事業承継・M&A補助金で評価対象となる加点項目は、以下のとおりです。
| 加点項目 | 内容の概要 |
| 地域未来牽引企業 | 経済産業省により「地域未来牽引企業」に選定されている企業 |
| 健康経営優良法人 | 「健康経営優良法人」に認定されている企業 |
| アトツギ甲子園出場 | 承継予定者(代表含む)がアトツギ甲子園に出場 |
| 特定創業支援等事業(Ⅰ型のみ) | 認定市区町村による創業支援を受けた場合(Ⅰ型限定) |
| 地域おこし協力隊 | 承継者が地域おこし協力隊として活動している |
| サイバーセキュリティお助け隊 | IPAのセキュリティ支援サービスを利用中 |
| 第三者作成のPMI計画書(Ⅰ型・Ⅲ型) | 専門家等が作成したPMI(統合)計画を提出している |
| 会計要領・指針の導入 | 「中小企業の会計に関する要領」または「指針」を導入済み |
| 事業継続力強化計画 | BCPとして「事業継続力強化計画」の認定を受けている |
| ワーク・ライフ・バランスの取組 | 下記①②のいずれかに該当すれば加点対象 ①女性活躍推進 ②次世代育成支援 |
| 経営関連計画の認定 | 以下いずれかの認定を受けている:・経営力向上計画・経営革新計画・先端設備等導入計画 |
「事業承継・引継ぎ補助金」は、中小企業・小規模事業者が円滑に事業を引き継ぎ、成長戦略を実行するための費用を支援する制度です。個人事業主も対象ですが、採択にはしっかりとした準備が不可欠です。特に個人事業主が意識すべき以下5点の採択のポイントを紹介します。
「去年と同じ内容で申請すればいい」と考えるのはNGです。補助金制度は毎年見直されるため、最新の公募要領を必ず確認しましょう。たとえば、以下の点は年度によって変わる可能性があります。
| 項目 | 変更されることが多い内容 |
| 補助額 | 上限額・下限額の見直し |
| 補助率 | 2/3から1/2に変更される年も |
| 対象経費 | 新たに追加・除外される費目あり |
| 申請区分 | 経営革新型・専門家活用型など枠組み変更も |
最新のルールに則った計画を立てることが採択の大前提です。
どれだけ中身が優れていても、書類の記入漏れや添付忘れがあると不採択の可能性が高まります。
電子申請に不慣れな方は、早めに準備を進めることが肝心です。
補助金には明確な採択基準があり、これを押さえることが成功のカギです。特に以下の要素は高く評価されます。
これらの要素を、単なる方針ではなく「具体的な取り組み」として事業計画に落とし込むことが重要です。
「書き方が分からない」「経営の計画なんて立てたことがない」という方は、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
プロに相談することで、事業の将来像を明確に描きやすくなり、書類の完成度も高まります。
補助金の審査では、「引き継いだあとにどんな発展を見込んでいるか」が非常に重要です。単に現状維持をするだけでは、採択されにくくなります。
こうした具体的な成長戦略や数値目標を、事業計画書に盛り込みましょう。M&Aの場合は「経営統合(PMI)計画」もポイントです。事業承継・引継ぎ補助金は、個人事業主にとっても貴重な支援制度です。
特に、後継者として事業を受け継ぎながら成長戦略を描いている方にとっては、資金的な後押しとなるチャンスです。採択のカギは、「実現性の高い成長戦略」と「丁寧な準備」。制度を正しく理解し、必要に応じて専門家のサポートを受けながら、しっかりとした計画と書類で勝負しましょう。
個人事業主でも「事業承継・M&A補助金」を活用することで、事業の成長や再チャレンジを実現することができます。ここでは、2025年度の各申請枠ごとに具体的な採択事例を紹介します。
事例:老舗和菓子店の事業承継による販路拡大
Aさんは、60年以上続く老舗和菓子店の経営者である父から事業を引き継ぐことになりました。
承継後、販路拡大と生産効率の向上を目指して、新しい製造設備を導入することを決意。補助金を活用し、最新の和菓子製造機器を導入することで、製造コストを20%削減。
また、オンライン販売システムも構築し、売上を大幅に伸ばすことに成功しました。
結果: 売上が前年対比150%に増加し、地域の特産品としてのブランド力も強化。
事例:美容サロンのM&Aによる経営拡大
Bさんは、個人で経営していた美容サロンを拡大するため、近隣で評判の良い別の美容サロンをM&Aで譲り受けることを決定。この際、フィナンシャルアドバイザー(FA)とデューデリジェンス(DD)の専門家を活用するための費用を補助金で賄うことができました。
結果: M&A後の店舗統合に成功し、サービス品質を維持しながら新規顧客を30%増加させることに成功。
事例:製造業のM&A後の経営統合(PMI)支援
C社は、製造業において競合他社をM&Aで買収しました。しかし、異なる社風や経営システムの統合に苦労していました。
PMI推進枠を利用して、経営統合のためのコンサルティングや新しいITシステムの導入に取り組みました。
結果: ITシステムの統合と経営方針の見直しにより、生産効率が25%向上し、コスト削減にも成功。
事例:飲食店経営からの業態転換と再挑戦
Dさんは、個人で経営していた飲食店を廃業する決意をしました。しかし、長年の飲食業で得たノウハウを活かし、新たにケータリング事業を立ち上げることを決意。
廃業にかかる在庫廃棄費や店舗の解体費用を補助金で支援され、再チャレンジのための資金を確保できました。
結果: ケータリング事業は軌道に乗り、地域のイベントや企業向けサービスとして広く支持されるようになりました。
事業承継・引継ぎ補助金の「経営革新枠」では、個人事業主が事業を引き継ぐ際に、最大で600万円の補助を受けることが可能です。
具体的な補助上限額は、事業の類型や内容によって異なります。例えば、「創業支援類型」や「経営者交代類型」など、各類型ごとに設定された上限額が適用されます。詳細は、最新の公募要領をご確認ください。
はい、個人事業主が「事業承継・M&A補助金」を申請する場合、補助額は申請する類型や事業内容によって異なります。
以下に、主な類型とその補助上限額をまとめました。
| 補助上限額 | 補助率 | 対象経費 |
| 最大600万円 | 2/3 | M&Aに伴う設備投資、販路開拓費用など |
| 補助上限額 | 補助率 | 対象経費 |
| 最大400万円 | 2/3 | M&A仲介手数料、デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用など |
個人事業主が申請するには、以下の要件を満たす必要があります。
事業承継・引継ぎ補助金の補助上限額は、申請する類型によって異なります。
例えば、「経営革新枠」の「創業支援類型」では最大600万円、「経営者交代類型」や「M&A類型」では最大800万円の補助が受けられる場合があります。また、補助率は原則として2/3です。具体的な金額や条件は、公募要領や公式サイトで最新情報をご確認ください。
はい、個人事業主が受け取る事業承継・M&A補助金は、所得税の課税対象となります。
この補助金は、交付を受けた事業年度の収益として計上されるため、所得税の申告時に含める必要があります。特に、補助金額が大きい場合は、納税額にも影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
また、補助金を固定資産の取得に充てた場合、一定の条件を満たせば、所得税法第42条に基づく「圧縮記帳」の適用が可能となる場合があります。これにより、課税所得を抑えることができる可能性があります。
ただし、適用には細かな要件があるため、事前に税理士などの専門家に相談することをおすすめします。補助金の交付を受けた際は、適切な税務処理を行うためにも、早めに専門家と連携し、必要な手続きを確認しておくことが重要です。
形式的な名義変更だけでは、申請は認められません。
事業承継補助金では、単なる書類上の名義変更ではなく、実質的に経営権が移転していることが求められます。たとえば、従来の経営者が引退し、新しい経営者が事業運営の意思決定を担っているかどうか、具体的な事業計画の再構築がなされているかが審査のポイントとなります。
承継の一環として法人化した場合は、申請可能です。
たとえば、後継者が個人事業を引き継いだうえで法人化した場合、その流れが明確に説明できるのであれば問題ありません。この際は、開業届・廃業届・法人設立届出書などの提出書類や承継計画の整合性が問われるため、事前に専門家への相談をおすすめします。
はい、M&Aによる事業承継も補助対象です。
近年では、親族内承継に限らず、第三者によるM&Aを活用した事業引継ぎも増えています。この場合も、譲渡契約書などの証憑類の整備や、実際に経営権が移転していることが客観的に確認できる体制が必要です。M&A支援業者を通じたサポート費用も、一部補助対象となる場合があります。
以下のような条件を満たす事業者が対象です(中小企業基本法第2条に準拠)。
詳細は以下をご確認ください。
参考:公募要領
参考:中小企業庁「中小企業の定義について」
対象外です。申請には以下の要件を満たす必要があります。
いいえ。被承継者・承継者の両方が青色申告者でなければなりません。
白色申告者は対象外です。
確定申告書Bと青色申告決算書(税務署印あり)の写しが必要です。
参考リンク:青色申告に必要な手続き(国税庁)
対象になりません。以下の両方が「中小企業者等」である必要があります。
条件付きで可能です(創業支援類型に限る)。以下のいずれかを補助事業期間中に満たす必要があります。
申請可能です。ただし、以下の情報が記載された住民票の提出が必要です。
参考:在留資格一覧表
参考:住民票の取得方法(例:神奈川県川崎市)
事業承継・M&A補助金に関するよくある質問をチェックする!
参考:事業承継・M&A補助金公式サイト
事業承継・M&A補助金は、中小企業や個人事業主が事業の引継ぎをスムーズに進めるための国の制度です。個人事業主も、青色申告をしていれば申請可能です。
補助金には以下の枠があります。
それぞれ対象となる事業や補助内容が異なるため、自分に合った枠を選びましょう。
申請の主な流れは以下のとおりです。
申請には時間がかかる準備もあるため、スケジュールに余裕を持って行動することが大切です。制度をしっかり活用して、事業の引継ぎを成功させましょう。
個人事業主に人気!小規模事業者持続化補助金の概要をチェックする
個人事業主が受けられる融資は?融資後の事業計画も解説
個人事業主もOK!リスキリングに使える助成金を分かりやすく解説します!
事業承継・M&A補助金(旧:事業承継引継ぎ補助金)の全枠の平均採択率は約57%です(9次公募まで採択率)。
採択率は申請する枠によって異なりますが、過去には枠によっては40%を切る公募回もありました。
専門的なサポートを受けることが採択への近道です!
弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります。
専門家による的確なアドバイスとサポートで、御社を採択へ導きます!ぜひお気軽に弊社にご相談ください。
「簡単な内容を伝えただけで、立派な書類に仕上げていただきました。急な変更にもすぐ対応してくれて、とても満足です!」
「電話やメールで手続きが完了するので非常に楽でした!LINEでも相談できる気軽さもよかったです。」
「必要な情報を渡すだけで専門家がすべて対応してくれます!リアリゼイションのマニュアルを活用すれば、必要なところを穴埋めするだけで書類ができますし、とにかく時間が浮きました。」
「事業承継引継ぎ補助金」の申請を検討中の方は、以下のフォームよりお問い合わせください!
「初めて補助金を活用するから不安!プロにサポートしてほしい!」
「うちの会社も事業承継引継ぎ補助金に申請できるかな?」
など、ご相談だけでもOK!あなたのお悩みをぜひお聞かせください。

本補助金はM&Aや事業承継をサポートするための設備投資や専門家に対する経費を補ってくれるものとなっています。申請する枠によって経費の内容や金額が異なって来ます。国の方としても事業承継などを推進する一助として本補助金を用意していますので検討できるようでしたら考慮してみると良いでしょう。