テレワーク導入に使える助成金は?
テレワーク導入時に使える助成金・補助金は複数あります。代表的なのは、
- 厚生労働省の「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」
- 同じく厚労省の「両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」
- 経済産業省の「IT導入補助金」
- 自治体独自のテレワーク助成金(東京都など)
- です。
本記事では、それぞれの対象経費・助成額・注意点をわかりやすく整理します。
テレワーク導入費用に助成金が活用できます。このコラムでは、テレワーク導入に使える国と自治体の助成金を紹介します!
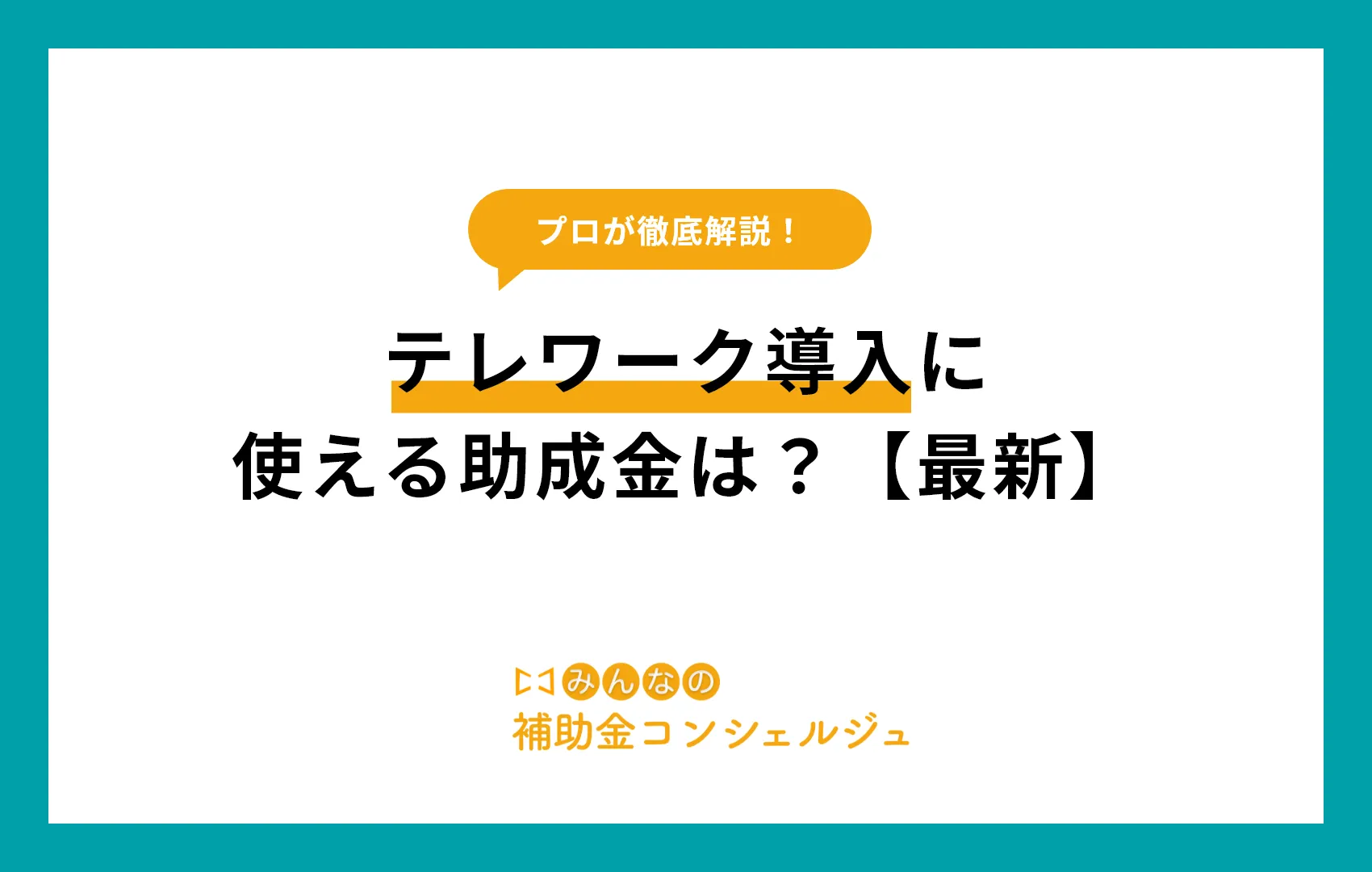

カミーユ行政書士事務所代表・行政書士
補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
テレワーク導入時に使える助成金・補助金は複数あります。代表的なのは、
本記事では、それぞれの対象経費・助成額・注意点をわかりやすく整理します。
テレワーク助成金は、パソコンやクラウドツールの購入費用だけでなく、導入時の研修・設定費用まで幅広く支援対象となります。ただし、消耗品や人件費などは対象外となるため、申請前に経費区分を明確にすることが重要です。
| 区分 | 主な内容 | 注意点 |
| ハードウェア | ノートPC、カメラ、VPN機器など | 購入は「交付決定後」が原則 |
| ソフトウェア | 勤怠管理、チャット、クラウド、セキュリティ対策ツール | 登録ベンダーからの購入が必要な場合あり |
| 導入費用 | コンサルティング、設定、研修 | 一部の助成金では重点対象 |
テレワーク導入にかかる費用の範囲は、制度によって対象が異なります。厚生労働省の「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」では、就業規則の整備や研修などの職場環境づくりに加えて、テレワーク用の通信機器やクラウドサービスの導入・運用費も支援対象となります。制度面と環境面の両方を整えるための助成金です。
一方、経済産業省の「IT導入補助金」では、業務効率化やテレワークに役立つクラウドツール・ソフトウェアの導入費が中心です。パソコンやタブレットなどのハードウェアは、対象ソフトと一体で導入する場合のみ補助対象となる点に注意が必要です。
また、多くの補助金・助成金に共通して「交付決定前に契約・購入したものは補助対象外」とされています。機器の購入やサービス契約は、必ず交付決定(または認定)後に行いましょう。目的(研修・IT導入・制度整備など)を明確にしたうえで、それぞれの制度の公募要領で対象経費を確認しておくことが大切です。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、企業がテレワーク制度を導入し、離職防止や柔軟な働き方の実現を目指す際に活用できる厚生労働省の助成金です。テレワークの導入準備から効果検証までを一貫して支援し、制度を社内に定着させることを目的としています。
この助成金では、テレワークを円滑に進めるための社内体制づくりや制度整備が中心です。
一方で、テレワーク実施に必要な通信機器やクラウドサービスの導入・運用費も助成対象に含まれます。
<対象となる取組例>
支給は2段階で行われます。
| 区分 | 内容 | 助成率・上限 |
| 機器等導入助成 | テレワーク用通信機器や研修などの導入・整備 | 対象経費の50%(上限100万円または対象労働者1人あたり20万円) |
| 目標達成助成 | 一定期間テレワークを実施し、離職率低下などの効果が確認できた場合 | 上限57万円(または対象労働者1人あたり15万円) |
この助成金は、単なる機器導入支援ではなく「制度・人材・風土づくり」までを支援する点が特徴です。テレワークを一時的に導入するだけでなく、企業文化として根付かせたい中小企業に向いています。
また、助成対象経費は「テレワーク実施計画の認定日以降に実施した取組」に限定されるため、計画認定前の契約や購入は対象外です。事前準備のタイミングには注意しましょう。
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)は、は、企業が育児期の従業員の仕事と家庭の両立を支えるために、複数の柔軟な働き方制度を導入・運用する際に活用できる、厚生労働省の助成金です。テレワークやフレックスタイム、短時間勤務など、複数制度を整備して実際に従業員が利用することで、働きやすい環境を作りつつ離職防止や定着促進につなげることを目的としています。
このコースでは、従業員が選べる柔軟な働き方制度を2制度以上導入し、さらに従業員による制度利用と利用後のキャリア支援を図る取り組みが助成対象です。導入制度には以下のようなものがあります。
<対象となる取組例>
いずれも就業規則や労働協約・規程等に制度内容を明記するとともに、対象従業員との面談・「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」の作成・社内周知を行ったうえで、制度利用開始から6ヶ月以内に一定の利用実績を満たす必要があります。
| 区分 | 導入制度数・利用実績 | 助成額(1人あたり) | 上限人数(1年度) | 備考 |
| A区分 | 2制度を導入し、従業員が実際に利用した場合 | 20万円 | 5人まで(最大100万円) | 制度導入+利用実績が条件 |
| B区分 | 3制度以上を導入し、従業員が実際に利用した場合 | 25万円 | 5人まで(最大125万円) | 多制度導入による上乗せ支援 |
| 加算 | 育児休業取得状況などを公表した場合 | +2万円/人 | 同上 | 公表制度の利用時に加算 |
この助成金の特徴は、制度導入だけでなく実際の利用・運用までを重視している点です。企業が一方的に制度を整えるだけでは対象にならず、従業員が制度を活用しやすい体制を整備することが求められます。また、申請時には以下の点に注意しましょう。
IT導入補助金は、企業の業務効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を支援する経済産業省の補助金です。勤怠管理・会計・チャット・商談管理・クラウドツールなど、テレワーク業務を支えるIT基盤の整備にも幅広く活用できます。
厚生労働省の助成金が「人や制度への投資」を支援するのに対し、IT導入補助金は「ITツールへの投資」を後押しする制度といえます。
この補助金では、生産性向上やテレワーク対応につながるITツールの導入費用が支援対象です。補助対象となるのは、事前に登録された「IT導入支援事業者」を通じて導入するツールに限られます。
<対象となるITツール例>
これらを導入することで、オフィスに依存しない働き方や、業務のデジタル化を進めることができます。
| 類型 | 補助率 | 補助上限額 |
| 通常枠 | 1/2(賃上げ実施で2/3) | 最大450万円 |
| 複数社連携枠 | 2/3 | 最大450万円 |
| インボイス枠 | 3/4(小規模は4/5) | 最大350万円 |
| セキュリティ枠 | 2/3 | 最大150万円 |
「インボイス枠」では、会計ソフトやクラウドツールに加えて、パソコンの購入も補助対象になります。一方、「セキュリティ枠」はテレワーク環境の安全性を高めるためのサイバーセキュリティ対策ツールが対象です。
IT導入補助金の特徴は、登録された「IT導入支援事業者(ベンダー)」を通じて申請・導入を行う点にあります。申請者が自由に購入することはできませんが、登録ベンダーが申請書作成から交付手続きまでサポートするため、初めてでも取り組みやすい制度です。
自治体でも、地域の実情に合わせたテレワーク助成制度が数多く設けられています。その中でも特に支援内容が充実しているのが東京都で、制度の目的や対象、支給額が明確に定められています。ここでは代表的な2つの制度を紹介します。
この制度は、企業がテレワークを一時的に導入するだけでなく、長期的に定着させることを目的とした支援制度です。企業内で課題を分析し、改善策を実行して継続的な働き方改革を進める取組を対象としています。
| 項目 | 内容 |
| 目的 | テレワークの定着・改善を支援 |
| 内容 | 課題調査・改善計画・新ルール策定など |
| 助成額 | 20万円 |
| 対象 | 東京都内の中堅・中小企業 |
この奨励金では、単なるツール導入ではなく、テレワークの実施体制そのものを見直す活動が評価されます。従業員アンケートや改善チームの設置など、「組織としてテレワークを根付かせる仕組みづくり」が支援の中心です。
参考:令和7年度テレワーク定着強化奨励金:東京しごと財団
この助成金は、テレワーク環境を総合的に構築することを目的とした支援制度です。専門家の伴走支援が受けられる点が特徴で、テレワーク導入の計画立案から実行・改善までを一貫してサポートします。
| 項目 | 内容 |
| 特徴 | 専門家(中小企業診断士等)による伴走支援付き |
| 対象範囲 | 育児・介護など柔軟な働き方に関連する支援も対象 |
| 助成率・上限額 | 事業内容により変動(例:上限250万円程度) |
この制度では、テレワーク環境の構築だけでなく、育児・介護など従業員の事情に合わせた働き方改革にも活用できます。特に初めてテレワーク導入に取り組む企業にとっては、専門家の支援を受けながら確実に制度を整えられる点が大きな利点です。
参考:令和7年度テレワークトータルサポート助成金:東京しごと財団
東京都以外にも、神奈川県・大阪府・愛知県などで独自のテレワーク支援策が設けられています。
それぞれの自治体で目的や助成額が異なるため、所在地に応じた制度を確認することが大切です。
テレワークに使える助成金・補助金を検索する
助成金・補助金の申請では、「交付決定前の購入をしない」「計画変更を避ける」などの基本ルールを守ることが非常に重要です。これらのルールを守らないと、せっかくの取組が不支給・返還対象になるおそれがあります。申請を進める前に、次の4つのポイントを必ず確認しておきましょう。
補助金・助成金はいずれも「交付決定通知が出た後の支出」しか補助対象になりません。契約や発注、機器購入、研修実施などを交付決定前に行うと、全額自己負担となります。
特にIT導入補助金や厚生労働省の助成金では、契約日や請求書の日付が厳密に確認されるため、スケジュール管理に注意が必要です。
一度提出した事業計画や実施期間は、原則として途中で変更できません。やむを得ない事情で延長や内容変更を行う場合は、事前に事務局への申請・承認が必要です。
無断で内容を変えた場合は、補助金が取り消されるケースもあります。
特に、年度内完了が条件となっている制度では、納期の遅れや研修日程のずれに十分注意しましょう。
助成金や補助金ごとに、対象となる経費の範囲が異なります。
例として、
複数の助成金・補助金を同時に申請することは可能ですが、同じ経費・同じ目的での併用は認められていません。例えば、テレワーク機器の購入費を「IT導入補助金」と「省力化補助金」で重複申請することは不可です。
また、過去に同様の助成金を受給している場合も制限があるため、過去の受給履歴を確認してから申請しましょう。
テレワークの導入・定着を進めるには、厚生労働省・経済産業省・自治体の制度を組み合わせて活用することが効果的です。職場環境の整備や研修には助成金を、ITツールや機器の導入には補助金を利用するなど、目的に応じて制度を使い分けましょう。また、助成金・補助金はいずれも毎年度内容が更新されるため、最新の公募要領を確認することが成功のポイントです。

テレワークには補助金、助成金の双方が検討出来ます。厚生労働省・経済産業省・自治体の制度を組み合わせて活用することが効果的です。職場環境の整備や研修には助成金を、ITツールや機器の導入には補助金を利用するなど、目的に応じて制度を使い分けされると良いでしょう。