車に関する省エネ補助金の概要
省エネ補助金は、CO₂排出を抑制する次世代車両の普及促進を政策ゴールに据え、環境負荷軽減と産業競争力の強化、地球温暖化対策への対応を複合的に目指す制度です。
購入コストの高さを克服するために、購入時に助成金として支援されます。
近年、環境意識の高まりとともに、自動車の省エネ化が急速に進んでいます。 本記事では、省エネ車に関する補助金制度の概要、対象車両、申請の流れなど、2025年の最新情報を網羅的に解説します。
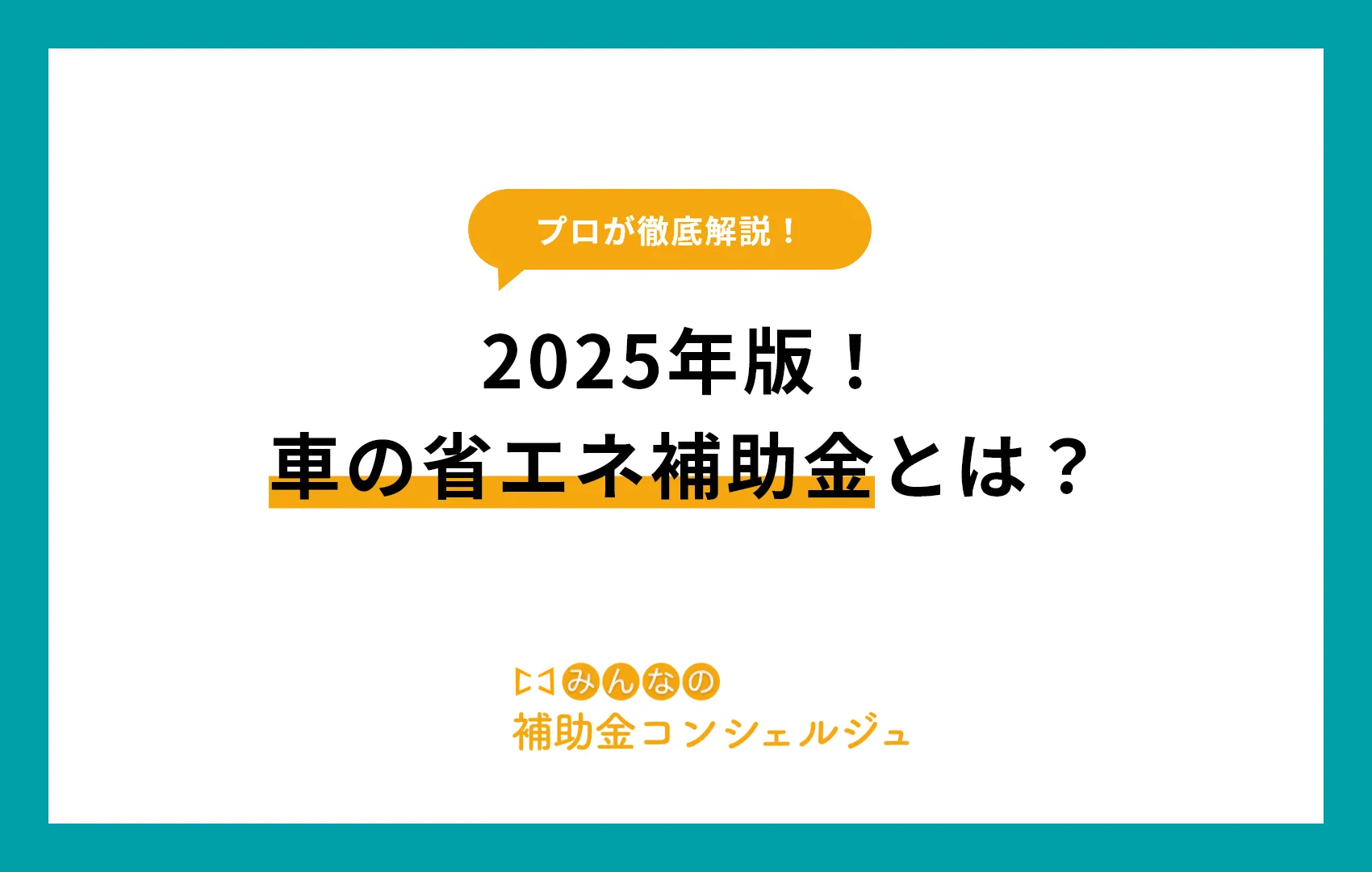

カミーユ行政書士事務所代表・行政書士
補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
省エネ補助金は、CO₂排出を抑制する次世代車両の普及促進を政策ゴールに据え、環境負荷軽減と産業競争力の強化、地球温暖化対策への対応を複合的に目指す制度です。
購入コストの高さを克服するために、購入時に助成金として支援されます。
ここでは、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」などの制度を例に、補助金の対象となる車両に関する具体的な条件を詳しく解説します。
前提として、補助金の対象となるには、その車両の型式(モデル)が、経済産業省が公表する「CEV補助金対象車両リスト」に登録されていなければなりません。
このリストは、毎年度の補助金制度にあわせて最新情報に更新されており、メーカー名、車両の型式、駆動方式、補助額などが明記されています。
仮にEVやPHVであっても、型式がリストに掲載されていなければ補助金の対象にはならないため、購入前にこのリストを必ず確認することが必須です。特に新型車や輸入車の場合、国内での補助対象としての登録が間に合っていないこともあるため注意が必要です。
また、同じ車種でもグレードや駆動方式の違いによって補助対象か否かが変わる場合もあります。
たとえば、4WD仕様のみが補助対象である一方、2WD仕様は対象外となるケースもあり、細かな仕様の違いにも目を向けなければなりません。
参考:次世代自動車振興センター(補助対象車両)
CEV補助金は、主に温室効果ガスの排出削減を目的として設けられているため、補助対象となる車両は排出ガスゼロ、または著しく少ないことが条件です。
具体的には、以下のような車種が対象となる傾向があります。
電気自動車(EV)
走行中にCO₂や排気ガスを一切排出しないため、補助対象の中心的な存在です。
プラグインハイブリッド車(PHV)
一定距離まではEVと同様に走行可能であり、CO₂排出量が大幅に少ないことから対象になります。
ただし、補助額はEVより低くなる傾向があります。
燃料電池車(FCV)
水素を燃料とし、走行時に排出するのは水のみであることから、最も環境負荷の少ない車種のひとつとして高額の補助対象となっています。
ガソリン車やディーゼル車は、たとえ低燃費仕様であっても、原則として補助の対象にはなりません。
また、ハイブリッド車(HV)は、PHVとは異なり充電機能がないため、通常は補助対象外です。
ただし、自治体によっては対象になる場合もあります。
補助金制度では、購入される車両が新車であることが原則条件とされています。
これは、新車の導入を通じてより多くのクリーンエネルギー車の普及を図るという目的から来ています。
新車とは、以下の条件を満たすものを指します。
登録・届出が未済の車両
一部の例外として、リース会社が新車を購入し、その車両をリース利用する形で補助申請を行う場合などは対象とされることがありますが、一般的に中古車、未使用車、展示車両などは補助金の対象外と考えてよいでしょう。
また、輸入車の場合は、正規ディーラー経由での新車購入が原則となり、並行輸入車は対象とならない場合が多いため、購入経路にも注意が必要です。
補助金制度では、車両そのものの条件だけでなく、申請者の属性(個人、法人、自治体、リース会社など)によっても条件や補助額が異なる場合があります。
個人での申請
個人がEVやPHVをマイカーとして購入する場合、居住地や所得制限は原則としてありませんが、車両の使用目的が業務ではなく、日常生活における移動であることが前提とされることがあります。
また、一定期間(多くは4年程度)の継続所有義務や、転売禁止などの制約が付くことがあります。
法人での申請
企業や団体が業務車両としてEVやFCVを導入する場合、車両の台数が複数になるケースが多く、補助額の合計が高額になることがあります。
このため、申請書類も個人より詳細で、使用目的や走行距離予測、削減効果などを具体的に記載する必要があります。
また、法人申請では、事業の持続性や環境対策に対する姿勢が審査対象となる場合もあり、経営体制や将来計画の提示が求められることもあります。
特に中小企業が導入する場合は、他の補助金(たとえば省エネ投資促進補助金)との併用が可能になる場合もあるため、申請前に戦略的に整理することが望まれます。
自治体や公共団体での申請
自治体が公用車や地域交通サービスの一環としてEVやFCVを導入する場合、補助率が高めに設定される傾向があります。
特に過疎地域や離島など交通アクセスに課題のある地域では、ゼロエミッション車の導入が地域政策の一環として重視されるため、国や環境省からの別の支援制度と併用されることもあります。
参考:次世代自動車振興センター(補助対象車両)
国の支援制度(CEV補助金など)を含め、車種別補助額の参考例は以下の通りです
自治体との併用で実質100万円以上の支援が得られる場合もあります。
参考:次世代自動車振興センター(銘柄ごとの補助金交付額)
補助金の対象者は基本的に購入者になります。
個人・事業者・自治体とそれぞれに条件がありますが、多くの場合環境性能が基準をクリアした新車を対象とし、中古車やリースは対象外または条件付きとなります。
2025年時点で実施されている、代表的な車関連の補助金制度について解説します。
自治体単位で導入推進。
かつ補助内容も柔軟で「地域の災害対応車」「カーシェア用EV」なども対象になりやすい制度。国補助との併用にも対応。
自治体別に内容がまちまちなので、市区町村の情報収集が重要です。
参考:地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
補助金を実際に申請する際の流れやスケジュールについて解説します。
型式を確認したうえで、補助対象枠の口数が残っているかをチェックしましょう。
交付申請は購入前に行うのがルールです。
交付決定後、ディーラーで契約・登録。領収書と車検証・登録証明書取得が必要です。
車両登録後から2〜4ヶ月以内に電子申請ポータルに登録書類を添付し、その後補助金が指定口座に振込みます。
申請タイプによって、補助額の一部返還が発生するケースもあるため、制度ルールを守る必要あります。
参考:CEV 補助金(車両)のご案内
メリットには下記があります。
注意点
補助金の対象となるかどうかは、車両そのものだけでなく、購入タイミングや申請手続きの正確さも重要です。
たとえば、以下のような点に注意が必要です。
このような手続きの流れを事前に理解していないと、「購入したのに補助対象外だった」といったトラブルに繋がる可能性があります。
日本国内では国や自治体が提供するさまざまな補助金制度が整備され、個人や法人がこれらの車両を導入しやすくなる支援が行われています。
この補助金は、経済産業省が主管し、環境に配慮した自動車の普及を推進するために創設された制度です。
対象となるのは、
などであり、これらの車両を新たに購入した場合に補助金が支給されます。
補助額は車種や用途によって異なり、EV乗用車の場合、最大で85万円の補助が受けられるケースもあります。
また、商用車や特装車など、業務用途の車両については、車両サイズや性能に応じて補助額が変動する仕組みとなっています。
申請にあたっては、導入車両が基準を満たしていることや、補助金の交付条件を確認する必要があります。
さらに、補助対象となる車両は、事前に国が公表する対象車両リストに掲載されている必要があるため、事前の調査と準備が不可欠です。
参考:経済産業省(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)
この制度は、地域全体での脱炭素化を支援する目的で設けられたものであり、自治体が主導するプロジェクトや計画に対して交付されるものです。
再生可能エネルギーの導入、地域輸送の電動化、地産地消型のエネルギー供給網の整備といった広範な施策が対象になります。
この交付金の中でも、交通分野に関する施策として、EVやFCVなどのクリーンエネルギー車両を地域の公共交通やシェアリングサービスに導入する場合に補助対象となるケースがあります。
特に地方自治体が、地域住民の移動手段として低炭素な輸送インフラを構築する際に、この補助金が活用される傾向にあります。
この制度は、あくまで自治体を主体とした申請が基本となるため、個人や企業が単独で直接申請することはできませんが、自治体が募集する参画事業や地域のパートナーとして関与することで間接的に支援を受けられる可能性があります。
補助の内容や対象範囲は年度ごとに見直されることが多く、地域のニーズや脱炭素ロードマップとの整合性が重視されるため、該当する自治体の公募情報を常にチェックしておきましょう。
参考:地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
国が提供する補助金とは別に、多くの自治体が独自に設定している補助制度も存在します。
特に大都市圏では、交通由来の温室効果ガス排出量が大きいことから、クリーンエネルギー車両の導入を強力に後押しするための補助制度が整備されている傾向があります。
東京都では、「ZEV導入促進補助金」という制度を設け、ゼロエミッション・ビークル(ZEV)として分類されるEVやFCVを導入する際の初期費用を支援しています。
特徴的なのは、国のCEV補助金と併用が可能なケースが多く、両制度を併せて活用することで、購入費用の実質負担を大幅に軽減できる点です。
東京都のZEV補助金では、EV乗用車の購入で最大60万円、商用車の場合は100万円を超える補助が設定されていることもあります。
また、EV充電設備の設置費用に対しても補助が出るなど、インフラ整備にまで対象が広がっているのが特徴です。
このような自治体独自の補助金は、それぞれの地域が直面する課題に応じて設計されているため、内容や補助額、対象条件は自治体ごとに大きく異なります。
また、年度の予算や議会の方針により内容が変更されることも多いため、該当地域の公式サイトや広報誌を通じて最新情報をこまめにチェックすることが大切です。
加えて、一部の自治体では中小企業向けに特化した支援制度を設けていることもあり、業務用車両をクリーンエネルギー車に切り替える事業者にとっては、コスト面だけでなく社会的評価の向上やCSRの強化というメリットも期待できます。
参考:東京都(ZEV補助金)
上記で解説した補助金制度を効果的に活用するためには、いくつかのポイントがあります。
国の補助制度は年度単位で募集が行われ、受付期間も限定的です。
申請には車両の見積書や納車予定日、購入先の情報などが必要となるため、準備に時間を要することもあります。
さらに、国の補助金と自治体の補助金を併用する場合には、それぞれの制度の申請要件や交付条件が整合するかどうかを事前に確認しましょう。
書類の不備や提出の遅れが原因で補助金を受けられなかったという事例も少なくありません。
補助金の交付後には一定期間の使用義務が課される場合や、報告義務があるケースもあります。
たとえば、車両を一定年数使用すること、定期的に稼働状況を報告することなどが義務付けられていることがあるため、交付を受ける前にこうした条件を十分に理解しておくことが重要です。
A.多くの場合、新車登録が必要。中古車向け制度は極めて限定的。
A.申請者がリース会社なら対象可。ユーザーが契約する場合は車体所有者を確認。
A.交付請求から約1〜3ヶ月後。ただし年度末・締切時点の処理が遅れることあり。
A.保有期間中に売却すると補助額の一部返還要件が発生することも。制度要項に記載あり。
車の省エネ補助金は、環境性能の高い新車を導入する際に活用できる強力な支援制度です。
EVやPHV、FCVなどが対象で、国や自治体による補助を併用すれば大幅なコスト削減が可能になります。
補助を受けるには、型式リストの確認や新車登録、購入前の申請などが必要です。
最新の制度情報をこまめに確認し、適切な準備を進めることで、経済的・環境的なメリットを最大限に享受できるでしょう。
全国の「電動自転車補助金」一覧【2025年最新】
小規模事業者持続化補助金でトラックは購入できる?
電気自動車(CEV補助金)はいつまで?対象車種と申請方法まとめ【2025年】

国が提供する補助金とは別に、多くの自治体が独自に設定している補助制度も存在しています。 EV車両のみならずEC充電装置に対しても補助金を用意している自治体もあります。新車が対象のケースが多いので注意しましょう。 車両購入前の情報収集が不可欠です。