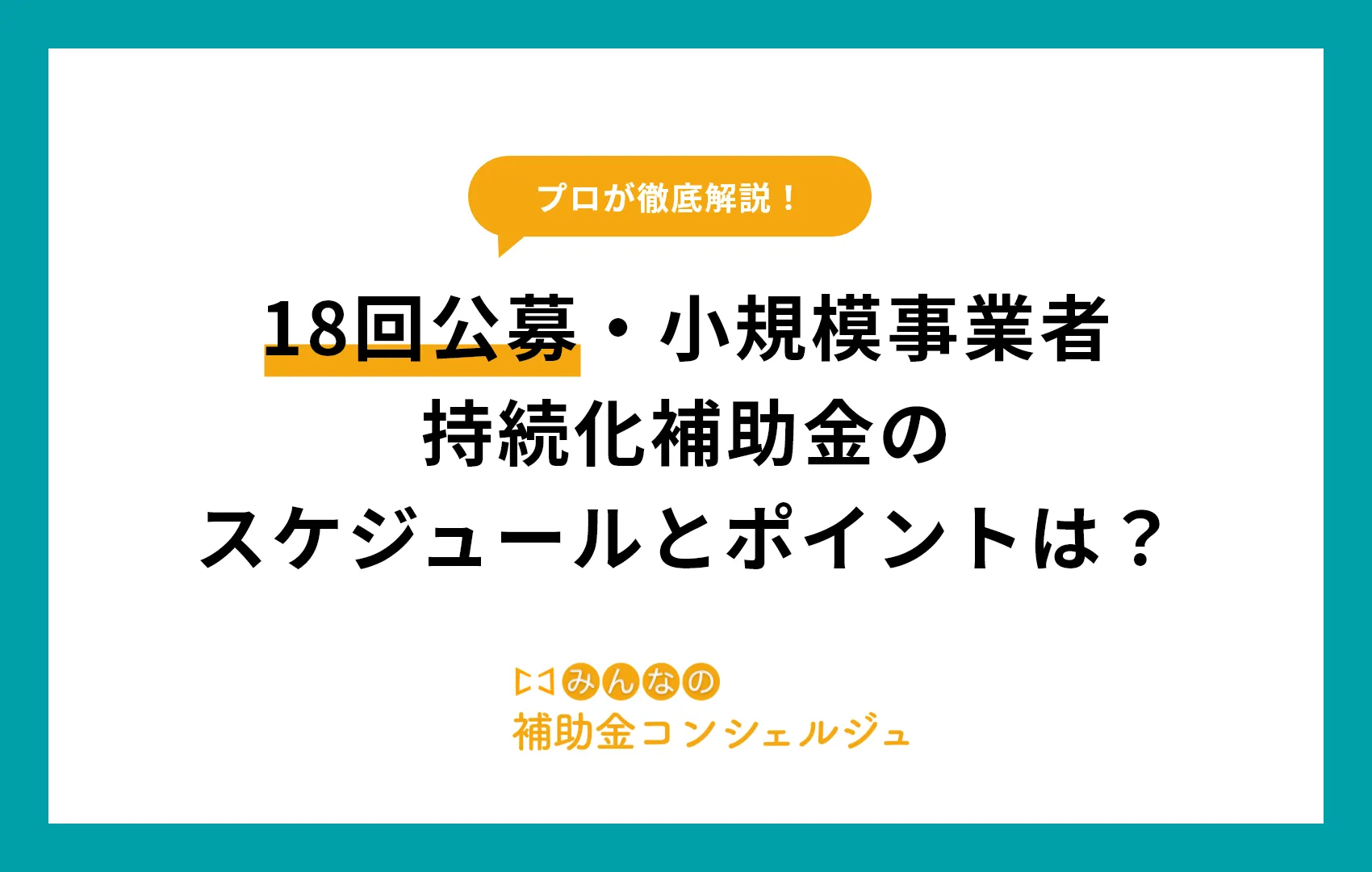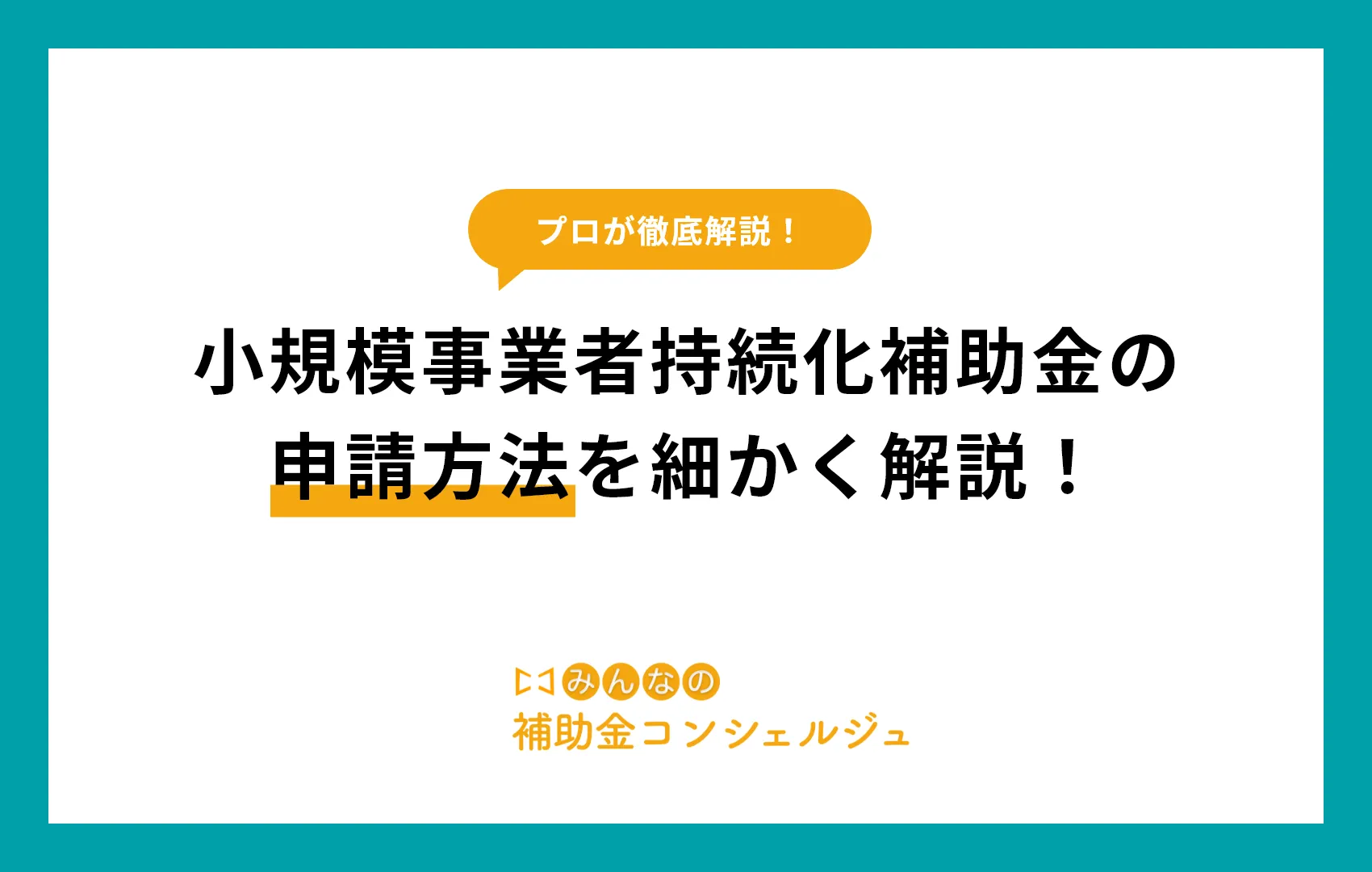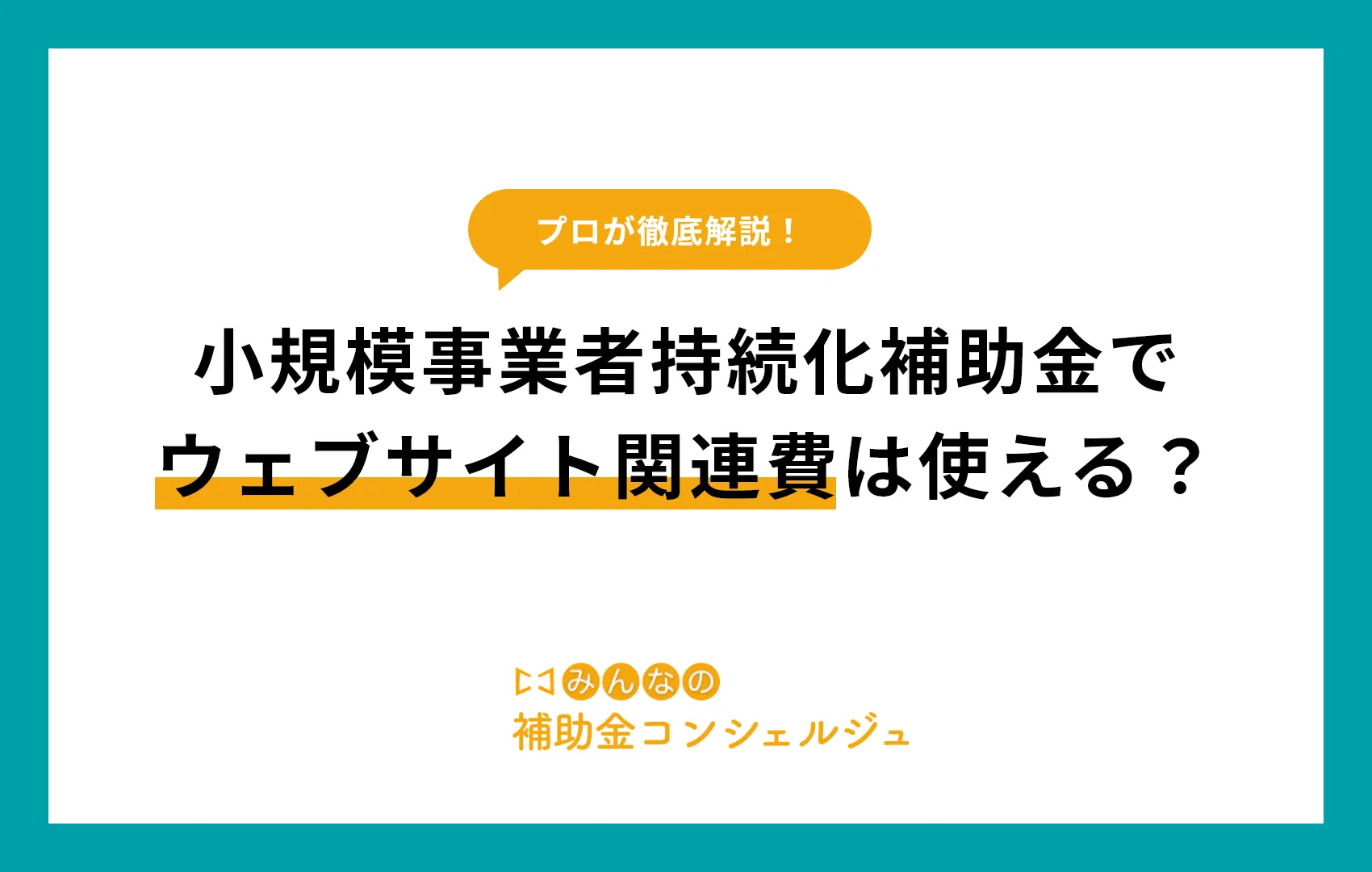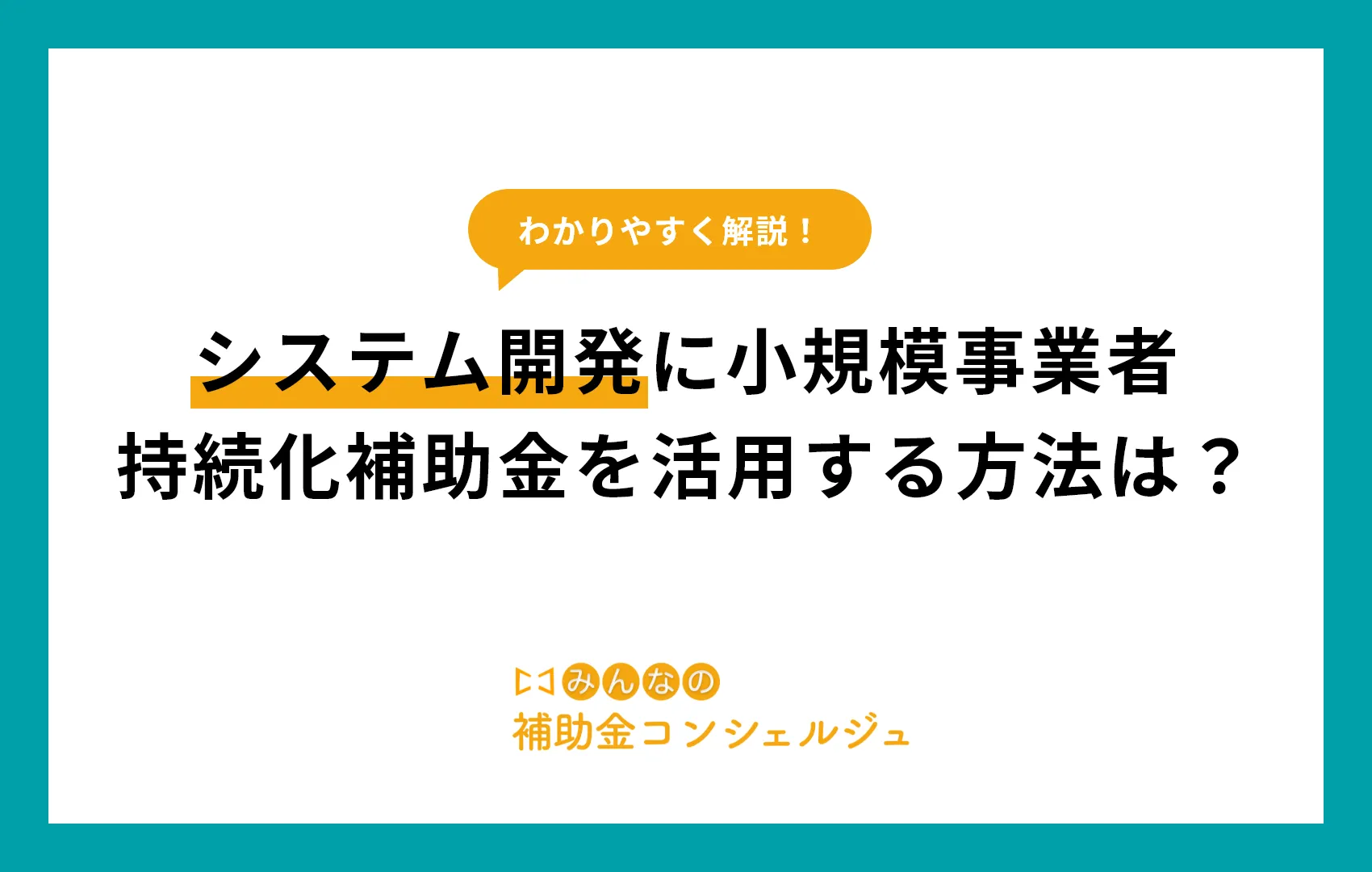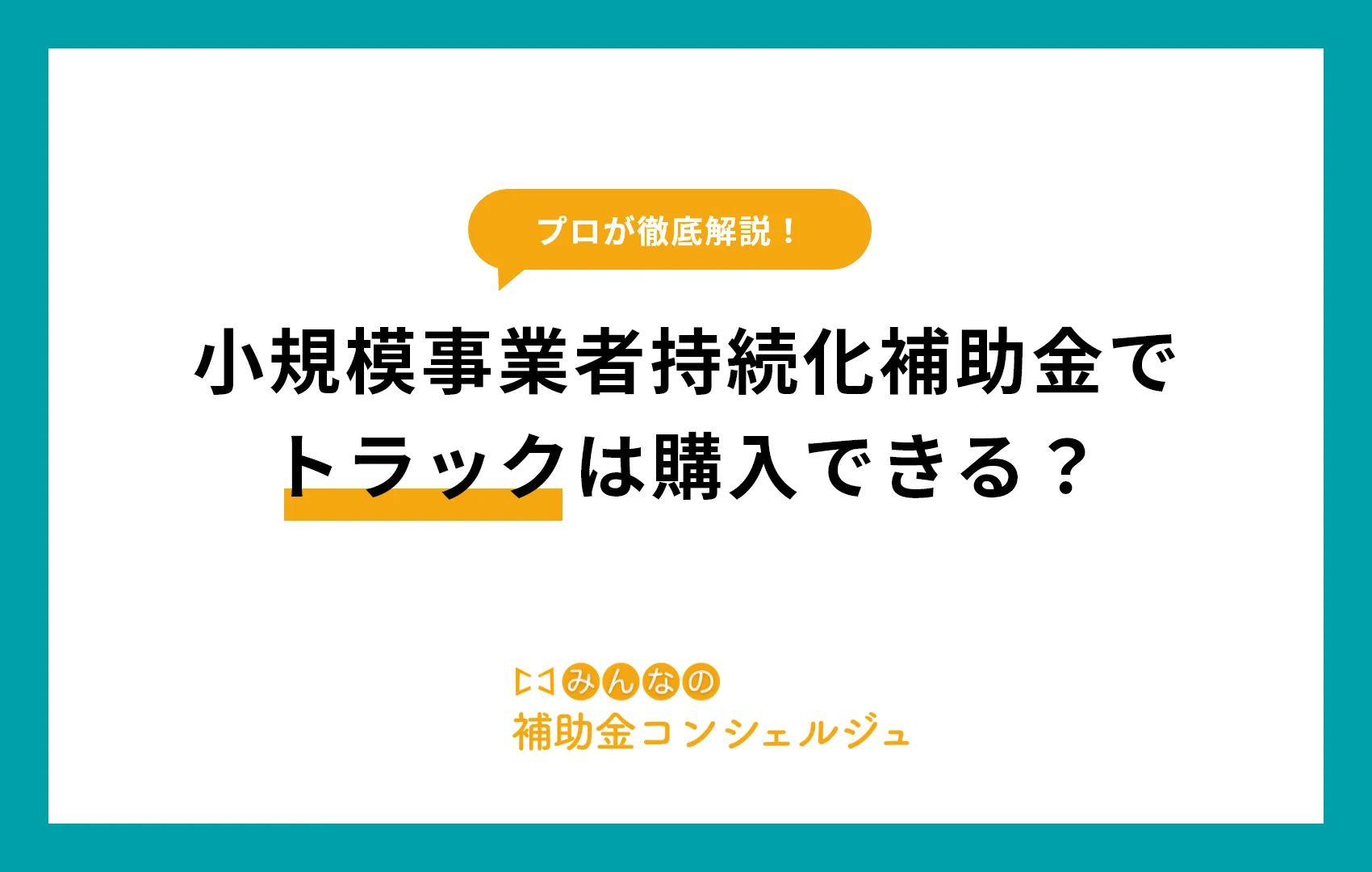18回公募・小規模事業者持続化補助金のスケジュールとポイントは?
第18回公募・小規模事業者持続化補助金のスケジュールが発表されました、本コラムでは、第18回公募のスケジュールの詳細と、前回公募との変更点、採択率予想を分かりやすく解説します。
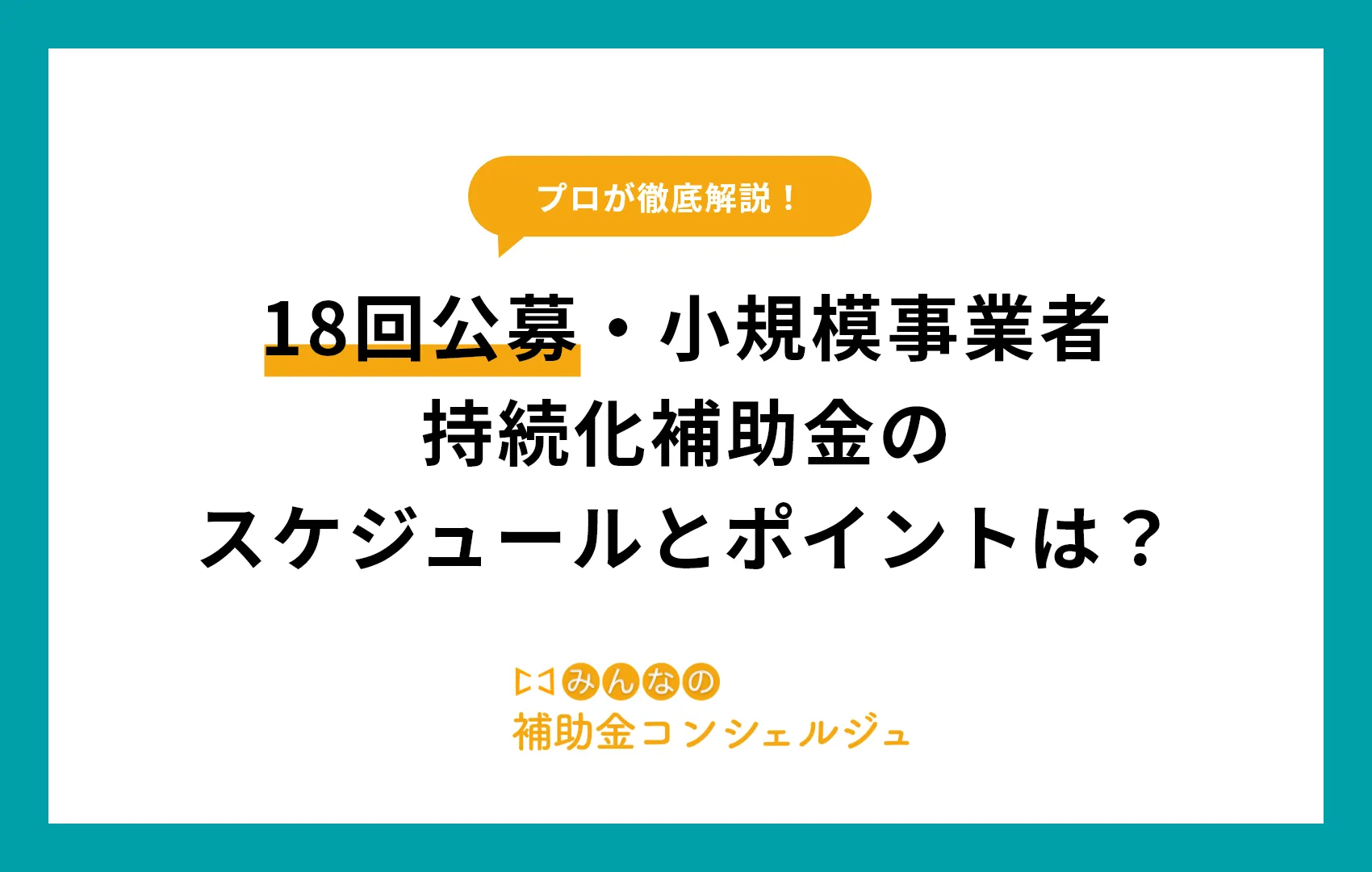
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
第18回小規模事業者持続化補助金のスケジュール
| 項目 | 内容 |
| 公募要領公開 | 2025年6月30日(月) |
| 申請受付開始 | 2025年10月3日(金) |
| 申請受付締切日 | 2025年11月28日(金)17:00 |
| 事業支援計画書交付の受付締切 | 2025年11月14日(金)(※予想) |
| 交付決定日 | 2026年1月17日(金)頃(※予想) |
| 事業実施期間 | 2026年1月下旬 ~ 2026年11月末頃(※予想) |
| 実績報告書提出期限 | 2026年11月30日(月)(※予想) |
交付決定から実績報告までの期間は約10か月あり、比較的余裕があります。ただし、年度内(2026年3月末)に事業を完了させたい場合は、早めの計画・発注が重要です。特に3月は納品が集中するため、スケジュールの遅れにご注意ください。
小規模事業者持続化補助金の概要をチェックする!
18回小規模事業者持続化補助金の変更点と注意点【17回と比較】
第18回の小規模事業者持続化補助金では、前回(第17回)と比べて大きな制度変更はありませんが、スケジュール面や申請ルールの厳格化など、注意すべきポイントがいくつかあります。以下、5点が主な変更点です。
- 電子申請専用で、郵送は不可に
- 提出書類の記入ルールがより厳格に
- スケジュールが明確化され、提出期限が厳格に
- 17回までに採択された事業者への提出義務も継続
- 補助上限額の構成は据え置き、要件の確認がより重要に
1. 電子申請専用で、郵送は不可に
前回に引き続き、申請は「電子申請システム」のみ対応となっています。郵送では一切受付されません。gBizIDプライムの取得も必須のため、早めの取得を推奨します。
2. 提出書類の記入ルールがより厳格に
様式2に記載する第三者支援の有無において、金額や名称の記載漏れがあると「虚偽の報告」とされ、不採択や交付決定の取消対象となります。支援者がいるにもかかわらず、「第三者アドバイスあり」にチェックしないケースは特にリスクが高いため注意が必要です。
3. スケジュールが明確化され、提出期限が厳格に
第18回では以下の通り、締切日が明示されており、1日でも遅れると申請できません。
| 項目 | 日程 |
| 公募開始 | 2025年6月30日 |
| 申請受付開始 | 2025年10月3日 |
| 申請締切 | 2025年11月28日(金)17:00 |
| 様式4の発行締切 | 2025年11月18日(火) |
※様式4(事業支援計画書)の発行依頼が締切後に行われた場合、理由のいかんを問わず受付不可とされています。
4. 17回までに採択された事業者への提出義務も継続
17回以前の補助金で採択されていた事業者は、「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」(様式14)を提出していないと18回の申請ができません。未提出のまま申請すると不採択になるため、過去採択者は必ず提出状況を確認しましょう。
5. 補助上限額の構成は据え置き、要件の確認がより重要に
第18回も補助上限額や補助率は前回と同様ですが、特例適用に関する要件確認の厳格化が目立ちます。
| 区分 | 補助上限 | 補助率 |
| 通常枠 | 50万円 | 2/3 |
| インボイス特例 | +50万円 | 同左 |
| 賃金引上げ特例 | +150万円 | 一部3/4(赤字事業者) |
| 両方の特例 | +200万円 | 一部3/4 |
特に注意すべき点は以下の通りです。インボイス特例:補助事業終了時点で「適格請求書発行事業者」でなければ不支給。賃金引上げ特例:申請時と補助事業終了時の賃金水準を比較して+50円以上の引上げが必要。対象者が退職した場合の対応など、細かい要件が設定されています。いずれも「1つでも要件を満たさないと全額不支給」となるため、申請前の要件確認が不可欠です。
18回小規模事業者持続化補助金の申請対象と補助内容とは?
小規模事業者持続化補助金(一般型)は、小規模事業者や個人事業主が行う販路開拓・業務効率化の取り組みに対し、その経費の一部を補助する制度です。第18回では、補助対象となる事業者の要件や使える経費に関して、明確な定義がなされています。
小規模事業者持続化補助金の申請対象者とは?
本補助金の申請対象者は、「常時使用する従業員数」に基づき、以下のように業種ごとに定義されています。
| 業種区分 | 常時使用する従業員数(上限) |
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
対象者に該当する条件
- 法人・個人事業主いずれも対象
- 日本国内において事業を営んでいること
- 申請時点で事業を行っていること
- 以下に該当しないこと(例:みなし大企業、政治団体、宗教法人など)
従業員数のカウントには、「代表者」や「パートタイム従業員」は含まれません。「みなし大企業」に該当する企業(親会社やグループ企業との資本関係が一定以上ある等)は対象外です。
補助額と補助率の基本枠
第18回では、事業内容や事業者の条件に応じて、以下のように補助上限額が設定されています。
| 区分 | 補助上限額 | 補助率 | 特記事項 |
| 通常枠 | 50万円 | 2/3 | 一般的な申請枠 |
| 賃金引上げ枠 | +150万円 | 2/3または3/4 | 要件あり(下記参照) |
| インボイス枠 | +50万円 | 2/3 | 適格請求書発行事業者が対象 |
| 両枠併用 | 最大200万円 | 条件により異なる | 併用可能だが要件厳格 |
補助対象となる経費の具体例
補助金でカバーされる経費は、販路開拓や業務効率化のために直接必要な費用です。具体的には次のような費用が対象となります。
| 補助対象となる経費の例 | 補助対象外の経費 |
機械装置等費:業務効率化のための設備・装置(例:冷蔵庫、作業用機器)
広報費:チラシ、パンフレット、Web広告など
展示会等出展費:小間料や出展に伴う輸送費等
開発費:新商品のパッケージデザイン費用等
資料購入費・専門家謝金・旅費:事業遂行に必要なものに限る | 家賃・光熱費
通常仕入や汎用消耗品
自社の人件費や交通費 |
補助対象経費には事前着手ルールがあり、交付決定前に支出した費用は原則対象外となります(例外申請が認められる場合あり) 。このように、補助金の対象となる事業者や経費は、明確に定義されています。申請前に自社が該当するかどうか、そして補助対象となる取り組みかどうかを慎重に確認しましょう。特に「従業員数のカウント方法」や「補助対象経費の範囲」は、間違えると不採択や返還のリスクがあるため、正確な理解が重要です。
18回持続化補助金の申請の流れ
第18回小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)では、申請から交付決定まで一貫して「電子申請」で行う必要があります。このセクションでは、初心者の方でも迷わず準備できるよう、申請までの以下ステップを順を追って解説します。
- gBizIDプライムの取得
- 必要書類を準備し、様式を作成
- 商工会・商工会議所からの支援を受ける(様式4の取得)
- 電子申請(jGrants)から提出
1.gBizIDプライムの取得(必須)
申請には「gBizIDプライムアカウント」が必要です。これは、法人・個人事業主向けの政府共通の電子申請用アカウントです。取得には郵送による本人確認が必要なため、2週間程度かかる場合があります。過去にIT導入補助金や他の公的補助金を申請したことがある方は、すでにIDを持っている場合があります。公募締切間際では間に合わない可能性があるため、できるだけ早めに申請しましょう。
GビズIDの取得方法を分かりやすく解説!
gBizIDプライムアカウントを取得する!
2.必要書類を準備し、様式を作成
提出が必要な基本書類は以下の通りです。
| 書類名 | 内容と作成ポイント |
| 様式1:事業計画書 | 補助対象経費の内容・目的・スケジュールなどを記載。全体構成の要となる書類。記入例を参考に丁寧に記載することが重要です。 |
| 様式2:経費明細表 | 使う経費の内訳と金額を記載。内容と金額の整合性に注意。 |
| 様式3:宣誓・同意書 | 電子署名を含む本人確認と補助金制度の理解を確認する文書。記入漏れがないように注意。 |
| 様式4:事業支援計画書(様式4-1/4-2) | 商工会・商工会議所に発行依頼が必要。2025年11月18日が発行期限。この締切を過ぎると申請不可。 |
| 決算書または確定申告書 | 法人の場合は直近の決算書、個人事業主は確定申告書の写し。収支状況の確認に用いられる。 |
| 直近期分の労働者名簿 | 賃金引上げ枠を希望する場合に必要。 |
補助金交付申請書や実施体制の説明など、一部の補助資料もオンライン入力が必要です。各様式は公式サイトから最新版をダウンロードしてください。
小規模事業者持続化補助金の必要書類を不備なく準備する方法とは?
ステップ3.商工会・商工会議所からの支援を受ける(様式4の取得)
補助金の特徴として、地域の商工会議所・商工会が「支援機関」として関わる点があります。申請には、事前に地域の商工会等に相談し、様式4(事業支援計画書)の発行を受ける必要があります。原則として、発行には複数回の面談や相談が求められます。早めに連絡し、余裕を持った対応を。
ステップ4.電子申請(jGrants)から提出
申請は電子申請システム「jGrants」からのみ受け付けており、紙による郵送申請は認められていません。締切は2025年11月28日(金)の17時までで、遅れると申請自体が無効となるため、時間厳守が求められます。
また、提出内容に不備があると審査に進む前に差し戻されてしまう可能性があるため、事前の丁寧な確認が重要です。申請が完了したあとは、提出記録として控えをPDFなどの形で保存しておくと安心です。
jGrantsの公式サイトを確認する!
18回持続化補助金の採択率を予想してみた!
第18回の採択率はおおよそ「35〜40%前後」と予想されます。直近の公募では採択率が40%を下回る回もあり、競争は年々激しくなっている傾向があります。
過去の採択率の推移から読み解く傾向
小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化などを目的とした取り組みに対して支援が受けられる制度です。毎回多くの申請が集まるため、過去の採択状況を知っておくことは、戦略を立てるうえで重要なポイントです。
以下は、直近の実績(通常枠)です。
| 公募回 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率(概算) |
| 第15回 | 約13,336件 | 約5,580件 | 約41.8% |
| 第16回 | 約7,371件 | 約2,741件 | 約37.2% |
| 第17回 | 未発表 | 未発表 | 不明 |
※ 出典:中小企業庁、支援機関、業界レポート等による公表情報に基づく。
第15回以降、応募件数の増減はあるものの、採択率は40%を下回る水準が続いていることがわかります。第18回も同様の競争率になると想定し、慎重な準備が求められます。
小規模事業者持続化補助金は、かつてよりも競争が激化しており、第18回の採択率は35〜40%前後になる可能性が高いと見られます。「申請すれば通る」時代は終わり、採択されるためには計画の精度や戦略的な準備が欠かせません。
採択率を上げたい方は、プロのサポートがおすすめです!弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります。小規模事業者持続化補助金の事業計画のチェックはぜひ弊社にお任せください!ご相談は、以下のフォームからお気軽にどうぞ!
【無料】補助金のプロに持続化補助金の相談をする!
18回持続化補助金の採択率を上げるには?|テーマ選びと書き方のコツ
申請の成否は、「どんなテーマを選び、どう表現するか」で大きく左右されます。ここでは、過去の採択事例から見えてきた評価されやすい事業テーマの傾向と、事業計画書の具体的な書き方の工夫を紹介します。
評価されやすい事業テーマの傾向とは?
持続化補助金では、社会的課題や地域課題に向き合ったテーマが特に評価されています。以下は、過去の採択事例に多く見られたテーマです。
| 分野 | 内容の例 |
| 地域密着型の新規顧客開拓 | 地域イベントと連動した新サービス、地元高齢者向けの訪問型サービスなど |
| デジタル活用による業務効率化 | ネット予約システムの導入、キャッシュレス決済対応、在庫管理の自動化など |
| 社会的変化への対応 | コロナ禍・物価高対応の新サービス、テイクアウト対応、低価格帯メニューの新設など |
| 観光・インバウンド対策 | 外国人向け商品開発、英語対応Webサイトの整備、多言語メニューの導入など |
これらのテーマに共通するのは、「地域や市場のニーズに的確に応え、新しい価値を提供していること」です。
採択されやすい事業計画書の書き方|4つの工夫
採択される計画書には、「読みやすく」「根拠が明確で」「審査項目にきちんと対応している」という共通点があります。以下の4点を意識して書くことで、通過率を高めることができます。
- 成果を数字で示す
- 課題と目的を明確に書く
- 審査の評価項目をすべて押さえる
- 事業の流れにストーリー性を持たせる
1. 成果を数字で示す
審査員は「投資に対する効果」がどれくらいあるかを重視します。できるだけ数値目標を明示しましょう。
例:
「予約管理システムの導入により、月間対応件数を30%増加させる」
「チラシ配布により、新規来店客を1カ月で50人増やす」など。
根拠が薄くても、仮説ベースで構いません。数字があるだけで計画の具体性が増します。
2. 課題と目的を明確に書く
まず「自社が抱えている課題」をはっきりと伝え、それに対して「補助金を使ってどう解決したいのか」をセットで書くことが大切です。
例:
×「LINE公式アカウントを導入したい」
○「既存顧客の再来店率が低いため、LINEを活用して定期的に情報を発信し、関係性を強化する」
問題と解決策が直結していることが、審査での納得感につながります。
3. 審査の評価項目をすべて押さえる
以下の観点が審査基準として存在します。すべてに触れるよう意識して構成すると、評価されやすくなります。
| 審査の評価項目 | 内容 |
| 革新性 | 他社と差別化できる新しさがあるか |
| 実現可能性 | 計画に無理がなく、実行できる体制が整っているか |
| 費用対効果 | 投資に対する見返り(売上・集客など)が期待できるか |
| 地域貢献 | 地元雇用や地域活性化など、社会的な意義があるか |
4. 事業の流れにストーリー性を持たせる
設備や広告費を単に「購入する」「出す」と書くのではなく、誰のために・なぜ・どう活用するのかをストーリーとして説明することで、説得力が増します。
例:
「高齢者層のリピーターを増やすために、地域新聞へ広告を掲載し、電話での予約受付体制を整える」といった一連の流れを明確に伝えます。
すべてに少しずつでも触れることで、採点の取りこぼしを防ぐことができます。
加点項目も活用しよう|採択率をさらに高める制度
持続化補助金では、事業計画の内容だけでなく、「加点項目」を満たしているかどうかも採択結果に大きく影響します。とくに競争率が高まっている昨今では、加点による差別化が採択率アップの決め手になるケースも多く見られます。以下は、代表的な加点項目です。該当するものがある場合は、必ず申請時に記載・証明しましょう。
| 加点項目名 | 内容とポイント |
| 経営力向上計画の認定 | 中小企業庁に認定された計画書。認定支援機関のサポートで事前取得が可能。認定済みなら加点対象。 |
| 地域未来牽引企業 | 経済産業省が選定した企業。該当する事業者は自動的に加点対象となる。 |
| 災害等被災事業者 | 地震・台風・火災等で被災したことが証明できる場合に加点。罹災証明書などの添付が必要。 |
| 連携体制の構築 | 商店街や地域団体など、複数事業者と連携して実施する事業であれば加点対象。 |
採択の可否は、「ギリギリのライン」で決まることも多くあります。計画書の内容が同程度であれば、加点の有無が最終的な差になることも十分にあり得ます。そのため、条件に該当する場合は、加点項目を確実に取得・記載し、証明資料も忘れずに添付しましょう。とくに「経営力向上計画」は、補助金申請より前に準備が必要となるため、早めの対応が重要です。
第19回公募のスケジュール
| 項目 | 内容 |
| 公募要領公開 | 2026年2月下旬(例:2026年2月23日(月)) |
| 申請受付開始 | 2026年3月6日(金) |
| 申請受付締切日 | 2026年4月24日(金)17:00 |
| 事業支援計画書交付の受付締切 | 2026年4月10日(金) |
| 交付決定日 | 2026年6月12日(金) |
| 事業実施期間 | 2026年6月中旬 ~ 2027年4月末頃 |
| 実績報告書提出期限 | 2027年4月30日(金) |
第18回の申請受付締切が2025年11月28日であることを踏まえると、第19回の申請受付開始は約3か月後と想定されます。受付期間については前回と同様に、およそ7週間程度が見込まれます。申請後の交付決定までは、例年どおり6〜7週間を要するのが一般的です。実績報告書の提出期限は、交付決定からおよそ10か月後、もしくは年度末が設定される傾向にあります。こうしたスケジュール感をもとに、第19回公募も同様の流れとなると予測されます。
年度をまたぐ事業実施には注意!
第19回公募(※予想)では、交付決定が2026年6月頃、実績報告の提出期限が2027年4月末頃となる可能性があります。つまり、2026年度(4月〜翌3月)をまたぐスケジュールになる点に注意が必要です。この場合、以下のようなリスク・留意点が発生します。
- 会計処理・決算とのバッティング
- 期末(3月)には発注や納品が集中しやすい
- 予算執行に関する行政側のチェックが厳しくなる
1. 会計処理・決算とのバッティング
法人の場合、補助金の会計処理(補助対象経費の支出・入金)が、自社の決算処理(売上・仕入・在庫・税金計算)と重なると、業務負荷が増大し、ミスや遅延の原因となります。
以下、具体的な解決策です。
- 会計処理のスケジュールを事前に可視化し、経理担当者と共有
- 補助金関連の支出・収入は専用の勘定科目を設定し、分離管理
- 顧問税理士や会計事務所と早めに連携し、圧縮記帳や補助金収入の扱いを相談
- 可能であれば3月決算企業は、補助事業完了日を2月中に設定するのが理想
特に補助金収入は「益金」扱いとなるため、税金の影響や決算への反映タイミングも考慮する必要があります。
2. 期末(3月)には発注や納品が集中しやすい
3月は、全国的に予算消化や決算対応のために官公庁・企業ともに発注が集中する時期です。
このため、補助金対象の設備・ツールについても以下のようなリスクがあります。
- 在庫の枯渇や価格上昇
- 納期の遅れ
- 工事業者の手配困難(特に内装・機械設置)
- 運送トラブルによる納品の未完了
これらの理由から、実施期間終了日(例:3月末)に滑り込むようなスケジュールは避けるべきであり、可能であれば年明け〜2月末頃までに主要な発注と納品を完了させておくことが望ましいです。
3. 予算執行に関する行政側のチェックが厳しくなる
補助金は国や自治体の年度単位予算(4月~翌年3月)で運用されているため、事業が次年度にまたがる場合、「その予算が次年度も有効か」「執行対象として認められるか」などの確認が必要になります。
特に以下のような状況では、行政側から追加書類の提出を求められることがあります。
以下、想定される追加書類の例です。
- 事業の進捗状況報告書(中間報告)
- 事業継続に関する誓約書や確約書
- 納品予定日の確認書/納品計画表
- 経費の支出予定表や見積書の再提出
- 次年度への繰越使用申請書(自治体によって異なる)
これらは、事業の遅延や補助金の不適正利用を防ぐために提出を求められることがあり、補助金事務局との密なやり取りが必要になります。
監修者からのワンポイントアドバイス
補助金申請で重要なのは補助金の申請時期と事業のスケジュールを勘案することです。今すぐに始める事業ではなく、近い将来始める事業の経費項目に対して補助金を当てはめていくという考え方が必要です。専門家に伴走支援して頂き、補助金を有効活用していきましょう。