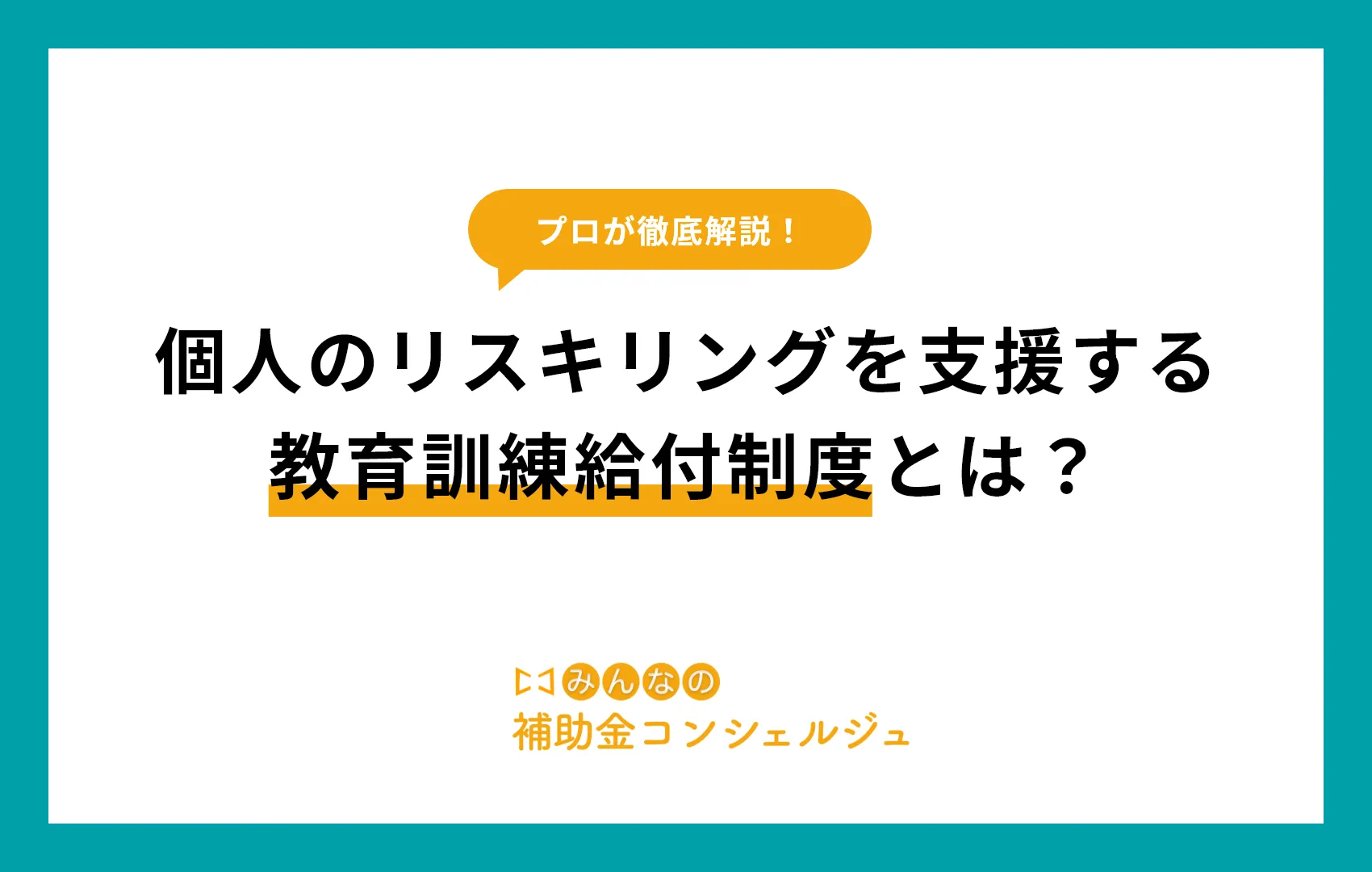教育訓練給付制度とは?対象者や支給内容をわかりやすく解説
教育訓練給付制度は、キャリアアップや再就職のために厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了すると、 講座の受講にかかった費用の一部が支給される制度です。本コラムでは教育訓練給付制度の概要や申請方法、デメリットなどを分かりやすく紹介します!
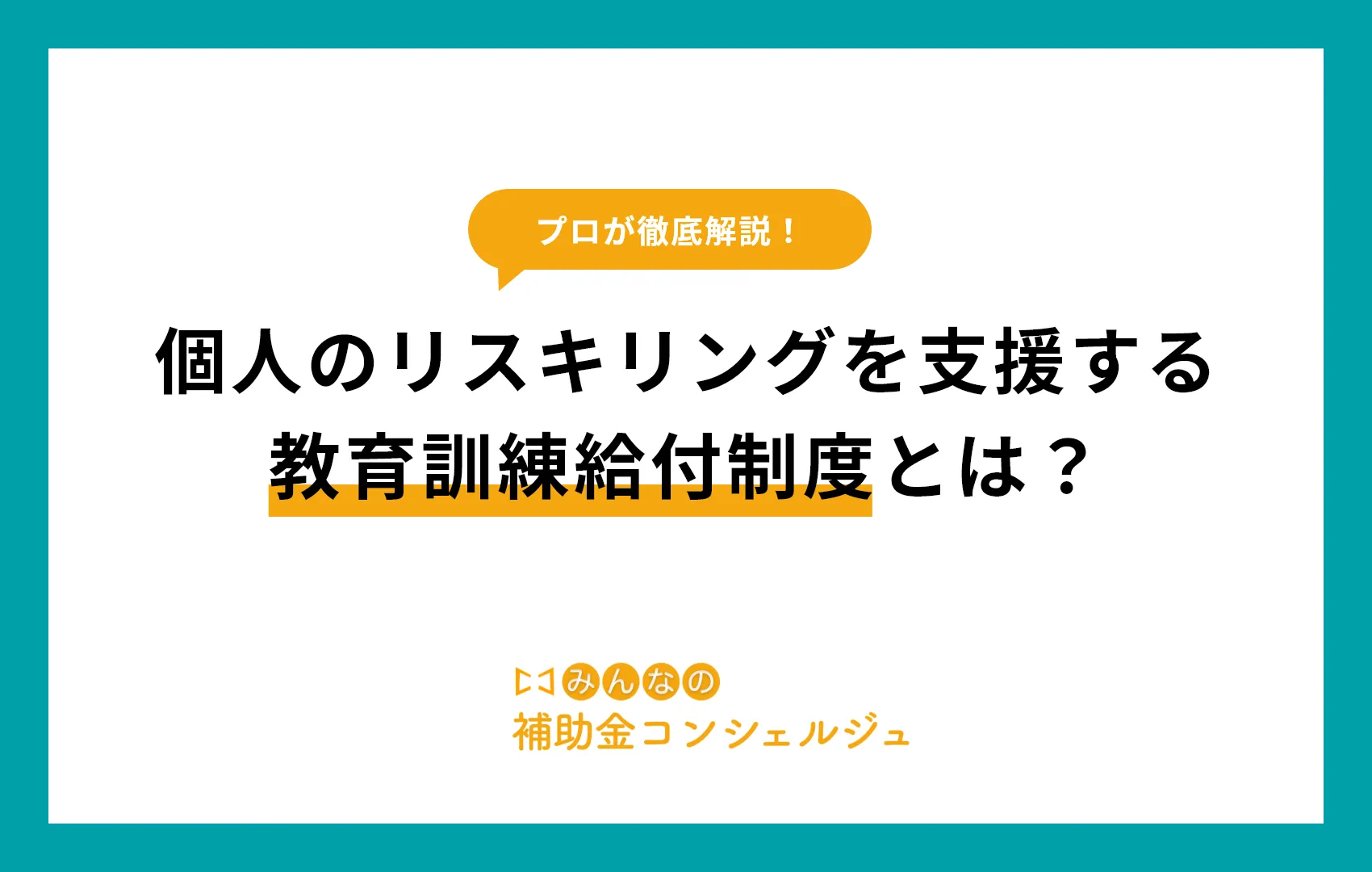
教育訓練給付制度とは?
教育訓練給付制度とは、働く人のキャリアアップや再就職を支援するために、厚生労働省が実施している公的な給付制度です。条件を満たした場合、指定された講座の受講費用の一部がハローワークから支給されます。この制度は、「自分のスキルを高めたい」「資格を取得して転職したい」「仕事をしながら学び直したい」と考えている方にとって、費用負担を軽減しながら学べる強力なサポートとなります。
教育訓練給付制度は3種類ある
教育訓練給付制度には、受講内容や目的に応じて以下の3種類があります。
| 制度名 | 主な対象 | 支給内容 |
| 一般教育訓練給付金 | 主に在職者・離職者 | 受講費用の20%(上限10万円) |
| 特定一般教育訓練給付金 | 主に専門性の高い講座を受講する在職者 | 受講費用の40%(上限20万円) |
| 専門実践教育訓練給付金 | 長期間の資格取得や国家資格取得を目指す方 | 最大受講費用の70%(年間上限56万円×最長3年) |
それぞれの制度によって対象となる講座や支給額が異なります。自分の学びたい内容や状況に応じて、適用される制度を選ぶことが重要です。
なぜ教育訓練給付制度が注目されているのか?
近年は、働き方の変化や雇用の不安定化により、「学び直し(リスキリング)」や「転職・キャリアチェンジ」への関心が高まっています。教育訓練給付制度は、こうした時代背景に合わせて制度が拡充されてきました。
たとえば、専門実践教育訓練給付金では、対象講座を修了後に一定条件を満たせば追加で20%の支給(「教育訓練支援給付金」)も受けられるなど、再就職を強く後押しする仕組みも整っています。
利用には条件と手続きがある
教育訓練給付制度を利用するには、雇用保険の加入期間や申請期限、対象講座の指定など、いくつかの条件を満たす必要があります。制度の対象になるかどうかは、受講前にハローワークで「受給資格の確認」を行うことが必須です。申請時の条件や必要書類などについては、次章以降で詳しく解説します。
教育訓練給付制度の対象者|在職中・公務員・60歳以上も利用できる?
教育訓練給付制度は、主に雇用保険に一定期間加入していた人が対象となる制度です。在職中の方や離職中の方、また年齢が高い方でも、条件を満たしていれば利用することができます。ただし、公務員など一部対象外となるケースもあるため、自分が利用できるかどうかを正確に把握することが重要です。
以下、制度を活用するにあたっておさえておきたい主なポイントです。
- 公務員は制度の対象外
- 雇用保険の加入期間が主な条件
- 離職後も一定期間は利用できる
- 在職中の方も積極的に活用されている
- 60歳以上の方も条件を満たせば利用可能
- 制度利用には「受給資格確認」が必要
1.公務員は制度の対象外
教育訓練給付制度は雇用保険に基づく制度のため、原則として国家公務員や地方公務員は対象外です。公務員は雇用保険の適用を受けないため、この制度の利用はできません。ただし、一部の公的機関職員や契約職員など、雇用保険に加入している立場であれば、対象となる可能性もあります。
2.雇用保険の加入期間が主な条件
制度を利用できるのは、原則として雇用保険に通算で2年以上加入している人です(初めて利用する場合は1年以上で可)。受講を始める時点で在職中であるか、または離職してから1年以内であれば、教育訓練給付の対象となります。制度の種類によってはさらに条件が細かく設定されており、たとえば「専門実践教育訓練給付金」では、修了後の就職なども要件に含まれます。
3.離職後も一定期間は利用できる
離職した場合でも、原則として離職後1年以内であれば制度を利用することが可能です。受給資格の確認や申請はハローワークを通じて行う必要があり、自己都合退職か会社都合退職かによっても取り扱いが異なる場合があるため、早めの相談が推奨されます。
4.在職中の方も積極的に活用されている
教育訓練給付制度は、在職中でも利用可能です。雇用保険に加入し、条件を満たしていれば、仕事を続けながら対象講座を受講し、申請することができます。夜間やオンライン、通信講座など働きながら学べる講座が多く、スキルアップや転職準備を目的に活用されるケースが増えています。
5.60歳以上の方も条件を満たせば利用可能
60歳を過ぎていても、雇用保険に加入しており、加入期間などの要件を満たしていれば制度を利用することができます。定年後も働いている方や再雇用中の方が、就業継続や新たな資格取得を目的に利用するケースも見られます。ただし、短時間勤務などで雇用保険の対象外となっている場合は注意が必要です。
6.制度利用には「受給資格確認」が必要
教育訓練給付制度を利用するには、受講する前にハローワークで「受給資格の確認」を受ける必要があります。この手続きを経ずに講座を受講してしまうと、給付の対象外になるため注意が必要です。受給資格の有無や申請に必要な書類などは、最寄りのハローワークで確認できます。
教育訓練給付制度の対象講座とは?資格一覧と検索方法も紹介
教育訓練給付制度では、厚生労働大臣が指定した「教育訓練講座」を受講する場合に限って給付金を受け取ることができます。すべての資格講座が対象ではないため、制度の対象となる講座を正確に把握することが大切です。対象講座には、就職・転職・キャリアアップに役立つ多様な分野があり、目的に応じて最適なコースを選ぶことができます。
給付制度の種類ごとに対象講座が異なる
教育訓練給付制度は「一般」「特定一般」「専門実践」の3種類に分かれており、対象となる講座の種類もそれぞれ異なります。
| 制度の種類 | 主な対象講座 | 補助率 |
| 一般教育訓練給付金 | 通信教育や短期間の資格取得講座(例:簿記、TOEIC、MOSなど) | 受講料の20%(上限10万円) |
| 特定一般教育訓練給付金 | 労働市場での即戦力となる実践的なスキルを習得する講座(例:宅建、登録販売者など) | 受講料の40%(上限20万円) |
| 専門実践教育訓練給付金 | 国家資格や専門職に直結する長期的な教育課程(例:介護福祉士、看護師、保育士、調理師、情報処理技術者など) | 受講料の最大70%(条件により最大3年間支給) |
人気の対象資格と講座の一例
制度の対象講座には多くの人気資格が含まれています。以下は代表的な資格の一例です(※指定講座として認定されているかどうかは年ごとに異なるため、必ず検索システムで確認してください)。
- 簿記検定(2級・3級)
- 宅地建物取引士(宅建)
- 社会保険労務士(社労士)
- 行政書士
- 登録販売者
- 介護福祉士
- 調理師
- 保育士
- ITパスポート/基本情報技術者
- キャリアコンサルタント
これらの講座は、就業支援・キャリアチェンジ・独立開業など幅広い目的で活用されています。
対象講座の検索方法(厚労省の公式システム)
対象となる講座は、厚生労働省が提供する検索システムで確認できます。講座名や資格名、実施機関、地域などで絞り込むことができ、制度ごとの区分(一般/専門実践など)も選択可能です。
教育訓練講座検索システム(厚生労働省)で講座を検索する!
検索時は、講座の開始日や給付制度の種類を間違えずに指定することがポイントです。とくに専門実践教育訓練給付金の対象講座は、講座単位ではなく年度や校舎によって異なる場合があるため、必ず最新情報を確認しましょう。
教育訓練給付制度のメリットとデメリットを徹底比較
教育訓練給付制度は、学び直しや資格取得を支援する心強い制度ですが、どんな制度にもメリットだけでなく注意すべき点(デメリット)があります。ここでは、制度を活用するうえで知っておきたいポイントを、メリット・デメリットの両面から整理して解説します。
メリット
主なメリットは以下4点です。
1. 在職中でも利用できる:仕事を続けながら対象講座を受講できるため、転職準備やキャリアアップの一環として無理なく活用できます。夜間やオンライン講座も多数あり、働きながら学ぶ人にとって現実的な選択肢です。
2. 費用の負担が大きく軽減される:受講費用の20%~最大70%(条件により最大96万円まで)がハローワークから支給されるため、自己負担が大幅に減ります。特に「専門実践教育訓練給付金」の場合は支給額が高く、長期的な資格取得にも対応しています。
3. 幅広い資格・分野に対応している:介護、医療、IT、不動産、ビジネススキルなど、対象となる講座や資格の幅が広いため、自分の目指すキャリアに合わせて柔軟に選べます。
4. 条件を満たせば追加給付も受けられる:専門実践教育訓練給付金では、受講後に対象分野に就職すれば追加で20%(合計最大70%)が支給される制度もあります。経済的リスクを抑えつつ、新しい職種への挑戦が可能です。
デメリット
主なデメリットは以下4点です。
1. 受給資格の条件がある:制度を利用するには、雇用保険の加入期間(初回1年以上、2回目以降は通算3年以上)などの条件を満たす必要があります。また、受講前にハローワークで「受給資格確認手続き」を行わなければなりません。
2. 講座の選定に注意が必要:給付の対象となるのは、厚生労働大臣が指定した講座に限られます。自己判断で講座を申し込んでしまうと、制度の対象外となり給付金を受け取れなくなるため、必ず事前に確認が必要です。
3. 給付は後払い(立て替え)が基本:多くの講座では、受講料をいったん全額自己負担した後、修了後に申請する形となります。申請から給付までに時間がかかることもあるため、一時的な負担には備えておく必要があります。
4. 講座修了が給付の条件となる:制度を利用するには、講座の修了(一定の出席率や成績の達成)が求められます。受講途中でやめた場合や要件を満たせなかった場合は、給付金が支給されません。
教育訓練給付制度は、制度の内容を正しく理解し、対象となる講座や受給条件を丁寧に確認することで、大きな支援となり得ます。反対に、条件を見落とすと「申し込んだのに給付が受けられなかった」といった事態も起こり得るため、必ず事前にハローワークで相談することをおすすめします。
教育訓練給付制度の申請方法
教育訓練給付制度を利用するためには、講座の受講前から受講後にかけて、ハローワークを通じた申請手続きが必要です。申請のタイミングや必要書類を正しく理解しておくことで、スムーズに給付金を受け取ることができます。
ここでは、申請の流れと準備すべき書類をわかりやすく解説します。
受講前のステップ
教育訓練給付金を受け取るには、**講座の受講前にハローワークで「受給資格確認手続き」**を行う必要があります。この手続きを行わずに受講を始めてしまうと、原則として給付対象外となるため注意が必要です。
【受講前の流れ】
- 指定された教育訓練講座を選ぶ
- 講座の実施機関から「教育訓練給付金支給対象講座である旨の書類」を取得
- 最寄りのハローワークで「受給資格確認」を申請
- ハローワークから「教育訓練給付金 支給要件回答書」が交付される
- 回答書を持って講座に正式申込
受講後のステップ
講座を修了した後、1ヵ月以内にハローワークへ給付金の申請を行います。遅れると申請できないため、修了後はできるだけ早く手続きに進むことが重要です。
【受講後の流れ】
- 講座の修了証明書など必要書類を受講機関から受け取る
- 給付金の申請書類をそろえる
- ハローワークに申請し、審査を経て給付金が支給される
教育訓練給付制度の必要書類
教育訓練給付制度の申請時には、以下のような書類を提出します。制度の種類や申請者の状況によって多少異なるため、事前にハローワークで確認しましょう。
| 書類名 | 説明 |
| 教育訓練給付金支給申請書 | ハローワークまたは講座実施機関で入手 |
| 教育訓練修了証明書 | 講座の修了時に実施機関から交付される |
| 領収書または支払証明書 | 受講料を支払ったことを証明する書類 |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 雇用保険被保険者証または離職票 | 雇用保険の加入履歴を確認するために必要 |
| 支給要件回答書 | 受講前にハローワークで交付された書類 |
| 振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー | 給付金の振込用口座を確認するため |
制度別の申請時期・注意点
- 一般教育訓練給付金:講座修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に申請
- 専門実践教育訓練給付金:複数回にわたり給付申請が可能(受講中と修了後)
- 教育訓練支援給付金:専門実践教育訓練を受講中の一定条件を満たす離職者が対象。毎月の申請が必要
制度の種類によって申請方法やタイミングが異なるため、各制度に応じた申請手順を確認し、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。
教育訓練給付制度を確実に活用するためには、「受講前の手続き」「修了後の申請期限」「必要書類の準備」をしっかり押さえることがポイントです。特に、初めて利用する方は、申請ミスや期限切れを防ぐためにも、早めにハローワークに相談しておくと安心です。
教育訓練給付制度と教育訓練支援給付金の違いとは?
教育訓練給付制度には、講座の受講費用を支給する「教育訓練給付金」と、離職中の生活を支える「教育訓練支援給付金」の2種類の給付があります。名前が似ていて混同しがちですが、対象者や給付の内容が大きく異なるため、特に離職中の方は違いを正しく理解しておくことが重要です。
| 比較項目 | 教育訓練給付金(受講費用) | 教育訓練支援給付金(生活支援) |
| 支給目的 | 受講費用の補助 | 受講期間中の生活費支援 |
| 主な対象 | 在職中または離職後1年以内で講座を受講する人 | 離職中で失業手当を受け取っていない人 |
| 対象講座 | 一般・特定一般・専門実践教育訓練 | 専門実践教育訓練のみ |
| 支給額 | 受講料の20~70%(上限あり) | 基本手当相当額を月ごとに支給 |
| 支給タイミング | 受講後に申請し一括支給 | 月ごとの申請により毎月支給 |
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度の中心となる「教育訓練給付金」は、講座の受講費用の一部を補助する制度です。在職中または離職後1年以内の方が、指定講座を受講し、一定の条件を満たした場合に支給されます。給付額は制度によって異なり、たとえば専門実践教育訓練給付金では受講費用の最大70%(年間上限56万円)が支給されます。
教育訓練支援給付金とは
一方で「教育訓練支援給付金」は、失業中の人が専門実践教育訓練を受講する場合に、生活費相当額を支給する制度です。簡単に言えば、「雇用保険の失業給付」に代わる、受講中の生活支援制度と考えると分かりやすいでしょう。この支援給付金は、基本手当(失業手当)と同水準の額が毎月支給され、講座の修了まで継続して受け取ることができます。
教育訓練支援給付金の対象者になるには
教育訓練支援給付金を受け取るには、以下のような条件をすべて満たす必要があります。
- 離職中であり、基本手当(失業手当)の受給資格があること
- 雇用保険の被保険者期間が2年以上(初回は1年以上)あること
- 専門実践教育訓練講座を受講すること
- 受講前にハローワークで「受給資格の確認手続き」を済ませていること
- 世帯の収入や資産など、一定の要件を満たすこと
また、支援給付金は毎月申請が必要で、受講継続や出席状況の報告も求められます。申請を忘れると、その月の給付を受け取れない場合があるため、注意が必要です。
失業中の方が専門実践教育訓練講座を受講する場合、教育訓練給付金(受講費用)と教育訓練支援給付金(生活費補助)の両方を併用できる可能性があります。ただし、併用にはそれぞれの制度要件を満たす必要があり、受講前の手続きが必須となるため、早めにハローワークで相談することが大切です。
教育訓練給付制度に関するよくある質問
教育訓練給付制度を調べると、「自分も対象になるのか」「手続きはどのタイミングでするのか」など、さまざまな疑問が出てきます。ここでは、実際に多くの人が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。
Q1.教育訓練給付制度は在職中でも使えますか?
はい、在職中でも利用できます。雇用保険に加入しており、一定の加入期間(初回利用の場合は1年以上)があれば、制度を利用して講座を受講し、給付を受け取ることが可能です。
Q2.退職後でも制度は利用できますか?
離職後1年以内であれば、原則として利用可能です。ただし、受講開始時点での状況や退職理由によっては申請期限が異なることもあるため、ハローワークでの事前確認が重要です。
Q3.公務員でも利用できますか?
原則として、国家公務員・地方公務員などの雇用保険非加入者は対象外です。ただし、契約職員や独立行政法人職員などで雇用保険に加入している場合は対象となる可能性があります。
Q4.60歳以上でも制度を利用できますか?
はい、60歳以上でも利用できます。雇用保険に加入しており、加入期間などの条件を満たしていれば対象になります。ただし、勤務時間が短く雇用保険の対象外となる働き方には注意が必要です。
Q5.対象講座はどうやって調べればいいですか?
厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で調べることができます。講座名や資格名、実施機関名、地域などで検索できるため、目的に応じた講座を探しやすくなっています。
検索ページで対象講座を探す!
Q6.申請はいつ行う必要がありますか?
受講前には「受給資格確認」の手続きが必要で、受講後には1ヵ月以内に給付金の申請を行う必要があります。特に受講前の手続きは必須条件なので、申請前に必ずハローワークで相談してください。
Q7.自己都合で講座を途中で辞めた場合はどうなりますか?
講座を修了しなかった場合や要件を満たさなかった場合は、給付金は支給されません。制度を活用するには、一定の出席率や成績の基準を満たす必要があります。
Q8.教育訓練給付金と教育訓練支援給付金は併用できますか?
はい、離職中に専門実践教育訓練を受講する場合は、両方の制度を併用できる可能性があります。受講前にハローワークでの手続きが必要となるため、早めに相談することをおすすめします。
教育訓練給付制度の公式サイト