助成金とは?
助成金とは、国や地方自治体、あるいは独立行政法人や各種公的団体が、特定の目的を持った取り組みや事業に対して、条件を満たした事業者や個人に対して支給する返済不要の資金です。
企業の活動を支援し、国の政策目標を達成するための手段として大事な役割を果たしています。
特に中小企業や個人事業主にとっては、資金調達の手段として有効です。
参考:東京都中小企業振興公社
当コラムでは、助成金サポートの重要性と活用方法を解説します。 申請プロセスや成功事例、専門家のサポートを受けるメリットを紹介し、資金調達をスムーズに進めるための具体的な戦略を学びましょう。
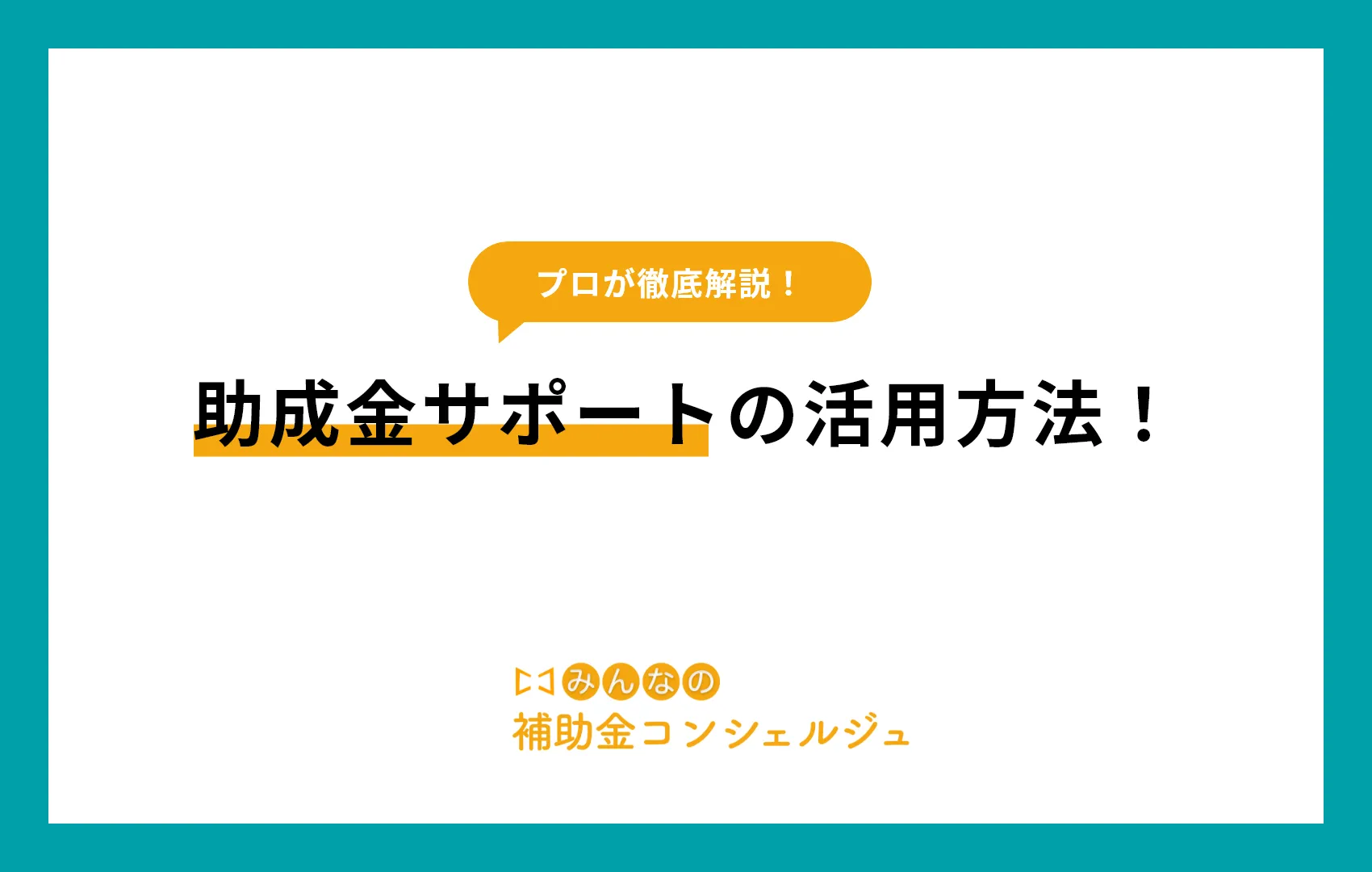

カミーユ行政書士事務所代表・行政書士
補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
助成金とは、国や地方自治体、あるいは独立行政法人や各種公的団体が、特定の目的を持った取り組みや事業に対して、条件を満たした事業者や個人に対して支給する返済不要の資金です。
企業の活動を支援し、国の政策目標を達成するための手段として大事な役割を果たしています。
特に中小企業や個人事業主にとっては、資金調達の手段として有効です。
参考:東京都中小企業振興公社
まず、助成金について整理しておきましょう。助成金の特徴として、以下のような点が挙げられます。
助成金は融資ではないため、支給された資金は返済する必要がありません。
ただし、不正な申請や使用、あるいは条件を満たさなかった場合は返還が求められることがあります。
助成金には実に多様な種類があります。
このように助成金は、あらゆる分野を網羅しています。
企業の課題や計画に応じて最適な助成金を選びましょう。
助成金の多くは、支給後に実績報告や使用状況の報告が求められます。
虚偽の報告や目的外使用が判明した場合には、支給取り消しや返還、さらには罰則の対象となることもあります。
助成金は無条件で支給されるものではなく、あらかじめ定められた要件を満たしていることが支給の前提です。
これには、雇用形態、就業規則、業種、事業の内容などが含まれます。
助成金は、国や地方自治体が掲げる政策目標の達成を促進するために支給されます。
たとえば、働き方改革や地域活性化、デジタル化推進、人材育成、女性活躍推進など、国策と密接に関わっているのです。
助成金と補助金は、いずれも公的資金による支援であり、返済不要という共通点があります。
しかし、制度の運用や申請の方法、審査基準、支給のタイミングなどにおいて大きな違いがあるのです。
補助金は、特定のプロジェクトや事業、政策目的に合致した取り組みに対して、競争的に支給される傾向があります。
つまり、申請者が多数いる中から、提出された事業計画の内容を審査し、評価の高いものに対して限定的に支給されるのが補助金です。
一方、助成金は、一定の条件を満たしていれば、原則として広く公平に支給されるという性質があります。
補助金は、多くの場合で公募形式が採用されており、採択件数が限定されています。
そのため、申請書類の質や事業内容の革新性、波及効果などが審査の対象です。
これに対し、助成金は要件を満たしていれば支給対象となるため、相対的に申請のハードルは低くなります。
補助金は公募期間が限られており、年に1回または数回しかチャンスがないことが一般的です。
申請から採択、交付決定、事業実施、報告書提出、支給までには数カ月を要することもあるでしょう。
一方で助成金は、制度によっては通年で申請を受け付けているものも多く、企業のタイミングに応じて柔軟に利用できるという利点があります。
補助金の場合、実際に事業を実施した後に経費が精算される形で支給されることが多く、先に資金を準備しなければなりません。
一方、助成金も原則として後払いですが、制度によっては中間払い、前払いや仮払いなど、柔軟な対応がなされることもあります。
補助金は主に経済産業省や中小企業庁、農林水産省などの各省庁が直接関与しており、国の産業政策や経済政策の一環として実施されるものです。
助成金は厚生労働省をはじめとする人材・雇用関連の政策を担う省庁や、地方自治体によって提供されることが多く、労働関係法令や就業規則に準拠した制度設計がされています。
補助金では、補助対象となる経費項目が細かく定められており、補助率(2/3や1/2など)も明確に規定されています。
助成金では、対象となる行為や取り組みに対して一律の金額が支給されるケースが多く、経費の証明は必要です。
しかし、補助率の概念が必ずしも適用されるわけではありません。
補助金では、定量的な成果(売上の向上、設備の導入効果、雇用の創出数など)を示すことが求められることが多いです。
一方で助成金では、対象となる取り組みを実施した事実と条件の達成状況が中心です。
参考:日本政策金融公庫(事業者support+)
助成金と補助金の違いを理解することで、どちらが自社のニーズに合っているかを判断しやすくなるでしょう。
企業が従業員の正社員化や職場環境の改善、社内研修の実施を予定している場合には、比較的要件が明確で申請しやすい助成金が向いています。
一方で、新しい製品の開発やITを活用した業務革新など、革新性や事業性が求められるプロジェクトには補助金が適しているでしょう。
補助金の申請には、事業計画の策定や収支見通しの作成、他の申請者との差別化など、より高度な準備が求められるため、専門家のサポートを受けるのが望ましいです。
資金調達が難しい中小企業にとって、助成金を活用するのは賢い選択肢のひとつです。
中小企業にとって、資金調達は事業運営の根幹を支える大事な要素となるでしょう。とはいえ、資金調達は常に容易ではありません。
特に、金融機関からの融資を受ける際には、厳しい審査基準が設けられています。
多くの中小企業は、担保や保証人を用意することが難しく、これが融資を受ける際の大きな障壁です。
助成金の申請には、専門的な知識が必要となるので、専門家の活用がおすすめです。
ここでは専門家のサポートを受けるメリットについて解説します。
専門家のサポートを受けることで、申請書類の質が上がるでしょう。
専門家は、過去の成功事例を基に、どのような情報を盛り込むべきか、どのように表現すれば良いかをアドバイスしてくれます。
これにより、申請書がより説得力のあるものとなり、採択される可能性が高まるのです。
助成金の申請には多くの時間と労力がかかりますが、専門家に依頼することで、企業は本業に専念できます。
申請手続きの煩雑さを軽減し、効率的に進められるため、企業にとっては大きなメリットです。
助成金申請には、スケジュール管理が不可欠です。
専門家は、申請に必要な書類の準備や提出期限を管理し、企業が適切なタイミングで申請を行えるよう支援してくれます。
これにより、申請の遅延や不備を防ぐことが可能です。
助成金は、適切な手続きとスケジュール管理が求められます。
ここでは、助成金申請の流れを詳しく解説していきます。
最初のステップは、自社の事業内容や目的に合致する助成金制度を選ぶことです。
助成金には数多くの種類があり、それぞれ対象となる事業や取り組み、申請者の条件が異なります。
まずは国の機関(厚生労働省、経済産業省など)や地方自治体の公式サイト、あるいは商工会議所・中小企業支援センターの情報を参考にして、どの助成金が利用可能かを確認しましょう。
助成金制度ごとに公募要項が公表されており、その中には対象者の条件、申請期間、助成内容、必要書類、支給の流れなどが詳細に記載されています。この要項を丁寧に読み、自社が条件を満たしているかを確認してください。
要件を満たしていない場合、申請しても不採択や支給対象外になってしまいます。
助成金は、明確な目的と計画に基づいて交付されるものであるため、事前に事業計画書を作成する必要があります。
特に補助金と異なり、助成金でも計画の明確化は必須です。
たとえば、従業員のスキルアップを図るための研修実施や、非正規雇用労働者を正社員化するための就業規則改定など、助成対象となる活動の内容・期間・目的・予算・実施体制を具体的に示すことが求められます。
助成金を申請する際には、主に以下のような書類が求められることが多いです。
【事業計画書】
助成金の使用目的やその実施計画を具体的に記載した文書です。
予算やスケジュール、成果の見込みなども含めて記述します。
【助成金交付申請書】
申請者情報(会社名、所在地、代表者名など)と申請内容を記載した正式な申請書類です。
自治体や省庁ごとにフォーマットが異なるため、公募要項で提示されている様式を使いましょう。
【就業規則や賃金規定】
助成金の内容によっては、雇用に関する制度や規定の整備が求められることがあります。
たとえば、キャリアアップ助成金の場合は、正社員転換制度が就業規則に明記されていなければなりません。
【経費に関する証明書】
支出の根拠となる見積書や請求書、領収書などが該当します。
これは支給決定後の報告時にも必要となるため、計画段階から整備しておきましょう。
【会社の登記簿謄本や決算書類】
法人であることを証明するための登記事項証明書、ならびに過去の財務状況を示す決算書類が求められることがあります。
【従業員名簿や雇用契約書のコピー】
人材関連の助成金を申請する場合には、対象となる従業員の雇用状況を証明する資料が必要です。
事業計画書を作成した後、実際に計画した取り組み(研修や設備導入、人材採用など)を実施する必要があります。
助成金の種類によっては、申請前に計画届(実施計画書など)を提出し、認可を得る必要があります。
書類提出後は審査があり、必要に応じて追加資料の提出や面談等を求められることがあります。
審査を通過すると交付決定となり、助成対象事業として認定されます。
交付決定後に助成対象事業を実施し、期間終了後に実績報告等を行います。
実施した取り組みについての証明書類(実施記録、領収書、写真、報告書等)を整理・提出します。
この工程は、助成金の申請で非常に重要です。
助成金ごとに申請期限や書式が異なるので、最新版の様式を使用し、期限を守る必要があります。
参考:厚生労働省
申請のタイミングや、申請における注意点について解説します。
助成金にはすべて申請期限が設けられており、それを過ぎると受付されません。
特に補助金に近い形式の助成金は、公募期間が短い場合もあるため、常に最新情報のチェックとスケジュール管理が必要です。
提出期限の消印有効か必着かも確認しておきましょう。
申請書や添付書類は必ず控えを取り、提出方法(電子申請)の証拠も保管しておきましょう。
郵送の場合は特定記録や簡易書留を利用し、発送日を証明できるようにしてください。
助成金申請で多く見られる不支給理由のひとつが書類の不備です。
記入漏れ、押印忘れ、誤記、添付資料の不足など、些細なミスが命取りになることもあります。
チェックリストを活用し、第三者の確認を受けるなどの工夫をしましょう。
申請の手続きが進む中で、事務局からの確認や追加書類の提出依頼があることもあります。
連絡に迅速に対応することで、スムーズに手続きが進みます。
申請書類の提出後も、事務局とのやり取りを丁寧に行いましょう。
助成金の多くは、事業の事前申請が求められます。
つまり、助成対象となる活動(研修や設備導入など)を始める前に、申請手続きを済ませなければなりません。
後から実施済みで申請した場合、不受理となることもあるため注意が必要です。
助成金は返済不要の資金であり、適切に活用することで事業の成長や効率化を図ることができます。
しかし、申請手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、専門家のサポートを受けるとより良いです。
今後の経営戦略において、助成金を効果的に活用し、企業の成長を促進するための一助として、ぜひ専門家のサポートを検討してみてください。
助成金を通じて、資金調達の選択肢を広げ、持続可能な事業運営を実現しましょう。
新規事業立ち上げに使える助成金・補助金まとめ
2025年最新版!個人事業主が使える国の助成金一覧
2025年最新!キャリアアップ助成金とは?申請条件等を解説!

補助金も助成金も事業者の方にとっては有用な資金調達の手段となります。 しかしながら申請要件の確認や必要な書類の作成には高い精度が求められています。 これらについては専門家のアドバイスに沿って準備を進めて行くことが得策と言えるでしょう。