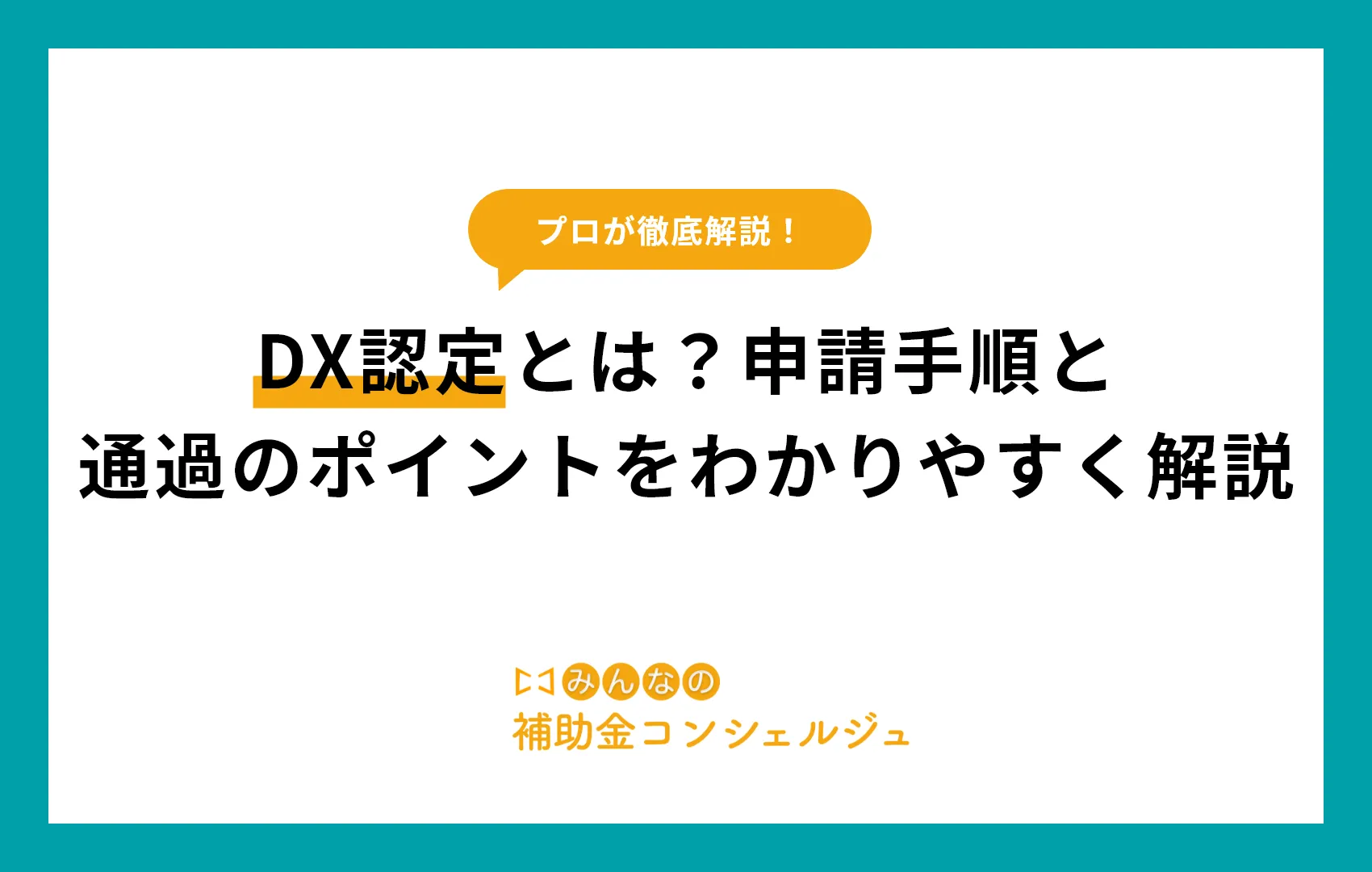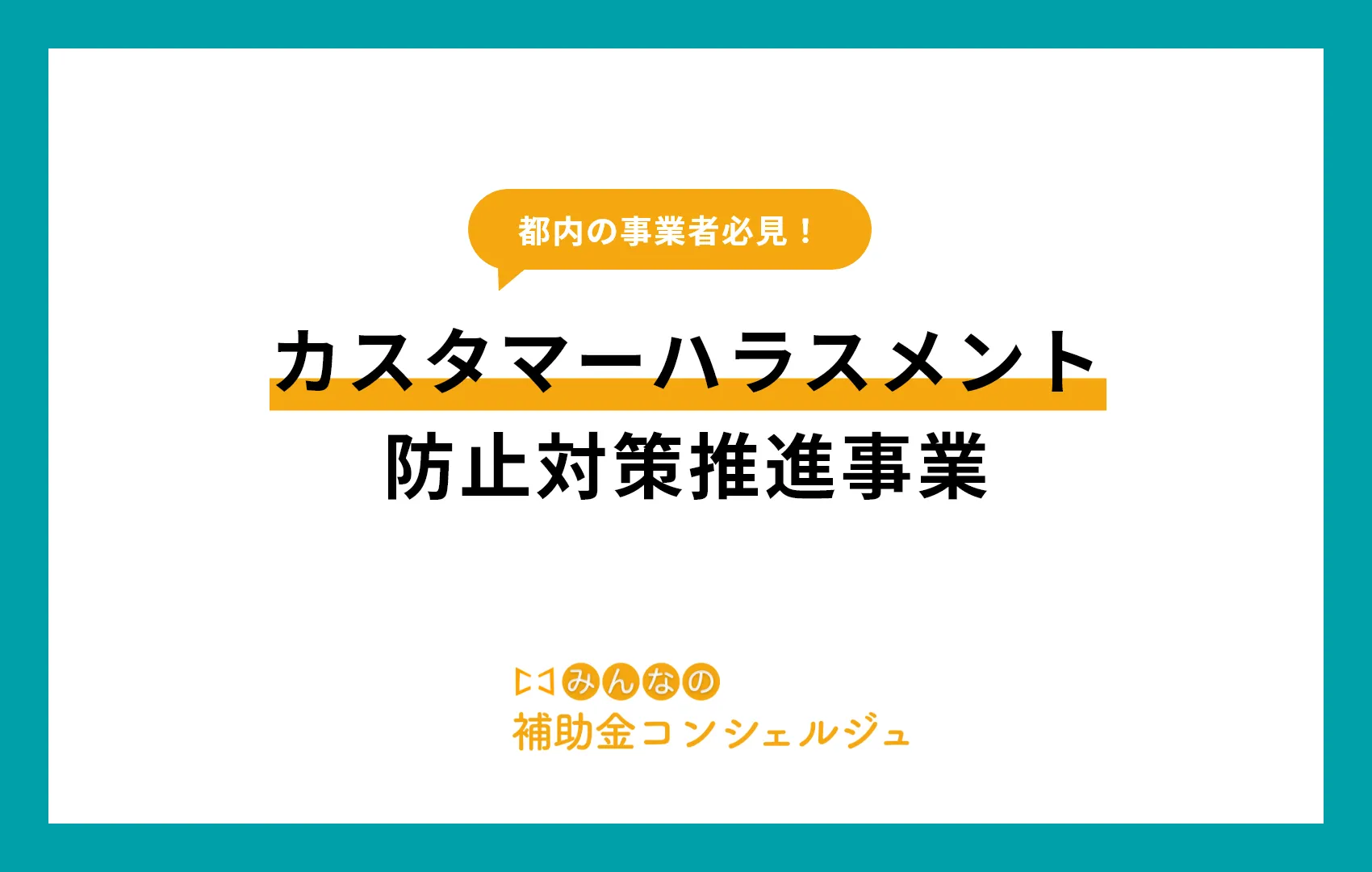DX認定とは?申請手順と通過のポイントをわかりやすく解説
本コラムでは、DX認定制度の概要、認定を受けるメリットと具体的な申請方法を分かりやすく解説します!
DX認定制度に興味のある方はぜひお役立てください。また、弊社ではDX認定制度の認定を目指す企業様のサポートを行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
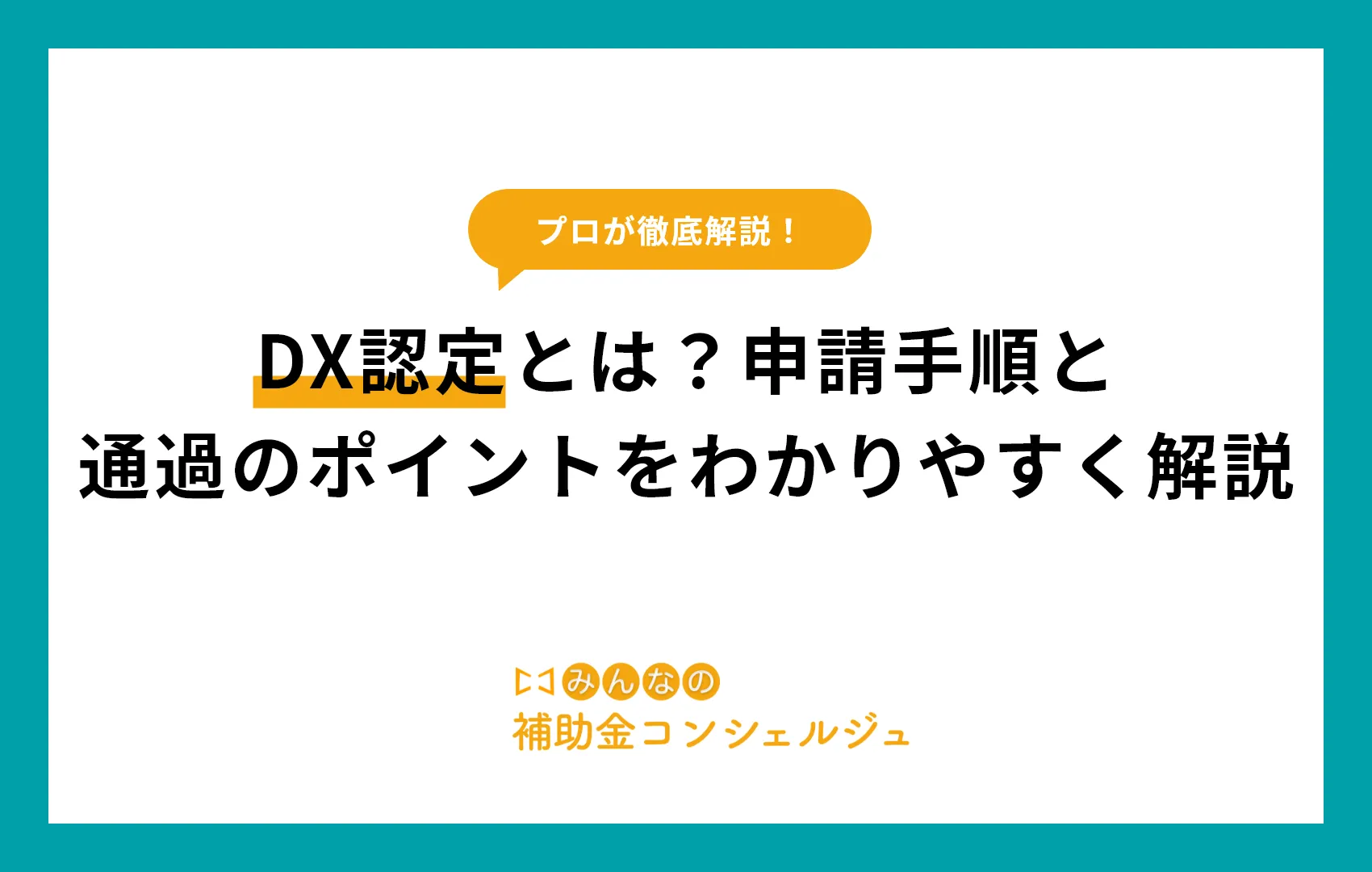
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
DX認定とは?申請前に知っておきたい制度の基本
DX認定とは、経済産業省が定めた要件を満たす企業に対し、デジタルによる経営改革(DX)に取り組む体制が整っていることを認定する制度です。ここでは、制度の基本的な仕組みや位置づけ、認定されることによる主なメリットについて、申請前に知っておくべきポイントを簡潔に解説します。
DX認定の取得を考えている方は、ぜひ一度弊社にご相談ください。弊社では、これまで多数の企業様のDX認定申請をサポートしており、計画策定から書類作成・添削までを丁寧にサポートしています。下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡くださいませ。
【無料】DX認定の申請について相談する!
DX認定制度とは
DX認定制度とは、企業がデジタル技術を活用して持続的な成長を目指す体制を整えているかどうかを、国が評価・認定する仕組みです。正式には「情報処理の促進に関する法律」に基づく制度で、経済産業省が所管し、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運用・審査を担当しています。
この制度は、単なるIT導入にとどまらず、経営戦略に基づく企業全体の変革(=DX)を推進している企業を認定することを目的としています。そのためには、経営層のリーダーシップ、明確なビジョン、IT投資方針、人材育成など、企業としての総合的なDX推進体制が求められます。DX認定を受けることで、企業としての信頼性向上や支援制度での優遇など、複数の実務的なメリットがあります。
| 項目 | 内容 |
| 信頼性の向上 | 経済産業省認定の制度であり、対外的な信用力が高まる |
| ロゴマークの使用 | 認定企業用ロゴをWebサイト・営業資料等で使用可能 |
| 補助金・税制での加点 | 一部の補助金申請・税制優遇制度において加点対象になる |
| 認定企業一覧への掲載 | IPAの公式サイトに企業名が掲載され、PR効果も期待できる |
DX認定の申請条件と対象企業
DX認定のの申請にあたって満たすべき条件は、経済産業省が示す「DX推進のための自己診断チェックシート」に基づき、以下のような観点で評価されます。
| 分野 | 求められる内容(要約) |
| 経営の方向性 | 経営者がDXにコミットし、デジタル技術を活用した事業変革の方針を示しているか |
| DX推進体制 | 組織内に推進責任者やプロジェクト体制が整っているか |
| ITシステムの整備 | 基幹システムの刷新やデータ活用の基盤整備に取り組んでいるか |
| 人材育成 | DX人材の育成方針や、リスキリングの実施体制があるか |
| セキュリティ対策 | 情報セキュリティ管理に関する基本的な取り組みがあるか |
このチェックシートはYes/No方式の簡易診断ですが、実際の申請では、これらの観点に沿って記述した「認定申請書」の提出が必要です。
経営ビジョン・IT投資方針の明文化が鍵
DX認定を受けるためには、単に「ITを導入している」だけでは不十分です。企業としてどのようなビジョンを持ち、なぜデジタル投資を行うのかを言語化しているかが重要です。たとえば以下のような内容を申請書に盛り込むことが求められます。
- 5年後を見据えた経営戦略とデジタル活用の位置づけ
- 顧客体験の変革や業務効率化に向けたIT投資計画
- 経営層の関与(社長・役員のリーダーシップ)に関する記述
DX認定の申請対象になる実例
以下のような中小企業でもDX認定を取得しています。
- 地域密着の小売業が、POSデータと顧客分析を活用して業務改善
- 地場の製造業が、生産管理にクラウドシステムを導入し、社内データの一元管理を開始
- 従業員30名規模の建設会社が、スマートフォンによる現場報告アプリを導入し、業務フローを改善
いずれも、「単なるIT導入」ではなく、「経営課題の解決にデジタルを使っている」という姿勢を明文化できていることが共通点です。
申請可能かどうかを判断するため、以下の点を自社で確認しましょう。
- 経営者がDXに明確に関与しているか?
- DXの取り組みを支える体制が社内にあるか?
- IT投資が業務改善や顧客価値向上につながっているか?
- 自社のDX課題や方向性を社内外に説明できるか?
DX認定の難易度は?不採択の原因と対策も紹介
DX認定の難易度の実態や、どのようなレベルが求められているかを解説します。あわせて、過去の申請で見られた不採択の原因とその対策も紹介します。
DX認定の通過率に関する目安
IPA(情報処理推進機構)や各種支援機関の公表資料では、通過率(審査通過の割合)を明示していません。しかし、支援実績を持つ専門家の声や公表データから推測すると、書類の内容に不備がなければ高い確率で認定される傾向があります。とはいえ、単なる「形式的な記入」では不十分であり、内容面での納得性・整合性が問われることは確かです。
認定されるにはどの程度のDXレベルが必要?
よくある誤解が、「ITツールを使っていればDX認定を取得できる」という考えです。実際には、IT活用が“経営戦略の中に位置づけられているか”が評価の軸になります。以下のような内容を申請書に盛り込めていれば、認定に近づきます。
| 観点 | 認定に向けた目安の内容 |
| 経営ビジョン | DXによって実現したい中長期的な事業方針が明示されている |
| IT投資方針 | IT導入の目的と、投資効果の見込みが明確にされている |
| 推進体制 | 経営層が関与し、社内にDX推進担当が明確化されている |
| 自己診断の整合性 | チェックシートの記載と申請書の内容に矛盾がない |
| 計画の現実性 | 現実的かつ実行可能なステップでDXを推進している |
不採択のよくある原因
支援事業者や申請者の報告から、不採択になりやすいパターンには以下のような傾向があります。
| 原因 | 注意点・例 |
| 記載内容が抽象的すぎる | ×「ITを活用して業務効率化を図る」○「クラウド型生産管理システムを導入し、工程別の作業時間を見える化。月間で40時間の業務削減を目指す」→ 成果や手段を定量的に記述し、具体性を持たせることが重要 |
| 経営層の関与が見えない | DX推進担当の記載はあるが、経営者の関与が記載されていないケースが多い→ 「社長自ら方針を策定」「予算決定に関与」などの記述が求められる |
| チェックシートとの整合性がない | チェックシートでは「できている」としているのに、申請書にその内容が一切記載されていない→ 実態と申請書の内容に矛盾があると「形式的な申請」と見なされる可能性がある |
DX認定では、派手な実績や高度な技術よりも、「経営戦略とデジタル活用の整合性」が重視されます。よって、背伸びをしたり、形だけのIT導入をアピールするのではなく、自社の実態に即した取り組みを、丁寧に言語化することが最も重要なポイントです。
また、申請書とチェックシートを別々に書くのではなく、セットで一貫性のある内容にすることで、審査側にも伝わりやすくなります。第三者の目線で客観的に確認してもらうことも、不備の防止につながります。
DX認定の申請に不安がある方へ
「どのように書けば伝わるのか分からない」「現状の取組で通るのか不安」と感じる場合は、ぜひ一度弊社にご相談ください。弊社では、これまで多数の企業様のDX認定申請をサポートしており、計画策定から書類作成・添削までを丁寧にサポートしています。下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
【無料】DX認定の申請について相談する!
DX認定の申請方法と準備フロー
DX認定の申請は、GビズIDを利用したオンラインで行います。ここでは、申請の基本的な流れや必要書類、作成時の注意点について、初めて申請する方でも分かりやすいように解説します。以下の手順に沿って準備を進めましょう。
| 手順 | 内容 |
| 1.GビズID取得 | 申請には「GビズIDプライムアカウント」が必要(取得に2週間程度かかる場合あり) |
| 2.必要書類の作成 | 認定申請書・自己診断チェックシートなどを準備 |
| 3.オンライン申請 | 専用申請サイトから書類をアップロードして申請完了 |
| 4.IPAによる審査 | 内容に不備がなければ、60営業日程度で審査完了 |
| 5.認定・公表 | 認定通知とともに、認定企業一覧に掲載される(IPAサイト) |
GビズIDを取得する!
補助金申請に必要なGビズIDの取得方法を分かりやすく解説!
提出が必要な主な書類一覧
申請には以下の書類が必要です。フォーマットはIPA公式サイトよりダウンロードできます。
| 書類名 | 概要 |
| 認定申請書 | 経営ビジョン、DX推進方針、IT投資計画などを記載するメイン書類 |
| 自己診断チェックシート | DX推進状況を「できている/いない」で自己評価(15項目) |
| 企業情報確認書類 | 登記簿謄本、定款など、法人情報の確認に使用される資料(必要に応じて) |
申請書・チェックシートの様式は、以下の公式ページにて入手可能です。
DX認定制度(経済産業省)公式ページ
書類作成のポイント|定性的な記述に説得力を持たせるには
DX認定の申請では、「認定申請書」に自社のDX方針や取組内容を文章で記載する必要があります。しかし、ただ「取り組んでいる」と書くだけでは不十分で、具体性や一貫性のある記述で審査側の納得感を得ることが重要です。以下の3つの工夫を意識すると、説得力のある申請書に仕上げることができます。
- 定量的な目標や効果を記載する
- 実行体制と役割分担を具体的に記載する
- 経営ビジョンとDX手段の因果関係を明確に示す
1.定量的な目標や効果を記載する
効果が伝わらない抽象的な表現は避け、「どれだけ」「どのように」改善されるかを数字で示すと、計画の実現性が高く評価されます。
NG例:「在庫管理の効率化を図る」
OK例:「在庫管理システムを導入し、棚卸作業時間を従来の1回あたり15時間から5時間に削減。年間で約150時間の工数削減を見込む。」
実現可能な範囲の数字でよく、将来見込みでも構いません。裏付けがあるとなお可です。
2.実行体制と役割分担を具体的に記載する
「社内で誰が何をするのか」「経営層がどう関与しているか」が見える記述が必要です。体制が曖昧な場合、実効性が疑われやすくなります。
NG例:「全社的にDXを推進する」
OK例:「代表取締役が全体方針を統括し、DX推進責任者(取締役)がプロジェクト進行を管理。専任のDXリーダー1名と各部署のサブリーダー計3名が推進体制を構成し、月1回の定例ミーティングで進捗を確認。」
役職や人数、頻度などを明記すると、実行体制の信頼性が高まります。
3.経営ビジョンとDX手段の因果関係を明確に示す
単なる施策の羅列ではなく、「なぜこの施策が必要なのか」「経営課題とどう結びつくのか」を丁寧に説明しましょう。
NG例:「CRMを導入して顧客管理を強化する」
OK例:「今後5年間で新規顧客売上比率を50%に引き上げるという中期目標を実現するため、営業活動の属人化を解消し、顧客データを一元管理する体制が必要と判断。CRMを導入し、見込顧客の育成プロセスを可視化する。」
ポイント:ビジョン → 課題 → 施策という順序で書くと説得力が増します。
DX認定では、企業規模や実績よりも、「自社の方向性と具体的行動を、自分たちの言葉で明確に表現できているか」が問われます。「経営者の意思と、現場の取り組みが分断されていないか?」「施策が単発ではなく、戦略に基づいた流れの中で語られているか?」これらを意識して文章を構成することで、審査通過の可能性は大きく高まります。
書類に不備や記載漏れがあると、IPAから修正依頼が入り、審査が一時中断されるケースがあります。とくに、以下のようなミスはよく見られます。
- 認定申請書のファイル名・形式に誤りがある
- チェックシートと申請書の整合性がとれていない
- GビズIDでのログインが完了していないまま申請を開始している
申請後のトラブルを防ぐためにも、提出前の最終チェックをおすすめします。
DX認定の申請に不安がある方へ
「どのように書けば伝わるのか分からない」「現状の取組で通るのか不安」と感じる場合は、ぜひ一度弊社にご相談ください。弊社では、これまで多数の企業様のDX認定申請をサポートしており、計画策定から書類作成・添削までを丁寧にサポートしています。下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
【無料】DX認定の申請について相談する!
DX認定取得できる企業の特徴とは?
「DX認定は一部の大企業だけが取得するものでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、実際には中小企業の取得事例も多数あります。認定企業の一覧から見えてくる業種や企業規模の傾向、自社の取り組みの参考になる事例を紹介します。
DX認定企業の業種・規模に見られる傾向
IPAの「DX認定取得企業一覧」に掲載されている企業は、大企業から従業員数10名以下の中小企業まで幅広く存在しています。
| 観点 | 内容 |
| 業種 | 製造業、建設業、情報通信業、医療・福祉、卸売・小売業など多岐にわたる |
| 規模 | 従業員10〜50名規模の中小企業から、1000人以上の大手企業まで幅広い |
| 地域 | 首都圏・地方問わず全国的に申請・認定実績がある |
このように、業種や規模にかかわらず、DXへの取組姿勢があれば認定を目指すことができます。
DX認定の実例
以下は、実際に認定を受けた中小企業の代表的な取組内容の一例です。
事例1|製造業(従業員30名)
| 背景 | DX取組 | 成果 |
| 紙の作業日報を手書きで管理。集計に1日以上かかっていた | タブレット入力+クラウド連携で日報をリアルタイム共有 | 月20時間の管理業務を削減し、経営層がデータを即時把握可能に |
事例2|建設業(従業員20名)
| 背景 | DX取組 | 成果 |
| 現場写真の整理や報告業務に手間がかかっていた | スマホからの写真登録アプリを導入し、クラウドで自動整理 | 作業報告書作成時間を半減。社員のストレス軽減にも貢献 |
いずれも「特別な技術」や「大規模な投資」があるわけではなく、現場の課題に合ったシンプルなDX施策を、経営と結びつけて実施している点が共通しています。
認定企業が行っている活用例(ロゴ・Web掲載など)
DX認定を取得すると、認定ロゴマークを自社サイトや会社案内資料などに掲載することが可能です。これにより、以下のような信頼獲得につながる事例が見られます。
- 補助金申請や制度活用時の加点要素としてアピール
- 営業資料にロゴを掲載し、「国の認定を受けている企業」として差別化
- Webサイトに「DX認定取得企業」の記載を追加し、採用や取引先への信頼性を向上
認定そのものが目的ではなく、取得後に「対外的な信頼」「社内のモチベーション向上」「施策の加速」に活かす姿勢が重要です。
DX認定の更新・有効期間と運用上の注意点
DX認定は一度取得すれば終わりではなく、有効期間や更新手続き、取得後の運用体制も重要なポイントです。認定の有効期間や更新のタイミング、認定後に求められる取り組みの継続について分かりやすく解説します。
DX認定の有効期間は「2年間」
認定を受けると、その有効期間は原則として2年間です。有効期間を過ぎると認定は自動的に失効するため、継続を希望する場合は、更新申請が必要になります。
| 項目 | 内容 |
| 有効期間 | 原則2年間(認定通知日から起算) |
| 更新申請のタイミング | 有効期限の60日前までに申請する必要あり |
| 更新内容 | 初回申請と同様に、チェックシート・申請書の提出が必要(※最新版様式に準拠) |
参考:IPA「DX認定制度に関するFAQ」および「更新案内メールの運用ルール」
認定後の取り組みが不十分な場合は?
DX認定は、「取得時点の状態」だけでなく、「その後の運用」も重視される制度です。更新時の申請では、以下のような点が審査対象となる可能性があります。
- 自己診断結果が形骸化していないか
- 経営層の関与や体制が継続されているか
- 認定時に掲げたビジョンや計画が、一定程度実行されているか
そのため、取得後に社内で「認定を取っただけ」になってしまうと、更新が難しくなるリスクがあります。
取得後も「運用」が重要な理由
認定後に求められるのは、単なる形式の維持ではなく、継続的な改善と体制の定着です。以下のような運用を意識することが、更新審査への備えとしても有効です。
- DX方針・計画の定期的な見直しと社内共有
- 社内のDX推進体制の継続(推進リーダーの活動など)
- 従業員向けの研修やリスキリングの実施状況の記録
- IT投資や業務改善の実績を資料として残しておく
こうした取り組みは、更新時の申請書作成にもそのまま活かすことができます。
更新案内はIPAからメールで送られますが、メールアドレスの登録ミスや担当変更により見逃すケースがあるため、社内体制で更新時期を管理しておくことが望ましいです。様式が変更される可能性もあるため、最新版の申請書式を必ず確認するようにしましょう。
まとめ
DX認定は、事業の信頼性を高め、補助金や優遇制度の活用にもつながる有効な手段です。ただし、申請にあたっては計画性・記述力・準備書類の質が問われるため、単なる「形式対応」では通過は難しいのが実情です。制度の要点を押さえたうえで、地に足のついたDX方針を明文化し、認定取得を目指しましょう。
DX認定制度の認定をお手伝いいたします!
「DX認定を受けたいけど、申請手続きが難しそう…」という企業さまに朗報です!
弊社リアリゼイションが御社の認定をサポートします。
私達もDX認定制度の認定企業なので、安心してお任せくださいませ。
ご相談やご依頼は以下のフォームよりお気軽にどうぞ!