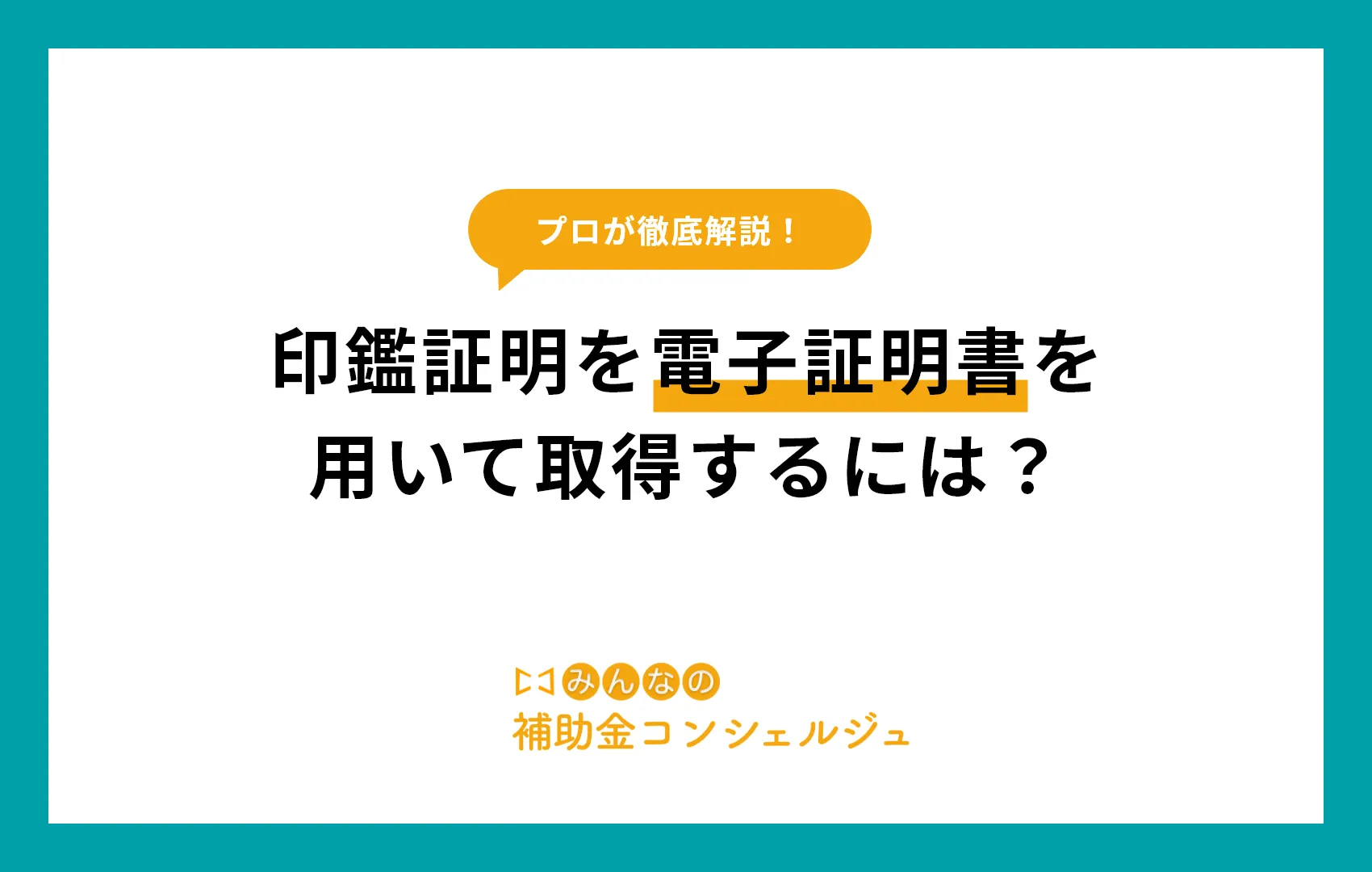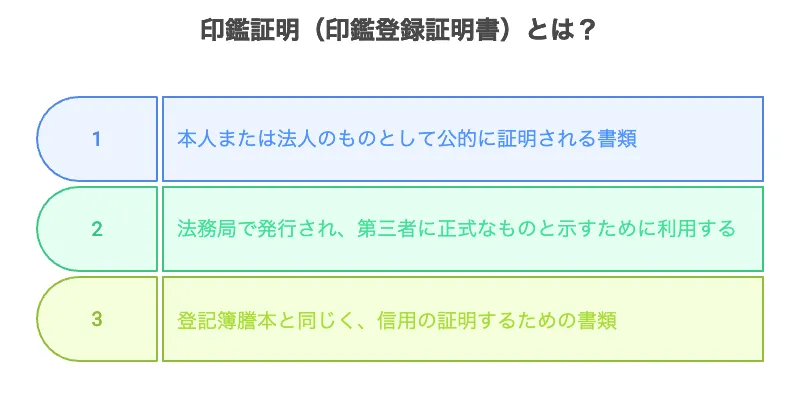印鑑証明を電子証明書を用いて取得するには?
印鑑証明を電子証明書を用いて取得するには、主に3つの方法があります。
また、印鑑証明と電子証明書の役割についても知ることで、必要性や適切な使用ができると思います。
このコラムでは、印鑑証明に電子証明書を用いる方法や、それぞれの役割について解説します。
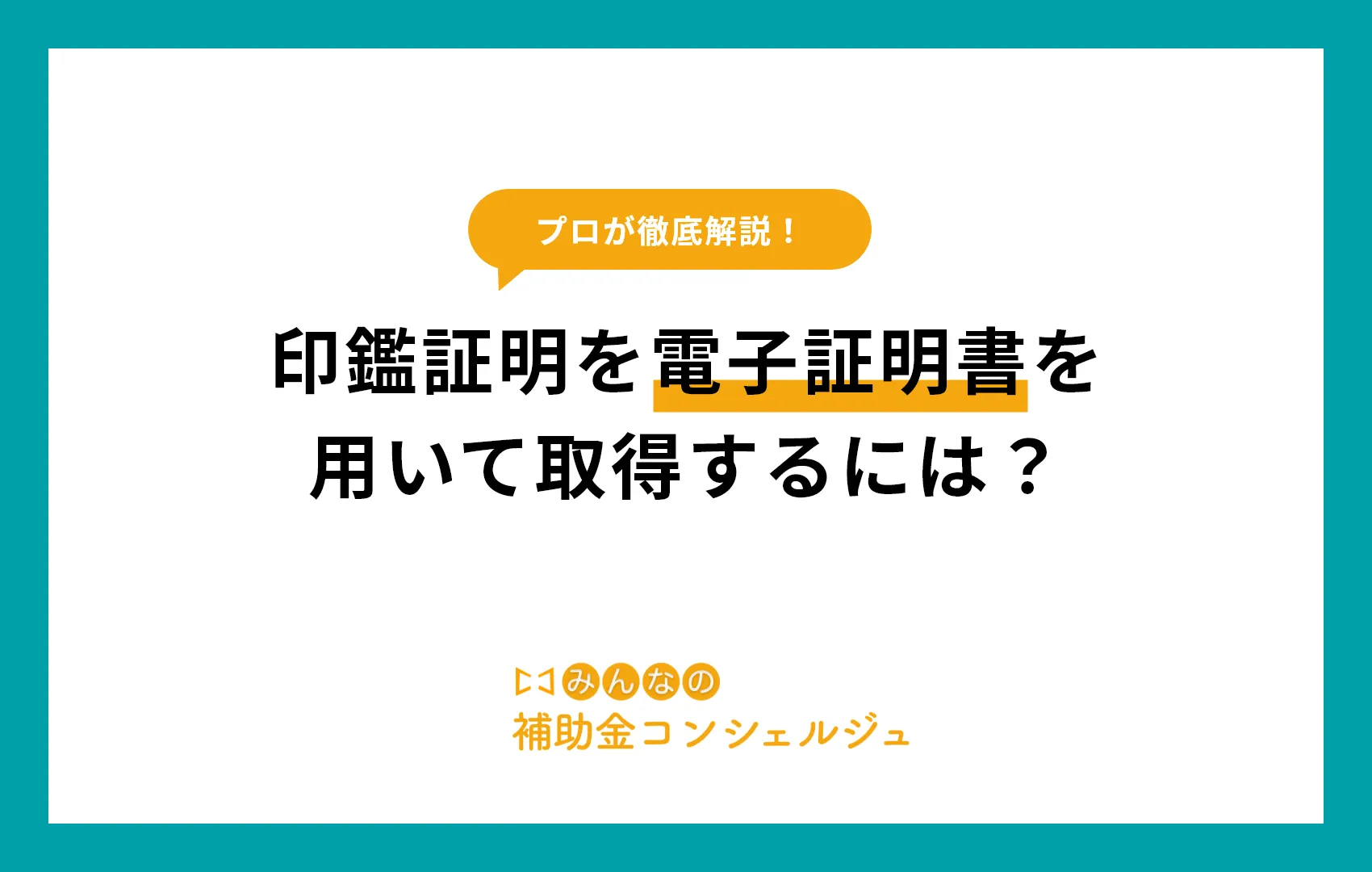
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
印鑑証明を電子証明書を用いて取得するには?
印鑑証明を電子証明書を用いて取得する方法は、下記の2つです。
オンライン申請
印鑑証明を電子証明書で取得する方法の一つに、オンライン申請があります。
申請には、電子証明書と専用の申請システムが必要であり、法務省が提供する「登記ねっと」などが代表例です。
オンライン申請の最大の特徴は、窓口に出向く必要がなく、時間や場所を問わず手続きができる点にあります。
平日の営業時間に法務局へ行けない場合でも、電子証明書とパソコン環境が整っていれば、24時間いつでも申請が可能です。
申請後は、法務局で証明書を受け取るか、郵送での受け取りを選ぶことができます。
オンライン申請のメリット
- 手続きの迅速化
- 書類記入ミスの削減
- 履歴の管理がしやすい
- 人件費や交通費といった間接的なコストの削減
一方で、デメリットもあります。
オンライン申請のデメリット
- 操作に慣れていない場合は導入に時間が必要であること
- 電子証明書の取得や更新に一定の手間と費用がかかること
- システムエラーや設定ミスが起きた際には、行政機関とのやりとりが発生する
専門家の代理取得
印鑑証明書を電子証明書で取得する際には、司法書士や行政書士などの専門家に代理取得を依頼する方法もあります。
この方法は、電子証明書の扱いや申請手続きに不慣れな事業者にとって、手間と時間を削減できる実務的な手段です。
専門家の代理取得の最大の特徴は、申請に関する煩雑な作業を専門家に任せられる点にあります。
たとえば、電子証明書の設定、登記ねっとの操作、必要書類の作成・提出など、さまざまな知識が求められる部分をすべて代行してもらえるため、申請者側の負担が大幅に軽減されます。
専門家の代理取得のメリット
- 書類作成の手間を省ける
- 手続きを正確かつ迅速に行える
- 申請の不備による再提出のリスクを減らせる
また、専門家がすでに電子証明書を保有している場合、依頼者自身が証明書を取得する手間を省けるケースもあります。
専門家の代理取得のデメリット
申請方法としては、依頼者が専門家に業務を委任し、必要書類(委任状、身分証明書など)を提出したうえで、専門家がオンライン申請や窓口手続きを行います。
書類の内容や申請の流れは事前に打ち合わせるのが一般的です。

証明書申請にかかる時間を短縮しませんか?
法人証明書請求とは、オンラインで印鑑証明の請求手続きができるサービスのことを指します。
このサービスでは、必要事項や電子証明書、手数料を用意することで簡単かつ手軽に証明書関連の請求が可能です。
弊社ではRakulia法人証明書請求というサービスを提供しており、証明書の請求にかかる時間を大幅に短縮できる点が特徴です。
最短1分で申請が完了し、24時間365日対応しているので、好きな時間、ご都合のよい時間に申請することができます。
一方で、申請にかかる手数料はオンライン申請よりも少し高くなるので、よく検討してください。
「申請に費やす時間を短縮して面倒な作業をしたくない!」という方は、下記リンクから詳細をチェックしてください。
Rakulia法人証明書請求で手軽に証明書を請求する!
印鑑証明(印鑑登録証明書)とは?
印鑑証明(正式名称:印鑑登録証明書)とは、法人や個人が役所または法務局に届け出た印鑑(登録印)が、間違いなく本人または法人のものとして公的に証明される書類です。
法人の場合、この証明書は法務局で発行され、会社実印(代表者印)が正規に登録されたものであることを第三者に示すために用いられます。
印鑑証明は、登記事項証明書(登記簿謄本)と並び、法人の信用を担保する基本的な書類のひとつです。
法人活動において信頼性を示す重要な書類であり、日常的な取引から法的な手続きに至るまで、多くの場面で必要とされます。
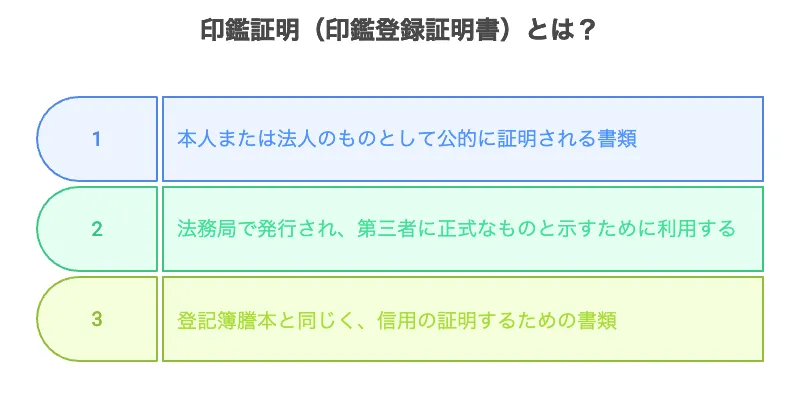
電子証明書とは?
電子証明書とは、インターネット上での本人確認やデータの真正性を証明するための電子的な証明書で、法人にとっては、代表者が確かにその法人を代表して電子手続きを行っていることを証明する手段となります。
紙の印鑑証明書に相当する電子的な証明として機能し、電子署名を行う際に不可欠な基盤技術として位置づけられています。
法人向けの電子証明書は、「商業登記に基づく電子認証制度」により、法務省が認証局(法務局または指定の民間事業者)を通じて発行します。
この電子証明書には、法人の名称、所在地、代表者名などの情報が含まれており、電子ファイルに電子署名を付与することで、書類の改ざん防止や送信者の特定が可能になります。
証明書はICカードの形態で提供されるのが一般的で、対応する専用ソフトウェアやICカードリーダーを用いて利用します。
参考:法務省
印鑑証明以外で電子証明書が必要な場面
電子証明書は印鑑証明に代わる手段として注目されていますが、その用途は印鑑証明だけにとどまりません。
法人が日常業務や公的手続きを電子的に進める際、多くの場面で電子証明書の提示や活用が求められます。
法人が電子証明書を必要とする場面
- 公的補助金申請
- 電子申請や電子契約
- 官公庁との電子契約
- 民間の電子契約サービス利用時
- 商業登記や不動産登記の電子申請
- 登記ねっとを利用した商業登記の手続き
電子証明書の取得用法
法人が電子証明書を取得するには、所定の申請手続きを経る必要があります。
電子証明書の取得場所
電子証明書の取得に必要なもの
- 手数料
- 印鑑証明書
- 登記事項証明書
- 電子証明書発行申請書
- 代表者印(会社の実印)
- 証明書発行申請ファイル
- 委任状(代理取得の場合)
- パソコン・インターネット環境
- 代表者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請が認められると、ICカード型の電子証明書が発行されます。
このICカードは、電子署名を付与する際に必要となるため、パソコンにICカードリーダーを接続して使用するのが一般的です。
また、民間の認証局を利用する場合は、オンライン上で申し込み手続きを行い、書類の郵送や対面での本人確認を経て発行される仕組みです。
手続きの所要時間は数日から2週間程度とされ、証明書の有効期限は1ヶ月〜27ヶ月の3ヶ月刻みで選択可能です。
期限が切れる前には更新手続きを行う必要があり、更新を怠ると電子署名が行えなくなるため注意が必要です。
また、利用時にはICカードとパスワードが求められるため、情報管理の徹底が重要です。
参考:法務局
電子証明書に関する相談場所
電子証明書に関する相談は、下記の場所でおこないます。
- 法務局
- 認証局
- 行政サポート窓口
- オンラインサポートセンター
法務局
電子証明書に関する相談を行ううえで、最も基本的かつ信頼性の高い窓口の一つが法務局です。
法務局では、商業登記に基づく電子証明書の発行・更新・失効などに関する業務を取り扱っており、法人代表者が電子証明書を取得する際の公式な申請先でもあります。
法務局で相談できる内容
- 必要な添付書類の確認
- ICカードの受け取り手続き
- 制度の基本から実務的な運用
- 電子証明書の申請書類の書き方
- 証明書の有効期限や更新方法など
電子証明書の取得に初めて取り組む法人や、更新・再発行の流れがわからない場合には、窓口で直接相談することで具体的な指導が受けられます。
相談は、法人の登記を所管する本店所在地の法務局で行う必要があります。
対応は原則として平日の開庁時間内となり、事前に電話で予約や確認をしておくとスムーズです。
法務省のウェブサイトでは、各地の法務局の所在地や連絡先、業務時間、担当部署の情報が公開されているため、事前に確認しておくと安心です。
参考:東京法務局
認証局
認証局とは、電子証明書の発行や管理、失効処理などを担う専門機関で、法務省の指定を受けた民間事業者がその役割を担っています。
民間認証局では、法人向けの電子証明書を発行し、オンライン申請や電子契約、電子入札などに必要な信頼性の高い電子証明の基盤を提供しています。
認証局に相談できる内容
- パスワード管理
- ICカードの利用方法
- 署名ソフトの導入手順
- 証明書の失効や更新方法
- 電子証明書の申請・取得手続きの流れ
- 導入前の相談から導入後のトラブル対応
また、民間認証局の多くは、オンラインでの申し込みに対応しており、全国どこからでも手続きを進められる点も利便性の一つです。
ただし、厳格な本人確認が求められるため、必要書類の提出や郵送、対面での確認などが発生する場合があります。
証明書の発行費用や有効期間、サポート内容は認証局ごとに異なるため、利用目的に応じた選定が重要です。
参考:e-Gov電子申請
オンラインサポートセンター
電子証明書に関する相談先として、行政機関が提供するサポート窓口の中でも特に実務的に役立つのが、法務省が運営する「登記ねっと」のサポートデスクです。
登記ねっとは、商業登記や不動産登記をオンラインで申請するためのシステムであり、電子証明書を利用した手続きが多数あります。
登記ねっとのサポートデスクで相談できる内容
- 電子署名が付与できない場合
- 電子証明書の読み取りができない場合
- 申請時のエラーに関するトラブルシューティング
- 署名プログラムや対応ソフトのインストール手順
相談方法は、電話・メールのほか、登記ねっとの公式サイトに掲載されている「よくある質問」や操作マニュアルでも情報を得ることができます。
特に、法人の電子証明書を用いた申請に関する実務的な疑問や、ICカードリーダーの設定といった機器周辺の相談にも対応している点が特徴です。
ただし、制度そのものに関する法的な判断や、申請書類の内容に関する助言は対象外となるため、必要に応じて法務局や専門家への相談と併用するとよいでしょう。
参考:登記ねっと
まとめ
今回は、印鑑証明に電子証明書を用いて取得する方法や、印鑑証明、電子証明書の役割について解説しました。
デジタル化やDX化が進んでいる近年、電子証明書をはじめとするオンライン上の取引はよりいっそう需要が高まっています。
印鑑証明のオンライン取得に関する相談もさまざまな場所でできるので、電子証明をはじめとするツールに慣れていない人は、少しづつ理解を深めていきましょう。