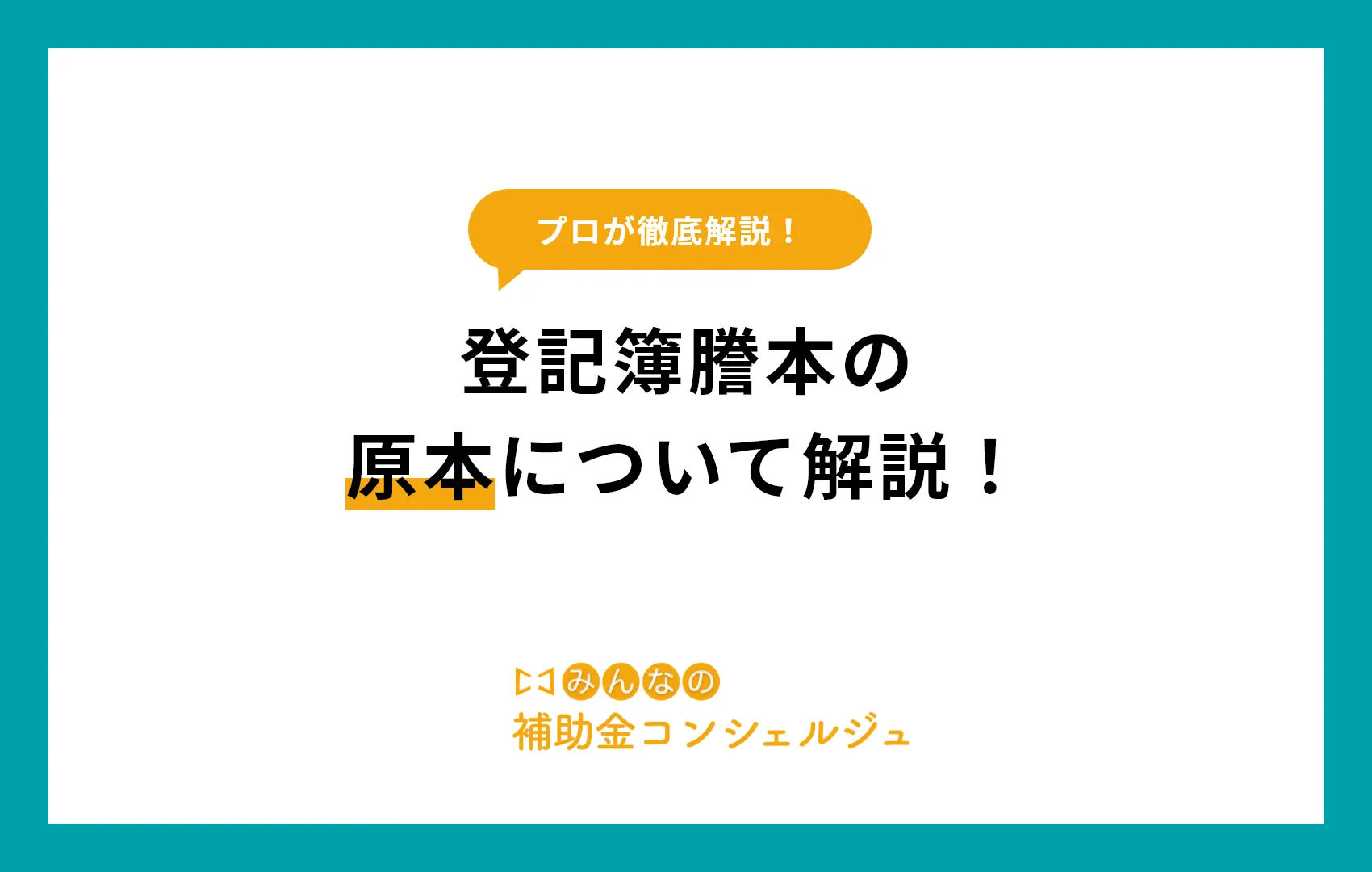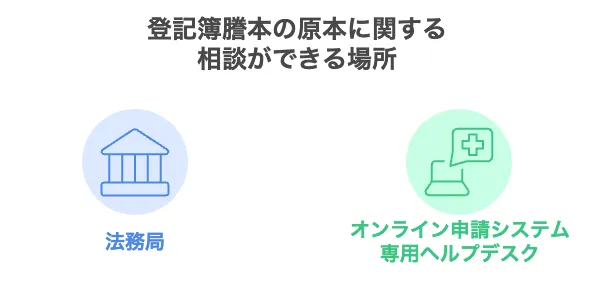登記簿謄本の原本について解説!原本の意味や目的とは?
登記簿謄本の原本は、法務局に保管されている重要な情報です。
この情報は、主に取引や手続きの際に情報が正確であるかを判断するために用いられます。
今回は登記簿謄本の原本について解説します。
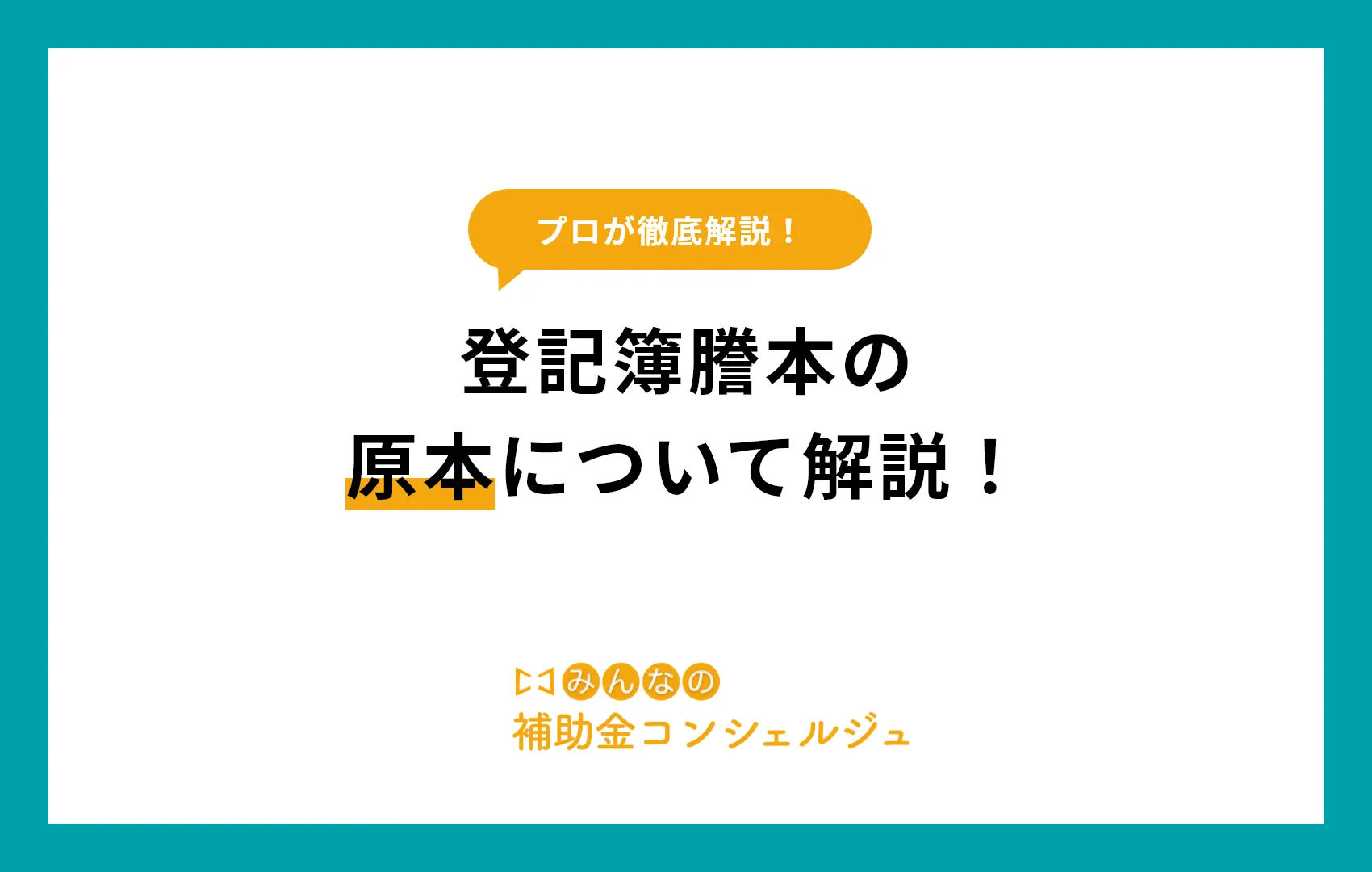
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
登記簿謄本の原本とは?
登記簿謄本の原本とは、法務局に保管されている登記情報の記録であり、登記内容を証明するための公的な文書です。
私たちが取得する登記簿謄本は「原本の写し」に該当しますが、ここでいう「原本」は法務局のデータベースに記録されている登記情報を指します。
登記制度の目的は、不動産や法人に関する重要な情報を公にして取引の安全を確保することにあります。
そのため、登記簿謄本の原本は「信頼できる情報源」としての役割を果たし、各種手続きにおいて登記内容の正確性を証明するために利用されます。
たとえば、不動産の売買や相続の際には、登記簿謄本を提出して所有者の情報や権利関係を確認する必要があります。
法人の場合でも、会社設立時や融資の申請時に登記内容を証明する書類として登記簿謄本が用いられます。
このような場合、申請者が取得する書面はあくまで「証明書」であり、原本自体は法務局が厳重に管理しています。
登記簿謄本の原本が必要な場面

登記簿謄本の原本とされる登記事項証明書が必要な場面は、不動産取引や各種手続きにおいて法的効力を証明するための書類が求められるときです。
不動産の所有者や抵当権の有無など、法的関係を公的に証明する必要がある状況において、登記事項証明書が正式な根拠書類として扱われるためです。
たとえば、住宅ローンの申し込み、不動産の売買契約、相続登記、法人設立時の本店所在地の証明など、さまざまな申請手続きで添付が求められます。
登記簿謄本の原本は取得できる?
登記簿謄本の原本は、個人が取得することはできません。
なぜなら、現在の登記情報はすべて法務局のデータベースで電子的に管理されており、紙の「原本」という形態そのものが存在しないからです。
たとえば、かつての登記制度では、不動産の登記内容を紙の台帳に記録し、それを「原本」とし、必要に応じて複写した謄本が交付されていました。
しかし、現在は登記簿が電子化され、登記事項証明書という形でその内容を証明する制度に変わっています。
登記簿謄本の取得方法
ここでは、登記簿謄本の取得方法について解説します。
郵送
登記簿謄本を郵送で取得する方法は、法務局の窓口に出向くことが難しい方にとって便利な手段です。
この方法では、法務局あてに申請書と手数料分の収入印紙、返信用封筒などを送付する必要があります。
手続きを郵送で行うことにより、遠方に住んでいる場合や平日に時間が取れない場合でも、自宅から書類を受け取ることができます。
申請書は法務局のウェブサイトからダウンロードでき、必要事項を記入したうえで、登記事項証明書1通あたり600円分の収入印紙を同封します。
返信用封筒には必ず切手を貼り、宛名を書いて同封する必要があります。
申請から書類の到着までは、通常3日から1週間程度かかりますが、法務局の混雑状況や郵便事情により前後する場合もあります。
法務局の窓口
登記簿謄本を確実かつ迅速に取得したい場合は、法務局の窓口での手続きが最も適しています。
窓口での申請はその場で職員の案内を受けながら進めることができ、記載ミスや不備があった場合にもすぐに修正できるため、時間的なロスを防ぎやすいという利点があります。
たとえば、最寄りの法務局にある申請用紙に必要事項を記入し、登記事項証明書1通につき600円分の収入印紙を購入して貼付します。
申請内容に問題がなければ、当日中に証明書を受け取ることが可能です。
ただし、混雑状況によっては待ち時間が発生することがあるため、余裕をもって訪問することが望ましいです。
登記簿謄本をオンラインで取得するには?
登記簿謄本は、法務省が提供する登記ねっとを利用することで、インターネットから申請して取得することができます。
オンラインでの取得には、申請だけをオンラインで行い、書類を郵送または窓口で受け取る方法が用意されています。
この手続きが可能になることで、遠方の法務局に出向く手間を省くことができ、時間と労力を節約するメリットがあります。
特に忙しいビジネスパーソンや、地方に住む方にとって利便性が高い手段といえます。
また、オンライン申請後、指定した法務局の窓口で登記簿謄本を受け取ることができます。この場合、取得手数料は1通につき490円です。
一方、オンライン申請後に郵送で受け取ることも可能で、その際の手数料は1通につき520円となります。
郵送による受け取りを選ぶ場合は、別途返信用封筒と切手を準備する必要があります。
オンライン取得では、事前に利用者登録が必要で、支払いにはインターネットバンキングやATMによる納付が必要になります。
申請に不慣れな場合は、法務局のサポートセンターや電話窓口で事前に確認しておくことをおすすめします。
法人証明書請求もおすすめ!
登記簿謄本を手軽に取得したい方は、法人証明書請求の活用がおすすめです。
弊社が提供しているRakulia法人証明書請求では、面倒な登記簿謄本の請求手続きを最短1分で行えます!
さらに、24時間365日いつでも請求が可能なため、登記簿が急に必要となった場合にも対応しやすいです。
詳細を知りたい方は、下記のリンクからチェックしてください。
Rakulia法人証明書請求
登記簿謄本に有効期限はある?
登記簿謄本自体には法律上の有効期限は設けられていませんが、提出先によっては一定期間内に取得されたものを求められるケースがあります。
つまり、書類としての効力は残っていても、実務上は「新しいもの」であることが求められる場面が多く存在します。
この理由は、登記情報が変更される可能性が常にあるためです。
登記簿には不動産や法人の所有者、所在地、役員構成などの重要な情報が記載されており、その内容は随時更新されます。
そのため、手続きに関わる機関や取引の相手方は、最新の状態を確認するために「何日以内に取得した登記簿謄本であるか」を重視します。
たとえば、不動産の売買や相続登記、会社設立の際には「発行から3か月以内」や「1か月以内」の登記簿謄本の提出を指定されることが一般的です。
また、金融機関での融資申込においても、登記内容の正確性が審査基準の一部となるため、取得日が古い書類は再提出を求められる可能性があります。
登記簿謄本の有効期限に関してまとめたコラムも参考にしてみてください。
登記簿の有効期限は法律上規定なし|なぜ「3ヶ月以内」なのか解説
登記事項証明書と登記簿謄本の違い
登記事項証明書と登記簿謄本は似たような目的で使用されますが、内容と形式に違いがあります。
両者はどちらも不動産の権利関係や所有者の情報などを証明するための書類です。
登記簿謄本という名称は過去の制度に由来する呼び方で、登記事項証明書は現在の登記制度に基づいて発行される正式な証明書という位置付けです。
たとえば、かつては登記簿の内容をそのまま写した書類を「登記簿謄本」と呼んでいました。
しかし、登記情報が電子化された現在では「登記事項証明書」として発行されており、法務局でもこの呼称が正式に使われています。
登記簿謄本に関するよくある質問
登記簿謄本に関するよくある質問を2つご紹介します。
Q.最寄りの登記所で他の登記所の登記事項証明書の請求ができますか?
A.全国の登記所間において、土地・建物に関する登記事項証明書の交付請求を相互にすることができる「登記情報交換サービス」があります。
登記事項証明書の交付を請求するときは,このサービスを利用して、最寄りの登記所で、その登記所の管轄外の登記事項証明書を請求し、受け取ることができます。
このサービスを利用するときは、登記事項証明書を請求しようとする土地・建物の所在(○市○町○丁目○番地)と地番・家屋番号をあらかじめ調べておいてください。
なお、土地・建物の地番・家屋番号は、いわゆる住居表示と一致しないことが多いので、正しい地番・家屋番号を、登記完了証や登記識別情報通知書又は登記済証(いわゆる権利証)等で確認してください。
Q.インターネットで登記情報を確認する方法はありますか?
A.登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用して、一般利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認することができるサービス(「登記情報提供サービス」といいます。)を提供しています。
提供される登記情報の種類は、次のとおりです。
- 商業登記簿
- 法人の登記簿
- 不動産の登記簿
- 動産譲渡登記事項概要ファイル
- 債権譲渡登記事項概要ファイル
- 地図、地図に準ずる図面、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図が記録されたファイル
利用料金
①不動産の所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所のみに関する情報(所有者情報):1件につき141円(登記手数料130円+指定法人手数料11円(消費税及び地方消費税を含む。))
②動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報:1件につき141円(登記手数料130円+指定法人手数料11円(消費税及び地方消費税を含む。))
③地図、地図に準ずる図面、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面
及び各階平面図が記録されたファイルに記録されている情報:1件につき361円(登記手数料350円+指定法人手数料11円(消費税及び地方消費税を含む。))
④ ①から③まで以外の物件:1件(1物件・1会社)につき331円(登記手数料320円+指定法人手数料11円(消費税及び地方消費税を含む。)
登録費用(消費税及び地方消費税を含む。)
①個人が登録する場合:300円
②法人が登録する場合:740円
③国又は地方公共団体が登録する場合:560円
決済方法
①個人の場合:クレジットカードによる決済
②法人の場合:銀行預金口座からの引き落とし
③国又は地方公共団体の場合:協会の指定口座への銀行振込
利用時間
| 登記情報 | 利用時間 |
| 登記記録の全部の情報(不動産・商業・法人) | 平日
午前8:30〜午後11:00
土日祝日
午前8:30〜午後6:00 |
| 所有者事項の情報 | 同上 |
| 登記事項概要ファイルの情報(動産譲渡・債権譲渡) | 同上 |
| 地図及び図面が記録されたファイルの情報 | 平日
午前8:30〜午後9:00 |
引用:法務局(よくある質問)
登記簿謄本の原本に関する相談ができる場所
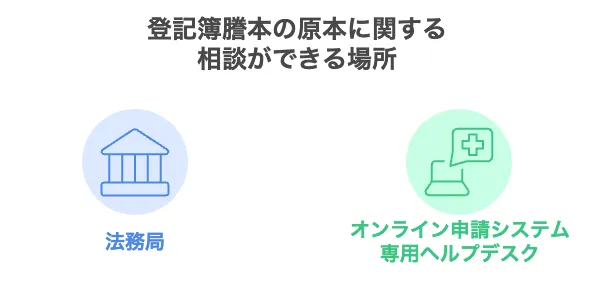
登記簿謄本の原本に関する疑問や取得手続きについて相談したい場合は、最寄りの法務局が最も信頼できる窓口です。
法務局では、登記制度に精通した職員が対応しており、申請方法や必要書類に関する具体的な案内を受けることができます。
公的機関で相談することで、誤った情報に基づく手続きミスを防ぐことができ、スムーズに目的の登記簿謄本を取得することが可能になります。
特に原本と写し、登記事項証明書の違いなどについては、専門的な判断を要することが多いため、自己判断ではなく公的な確認が重要です。
不動産登記に関する相談であれば、法務局の不動産登記部門へ問い合わせることで、対象物件の所在地を管轄する支局や出張所の案内を受けられます。
また、法人登記についての相談も同様に、法人登記部門での対応が可能です。
さらに、オンライン申請に不安がある場合には、登記・供託オンライン申請システムの専用ヘルプデスクが利用できます。
この専用システムで、手続きの流れや技術的な問題についても解決できるでしょう。
まとめ
今回は登記簿謄本の原本について解説しました。
登記簿謄本の原本自体は取得できませんが、その写しにあたる登記事項証明書を取得することで書類を準備したり、提出したります。
登記簿に関する相談や質問したいことがある場合は、法務局や法務局の専用ヘルプデスクに相談すると良いでしょう。
法人証明書請求は反社チェックにも役立ちます!
登記簿の請求手続きを手軽にできる法人証明書請求ですが、弊社のサービスにおいて反社チェックを目的として利用されている方が増えています。
法人証明書請求は幅広い用途でご利用できるので、この機会にぜひご利用ください!