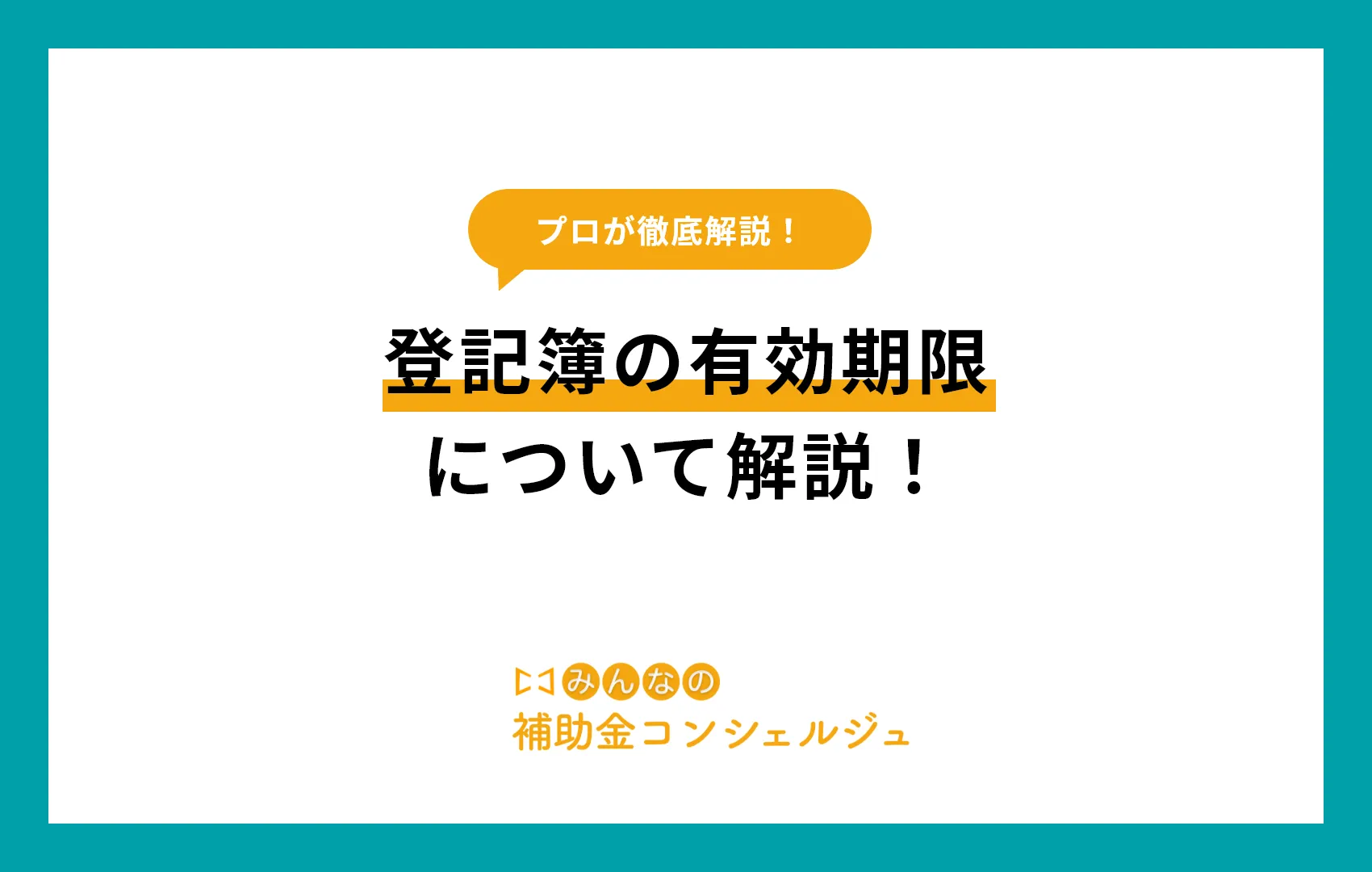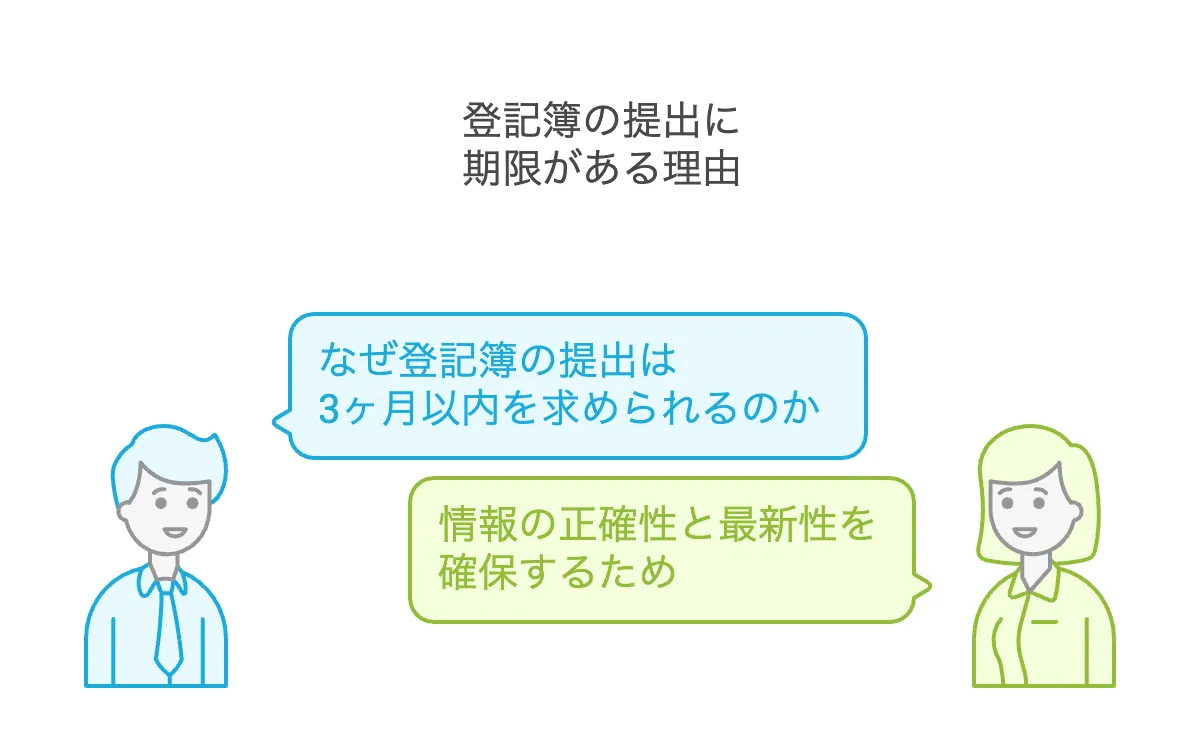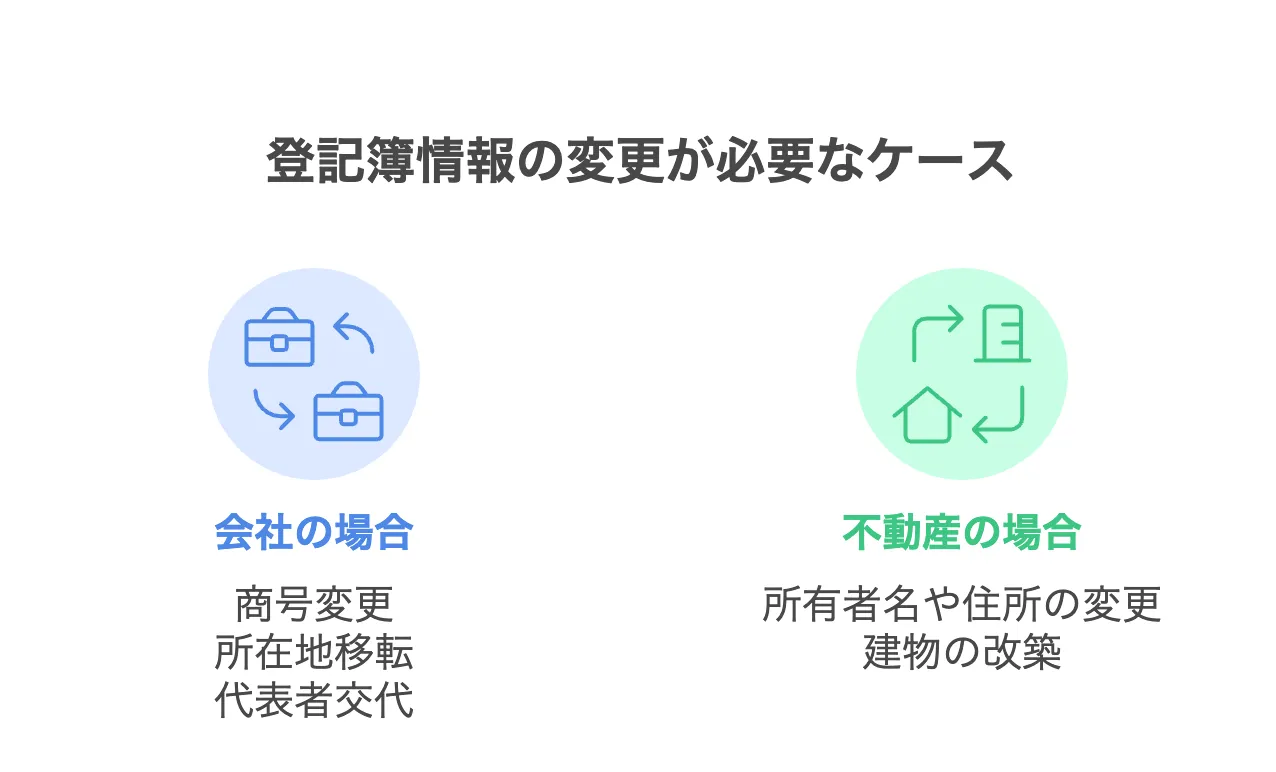登記簿の有効期限は法律上規定なし|なぜ「3ヶ月以内」なのか解説
登記簿の有効期限は、法律上規定がありません。
しかし、発行日から3ヶ月以内の登記簿を提出する場面がほとんどです。
今回は登記簿の有効期限について解説します。
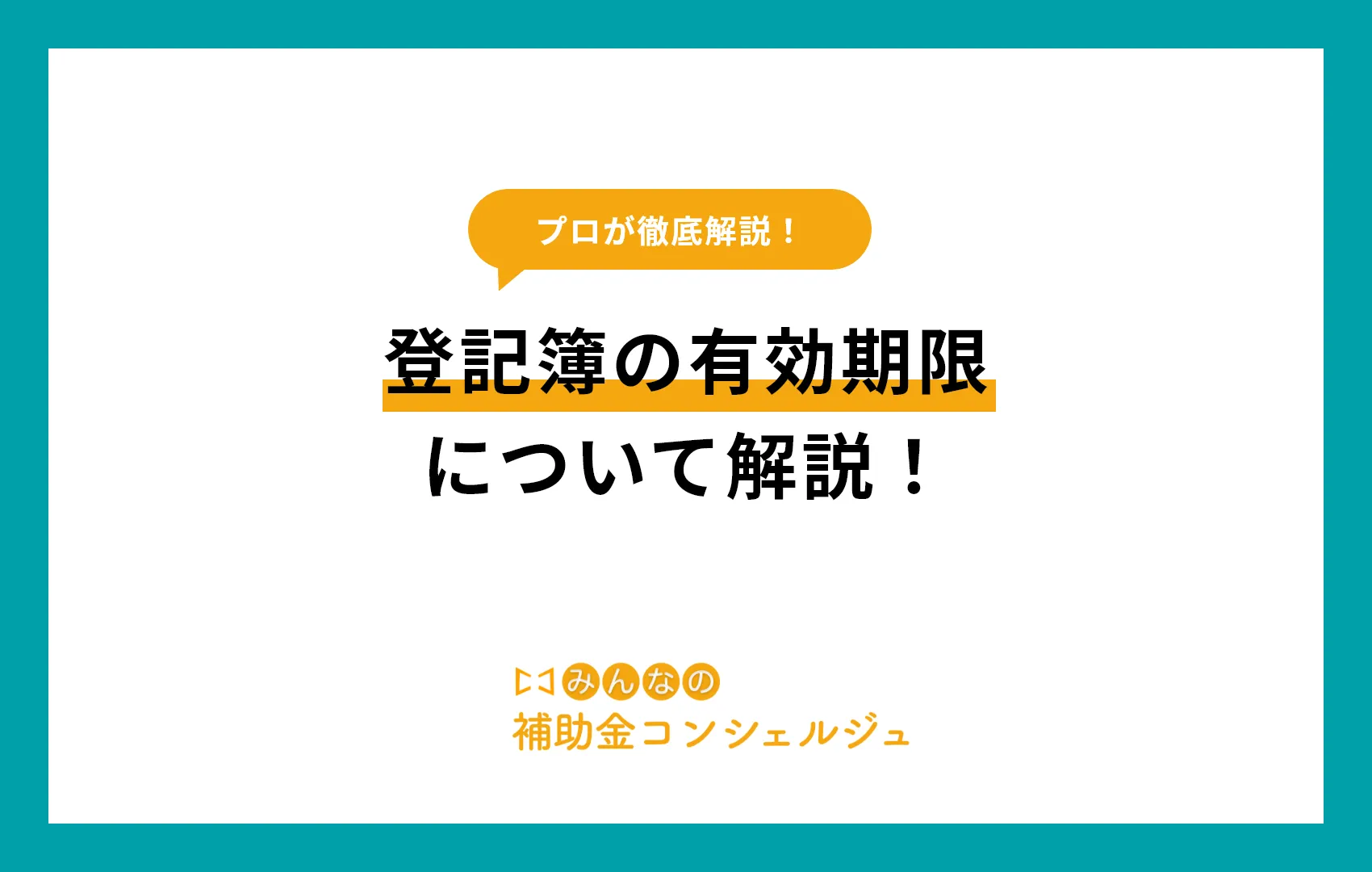
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
登記簿の有効期限は法律上決まりはない
登記簿には法律上の有効期限が定められていません。
不動産登記法や会社法などの関連法令を見ても、登記簿の有効期限に関する規定はなく、一度発行された登記簿は理論上いつまでも使用できます。
しかし、実際の手続きでは、発行後一定期間内のものを求められることが多いです。
これは、提出を求める側の実務上のルールとして運用されているものです。
不動産の売買や賃貸契約、住宅ローンの申し込み、法人登記に関する手続きでは、発行から一定期間内の登記簿の提出が求められる場合があります。
金融機関や行政機関、取引先企業などが登記簿の提出を求める際には、発行日の条件を設定していることが一般的です。
そのため、必要な場面に応じて、あらかじめ最新の登記簿を取得しておきましょう。
参考:法務局(よくある質問)
なぜ登記簿の提出は3ヶ月以内を求められるのか
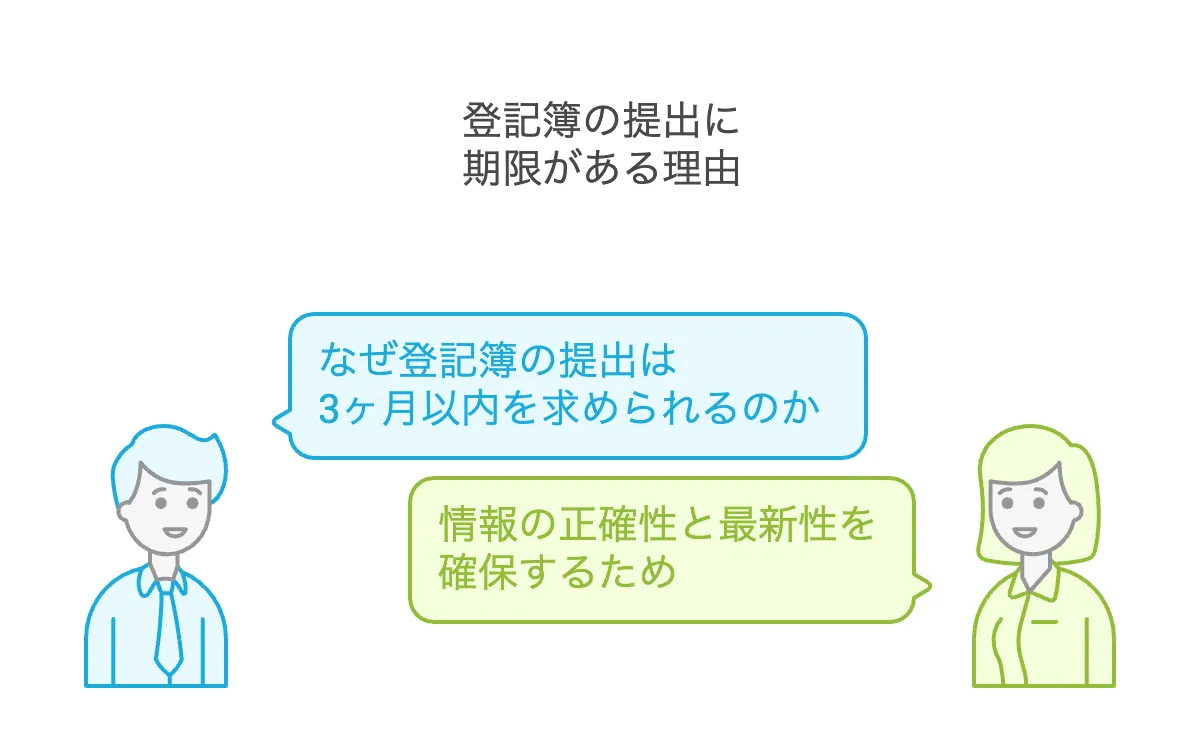
登記簿の提出時に「3ヶ月以内に発行されたもの」が求められるのは、情報の正確性と最新性を確保するためです。
登記簿は、不動産や法人の登記情報を示す公的な書類ですが、登記事項に変更があった場合、発行日が古いものでは最新の情報が反映されていない可能性があります。
特に、不動産取引や金融機関での融資手続き、法人の信用調査などでは、登記情報が最新であることが求められます。
不動産の所有権が直近で変更されていた場合、発行日が古い登記簿では新しい所有者の情報が記載されていない可能性があります。
そのため、取引や審査を行う際に正確な判断をするために、3ヶ月以内の登記簿の提出を求められることが一般的です。
なお、「3ヶ月以内」という期間は法律で明確に定められているわけではなく、各機関が独自の基準として設定しているものです。
そのため、提出先によっては「6ヶ月以内」や「1ヶ月以内」といった別の基準を設けている場合もあります。
登記簿を提出する際は、事前に提出先の要件を確認し、適切な発行日であるかをチェックすることが大切です。
登記簿発行日を新しくしておくには?
発行日の指定がある以上、登記簿の発行日をできるだけ新しいものにしておきたいですよね。
登記簿の発行日を新しいものにしておくには、定期的に登記簿を取得する以外の方法はありません。
そんなときは、Rakulia法人証明書の定期取得がおすすめです。
登記簿を法務局で申請する場合、その都度手続きをすると手間がかかりますが、Rakulia法人証明書であれば面倒な手続きを簡略化できます。
いつでもどこでも請求可能。最短1分で手続きが完了するので、興味のある方は、ぜひご確認ください!
Rakulia法人証明書で登記簿の更新をする!
登記簿発行日の期限は提出先の裁量で決まる
登記簿の提出期限は、提出先によって異なります。
法律で統一された有効期限は定められておらず、各機関や企業が独自の基準を設けています。
そのため、提出する際には、事前に提出先のルールを確認することが重要です。
不動産の売買契約や住宅ローンの審査では、一般的に「発行から3ヶ月以内」の登記簿を求められることが多いです。
これは、登記情報が最新であることを確認し、正確な取引を行うためです。
一方で、金融機関によっては「1ヶ月以内」など、より厳しい期限を設定している場合もあります。
また、法人登記簿(履歴事項全部証明書)を提出する場面でも、取引先や審査機関によって求められる期限が異なります。
信用調査や契約締結の際には、新しい情報を確認するために、最近発行された登記簿の提出が求められることが一般的です。
一方、特定の行政手続きでは「期限なし」とされる場合もあり、古い登記簿でも受理されることがあります。
登記簿発行日の記載箇所
登記簿(登記事項証明書)の発行日は、一般的に書類の一番下に記載されています。
発行日とは、法務局が登記事項証明書を発行した日を示しており、この日付を基準に有効期限が判断されます。
そのため、登記簿の有効期限を確認する際には、必ず「発行日」の記載箇所を確認するようにしましょう。
登記簿情報を変更する場合について
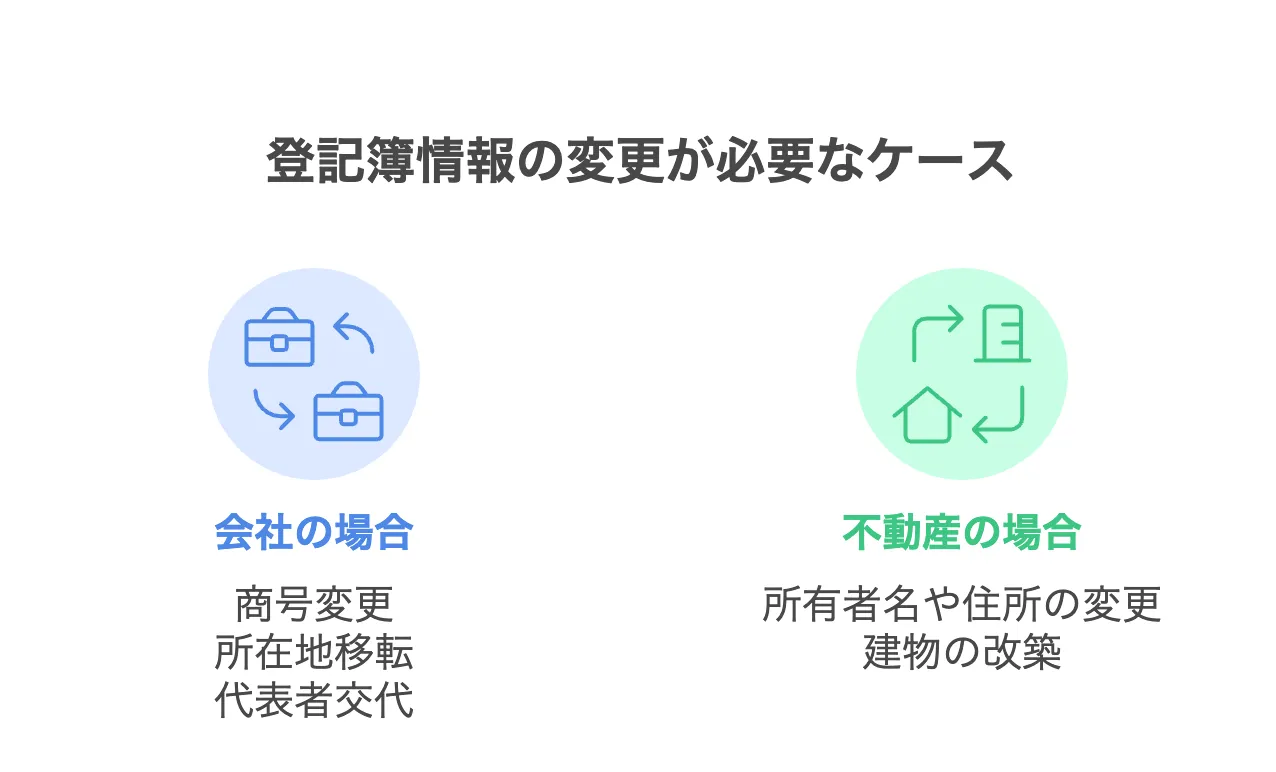
登記簿の情報に変更が生じた場合は、正しい情報を反映させるために登記の変更手続きを行う必要があります。
変更手続きを怠ると、取引や各種手続きの際に不都合が生じる可能性があるため、適切なタイミングで対応することが重要です。
登記簿の変更が必要になるケースとして、会社であれば商号の変更、本店所在地の移転、代表者の交代などがあります。
不動産に関する登記では、所有者の氏名変更や住所変更、建物の増改築などが該当します。
たとえば、法人が本店を移転した場合は、法務局へ「本店移転登記」を申請しなければなりません。
この手続きを怠ると、契約書作成時や行政手続きで登記簿謄本を提出する際に、情報の不一致が発生し、問題となることがあります。
登記の変更手続きは、法務局で申請を行います。手続きに必要な書類は変更内容によって異なるため、事前に確認することが大切です。
たとえば、会社の代表者が変更になる場合は、株主総会議事録や就任承諾書などの書類が求められます。
適切な手続きを行うことで、最新の登記情報が正しく反映され、円滑な取引や手続きを進めることができます。
参考:法務局
登記簿の有効期限に関して相談ができる場所
登記簿の有効期限について不明な点がある場合は、適切な相談先に問い合わせることで、正確な情報を得ることができます。
有効期限の取り扱いは提出先によって異なるため、相談する機関を選ぶ際は、目的に応じた窓口を利用することが大切です。
登記簿の基本的な内容や発行手続きについて知りたい場合は、法務局が最も信頼できる相談先です。
全国の法務局では、不動産登記簿や法人登記簿(履歴事項全部証明書など)の取得方法、記載内容に関する相談を受け付けています。
電話や窓口で問い合わせが可能で、手数料や申請手続きの詳細についても説明を受けることができます。
一方で、登記簿をどの期限まで有効とするかは、提出先が独自に決めるため、提出先の担当部署に直接確認することが重要です。
不動産取引であれば仲介業者や金融機関、法人登記簿の提出であれば契約先の企業や行政機関に問い合わせることで、必要な発行日を把握できます。
また、登記手続きや有効期限についてより詳しく相談したい場合は、司法書士や行政書士に相談するのも有効です。
特に、不動産売買や会社設立などで登記簿の提出が必要な場合は、専門家に相談することで手続きがスムーズに進みます。
登記簿(登記事項証明書)について
登記簿(登記事項証明書)は、不動産や法人の登記情報を記録した公的な書類です。
これにより、不動産の所有者や法人の基本情報を第三者が確認できる仕組みになっています。
登記情報は法務局で管理されており、必要に応じて証明書として取得できます。
不動産登記簿には、土地や建物の所在地、所有者の氏名、権利関係(抵当権の設定など)が記載されています。
不動産取引やローン契約の際には、この登記事項証明書が必要とされることが一般的です。
一方で、法人登記簿には、会社の商号、所在地、代表者、資本金の額などが記載されており、取引先との契約や銀行口座の開設などに提出を求められます。
登記簿の取得は、全国の法務局やオンラインサービス「登記ねっと」を利用することで可能です。
発行には手数料がかかりますが、証明書の用途によっては電子申請を活用することで手続きが簡略化できます。
登記簿の取得方法
登記簿の取得方法についても解説します。
郵送
郵送で登記簿を取得する場合は、申請書を作成し、必要な手数料を納付したうえで法務局へ郵送します。
申請書は法務局のホームページからダウンロードでき、必要事項を記入したうえで、収入印紙を貼付して提出します。
手数料は1通あたり600円ですが、別途返信用封筒を同封する必要があります。
宛名を記入し適切な切手を貼ることで、発行された登記事項証明書が指定した住所に郵送されます。
通常、申請から1週間程度で受け取ることができますが、法務局の繁忙期や郵送の状況によって日数が変動するため、余裕をもって手続きを行うことが望ましいです。
オンライン
オンラインでの取得は、法務局が提供する「登記ねっと」を利用することで可能です。
利用には事前のユーザー登録が必要であり、電子証明書を用いた本人確認が求められる場合もあります。
オンライン申請には2種類の方法があり、1つは申請後に郵送で証明書を受け取る方法、もう1つは最寄りの法務局窓口で交付を受ける方法です。
郵送受け取りの場合、手数料は520円です。また、法務局の窓口で受け取る場合は、490円となります。
手数料を比較的抑えられることが特徴ですが、システムの操作に慣れていない場合は、事前に利用方法を確認しておくとよいでしょう。
法務局の窓口
法務局の窓口では、直接申請を行い、即日で登記簿を取得することができます。
申請には「登記事項証明書交付申請書」の記入が必要であり、申請する登記簿の種類や対象となる不動産・法人の情報を正確に記入することが求められます。
手数料は1通あたり600円で窓口で収入印紙を購入して支払う形式であり、即日発行されるため、急ぎで書類が必要な場合に適しています。
ただし、法務局の開庁時間(9時〜17時)に行く必要があり、待ち時間が発生することもあります。
スムーズに手続きを進めるために、事前に営業時間や混雑状況を確認しておきましょう。
まとめ
今回は登記簿の有効期限について解説しました。
登記簿の有効期限は、法律上の規定はないものの、提出先によって有効期限を定めている場所が多いです。
そのため、登記簿提出時は発行日をよく確認し、できるだけ最新のものを提出するようにしましょう。
今回のコラムを参考に、まずはご自身の登記簿発行日時を確認してみてください。