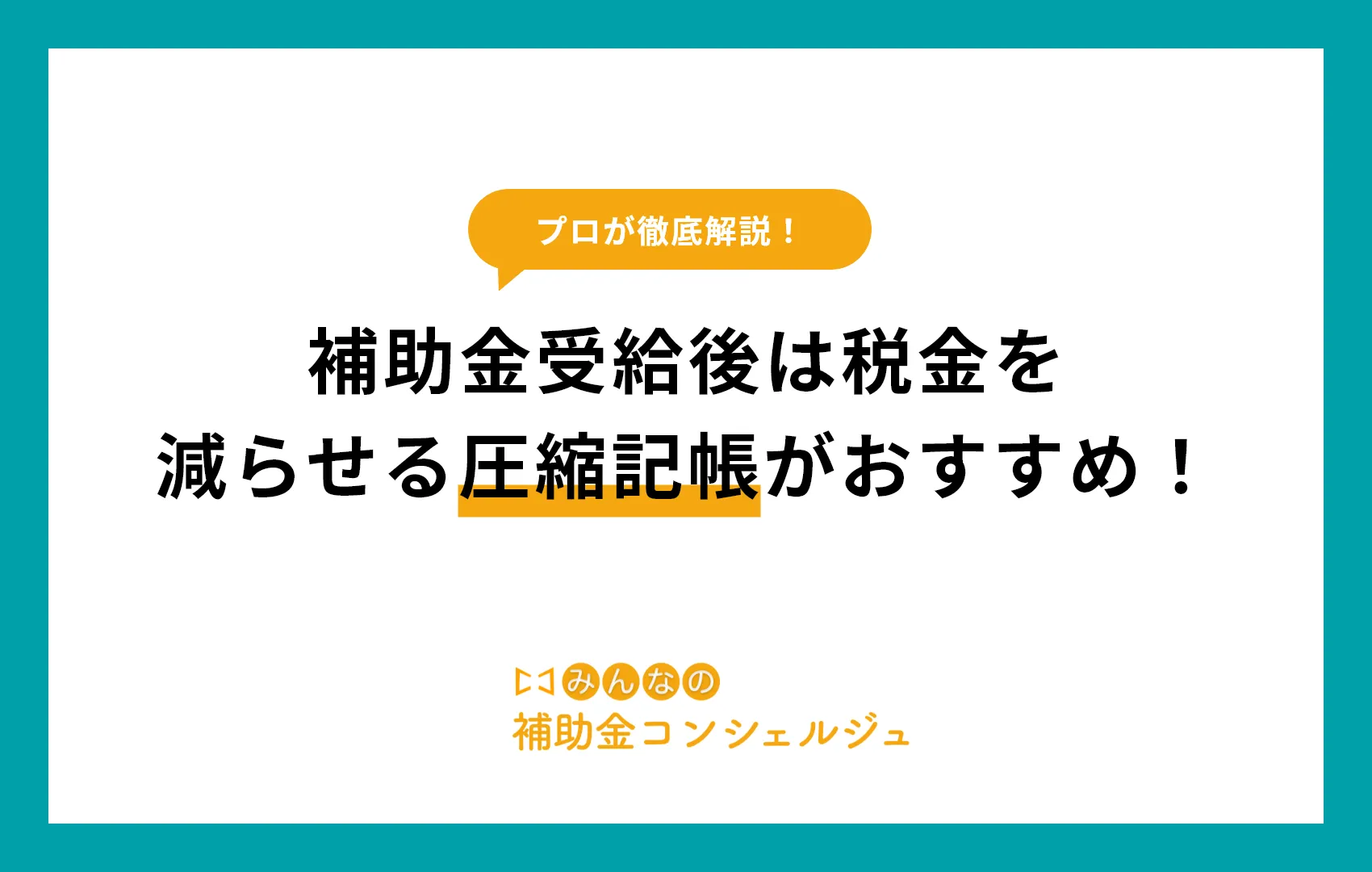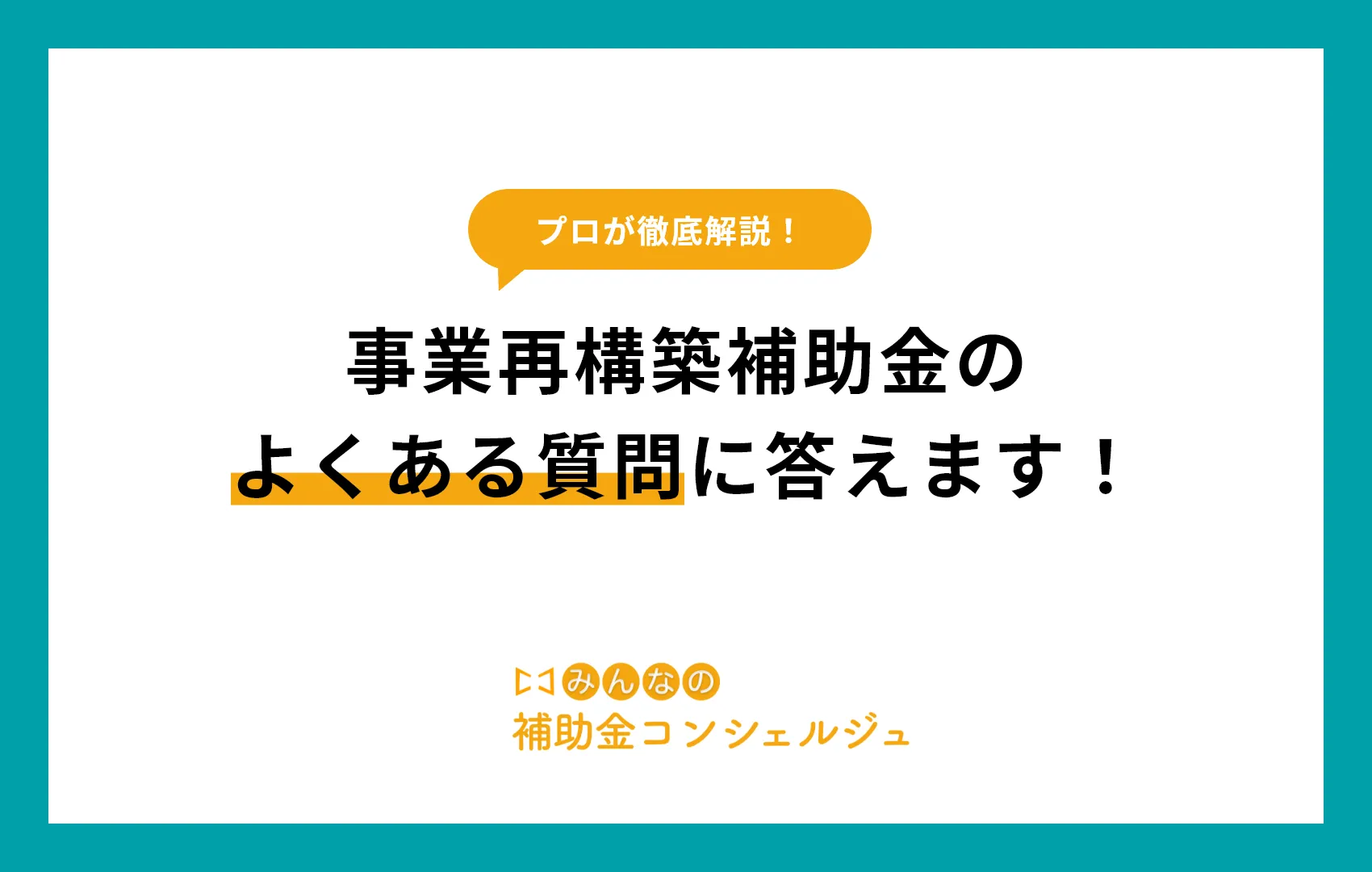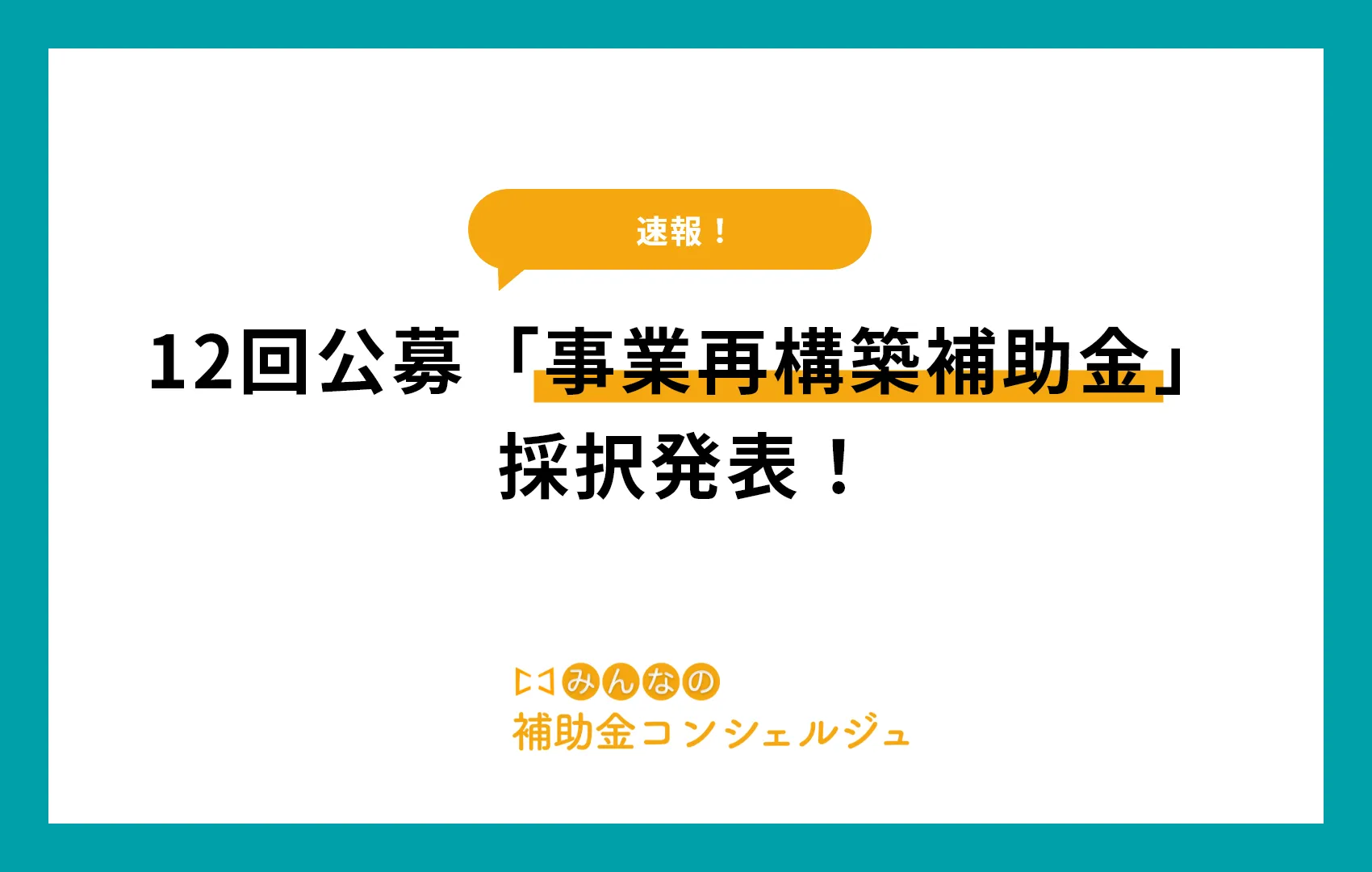補助金を受けたらどうする?圧縮記帳で税金を減らす方法を分かりやすく解説!
補助金を受給したら、税金が減らせる仕組みである圧縮記帳を活用するのがおすすめです。本コラムでは補助金を受給した場合に税金が増える仕組みと、節税ができる圧縮記帳の基本的な仕組みやメリットなどを解説します。
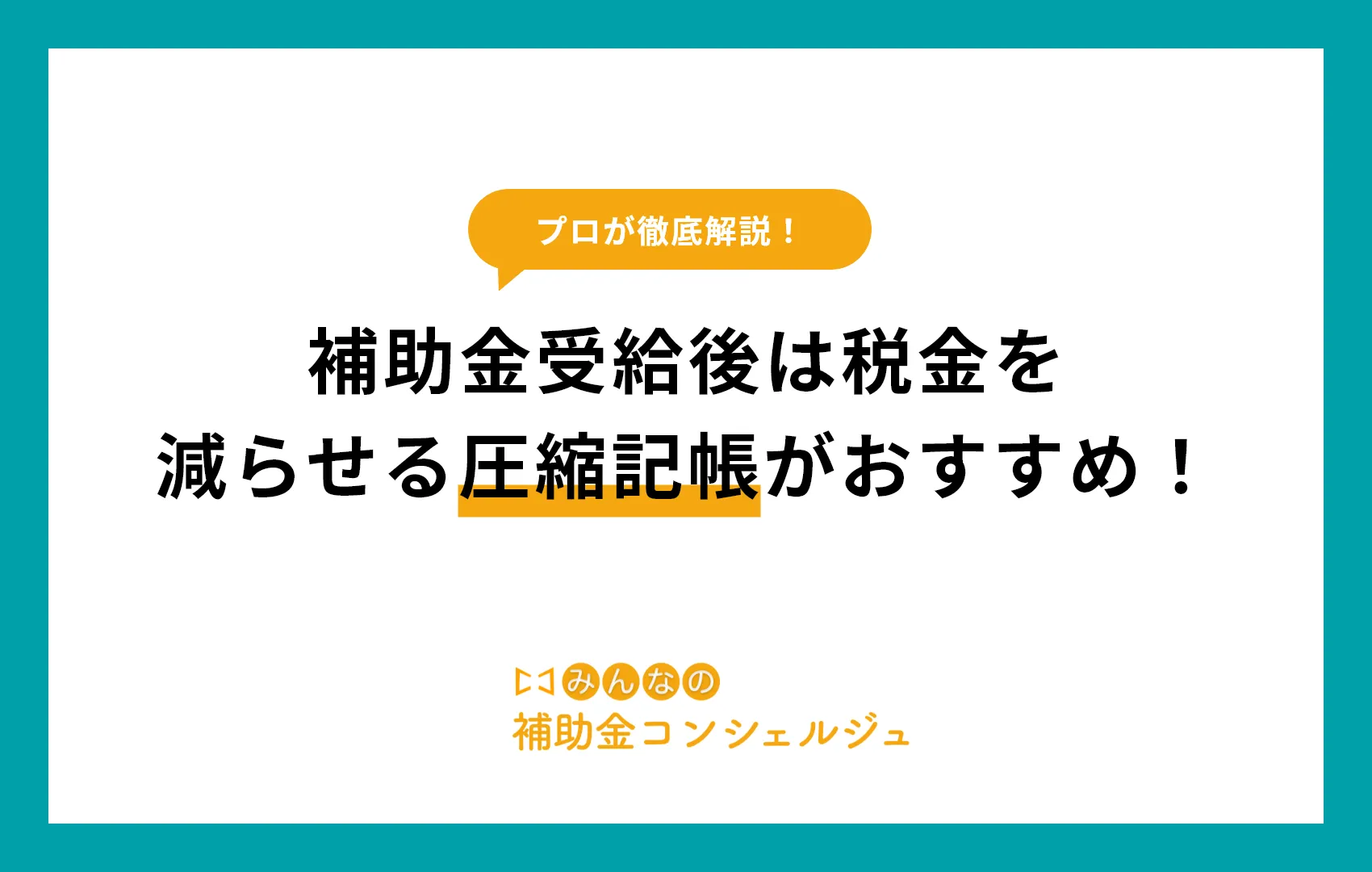
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
補助金をもらったら税金が増えるって本当?
事業に使う設備やシステムを導入する際、国や自治体から補助金を受け取ることがあります。「経費が助かってありがたい」と感じる一方で、補助金を受け取ったことで税金が増えるというケースがあることをご存じでしょうか?
実は、補助金の多くは「収益(雑収入など)」として会計上の利益に加算されるため、最終的に法人税や所得税の課税対象になります。たとえば、500万円の機械を導入するために300万円の補助金を受け取った場合、その300万円は利益とみなされ、利益が増えた分だけ税金が増えることになります。
「採択されたけど実績報告ってどう書けばいいのか分からない!」「他の補助金も活用してみたい!」
など、補助金活用の不安や疑問は、経験豊富なスタッフにご相談ください。
【無料】補助金のご相談はこちら!
補助金のメリットを活かすには「圧縮記帳」の活用を
こうしたケースで有効な手段として、「圧縮記帳(あっしゅくきちょう)」という会計処理方法があります。これは、補助金の金額分だけ、対象となる固定資産の帳簿価額を減らすことで、利益への影響を帳簿上で調整する方法です。圧縮記帳を使うことで、補助金を受け取っても利益を過度に増やさずに済み、税負担を抑えることが可能になります。
圧縮記帳は「税金を減らすための選択肢」
圧縮記帳は義務ではなく任意ですが、税務署でも認められた制度であり、正しく適用すれば合法的な節税につながる重要な手段です。ただし、対象となる補助金の種類や資産の内容、申告の方法など、いくつかの要件があります。次のセクションでは、「圧縮記帳とは具体的にどんな制度なのか?」を初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
圧縮記帳とは?補助金にも使える“税金を減らす会計処理”
「圧縮記帳」という言葉を聞いたことがない方も多いかもしれません。これは、補助金などを受け取ったことで増えた利益に対して、税金が増えすぎないように調整するための会計処理です。
圧縮記帳の基本的な仕組み
圧縮記帳とは、固定資産の取得に使った補助金の金額分を、帳簿上の資産価額から差し引いて記録する方法です。これにより、補助金を受け取っても帳簿上の利益が増えず、税金も抑えることができます。
たとえば、
- 500万円の設備を導入
- 300万円の補助金を受け取った場合
通常であれば、補助金300万円は「収益」として利益に加算され、税金が増えます。しかし、圧縮記帳を使うと、設備の帳簿価格を500万円 → 200万円に圧縮できるため、補助金分の利益を相殺する形になります。
補助金にも圧縮記帳が使える!
はい。国や地方自治体から支給される補助金のうち、「資産の取得に充てることが明確なもの」であれば、原則として圧縮記帳の対象になります。たとえば、以下のような補助金が対象になる可能性があります。
| 補助金名 | 圧縮記帳の適用可能性 |
| ものづくり補助金 | 〇(設備取得に使う場合) |
| IT導入補助金 | △(ソフトウェア等の扱いに注意) |
| 小規模事業者持続化補助金 | △(広告費などは対象外) |
詳しくは税務署または税理士に確認するのが安心です。
圧縮記帳は、特別な節税スキームではなく、国税庁が正式に認めている合法的な制度です。法人税法第42条においても「国庫補助金等によって取得した資産については、その金額に応じた圧縮記帳が認められる」と明記されています。
補助金を受給するとどうして税金が増えるの?
補助金は「返さなくていいお金」だから、税金の計算とは無関係だと思っていませんか?実は、補助金の多くは「収益」として扱われるため、税金の計算に影響します。この仕組みを理解しておくことで、思わぬ納税トラブルを避けることができます。
補助金=利益になる?その仕組みとは
法人や個人事業主が受け取った補助金のうち、設備投資や事業活動に使うことが明確なものは、原則として「益金(=利益)」に含める必要があります。つまり、補助金は「雑収入」や「受贈益」などの名目で収益として計上され、会計上の利益が増える=課税対象が増えるという流れになります。
補助金で設備を買った場合も利益が増える?
たとえば、500万円の機械を購入し、そのうち300万円を補助金でまかなったとします。
- 補助金300万円 → 雑収入として益金に計上
- 資産(機械)500万円 → 減価償却で数年に分けて経費化
この場合、補助金は受け取った年に全額益金となる一方、資産の取得費用は減価償却によって毎年少しずつ経費計上されるため、初年度の利益が実態よりも大きく見えることになります。その結果、税金が増えてしまうというわけです。
補助金はすべて課税対象?
原則として、補助金は課税対象になりますが、以下のような例外もあります。
| 補助金の使い道 | 課税対象? | 説明 |
| 設備の購入資金 | 課税対象 | 圧縮記帳で調整可能 |
| 広告宣伝費などの経費 | 課税対象 | 他の経費と同様に処理 |
| 災害見舞金など | 非課税 | 非課税所得に該当するケースあり |
※非課税かどうかは補助金の性質や目的により異なります。詳細は補助金の交付要綱や税務署への確認が必要です。
圧縮記帳を使えば利益の増加を抑えられる
こうした補助金による利益増を調整できるのが、圧縮記帳という会計処理です。補助金分だけ資産の帳簿価額を減らすことで、結果として利益と税金の増加を抑えることができます。
補助金に圧縮記帳を使う場合のメリットと注意点
補助金を受け取ると利益が増え、その分税金も増える可能性があります。その対策として使えるのが「圧縮記帳」です。では、圧縮記帳を行うと、実際にどのような効果があるのでしょうか?ここではメリットと注意点を初心者の方向けにわかりやすく整理します。
圧縮記帳を行うメリットとは?
最大のメリットは、税金の負担を抑えられることです。補助金の金額分を資産の取得価額から差し引いて記帳することで、利益を圧縮=税金の対象となる金額を減らせるのが圧縮記帳の特徴です。たとえば、以下のような違いがあります。
| 圧縮記帳の有無 | 補助金の課税影響 | 記帳処理の複雑さ |
| する | 補助金分の利益を圧縮 → 税負担軽減 | 別表の作成など申告がやや複雑 |
| しない | 補助金が全額利益 → 税額が増える | 一般的な記帳で済むため簡単 |
このように、圧縮記帳を行うことで、補助金を受け取ったことによる税負担の増加を防ぐことができます。
圧縮記帳は義務ではない
圧縮記帳はあくまで任意の制度です。行わなくても違法ではありませんし、会計処理が簡単になるという理由で「あえてしない」選択をする事業者もいます。ただし、圧縮記帳を行わない場合は、補助金がそのまま益金になり、税金が増えるため、経営上の資金繰りに影響が出ることもあります。
圧縮記帳には要件や手続きがある
圧縮記帳を適用するには、次のような条件を満たす必要があります。
- 対象となる補助金であること(資産の取得が目的であることが明確)
- 補助金で取得した資産が明らかであること
- 取得した資産を固定資産として計上していること
- 確定申告の際に適切な処理・書類の提出を行うこと(法人税申告書の別表など)
これらの要件を満たし、正しく処理を行う必要があるため、税理士などの専門家への相談が推奨されます。
圧縮記帳は「節税」と「リスク管理」の両面で重要
圧縮記帳は単なる節税策ではなく、会計上の利益を適切に調整し、事業実態に即した税負担とするための制度です。補助金を活用する事業者にとっては、事後処理まで含めた計画が重要です。
圧縮記帳など会計に関すること以外にもお悩みはありませんか?
「採択されたけど実績報告ってどう書けばいいのか分からない!」「他の補助金も活用してみたい!」
など、補助金活用の不安や疑問は、経験豊富なスタッフにご相談ください。
【無料】補助金のご相談はこちら!
補助金受給後、圧縮記帳しないとどうなる?
ここまでで、圧縮記帳は補助金による税負担を軽減するための制度であることをご紹介しました。では、圧縮記帳は必ずしなければならないのでしょうか?また、行わなかった場合にはどのような影響があるのでしょうか。
まず大前提として、圧縮記帳は義務ではなく、任意で選択できる制度です。法人税法第42条では、補助金等により資産を取得した場合において、所定の方法で圧縮記帳を行うことが“できる”とされています。つまり、事業者自身が「圧縮記帳を行うかどうか」を判断してよく、しないからといって法律違反になるわけではありません。
圧縮記帳をしないとどうなる?
圧縮記帳を行わず、補助金を受け取ったまま申告した場合、補助金はそのまま「収益」として課税対象になります。たとえば、以下のような影響があります。
| 圧縮記帳の有無 | 補助金の課税影響 | 記帳処理の複雑さ |
| する | 補助金分の利益を圧縮 → 税負担軽減 | 別表の作成など申告がやや複雑 |
| しない | 補助金が全額利益 → 税額が増える | 一般的な記帳で済むため簡単 |
したがって、圧縮記帳をしない場合でも会計処理は完了しますが、税金が増える可能性があることを理解しておく必要があります。
圧縮記帳をするかどうかの判断基準
圧縮記帳を行うべきかどうかは、以下のような観点から判断するのが一般的です。
- 法人税・所得税の節税を重視するか
- 補助金の金額が大きく、税負担が増えそうか
- 申告手続きにかかる手間をどう評価するか
- 圧縮記帳に対応できる税理士・専門家がいるか
とくに補助金の規模が大きい場合、圧縮記帳を行うことで税額が数十万円単位で変わるケースもあります。一方で、補助金額が少額であれば、あえて圧縮記帳を行わず、手続きの簡易さを優先する選択も考えられます。
税理士と相談しながら判断するのがおすすめ
圧縮記帳には要件や申告上の手続きが伴うため、事業者単独で判断・処理するのは難しいのが実情です。制度の適用可否や効果を正しく見極めるためにも、補助金を活用した際は、必ず税理士や会計の専門家に相談することをおすすめします。
補助金の圧縮記帳ってどうやるの?
圧縮記帳は税金を抑える上で有効な手段ですが、適用には一定の条件や正しい会計・税務処理が求められます。ここでは、実際に圧縮記帳を行う際の流れと、対応方法についてわかりやすく解説します。
圧縮記帳には2つの方法がある
法人税法では、補助金等で取得した固定資産に対する圧縮記帳の方法として、以下の2つが認められています。
| 方法 | 概要 | 特徴 |
| ① 直接減額方式 | 固定資産の帳簿価額を補助金分だけ直接減額する | シンプルな処理だが、帳簿上の資産額が変わる |
| ② 圧縮積立金方式 | 補助金分を「圧縮積立金」として特別勘定に計上 | 後年度の取崩し処理が必要で複雑になりやすい |
圧縮記帳を適用する場合は、法人税の確定申告書において、次のような書類の提出が必要になります。
- 別表十(一) 圧縮記帳に関する明細書
- 別表十(二) 積立金方式を選択した場合の明細書(必要に応じて)
- 圧縮の根拠となる補助金の交付決定通知書や契約書の写し
これらを適切に作成し、税務署に提出することで、圧縮記帳の適用が正式に認められます。
会計ソフトだけでは対応しきれないケースも
クラウド会計ソフトや会計アプリを使っていても、圧縮記帳の処理は自動化されていない場合が多く、経理の知識がないと誤処理のリスクがあります。また、補助金の内容や資産の種類によって、適用可否が分かれるケースもあるため注意が必要です。
税理士に相談するのが安心
補助金を受け取った際に圧縮記帳を適用すべきかどうかは、税務・財務の状況を踏まえた判断が必要です。間違った処理を防ぐためにも、補助金の交付が決定した段階で、税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。専門家に相談すれば、以下のようなサポートが受けられます。
- 適用可否の判断
- 仕訳や記帳の実務サポート
- 申告書・別表の作成
- 税務調査への対応リスク軽減
補助金を活用している事業者にとって、圧縮記帳は税金面の大きな助けになります。ただし、正しい処理が前提となるため、制度を理解し、適切に対応できる体制を整えることが重要です。
圧縮記帳など会計に関すること以外にもお悩みはありませんか?
「採択されたけど実績報告ってどう書けばいいのか分からない!」「他の補助金も活用してみたい!」
など、補助金活用の不安や疑問は、経験豊富なスタッフにご相談ください。
【無料】補助金のご相談はこちら!
まとめ
補助金は税金の対象となる場合があり、受け取った後の会計処理が重要です。圧縮記帳を活用すれば、税負担を抑えることができます。制度は任意ですが、金額が大きい場合などは検討の価値があります。迷ったら専門家に相談するのが安心です。
2025年度、補助金を活用したい方はこちら!
実は、「補助金は申請すれば受給できる」わけではありません。
厳しい審査をクリアする必要があり、4社に1社しか通過できない難関補助金も多いのです。
審査通過率を飛躍的に上げるには、申請サポート会社の力を借りるのが鉄則!
提出書類の抜け・漏れがないように、弊社が万全のサポートで審査通過を目指します。
弊社がサポートさせていただいた方のお喜びの声
弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります。
専門家による的確なアドバイスとサポートで、御社を採択へ導きます!
サポートさせていただき見事採択された方々のお喜びの声をご紹介します。
「簡単な内容を伝えただけで、立派な書類に仕上げていただきました。急な変更にもすぐ対応してくれて、とても満足です!」
「電話やメールで手続きが完了するので非常に楽でした!LINEでも相談できる気軽さもよかったです。」
「必要な情報を渡すだけで専門家がすべて対応してくれます!リアリゼイションのマニュアルを活用すれば、必要なところを穴埋めするだけで書類ができますし、とにかく時間が浮いて、本業に集中することができました!」
補助金に関するお悩みやご相談がある方は、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。担当者があなたのお悩みに丁寧に回答いたします!
監修者からのワンポイントアドバイス
圧縮記帳は補助金を獲得した際に任意で行うことが前提です。要件や申告上の手続きが伴うため、事業者の方が判断したり、処理したりすることは難しいです。制度の適用可否や効果を正しく見極めるためにも、補助金を活用した際は、必ず顧問税理士に相談するようにしましょう。