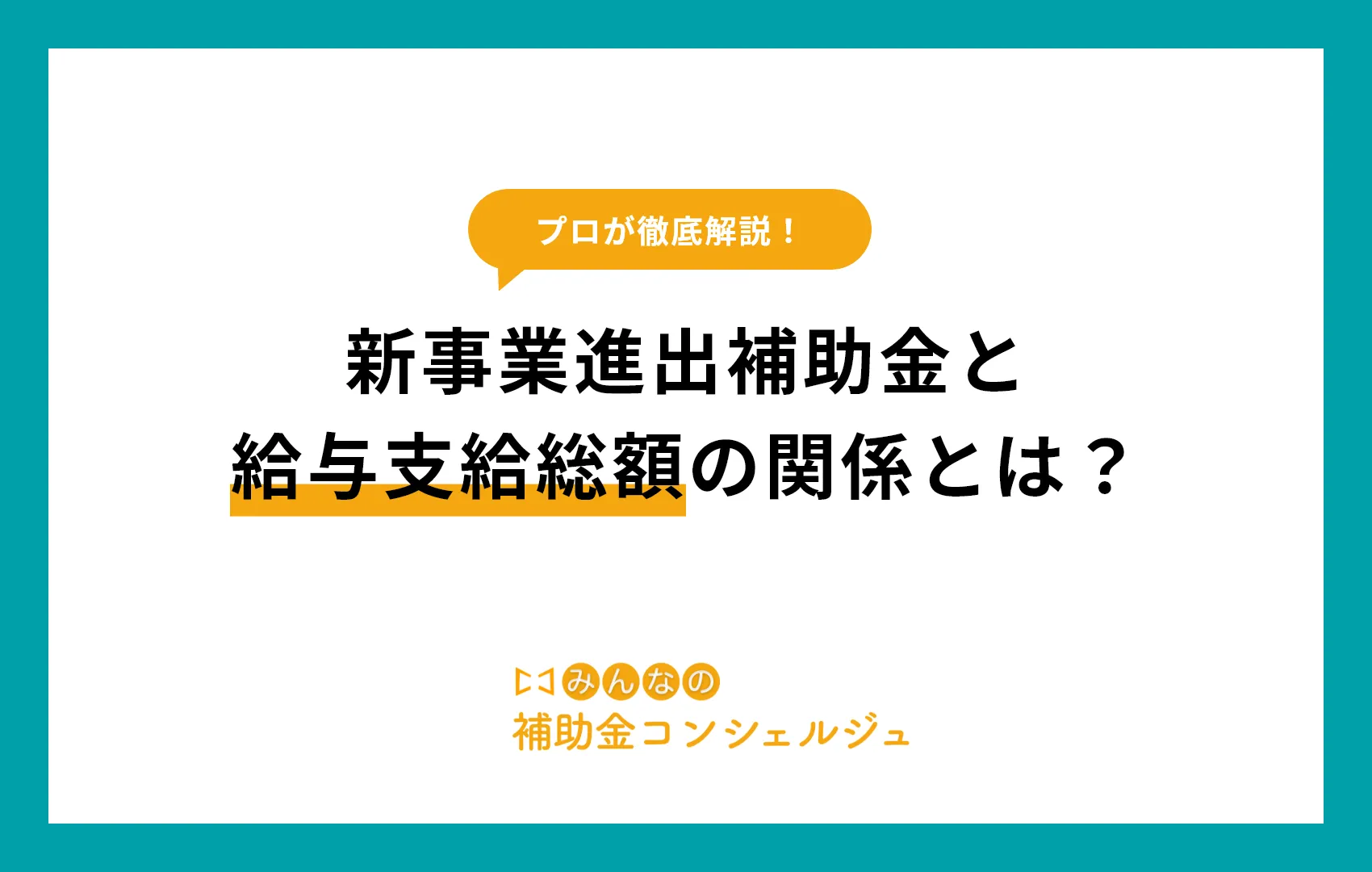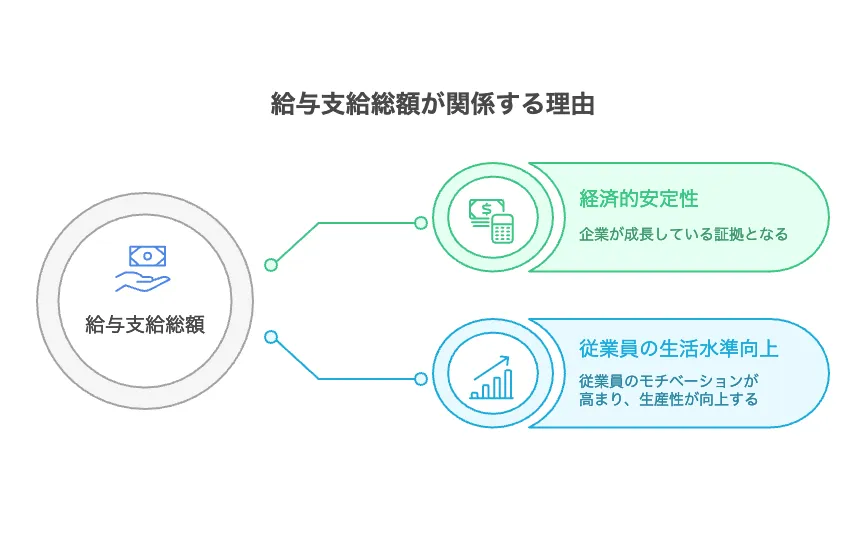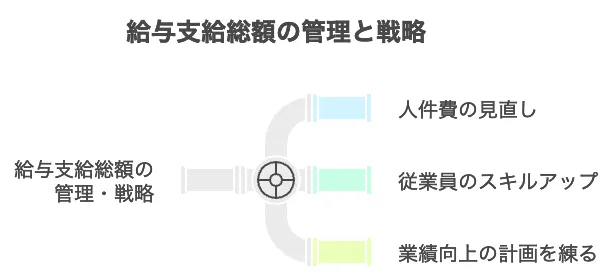新事業進出補助金と給与支給総額の関係とは?
本記事では、新事業進出補助金の申請要件に含まれる「給与支給総額」の意味や注意点を、わかりやすく解説します。
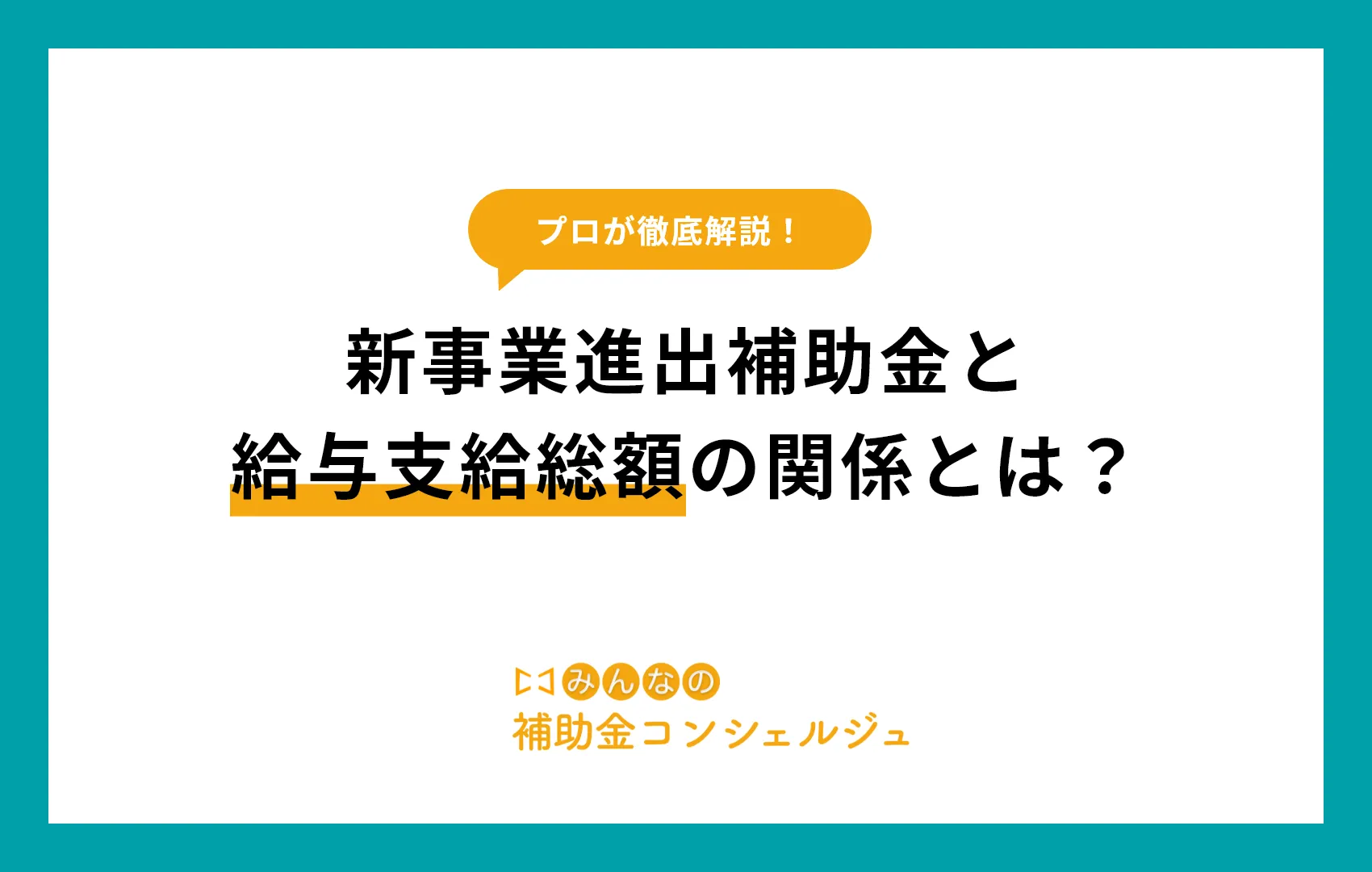
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
新事業進出補助金とは?
新事業進出補助金は、中小企業が新たな市場や高付加価値事業に進出する際の設備投資を支援するための制度です。
この補助金は、企業の成長を促進し、持続的な賃上げを実現することを目的としています。
新事業進出補助金の目的は?
新事業進出補助金は、中小企業が既存事業とは異なる新市場や高付加価値事業に進出するための支援を行う制度です。
これにより、企業の規模拡大や生産性アップを図り、賃上げにつなげることを目指しています。
特に、物価高や人手不足といった厳しい経営環境に直面している中小企業にとって、大切な支援策といえます。
補助金額と補助率
- 最大補助金額:9,000万円
- 補助下限額:750万円(最低でも1,500万円の投資が必要)
- 補助率:通常は1/2(50%)、小規模事業者や賃上げ要件を満たす場合は2/3(66.67%)となります。
対象者
新事業進出補助金の対象となるのは、以下のような中小企業や小規模事業者です。
- 新たな顧客層にアプローチしたい経営者
- 地域のニーズを捉えた新ビジネスモデルを検討している方
- 既存の技術を応用して新製品や新サービスを展開したい事業者
申請要件
申請にはいくつかの要件があります。主な要件は以下の通りです。
- 付加価値額要件:年平均成長率が4.0%以上
- 新事業進出要件:既存事業とは異なる新たな事業に挑戦するつもり
- 賃上げ要件:事業終了時点で、事業場内最低賃金を50円以上引き上げること、または給与支給総額を6%以上増加させる
補助対象経費
補助対象となる経費は幅広く、以下のような項目が含まれます。
- 建物費→新たな事業活動の拠点となる建物や施設の建設・改修費用
- 設備投資→ 機械装置、システム構築費、測定・検査器具、専用ソフトウェアなど
- 広告宣伝費→パンフレットやチラシ、ウェブサイトの構築費、展示会出展費用など
ただし、補助対象外となる経費もありますので、注意が必要です。
たとえば、フランチャイズ加盟料や一般管理費、通信費などは対象外です。
申請方法は?
申請は、所定の申請書類を準備し、指定された期間内に提出する必要があります。具体的な手続きは以下の通りです。
- 事業計画書の作成:事業の目的、内容、経費の詳細などを記載した事業計画書を作成
- 必要書類の準備:申請に必要な書類を揃える(財務諸表や税務申告書、賃金台帳などが含まれる)
- 申請の提出:指定された期間内に、オンラインで申請書類を提出してください。
参考:新事業進出補助金
給与支給総額が関係する理由って何?
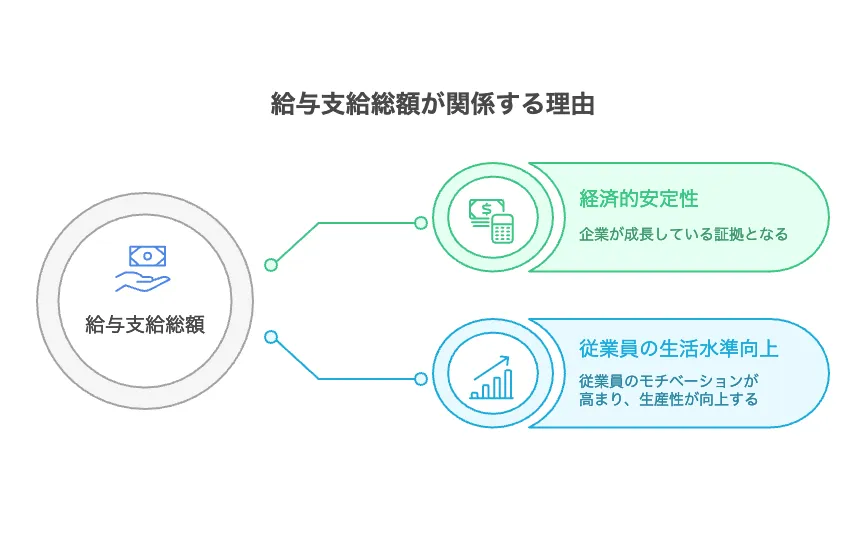
新事業進出補助金において、給与支給総額が関係する理由は多岐にわたります。
以下に、給与支給総額が関係する理由を詳しく解説します。
給与支給総額の定義
給与支給総額とは、企業が従業員に支払った給与、賃金、賞与などの総額を指します。
この総額は、企業の人件費の指標であり、企業の経済的健康状態や従業員の生活水準が反映します。
新事業進出補助金では、給与支給総額の増加が求められる理由は、以下の通りです。
経済的安定性の指標
給与支給総額が増加することは、企業が成長している証拠であり、経済的な安定性を示します。
これにより、企業が新たな事業に進出するための基盤が整っていることが確認されます。
従業員の生活水準が上がる
給与が増加することで、従業員の生活水準が向上し、企業への忠誠心やモチベーションが高まると考えられます。
これにより、企業の生産性が向上し、結果的に新事業の成功が期待できるのです。
賃上げ要件と補助金の関係とは?
新事業進出補助金には、賃上げに関する特定の要件があります。
年平均成長率
補助事業実施期間中に、給与支給総額を年平均で6%以上増加させることが求められます。
この要件を満たすことで、企業は補助金の上限額を引き上げる特例を受けることができます。
最低賃金アップ
事業場内の最低賃金を年額50円以上引き上げることも求められます。
これにより、企業は地域の最低賃金を上回る水準で従業員を雇用することが求められ、労働環境の改善が促進されるでしょう。
給与支給総額の増加がもたらす効果
給与支給総額の増加は、企業にとってさまざまな効果をもたらします。
人材確保が定着する
給与が高い企業は、優秀な人材を確保しやすくなります。
また、従業員が長く働くことで、企業のノウハウが蓄積され、競争力が向上します。
企業のイメージアップ
高い給与水準は、企業の社会的責任を果たす一環として評価され、企業イメージアップにつながります。
これにより、顧客や取引先からの信頼も得やすくなるでしょう。
地域経済に貢献できる
社員の給与が増えれば、地域経済にも好影響を与えます。
従業員が得た給与を地域で消費することで、地域の経済活動が活性化します。
給与支給総額って何?(賃金台帳ベースか?賞与含むか?)
給与支給総額は、企業が従業員に支払う給与や賃金の合計額を指し、賃金台帳や給与明細に基づいて計算されます。
給与支給総額の定義とは
給与支給総額は、企業が従業員に支払ったすべての給与、賃金、賞与などの合計を指します。
具体的には以下のような要素が含まれます。
- 基本給→ 従業員に支払われる基本的な賃金
- 賞与→ 年2回支給されることが一般的なボーナス
- 手当→ 通勤手当、家族手当、住宅手当などの各種手当
ただし、役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金などは給与支給総額には含まれません。
これらの要素は、企業の人件費として別途管理されます。
賃金台帳ベースか?賞与を含むか?
給与支給総額は、賃金台帳に基づいて計算されます。
賃金台帳には、各従業員の勤務時間、支給された賃金の詳細が記載されており、これをもとに給与支給総額が算出されるのです。
ボーナスも給与支給総額に含まれるため、年末や夏季に支給される賞与も考慮に入れましょう。
雇用保険や社会保険との関係は?
給与支給総額は、雇用保険や社会保険の計算においても重要な役割を果たします。
雇用保険
雇用保険は、従業員が失業した際の生活を支援するための保険です。
給与支給総額に基づいて保険料が計算され、企業は従業員の給与に応じた保険料を負担します。
社会保険
健康保険や厚生年金保険などの社会保険も、給与支給総額に基づいて保険料が決定されます。
これにより、従業員は医療や年金の保障を受けることができます。
よくある誤認・ミス例
給与支給総額に関する誤認やミスは、特に補助金申請や人事管理においてよく見られます。以下にいくつかの例を挙げます。
役員報酬についての誤認
新事業進出補助金などの申請において、役員報酬を給与支給総額に含めてしまうケースがあります。
新事業進出補助金では、役員報酬は含まれないため、誤って計上すると不採択の原因となるのです。
賞与の計上ミス
賞与を給与支給総額に含めるべきかどうかの誤解もあります。
賞与は通常、給与支給総額に含まれるため、これを除外して計算すると、実際の支給額よりも少なく見積もられることがあります。
福利厚生費を誤認
福利厚生費や法定福利費を給与支給総額に含めてしまうこともあります。
これらは別途管理されるべき項目であり、給与支給総額には含まれません。
従業員数の間違い
給与支給総額を計算する際に、常時使用する従業員の定義を誤解し、役員やアルバイトを含めてしまうことがあります。
これにより、補助金の申請要件を満たさない場合があります。
【無料】御社に合った補助金・助成金を診断! 新事業進出補助金における賃上げ要件とは?
中小企業新事業進出補助金における賃上げに関する3つの要件と、未達成の場合の影響について詳しく解説します。
目標を達成できない場合、交付された補助金の返還が求められる可能性があるため、慎重に計画しましょう。
新事業進出補助金の賃上げに関する3つの要件
賃上げ要件
補助事業終了後の3~5年の事業計画期間中に、以下のいずれかの水準以上の賃上げを実施する必要があります。
- 給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上に増加させる
- ひとり当たりの給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上に増加させる
事業場内最賃水準要件
補助事業終了後の3~5年の事業計画期間中、毎年事業所内の最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準であることが求められます。
賃上げ特例要件
補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させ、かつ事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げることが必要です。
この特例を適用することで、補助金の上限額を引き上げることが可能です。
要件未達の場合の補助金返還義務
賃上げに関する要件を達成できなかった場合、交付された補助金の返還義務が生じます。
賃上げ要件
従業員に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、補助金全額の返還が求められます。
また、目標値を達成できなかった場合は、補助金交付額に達成度合いの高い方の目標値の未達成率を乗じた額を返還しなければなりません。
事業場内最賃水準要件
地域別最低賃金より30円以上高い水準になっていなかった場合、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額を返還しなければなりません。
賃上げ特例要件
いずれか一方でも要件を達成できなかった場合、賃上げ特例の適用による補助上限額引上げ分の額を返還しなければなりません。
このように、賃上げに関する要件も把握しておくべきです。
達成できなかった場合の影響も大きいため、事前にしっかりとした計画を立てることが求められます。
補助金申請での注意点とは?
中小企業新事業進出補助金の申請において、給与支給総額の増加要件は大事なポイントです。
以下に、注意点や条件例、計画段階での設定のポイントについて詳しく説明します。
リスク管理
計画段階で予測されるリスクを洗い出し、その影響を最小限に抑えるための対策を講じてください。
これにより、計画の途中での予期せぬトラブルを未然に防ぐことが可能です。
リソースの評価
計画を実行するために必要なリソース(人員、予算、設備など)を事前に評価し、確保しましょう。
リソースが不足していると、計画の実行が阻害される可能性があります。
事前着手はしない
補助金の交付決定前に契約や発注を行うことはできません。
これを「事前着手の禁止」と呼びます。
実績報告義務を果たす
補助事業が完了した後、実績報告を提出する必要があります。
これには、成果物の写真や広告掲載の記録資料が必須です。
コミュニケーションの確保
計画の内容や進捗状況を関係者全員と共有し、フィードバックを得ることで、計画の精度を高めることができます。
これにより、計画に対する全員の理解と協力を得ることが可能です。
給与支給総額の増加要件について
給与支給総額の増加要件は、補助金を受けるために企業が達成しなければならない条件のひとつです。
具体的な条件は下記の通りです。
前年比〇%以上増加
たとえば、給与支給総額を年平均で2.5%以上増加させることが求められることがあります。
こうした具体的な数値目標を設定することで、企業は明確な達成基準を持てるでしょう。
SMART原則に基づいて目標を設定する
計画段階での設定は、補助金申請の成功に直結します。以下のポイントを考慮してください。
Specific(具体的)
目標は明確で具体的であるべきです。
「給与支給総額を増加させる」という漠然とした目標ではなく、「給与支給総額を前年比3%増加させる」といった具体的な数値を設定すると良いです。
Measurable(測定可能)
目標達成度を測定できるように、具体的な数値を設定します。
これにより、進捗を確認しやすくなります。
Achievable(達成可能)
現実的に達成可能な目標を設定しましょう。無理な目標設定は、計画の実行を困難にします。
Relevant(関連性)
設定した目標が、企業の全体戦略やビジョンに関連していることを確認してください。
Time-bound(期限付き)
目標には明確な期限を設け、いつまでに達成するかを明示します。
悪質なコンサルタントに引っかからない
高額な報酬を請求する無資格のコンサルタントには注意が必要です。
行政書士法に基づき、書類の有償作成は行政書士に限られています。
給与支給総額の管理と戦略
企業は、給与支給総額を適切に管理し、戦略的に増加させる必要があります。
人件費を見直す
給与支給総額を増加させるためには、まず人件費の見直しが必要です。
無駄なコストを削減し、効率的な人材配置を行うことで、給与を増やします。
従業員のスキルアップ
従業員のスキルを向上させることで、生産性を高め、給与の増加を実現します。
研修や教育プログラムを導入し、従業員の成長を促進します。
業績向上に向けて計画を練る
売上や利益を上げるための施策を講じましょう。
新規事業の展開やマーケティング戦略の強化など、業績向上に向けた取り組みが求められます。
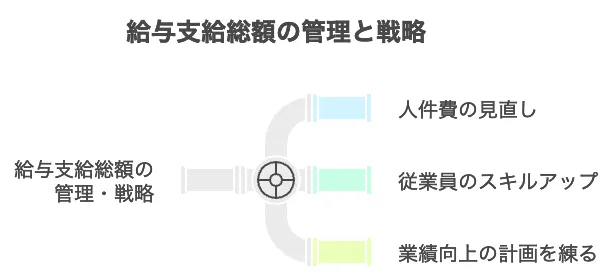
実務で気をつけたいことは?
実際の作業の中で気を付けたいことがあります。
雇用人数とのつり合いを取る
給与総額はひとりあたりではなく全体の合計です。
そのため、たとえ一部の社員に賃上げをしても、他の社員が退職して全体の給与総額が下がってしまえば、要件未達となることもあるでしょう。
新規採用と賃上げのバランスを取り、給与支給総額全体を確実に押し上げてください。
賃上げのタイミングや記録を残す
中小企業新事業進出補助金では給与支給総額の増加が要件となっているため、賃上げのタイミングが大切です。
たとえば、賃上げが期末ギリギリになると、給与支給総額が要件を満たさない可能性があるのです。
また、支給した給与については、賃金台帳・給与明細・振込記録・就業規則や給与改定通知などの証拠書類を残しておきましょう。
補助金の事後確認で証明できない場合、補助金の返還を求められる可能性があります。
期中の途中退職などで起こる落とし穴に注意
社員が退職すると、その月以降の給与が支払われなくなるため、給与支給総額が大きく減ってしまうリスクがあります。
対策としては、複数名の給与を底上げする・計画的に採用活動を行う・賞与の支給月を調整するなどのリスク分散です。
他の補助金制度との違いは?
新事業進出補助金では「給与支給総額の増加」が直接的な要件であり、実際の支給実績をもとに審査されます。
それに対してほかの補助金制度では、事業年度ベースでの賃上げ計画が求められ、やや長期的な視点になる場合があります。
制度によっては「平均給与の引き上げ」や「地域別最低賃金との比較」など、別の指標が要件になることもあります。
「給与支給総額」とは、あくまで全社員への給与の合計額であるため、他の制度と混同すると誤解・要件未達の原因となります。
新事業進出補助金の最新スケジュール
新事業進出補助金の第1回公募は、2025年7月15日で募集が終了しています。
しかし、第2回公募が9月12日に開始され、申請受付は11月10日に始まりました。
また、応募締め切りは12月19日の18時までとなっているため、締め切りまでに十分時間があります。
申請する方は、しっかりと書類等の準備をして、申請に臨みましょう。
おわりに
新事業進出補助金における給与支給総額の増加要件は、中小企業が新たな市場や事業に挑戦する際に求められる要件です。
企業の成長と従業員への還元を促す目的があり、申請時に明確な理解が必要です。
給与支給総額とは、従業員に支払った給与・賃金・賞与の合計を指し、役員報酬や福利厚生費は含まれません。
要件を満たすためには、たとえば年平均で6%以上の増加が求められることがあります。
この目標を達成するには、昇給のタイミングや雇用人数とのバランスが大切。
途中退職があると総額が下がるため、人員計画も必要です。また、証拠として賃金台帳や給与明細の保存も不可欠でしょう。
制度の活用にあたっては、事前に計画を立て、補助金の目的や要件を正しく把握しましょう。
要件未達成の場合は、補助金の返還が求められるリスクがあるため注意しましょう。
新事業進出補助金は、従業員の生活向上や企業の競争力強化を支える制度でもあります。
正確な理解と準備が、効果的な活用に直結するでしょう。
監修者からのワンポイントアドバイス
給与支給総額と似た言葉に人件費があります。それぞれ含まれる項目が異なっていますので注意しましょう。
給与支給総額をしっかりと上げていくことが補助金の要件となっています。
専門家に伴走頂き、自社で実現可能な計画を策定していくことが重要です。
賃上げ特例に関しては自社の負担が大きくなる場合もありますので慎重な判断が求められます。