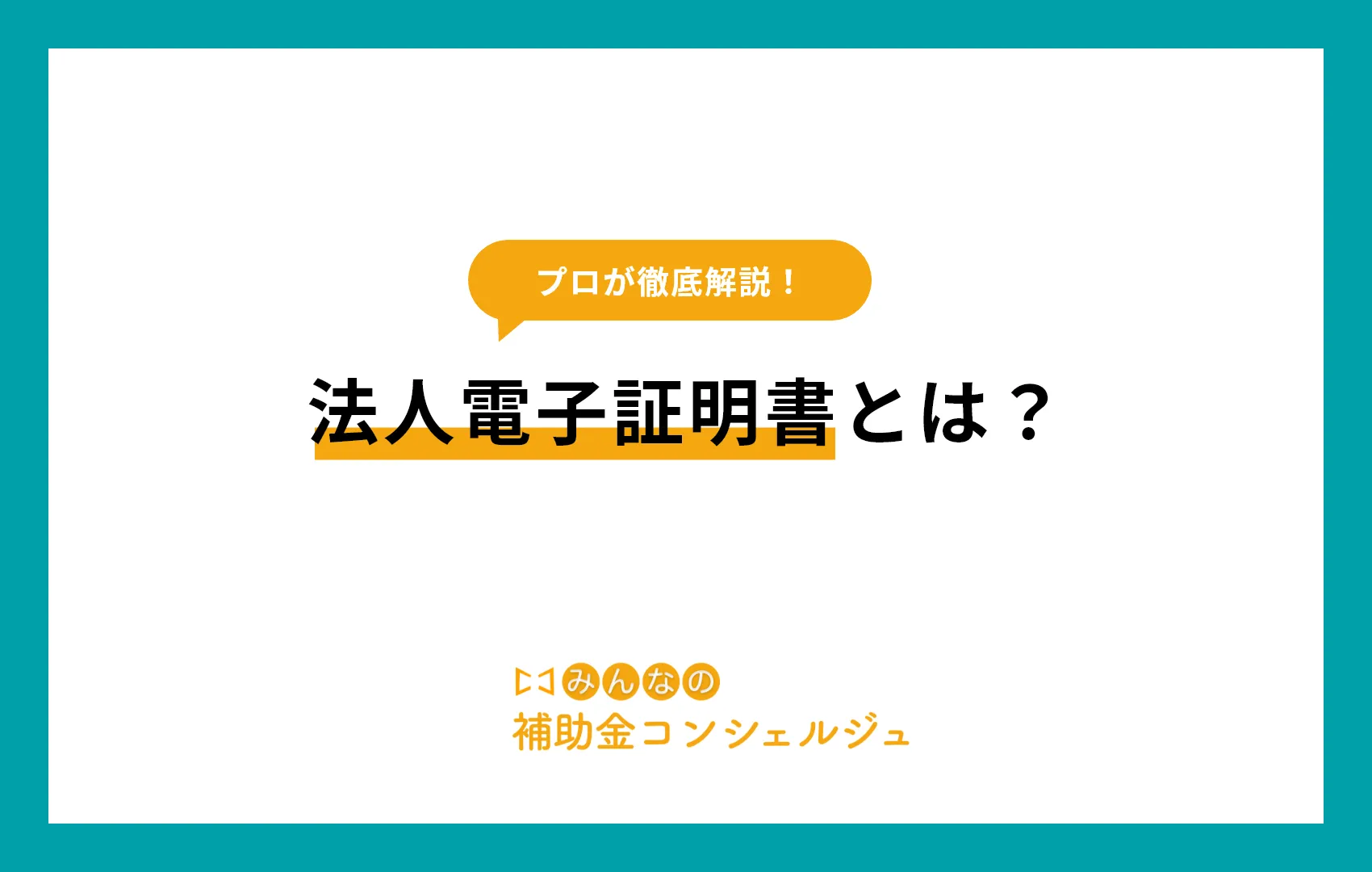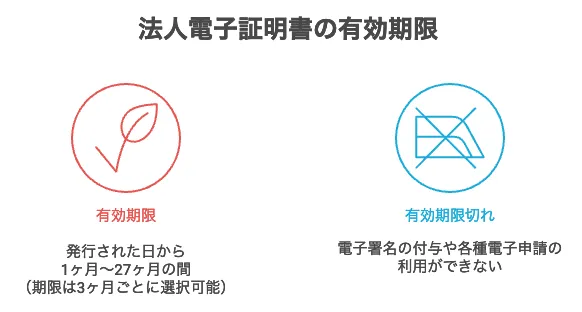法人電子証明書とは?はじめて利用する方に向けて解説
法人電子証明書とは、オンライン上での取引や契約において法人代表者本人であることを証明するものです。
今回は、法人電子証明書について、役割や取得方法、電子署名との違いについて解説します。
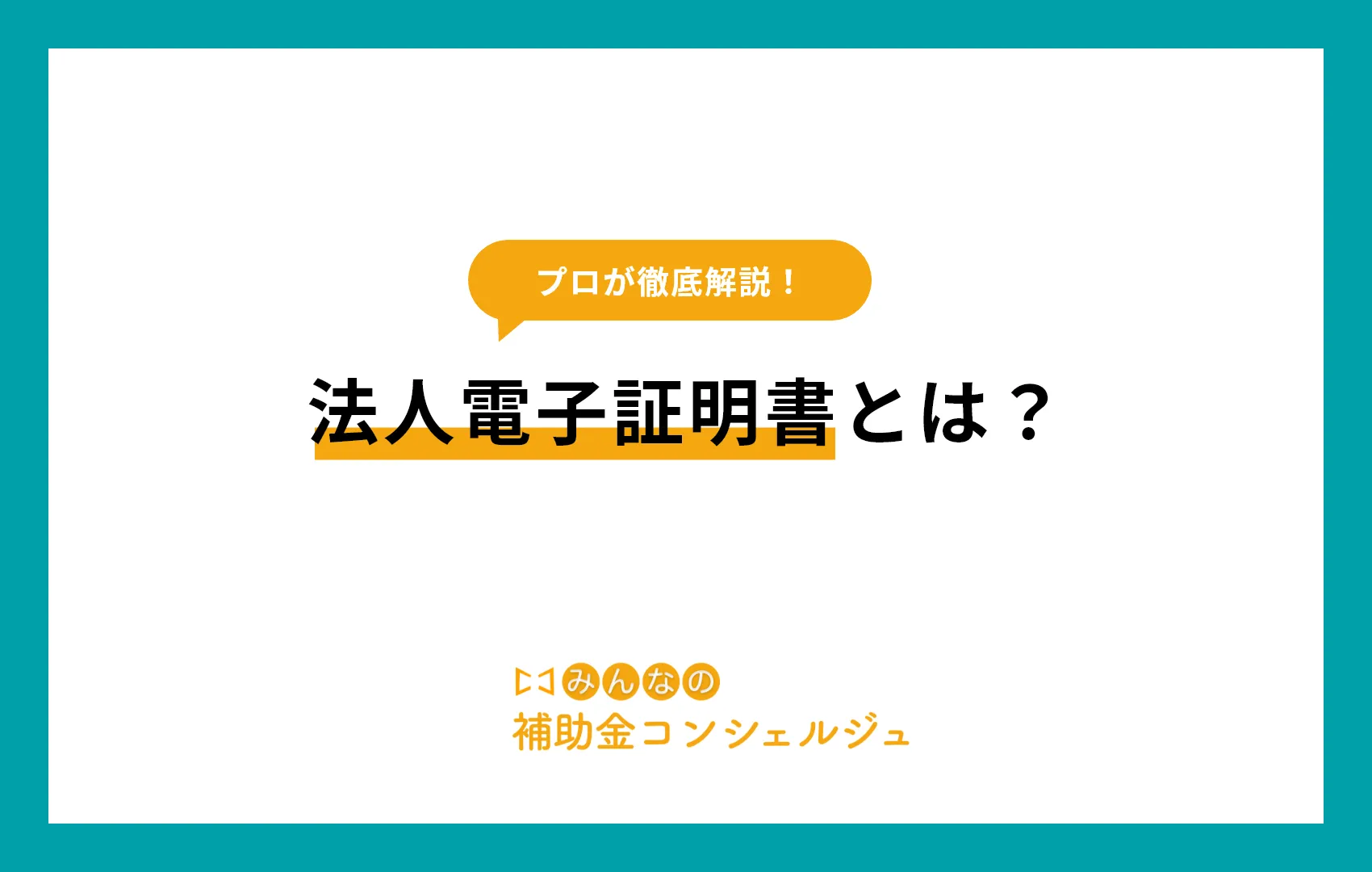
この記事を監修した専門家

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
法人電子証明書とは?
法人電子証明書とは、法人のなりすましや不正利用を防ぐために、その法人が実在し、正当な代表者が手続きを行っていることを証明するための電子的な証明書です。
これは、法務局(商業登記認証局)によって発行される公的な証明書であり、登記情報に基づいて発行されるため、信頼性が高いことが特徴です。
この証明書は、紙の印鑑証明書に相当するものであり、オンライン上での本人確認や電子署名の裏付けとして使用されます。
法人名、所在地、代表者名、発行日、有効期限などが記録されたICカード形式で提供され、e-Taxや登記ねっと、電子契約サービスなど、さまざまな電子申請・取引に利用されます。
参考:商業登記電子証明書はじめてガイド
法人電子証明書の3つの役割
法人電子証明書の主な役割を3つ紹介します。
- 電子署名の裏付けとしての役割
- 電子取引・申請の信頼性を支える役割
- 法人の「本人確認」の手段としての役割
電子署名の裏付けとしての役割
法人電子証明書は、電子署名を付与する際に用いられます。
電子署名は、紙の契約書における押印に相当しますが、単体では本人確認や法的効力を担保しきれません。
電子証明書があることで、その署名が特定の法人に帰属することが法的に保証されます。
電子取引・申請の信頼性を支える役割
電子証明書は、登記・供託オンライン申請、e-Tax、電子契約、電子入札など、さまざまな公的・民間の電子手続きで用いられています。
これらのシステムにおいて、証明書を介して法人情報の正確性を確認することで、信頼性の高い電子取引や申請が可能です。
法人の「本人確認」の手段としての役割
電子証明書は、商業登記に基づいて発行され、法人の基本情報(商号、本店所在地、代表者氏名など)が格納されています。
これにより、オンライン上で手続きを行う際に、確かにその法人の代表者が申請していることを公的に証明できます。
法人電子証明書が必要な6つの場面
ここでは、法人電子証明書が必要となる主な場面を6つ解説します。
- 電子契約
- 電子入札
- 電子定款の認証
- 税務手続き(e-Tax)
- 登記ねっとの申請時
- 補助金・助成金申請(オンライン)
電子契約
電子契約サービスを利用して契約書を締結する場合、法人電子証明書を用いた電子署名を行うことで、契約当事者の本人性と改ざん防止が保証されます。
紙の契約書における押印の代替として機能します。
電子入札
国や自治体の発注する工事や物品購入などの電子入札に参加するには、法人電子証明書の提出が必要です。
入札参加者が正当な法人であることを証明する役割を果たします。
電子定款の認証
株式会社設立時の定款を電子化して認証を受ける「電子定款認証」では、公証役場に提出する際に法人電子証明書による電子署名が必要です。
これにより紙の定款に印紙を貼る必要がなくなり、コスト削減にもつながります。
税務手続き(e-Tax)
法人税や消費税などの税務申告をe-Taxで行う場合、法人電子証明書を用いて電子署名を行う必要があります。
これにより、申告書類の真正性と法人の本人性が担保されます。
登記ねっとの申請時
登記ねっとを通じて、会社の設立、役員変更、本店移転などの登記申請を行う際には、法人電子証明書が必須です。
申請内容に電子署名を付けることで、正当な申請であることが確認されます。
補助金・助成金申請(オンライン)
補助金や助成金を電子申請で行う際にも、法人電子証明書が必要な場合があります。
代表者が自ら申請していることを電子的に証明するためです。
電子証明書と電子署名との違い
電子証明書と電子署名は、どちらも電子的なやり取りにおける「本人性」や「改ざん防止」のために使われる重要な仕組みですが、それぞれが果たす役割や意味は明確に異なります。
混同されやすいため、ここで詳しく整理して解説します。
電子署名とは
電子署名とは、電子データに対して、本人が確かに同意・作成したことを示すための電子的なサインです。
紙の書類で言えば直筆の署名や押印に該当します。
主に、以下の機能を持ちます。
・データの作成者が誰かを示す
・署名後にデータが改ざんされていないことを証明する
たとえば、契約書のPDFファイルに電子署名を付けることで、誰がその文書に同意したのかが明確になり、改ざんがあれば署名の検証が失敗する仕組みになっています。
電子証明書は、その電子署名が、誰によって行われたかを第三者が保証するための役割を持っています。
つまり、電子証明書は「この電子署名は、確かに○○株式会社の代表者が行ったものだ」と証明してくれる存在であり、電子署名の信頼性を裏付けるために不可欠なものです。
法人電子証明書の有効期限
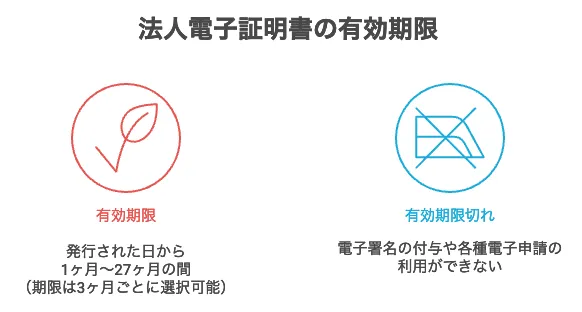
法人電子証明書には有効期限があり、発行された日から1ヶ月〜27ヶ月の間が有効期間とされています。
電子証明書は、有効期限を過ぎると自動的に無効となり、電子署名の付与や各種電子申請への利用ができなくなります。
そのため、有効期限の1か月前を目安に更新手続きを開始することが推奨されています。
証明書の有効期限は、申請用総合ソフトを利用することで確認することができます。
ICカードをカードリーダーに挿入し、証明書情報を読み取ると、発行日と有効期限が表示されます。
また、法人に登記事項の変更(代表者の変更、本店所在地の移転など)があった場合でも、証明書の有効期限が残っていればそのまま使用できます。
ただし、変更内容が証明書の情報と一致しなくなった場合は、更新や再取得が必要になる場合もあるため注意が必要です。
参考:電子証明書の取得方法について
法人電子証明書が取得できる場所
法人電子証明書は、公的な認証を必要とするため、特定の公的機関を通じてのみ取得することができます。
主に以下の2つの場所・手段で取得可能です。それぞれの取得先とその特徴を解説します。
法務局
法人電子証明書の発行元は商業登記認証局であり、これは全国の法務局に設置されています。
法人電子証明書の取得においては、本店所在地を管轄する法務局での申請・受け取りが原則となります。
申請はオンラインで行い、その後、指定した法務局で証明書(ICカード)を受け取る流れです。
受け取りの際には、代表者または正当な代理人が本人確認書類を持参して、窓口で手続きを行う必要があります。
参考:法務省
オンライン(登記ねっと)
法人電子証明書の申請自体は、登記ねっとを通じてオンラインで行うことができます。
「申請用総合ソフト」を利用して、必要事項の入力、電子署名の付与、電子納付などを完了させたうえで、証明書の受取先法務局を指定します。
オンライン申請は平日の8時30分から21時までです。受取は平日の法務局窓口営業時間内に行う必要があります。
※申請書情報が、17時15分以降に登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は、申請書情報を送信した日の翌日(翌営業日)に管轄の登記所で受付されます。
参考:登記ねっと
注意点
法人電子証明書は、セキュリティ上の理由から、現時点では完全なオンライン取得には対応していません。
オンラインで申請しても、ICカードの受け取りは法務局での対面手続きが必要です。
法人電子証明書の取得に必要なもの
法人電子証明書を取得に必要なものについて解説します。
利用者登録
登記・供託オンライン申請システムで電子証明書を取得するには、まず「申請者情報の利用者登録」が必要です。
登録時には以下の情報が求められます。
- 代表者氏名
- 法人名・本店所在地
- 連絡先メールアドレス
- 登記簿上の法人番号(13桁)
ICカードリーダー
法人電子証明書はICカード形式で提供されるため、電子署名を付与するためにはICカードリーダー(公的個人認証サービス対応機種)が必要です。
これは電子申請を行うパソコンに接続して使用します。
電子証明書発行申請書
申請用総合ソフトを使って電子証明書の発行申請を行う際、申請書を作成してオンラインで提出します。
電子署名を行う際には、ICカードを発行する法務省のルート証明書がPCにインストールされている必要があります。
ICカード受け取り時に必要な書類
ICカード形式の電子証明書を受け取る際には、以下の書類・情報が必要です。
代表者本人が行く場合
- 申請時に交付された「申請番号」または「受付番号」
- 代表者本人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
代理人が受け取る場合
- 代理人の身分証明書
- 申請番号または受付番号
- 委任状(法人代表者の押印があるもの)
- 代表者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
法人の基本情報に基づく登記データ
登記情報は、法務局の商業登記簿に登録されている法人名、本店所在地、代表者氏名などの情報です。
申請にはこれらが正確に登録されている必要があります。
もし変更がある場合は、先に登記内容を変更してから申請する必要があります。
電子納付用の金融機関口座またはペイジー対応の支払い手段
申請手数料の支払いは電子納付で行います。
ネットバンキング、ATM、またはペイジー対応の金融機関を利用して、所定の金額を支払います。
法人電子証明書の取得方法
法人電子証明書の取得方法は、オンライン申請と法務局での受取という2つの手順に分かれています。
下記で、場所ごとの具体的な取得手順を解説します。
オンライン申請の流れ(登記ねっと)
1.申請環境の整備
「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールします。
加えて、電子証明書を格納するICカードリーダー、Java実行環境、対応ブラウザなどの環境を整えておく必要があります。
2.利用者情報の登録
法人名、本店所在地、代表者名、メールアドレスなどを入力して利用者登録を行います。
この登録情報に基づいて申請が行われます。
3.証明書発行申請書の作成
申請用総合ソフトを使って、電子証明書の発行申請書を作成します。
法人の登記情報に基づいた内容を入力し、電子署名を付与したうえでオンライン送信します。
4.電子納付の実施
申請手数料(500円〜8,300円、証明期間により変動)をペイジー、ネットバンキング、ATMなどを利用して納付します。
納付完了後、受取可能通知がメールで届きます。
法務局での証明書受け取り
1.受け取り予約
多くの法務局では事前予約なしで受け取れますが、混雑が予想される地域では予約が必要な場合もあります。
申請時に指定した法務局を確認しておきましょう。
2.必要書類を持参して窓口へ
代表者本人が受け取る場合は以下を持参します。
・身分証明書(運転免許証など)
・申請時の受付番号または通知書
代理人が受け取る場合は、以下が追加で必要です。
・委任状
・代理人の身分証明書
・代表者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
3.ICカード受け取りと確認
法務局の窓口で手続きを行い、ICカード形式の法人電子証明書を受け取ります。
その場で内容に誤りがないかを確認することが推奨されます。
法人電子証明書に関する相談ができる場所
最後に法人電子証明書に関する相談ができる場所についてご紹介します。
法務局(商業登記所)
法人電子証明書の発行元である商業登記認証局は、各地の法務局に設置されています。
証明書の申請、受け取り、更新、ICカードの不具合などに関する相談が可能です。
特に、ICカードの再発行や失効に関する手続きは、法務局での対応が必要です。
参考:法務局
登記ねっとヘルプデスク
申請ソフトの操作方法や、申請時の不具合、電子署名が正常にできない場合などは、法務省が設置している登記ねっとの専用ヘルプデスクに相談できます。
受付時間:平日 8:30~17:15
ソフトの不具合やインストールに関する詳細な案内を受けることができます。
参考:登記ねっと
商工会議所や中小企業支援機関
各地の商工会議所や、中小企業診断士による相談窓口でも、法人運営に関する手続きの一環として、電子証明書の取得や使い方に関する助言を受けられる場合があります。
司法書士・行政書士などの専門家
法人設立や登記、電子申請を専門に扱う司法書士・行政書士に相談することも有効です。
電子証明書の申請を代行している事務所も多く、実務に即したアドバイスや代理申請の依頼が可能です。
とくに、登記と同時に電子証明書を取得する際には、スムーズな対応が期待できます。
法務省:商業登記認証局公式ウェブサイト
法人電子証明書に関する最新の申請方法や、Q&A、関連資料、各種マニュアルが掲載されています。
自己解決できる情報も豊富で、申請前の確認に役立つでしょう。
参考:法務省(よくある質問)
まとめ
今回は、法人電子証明書とは何か、電子署名との違いや取得方法について解説しました。
電子証明書は公的証書のため信頼性が高く、取引や契約時において安心して契約を結ぶことができます。
DX化をはじめ、オンライン上でやりとりをする機会が増えているので、この機会に電子証明書についての知識を深めていきましょう。
今回のコラムを参考に、まだ電子証明書を利用したことがない方は、電子証明書を用いて手続きが可能なものを探し、実際に電子証明書の使い方に慣れることからはじめてみてください。
関連コラム一覧
法人電子証明書の更新をするには?
印鑑証明を電子証明書を用いて取得するには?
法人電子証明書とは?はじめて利用する方に向けて解説